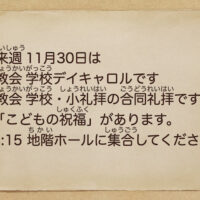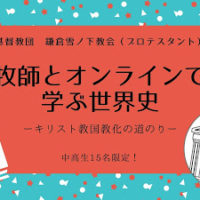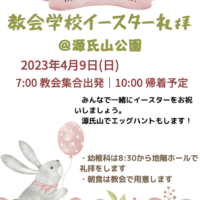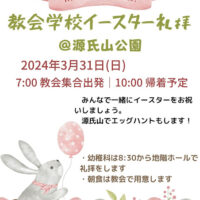人は神の義によって生きる
ローマの信徒への手紙 第1章16-17節
川崎 公平

主日礼拝
■1月からローマの信徒への手紙を礼拝で読み始めて、ようやく第1章の17節まで進みました。その最後のところに、旧約聖書ハバクク書第2章4節が引用されています。「正しい者は信仰によって生きる」。これを引用したパウロは、どんなに深い思いを込めて、この預言者の言葉を引用したことだろうかと思います。ローマの信徒への手紙というのは、言ってみれば、このひとつの言葉の意味を説き明かすために書かれたと言っても過言ではないのです。「正しい者は信仰によって生きる」。「あなたは、生きるのだ」。もとより、生きたいと願っていない人などひとりもおりません。誰もが切実に願っていることは、生きたい、ということです。死にたくない。滅びたくない。ただ問題は、真に生きるとはどういうことかということです。
ハバククという預言者が神によって立てられたとき、そこでも人びとは生きるか死ぬかの危機にさらされていました。ハバクク書第1章6節に、「私はカルデア人を興す」という神の言葉が記されています。カルデア人というのは言い換えれば大帝国バビロニアのことです。「私はカルデア人を興す。/彼らは残忍で残虐な国民。/遠くの地まで軍を進め/他人の住む土地を手に入れようとする」。そのような人びとが、国を滅ぼそうとしている。そのようなときに、この預言者は、神の言葉を待ちました。「私は見張り場につき/砦の上に立って見張りをしよう。/主が私に何を語り/私の訴えに何と答えられるかを見よう」(第2章1節)。すると、神のみ声が聞こえてきました。
主は私に答えられた。
「この幻を書き記せ。
一目で分かるように板の上にはっきりと記せ。
(2節)
ここに「一目で分かるように」という表現が出てきます。聖書協会共同訳の、小さな字で注が付いている版をお持ちの方があると思いますが、その注には「直訳 それを読む者が走るために」とあります。これはたいへん味わい深い表現で、この「走る」という言葉をきちんと残しておいてほしかったと思わないでもありません。新共同訳では、「走りながらでも読めるように/板の上にはっきりと記せ」と訳されました。なぜ走るのでしょうか。敵が攻めて来るからです。皆どこかで、滅びを予感しているのです。武器を持った人に追われるというのは、恐ろしいことです。生きた心地もしないまま、人びとが右往左往している中で、走りながらでも、いやむしろそのような危機においてこそ、神の言葉を聴かなければならない。「走りながらでも読めるように」、「一目で分かるように」はっきりと記せ。「見よ、高慢な者を。/その心は正しくない。/しかし、正しき人はその信仰によって生きる」(4節)。
「あなたは、生きるのだ」。しかしどうしたら生きることができるのでしょうか。「正しい人は、ただ信仰によって生きるのだ」。そう言われるのです。これは、ある人を励まし、あるいは戸惑わせ、あるいはまた人を失望させる発言ではないかと思います。私どもは、このような神の言葉を聴く用意があるでしょうか。
「正しい者は信仰によって生きる」。正しい者は、必ず生きるのです。正しくない者は、必ず滅びるのです。それが神のみ旨です。今朝はこの礼拝のあと、定例の教会総会を行います。そのような時に、いちばんふさわしい言葉を神が与えてくださったと言わなければならないでしょう。この教会も、信仰によって生きる。信仰によって生きていなければ、どんなに正しく生きようとしても、死んでいるのと同じです。正しい者は、信仰によってのみ生きる。しかし、どこにその正しい人がいるのでしょうか。
■ここですぐに思い起こされるのは、ルカによる福音書第18章9節以下の、主イエスのお語りになった譬え話であります。ふたりの人が祈りをするために神殿に上った。ひとりはファリサイ派の人、もうひとりは徴税人であったと言われるのですが、より正確に主イエスの意図を汲むために、ここはひとつ、「ファリサイ派と徴税人」ではなく、「善人と悪人」と読み替えることにします。最初に主イエスから直接この譬え話を聴いた人たちは全員そのように聞いたはずですから、そのように言い換えてもまったく差し支えないと思います。
昔々あるところに、善人と悪人がいました。ある日、この善人と悪人が、教会に行ってお祈りをしました。まず善人がこういうお祈りをしました。「神さま、ありがとうございます。わたしは善人です。悪いことは何もしていません。こんないいことをしています。あんないいことをしています。感謝します。アーメン」。念のために申しますが、この人は口先だけでこういう祈りをしたのではありません。口先だけは立派だけどお腹の中は真っ黒、というのではなくて、福音書には「心の中でこのように祈った」と書いてあります。このファリサイ派の人は、心の中まで、完璧な善人でした。本当の本当に、悪いことはひとつもしたことがありませんでした。
次にもうひとり、悪人が祈りました。この徴税人は、本当に悪い人でした。この悪い人のせいで、みんな困っていました。誰もがこの悪い人を恨みました。その悪人が、遠くに立って、目を天に上げようともせず、ただうつむいて小さな声で言いました。「神さま、どうか、罪人のわたしを憐れんでください」。
「言っておくが、義とされて家に帰ったのは、この人であって、あのファリサイ派の人ではない」(ルカによる福音書第18章14節)と主イエスは言われました。この主イエスの譬え話は、ローマの信徒への手紙第1章17節の意味を、見事に明らかにしていると思います。
「正しい者は信仰によって生きる」。しかし「正しい者」とは誰のことでしょうか。主イエスがこの譬え話でお語りになったこと、そしてまたローマの信徒への手紙がここから言葉を尽くして明らかにしようとしていることは、「正しい者とは誰か」ということです。「正しい者が、生きるのだ」ということです。その正しい者とは、自分で自分の正しさを自任する人のことではありません。神が正しいと認めてくださる人のことです。
あの主イエスの譬え話の中で、特に私が愛している表現があります。「義とされて家に帰った」と書いてあります。本当に率直に言って、私はこの言葉が好きです。「義とされて家に帰ったのは、この人であった。この徴税人であった」。日曜日の朝の礼拝が終わるたびに毎回、この言葉を思い出してもよいと思うほどです。皆さんが礼拝を終えて家に帰る。そのときに、ああ、わたしは神に義とされて家に帰るのだ、神がわたしと共に家路についてくださるのだと信じることができるなら、どんなに幸いなことでしょうか。ここにおられる皆さんは、ひとり残らず例外なく、義とされて家に帰る。そこに信仰もまた生まれるのです。
それに対してもうひとつ、この譬え話の中でたいへん際立っているのは、まずファリサイ派の人が「自分自身に向かって祈った」と書いてあることです。私どもの翻訳では「心の中でこのように祈った」とありますが、声を出さずに黙祷したという意味ではありません。直訳すれば、「自分自身に向かって祈った」。彼の祈りの相手は神ではなくて、自分自身であった。ひとりで神殿に来て、ひとりで祈って、自分に向かって祈って、そしてひとりで家に帰りました。ずっとひとりぼっちです。そして、ここは大事なところですから声を大にして言いたいと思いますが、神がこのファリサイ派の人を捨てたのではありません。ファリサイ派が神を捨てたのです。神を無視して、それで神ではなくて自分自身に向かって祈ったのです。もちろんそこには、信仰などありませんでした。信仰がなければ、本当の意味で生きることもできないのです。
■そこで改めて、ローマの信徒への手紙第1章17節を最初から読み直してみたいと思います。というのも、まだ17節の前半にまったく触れていないからです。そしてこの部分は、読めば読むほど、よくわからなくなってくるのではないかと思います。
神の義が、福音の内に、真実により信仰へと啓示されているからです。
昨晩遅く、私が説教の準備をしていると、小学生の息子がやって来て、「ねえ、お父さん、明日の説教やってるの? どんな話? ヒントちょうだい」。ヒントっていったい何だい、と聞き返したら、「えーと、だからさ、聖書の言葉を教えて。どんな話か当てるから」。「わかった、じゃあ読むぞ。『神の義が、福音の内に、真実により信仰へと啓示されているからです』」。「……ああ~、こりゃ無理だ~、おやすみ~」と言って、どこかに行ってしまいました。しかし子どもも大人も関係なく、こんな文章、本当に当時のローマの教会の人たちは理解したんだろうかと、少し不思議になりました。
そこで、丁寧に解きほぐしながら読んでみます。まずひとつ言われていることは、「神の義が、福音の内に啓示されている」ということです。「啓示される」というのは、この動詞が名詞になるとそれがそのまま「黙示録」という言葉になります。新約聖書最後の文書の黙示録です。もともとは「隠されていたものを明らかにする」という意味の言葉です。それまで隠されていた神の義が、福音の内に、初めて明らかに表れた。啓き、示された。ここでもあの主イエスの譬え話を思い出すのがいちばんわかりやすいのではないかと思います。いい人と悪い人が祈りをした。誰がどう考えても、いい人がいい人、悪い人が悪い人だと思っていたのに、福音の内に啓き示された神の義、それまでは隠されていた神の正しさというのは、罪人を赦し、一緒に家に帰ってくださる正しさであったと言われるのです。
その上で、ひとつわかりにくいのは、「真実により信仰へと啓示されている」という、この文章です。実は、この部分については、きわめて多くの解釈があり、したがってまた実に多様な翻訳が試みられていて、それをひとつひとつ紹介していると、どんどんこのあとの教会総会の時間が心配になってきます。それでも最低限の説明をすると、まずしばらく前まで使っていた新共同訳という翻訳ではこのように訳されました。
福音には、神の義が啓示されていますが、それは、初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。
「初めから終わりまで信仰を通して」。それが新しい翻訳では「真実により信仰へと」啓示される、となりました。これはどうも、あまりにも違い過ぎて、どちらかが翻訳を間違えたのではないかと疑いたくもなりますが、どちらも誤訳ではありません。さらにその前の口語訳という翻訳では、こうなっていました。
神の義は、その福音の中に啓示され、信仰に始まり信仰に至らせる。
原文を直訳すると、「信仰から信仰へ」という表現です。それを口語訳では、「信仰に始まり信仰に至らせる」、また新共同訳はこれを少し意訳して「初めから終わりまで信仰を通して」、つまり徹頭徹尾信仰のみ、という訳し方をしたわけです。それに比べて、新しい聖書協会共同訳の「真実により信仰へと啓示される」という翻訳は、非常に意味をとりにくいのですが、私はたいへんすぐれた翻訳の試みだと思いますし、また実際に有力な神学者、聖書学者が支持しているものです。今申しましたように、「信仰から信仰へ」というように、原文では同じ単語が二度繰り返されるわけですが、その繰り返しを聖書協会共同訳は、「真実により信仰へと」というように、それぞれ別の日本語に訳してしまいました。どうして同じ単語を違う日本語に移すのか、という批判もあり得るかもしれませんが、聖書の心をよく汲み取った翻訳だと、私はそう受け止めています。
「真実により信仰へと」。その心は、こういうことだと思います。ここでもまた、主イエスのあの譬え話の助けを借りたいと思います。あの徴税人が、神に義とされて家に帰った。そのようにして、誰も想定しなかったような形で、神の義が啓示されたのですが、その出発点は、あの徴税人の信仰ではありません。あの徴税人の誠実な悔い改めとか、一途な信仰とか、心のこもった祈りとか、そんなものが神の義の出発点になることはない。神の義の出発点は、神の真実の愛でしかありません。けれどもその神の義は、目指すところがある。神の義が啓示される出発点は神の真実であり、その啓示の目指すところは、私どもの信仰です。信仰がなければ、神の真実を受け止めることはできません。それをここでは、「神の義が、福音の内に、真実により信仰へと啓示されている」と言うのです。
■あの徴税人を義として、一緒に家に帰ってくださった神の真実があったから、そのような神の真実をイエス・キリストが啓き示してくださったから、私どもも主イエス・キリストの父なる神を信じました。私どもだって、どこまで行っても罪人でしかないのです。ヤコブの手紙は、人の悪口を言ったその唇で、どうして神を賛美することができるかと言うのですが、そんなことを言われたら、私どもはうつむいて胸を打つどころか、礼拝に来ることすらあきらめなければならないかもしれません。けれどもそんな私どものためにこそ、神の正しさが啓示されたのです。神の真実が啓き、示されたのです。「わたしは、あなたと一緒に、あなたの家に帰る」。この神の真実に始まり、私どもの信仰を目指して、神の正しさが示されたのです。
もし神が私どもを義としてくださるなら、何も恐れることはありません。ローマの信徒への手紙第8章の最後のところは、ローマの信徒への手紙のひとつのクライマックスです。パウロはこう言います。「神が味方なら、誰が私たちに敵対できますか」(第8章31節)。「誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです」(33節)。もし神が味方なら。もし神が私どもを義としてくださるなら。「私は確信しています。死も命も、天使も支配者も、……他のどんな被造物も、私たちの主キリスト・イエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないのです」(38、39節)。
たとえ敵に追われて、正気を失って走り続けなければならないときにも、いやそういうときにこそ、「一目で分かるように板の上にはっきりと記せ」と言われるのです。「あなたは、信仰によって生きるのだ」。しかしもしかしたらここも、「神の真実によって、わたしたちは生きる」と読んだほうがよいかもしれません。
■このような神の義が、神の正しさが、「福音の内に啓示されている」と言います。ある人がこの言葉をとらえて、こういうことを言っています。注意してほしい。ここでパウロは、「神の義が啓示された」とは言っていない。神の義が福音の内に「啓示されている」。動詞は過去形ではなくて、現在形であることに注意してほしい、というのです。なるほど、本当にそうだと思わされました。神の義は、「啓示された」のではないのです。「今、啓示されている」のです。この言葉は、ローマの信徒への手紙の中心であり、ということはこれが聖書の中心聖句だと言っても過言ではない、と思っていたのですが、そんな大事な聖書の言葉を、実は自分は正確に読んでいなかったことに気づかされて、正直に言えば少しショックを受けました。
たとえばキリストの十字架の内に、キリストの復活の内に、神の神たることが啓示された。はっきりと示された。そういう話なら、過去形で書けばいいのです。「キリストの十字架を見よ。その復活を見よ。あそこに、神の義が見事に啓示されたのだ」。けれどもパウロはここで過去形を使わないのです。現在形で、「神の義は、福音の内に、今啓示されている」と言います。「福音の内に」という言葉が大切です。それはたとえば、今この教会がキリストの福音を語っている。キリストの福音を聴いている。キリストの福音を告げ広めている。私どもが福音を聴いている今、神ご自身がその正しさを啓き示してくださるし、私どもがこれから神に伴われて家路につくときにも、今啓き示される神の真実のすばらしさを味わい、知ることができるのです。
パウロは、そのような意味で、福音の力を信じておりました。だからこそ、これに先立つ第1章8節以下では、何としてもあなたがたのところに行きたい、お互いの信仰によって励まし合いたい、さらに世界宣教に向かっての力を得たいと、そう書いたのでしょう。福音の力を信じるとは、たとえば言い換えて、聖書の力を信じる、説教の力を信じる、あるいは、われわれの教会の伝道の力を信じる、と言い換えてもよいのです。
もしもです、もしも私どもが、もはや福音の力を信じることができなくなったら、このあと行われる教会総会などは、何の意味も持たなくなるのです。今、ただ神の真実の前に立ちたいと願います。わたしたちは、ただ信仰によってのみ生きると、その思いをひとつにしたいと願います。そこにまた福音伝道の志も新しく与えられると信じます。お祈りをいたします。
父なる御神、ひとりの罪人が悔い改めるとき、天には大きな喜びがあるとあなたのみ子は言われました。そこに鮮やかに現れたあなたの義の現われを、ただ信仰によって受け入れる者とさせてください。これから行われる教会総会もまた、私どもの正しさではなく、あなたの義と真実の現れる場所としてくださいますように。主のみ名によって祈り願います。アーメン