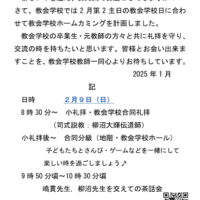群衆に押しつぶされるイエス
川崎 公平
マルコによる福音書 第3章7-12節

主日礼拝
イエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去られた。ガリラヤから来たおびただしい群衆が従った(7節)。
このような書き出しで始まる今朝の福音書の記事は、どうということもない、特に聖書に長く親しんでいる人であればあるほど、ほとんど心を動かされることもないかもしれません。これだけの記事で、牧師はいったいどんな説教をするんだろうかと心配してくださる方もあるかもしれません。しかし、この福音書を書いたマルコは、たいへん深い思いを込めて、この部分を書いたと思います。
ここでマルコ福音書が伝えようとしていること、少なくともそのひとつの主題は明らかで、ここで初めて「群衆」が前面に出てくるのです。「おびただしい群衆」と書いてあります。どのくらいの人数だったのでしょうか。どこから現れたのでしょうか。最初に出てくる「湖」とは明らかにガリラヤ湖のことですが、そのガリラヤ周辺の群衆だけでなく、「ユダヤ、エルサレム、イドマヤ、ヨルダン川の向こう側、ティルスやシドンの辺りからもおびただしい群衆が、イエスのしておられることを残らず聞いて、そばに集まって来た」と言います。その結果、主イエスは群衆に押しつぶされそうになって、やむなく弟子たちに頼んで小舟を用意させて、群衆から逃げなければならなくなりました。小舟に乗って適切な距離を取った上で、その舟の上から、み言葉をお語りになったのかもしれません。いずれにしても主題は「群衆」であります。
マルコによる福音書のここまでの部分に「群衆」という言葉が出てこなかったわけではありません。しかしそれはあくまで脇役扱いです。この福音書において、まず舞台の正面に登場してきたのはファリサイ派、あるいは律法学者と呼ばれる人たちです。主イエスとその人たちとの間で、かなり険悪な争いが生まれました。それが正確に言えば、第2章1節から第3章6節までです。その部分の最後の第3章6節には、遂にファリサイ派の人たちが、ヘロデ派の人たちとも相談しながら、どうやったらイエスを殺すことができるかという謀略を練り始めた、と書いてあります。けれどもそれは、そう簡単なことではありません。なぜなら、主イエスは群衆に人気があったからです。福音書の終わりの方でも、いよいよ主イエスが殺される2、3日前という時に至ってなお、何とかしてイエスを殺したいけれども、民衆が騒ぎ出すとまずいから、何かいい作戦はないかと相談を続けていたという記述があります。
その意味では、今日読んだ箇所に出てくる「おびただしい群衆」というのは、善玉か悪玉か、悪者かいい者かと言えば、それは明らかに善玉として登場しているのだろうと考えたくなります。明らかに悪役として登場しているファリサイ派が、何とかしてイエスを殺したいと思った。ところがそのイエスのもとに、おびただしい群衆が癒しを求めて、慰めを求めて、押し寄せたのです。けれども、今善玉とか悪玉とか、わざと幼稚な言い方をしましたが、マルコは決してそんな単純な見方をしていないと思います。ファリサイ派、律法学者が、あれほど願ったイエスの死を遂に実現させることができたのは、まさにこの「群衆」を味方につけることができたからです。この福音書のほとんど最後のところ、第15章において、「イエスを殺せ、十字架につけろ」と、最後まで大声で叫び続けたのは、ほかでもない「群衆」であったのです。
もちろん、こういう読み方に対して、慎重な姿勢もあり得るだろうと思います。「いやいや、いくら何でもそれは。ここに出てくるガリラヤの群衆と、最後の十字架の場面に出てくるエルサレムの群衆は、別の群衆じゃないですか」。しかしそれはおそらく、福音書を書いたマルコの本意ではないだろうと思います。だいたい、今日読んだ8節の最初のところにも、「エルサレム」と書いてあるではないですか。このとき、ガリラヤ湖に集まってきたおびただしい群衆の中には、はるばるエルサレムから来た群衆も混じっていたし、それほどの群衆を恐れたからこそ、ファリサイ派や律法学者たちはなかなか主イエスを殺すチャンスを見つけることができなかったし、けれども最後の決め手になったのは、群衆の叫びであったというのです。
福音書を書いたマルコは、「群衆」というものをたいへん神学的に描いていると思います。「神学的」なんて、少しかっこつけた言い方で恐縮ですが、その「群衆」という言葉の持つ神学的な意味を読みそこなうと、福音書そのものを正しく読み解いていくこともできないだろうと思うのです。
■ところで、ここまで「群衆、群衆」と何気なく繰り返してきましたが、「群衆」という日本語は、必ずしもあまりいい意味を持たないかもしれません。「本当は『群衆』なんてものは存在しないのだ。人間というのは、ひとりひとり、その人だけの尊い人格を持っているので、それを十把一絡げに『群衆』と呼んでしまうのはおかしい」。そういう見方だってあるかもしれません。というよりも、私ども自身が、群衆のひとりだと見られることに抵抗があるのではないでしょうか。聖書の中に「群衆」という表現が出てきても、自分もその中のひとりだとは、実はあまり本気で考えていないかもしません。「わたしはわたしなんだ。『群衆』なんて呼ばないで、この〈わたし〉を〈わたし〉として扱ってほしい」……と、いっちょ前に言うくせに、他人のことになると、実はわれわれも案外簡単に人を十把一絡げに扱うことがあります。「最近の若い人は」「年寄りはこれだから」「男なんて所詮」「女の考えることは分からん」「田舎もんは」「都会もんは」「中国人が」「アメリカ人が」「右翼が」「左翼が」……。本当は、ひとりひとりが、その人だけの心を持ち、人格を持った存在であるはずですが、私どもは実に簡単に人を群衆扱いするし、しかも事実、私ども自身が結局は群衆のひとりになって、「イエスを十字架につけろ」と叫んだり、そうでなくても、群衆というのはいろいろとんでもないことをやらかすものです。インターネットの発達によって、この「群衆」という存在の持つ意味は、ますます巨大化しているかもしれません。誰かが何か失敗をした。悪いことをした。けしからん。そう言って、何万人、何十万人、何百万人という人が、文字通り顔を持たない、名前も持たない、匿名の「群衆」と化してひとりの小さな人を押しつぶすようなことが、現実にいくらでも起こっているのです。
11節には、突然「汚れた霊どもは」と書いてあります。10節では、「病気に悩む人たちが皆、イエスに触れようとして、そばに押し寄せた」と言っておきながら、イエスに触れた結果、声を上げたのはその人たち自身ではなく、その人たちの内に巣食っていた汚れた霊どもであった。この群衆は、神の支配のもとに立っていない、そうではなくて、汚れた霊の支配下にあったのだという、この群衆の根本的な問題を、福音書は決して見逃さないのであります。これは決して、大昔の話ではありません。実に現代的な意味を持つ話だと思います。
■「群衆」とは、いったい何者なのでしょうか。マルコによる福音書は「群衆」というものを神学的にとらえていると申しましたが、これをもう少しきちんと言い直すと、神は群衆をどのように見ておられるのだろうか。主イエスは群衆をどのように見ておられるのだろうか。
第3章、第4章、第5章と読んでまいりますと、群衆が前面に出てきたり、また消えたり現れたりします。そして第6章の30節以下の段落では、主イエスが5つのパンと2匹の魚で、おびただしい群衆をおなか一杯にしてくださったという、有名な記事があります。しかし興味深いのは、そのパンの奇跡の前の、場面設定です。相変わらずたいへんな数の群衆に取り囲まれて、主イエスも弟子たちも、食事をする暇もなかったと書いてあります。それで、遂にたまらず、主イエスと弟子たちはまたもや小舟に乗って群衆から逃れようとしたけれども、群衆はそれでも主イエスを乗せた舟を見失うまいと一斉に先回りして、つまり湖沿いの道を走って追いかけたんでしょうね。「舟はあっちに行ったぞ」などと言いながら、遂に主イエスを待ち伏せすることに成功した群衆の数は五千人であったと、ちょっと考えられないような数字が残っています。もしもこの建物に500人の人が一度に集まったら、消防法に違反するかもしれません。その10倍の人数です。主イエスはその群衆を見て……第6章34節にはこう書いてあります。
イエスは舟から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のような有様を深く憐れみ、いろいろと教え始められた。
この群衆には、飼い主がいなかったのであります。それを主イエスはご覧になって、「深く憐れまれた」と書いてあります。聖書の元の言葉にさかのぼって理解するならば、おなかが痛くなるほどの感情を抱かれた、と読み替えてもよいところです。こういう言葉を読みますと、「群衆は善玉か、悪玉か」という読み方がどんなにくだらないものであるか、よく分かります。飼い主のいない羊だったからこそ、主イエスを押しつぶさんばかりに押し寄せたし、先ほど触れた第3章11節の「汚れた霊」というのも、その関連で理解しなければならないでしょうし、だからこそこの群衆が、「イエスを十字架につけろ」と、わめき続けるようなこともしたのです。
けれども、この飼い主のいない羊のような群衆のただ中に、まことの羊飼いが立っておられます。群衆はそのことを知りません。けれどもまことの羊飼いイエスは、ご自分の羊を知っていてくださいます。そしてもちろん主イエスは、群衆を群衆として十把一絡げに扱うようなことは決してなさいませんでした。「ガリラヤから来たおびただしい群衆が」、「また、ユダヤ、エルサレム、イドマヤ、ヨルダン川の向こう側、ティルスやシドンの辺りからもおびただしい群衆が」集まったときにも、主イエスはひとりひとりの心をじっとご覧になり、その飼い主のいない羊のような有様を深く憐れみ、その主イエスの深い憐れみは、エルサレムの群衆が「殺せ、殺せ、十字架につけろ」と狂ったように叫び続けたときにも、ますます深くなった。主の深い憐れみはそのとき、いちばん深くなったに違いないのです。「大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のような有様を深く憐れみ……」。今私どもも、その主イエスのまなざしのもとに立つのです。
■おびただしい群衆が主イエスのもとに押し寄せたという、この情景を思うとき、もうひとつ私が思い起こすマルコ福音書の記事があります。第3章、第4章、第5章と群衆の姿が出たり入ったりすると申しましたが、第5章21節以下でも再び主イエスは大勢の群衆に取り囲まれることになります。24節の後半には、「大勢の群衆も、イエスに従い、押し迫って来た」と書いてあります。その大勢の押し迫る群衆の中で、他の人とは違う押し迫り方をしたひとりの女性がいました。他の人とは違う、というのはおかしな言い方ですが、事実そうであったと思うのです。12年間も出血の止まらない女性、つまりそれは明らかに婦人科の病気に悩まされて、その人からしたらほとんど自分の人生を棒に振ったと思ったとしても無理もありません。けれどもこの女性が、もしかしたらと思って、思い切って主イエスの服に後ろからそっと触れました。そうしたら、たちまち病気は治ったのですが、主イエスは、ご自分の内から力が出て行ったことに気づいて、「誰だ。今わたしに触れたのは」と振り返ってお尋ねになりました。弟子たちはびっくりして、「いやいや先生、こんなおびただしい群衆があなたを押しつぶしそうとしているのに、『誰が触ったのか』って、何をおっしゃいますか」。けれども、主イエスはご自分に触れた人を、そのひとりの人をお探しになりました。それで、この女性はいよいよ観念して主イエスの足元にひれ伏し、すべてをありのまま話しました。主イエスは、どんなに嬉しかっただろうかと思うのです。それは、飼い主からはぐれた一匹の羊を見つけた、羊飼いの喜びであります。その主イエスの御心を、この福音書は証ししようとしているのです。
ある説教者がこういうことを言っています。「主イエスは、群衆を恐れなかった。群衆を軽蔑することもなかった。ただ主イエスは、群衆のためにお疲れになったのだ」。無限の深みを持つ言葉だと思います。そうではないでしょうか。おびただしい群衆に押しつぶされそうになったとき。「十字架につけろ、十字架につけろ」と叫び続ける群衆の声をお聞きになったとき。そのときにも主イエスは、群衆を恐れたり、軽蔑するようなことは決してなかった。ただ、飼い主のいない羊のような有様を見て、深い憐れみにつき動かされるように、ひたすらお疲れになったのです。群衆のために。そのひとりひとりを、愛されたからです。
そして、ふとこんなことを思うのです。もしも主イエスが、その服にさえ触れれば、バンバン病気が治る、悩みも解決する、ついでにお金も儲かるというような救い主であったなら、主は決してお疲れになることはなかったでしょう。あの出血の止まらなかった女だけでなく、主イエスのもとに押し寄せた群衆が皆、主イエスに触れたら病気が治った、その服に触っただけで悩みが消えた、もしもそういう救い主として主イエスが登場なさったのであれば、主イエスは決してお疲れにならなかっただろうし、あの女がそっと主イエスの服に触れたときにも、いちいち振り返ることもなかったかもしれません。
けれども、もう一度申します。あの12年間出血が止まらなかった女が、主イエスの衣に触れたとき、主はすぐさま振り返って、「わたしに触れたのは誰か」と、その人をお探しになりました。その前に、「自分の内から力が出て行ったことに気づいて」とも書いてあります。福音書は、そのような表現をもってしてもまた、たったひとりのために疲れをいとわなかった主の憐れみを証ししようとしているのかもしれません。今私どもも、この主の愛の前に立つのです。このわたしのためにも、主は振り返ってくださると信じて、しかしまた、このわたしのために主がお疲れにならなければならないとは、いったいどういうことかと恐れおののきながら、それでも今は、このお方以外に私どもの羊飼いはいないと知っておりますから、私どもは今、このお方の憐れみの中に立たせていただくのです。
■ここまでで、今日の話を終えてもよいかもしれませんが、最後にもうひとつのことを申します。今朝読んだところで、主がおびただしい群衆に押しつぶされそうになったときに、ひとつ大切な決断をなさいました。今日は7節から12節までを読みましたが、マルコによる福音書を連続で説き明かす多くの人が、この部分だけでなく、さらに19節までを一緒に読みます。主イエスが12人の弟子をお選びになって、伝道に遣わすために、使徒として任命されたというのです。それはつまり、群衆に押しつぶされそうになった主イエスが、弟子たちに助けを求められたということでしょう。
考えてみれば、本当に不思議なことです。神の御子に他ならないお方が、群衆に押しつぶされそうになって、それで疲れ果てて、お願いだから少し休ませてくれ、小舟を用意して、少し横になるだけでもいいから、しばらく休ませてくれと言われるのです。そしてそれだけでなく、主は弟子たちにご自分の仕事を委ねます。あなたがたも、この押し迫る群衆の悩みを一緒に受け止めてくれないか。この人たちの、ひとりひとりの悩みはあまりにも深すぎて、わたしひとりでは到底担い切れないから。そう言われるのです。そこに私どもの教会の原点があります。群衆に押しつぶされそうになった主イエスが、弟子たちに助けを求められた、私どもに協力をお求めになった、そこに私どもの伝道の原点があるのです。
この箇所を説き明かす聖書の学者たちは、しばしばこういうことを申します。7節から8節にかけて、「ガリラヤ、ユダヤ、エルサレム、イドマヤ、ヨルダン川の向こう側、ティルスやシドン」と7つの地名が出てくる。しかし、これは歴史的な事実を反映してはいないだろうと言うのです。主イエスが地上におられたときに、こんな広い地域の人たちが集まったわけがない。何となく〈7〉というきれいな数字に合わせただけだろう、と言う学者もいますし、しかしまたある人はこういうことを言います。「確かにこれは歴史的な事実ではないだろう。マルコがここに7つの地名を書いたのは、当時マルコの生きていた教会が、これらの土地で伝道しなければならないと考えていたからではないか」。なるほど、きっとそうであるに違いないと私も思いました。今私どもも、鎌倉という場所に立つ教会として、ここにまた自由に、7つの地名を入れてみることも許されるかもしれません。
今、群衆に押しつぶされそうになった主イエスのことを思いながら、何よりも主が、「大勢の群衆の、飼い主のいない羊のような有様を深く憐れみ」、その憐れみの心を弟子たちにも分けてくださったことを思いながら、今私どもも、主の弟子として立つべき場所に立ちたいと願います。お祈りをいたします。
思えば、今ここに集まる私どもも、不思議な力に導かれるように、主のもとに招かれました。主イエスに触れるために、いやむしろ、主イエスに触れていただくために、北から南から、西から東から、ひとりひとり、この場所に導かれてまいりました。ただあなたの憐れみによって立つ、この教会であることを思いながら、だからこそ、なお無数の人びとのために憐れみの心を砕いておられる主の思いを大切に受け止めさせてください。私どももまた、ひとりの友のために、ひとりの隣人のために心砕いて、主の愛を証していくことができますように。あなたの立ててくださったこの教会を、主の愛によって励ましてください。主のみ名によって祈り願います。アーメン