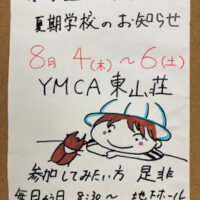死について知っておくべきこと
川崎 公平
テサロニケの信徒への手紙一 第4章13-18節

主日礼拝
■今朝の週報にも――という言い方をしても差し支えないかもしれませんが――教会の仲間の逝去と葬儀についての報告が書いてあります。先週の火曜日、この場所にご遺族を迎えて、葬りのための礼拝を行いました。その人の信仰の歩みがそのまま表れたような、すがすがしい葬儀になったことを私も感謝しておりますが、他方から言えば、愛する者を葬るということは、やはり厳しいことです。先週の葬儀でも、最初から最後まで涙が止まらなかったというようなご家族の顔を見ながら、何しろ私のことですから、それだけでもらい泣きしそうになるわけですが、そのようなときに私がよく思い出すのが、このパウロの言葉なのです。テサロニケの信徒への手紙Ⅰ第4章13節。
兄弟たち、既に眠りについた人たちについては、希望を持たないほかの人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。
これは、誰が死のうが悲しんではいけないとか、そんな無茶な話ではありません。愛する者が喪われる。悲しみが生まれるのは当然です。けれどもそれが「希望を持たないほかの人々のような」悲しみ方であったら困る。おかしな言い方かもしれませんが、ここでパウロは、希望を与えられている人間として悲しむことができているかと問うているのです。そのために、「ぜひ次のことを知っておいてほしい」。原文はむしろ、「無知であってほしくない」という表現で、そのように直訳した方がよかったかもしれません。あなたがたは、既に希望を与えられているのだから、「既に眠りについた人たちについて」、無知であってはいけない。知るべきことを知ってほしい。そう言うのです。
今日の説教の題を、「死について知っておくべきこと」としましたが、もしかしたら、この題は間違っていたかもしれません。パウロがここで教えていることは、「死について」ではないのです。「死とは何か」というような哲学的な命題を掲げて、あれこれ思索を巡らすというのではありません。「既に眠りについた人たちについて」、知るべきことを知ってほしい。ですから説教の題も、「死について」ではなくて「死者について知っておくべきこと」とすればよかったと思います。非常に具体的な話なのです。大切な人が死んでしまった。その体を柩に納めながら、この人は、いったいどうなったんだろう、これからどうなるんだろう、という話です。きっと今、皆さんの中にも、何年も前、何十年も昔に死んでしまった大切な人のことを思いながら、今ここに座っておられる方があるだろうと思います。そういう私どものためにも、パウロは言うのです。「兄弟たち、既に眠りについた人たちについては、希望を持たないほかの人々のように嘆き悲しまないために」、どうか、無知であってほしくない。しかし、私どもは本当は、もともと無知であったのであります。死について、いや、死んだ人について、私どもはもともと、何の知識も持っていなかったのです。
死んだらどうなるのか。人間は、昔から、そのことを問い続けてきました。そして私どもは、漠然と、いろんなことを考えるのです。「いろんなこと」というのはつまり、死んだおじいちゃんが天国でわたしたちを見守ってくれるとか、今頃天国でおばあちゃんと夫婦漫才しているに違いないとか、そんなのんきな話でなくても、これでお母さんは、何十年来の病気の苦しみから解放されたのだとか、たいていはなるべく自分に都合のいいことを想像して、そうやって自分を慰めるのです。当時のテサロニケの人たちだって、死者についての希望というか、妄想というか、そういう考えを持っていたと思います。古今東西、いろんな文化を調べてみれば、死者についての考え方というのはきっと、驚くほどさまざまであるに違いありません。しかし本当のところを言えば、死んだらどうなるか、誰も知りません。誰も知らないからこそ、自由に想像の翼を広げることができるのです。誰も知らないというのはつまり、私どものうち死んだことのある人はひとりもいない。正確に言えば、死んでから、もう一度われわれのところに戻ってきた人はいないから、だから、「死んだらどうなるか」ということについても、いくらでも好きなことを考えることができるのです。
■ところが、そういうところに、死人の中から甦られたイエスというお方の名前が告げられるのです。そのイエスという驚くべき名と深く結びついた驚くべき福音を、テサロニケの人たちも聞かされたのです。14節。
イエスが死んで復活されたと、わたしたちは信じています。神は同じように、イエスを信じて眠りについた人たちをも、イエスと一緒に導き出してくださいます。
細かいことのようですが、ここでパウロは「イエス」という呼びます。この手紙に限らず、パウロのどの手紙を読んでも、主の名をパウロが呼び捨てにすることはほとんどありません。「イエス・キリスト」あるいは「主イエス」と呼ぶのが普通ですし、私も説教の中でイエスさまのことを呼び捨てにすることはほとんどないでしょう。けれどもそれだけに、ここでは深い思いを込めて、「イエス」と、その名をしかも二度、三度と繰り返して呼びます。人間となってくださった神の子イエス、人間として死んでくださったイエスです。ところがこのイエスが、人間の中でたったひとり、死人の中から甦られた。死の向こうから、もう一度われわれのところに戻って来てくださったというのです。
私どもは、死んだ者について、本当はまったくの無知なのです。「死んだらどうなるか」、聖書もまた、私どもにそういった知識を与えてはくれません。けれども、私どもにただひとつ与えられているのは、イエスという名前だけです。そしてパウロは、このイエスというお方について無知であってはならないと、そう言うのです。もう一度14節を読みます。
イエスが死んで復活されたと、わたしたちは信じています。神は同じように、イエスを信じて眠りについた人たちをも、イエスと一緒に導き出してくださいます。
その当然の帰結として、18節では最後にこうも言うのです。「ですから、今述べた言葉によって励まし合いなさい」。あなたがたには、主イエスのみ名が与えられているではないか。互いに励まし合い、慰め合う言葉を既に与えられているではないか。
ここでパウロが問題にしていることは、私どもが、互いに励まし合うことができるかどうかということです。「希望を持たないほかの人々のように嘆き悲しまないために」、その悲しみを慰める言葉を持っているか、ということです。本物の慰めは、事実に裏付けられていなければならないと思うのです。無知に根ざす、何の根拠もない希望は、本物の希望にはならないと、私は思うのです。そして事実、私どもは、死に直面したときに、本当は何ひとつ慰めの根拠を持っていない、それがもともとの人間の、本当の姿だったと思うのです。死にのみ込まれてしまったら、それでおしまい。たいへん残酷な話ですが、もしイエスの名を知らなかったら、本当は、そういうことにしかならないはずだと思うのです。けれどもパウロはそこで、イエスというひとりのお方の名を告げるのです。「イエスが死んで復活されたと、わたしたちは信じています」。このイエスの名によって励まし合いなさい、慰め合いなさいと言うのです。
■この「イエス」という呼び名が既に、パウロの深い思いをよく表しているだろうと、先ほど申しました。このお方は、神ご自身と等しい方でありながら、本当に人になってくださったのです。しかもこのお方は、自分は神の子だから、死ぬのなんか怖くない、悲しくもないという態度をお取りになったことは、一度もないのです。生身の人間として、死ぬことの恐ろしさも悲しさも、よく知っておられました。
昨日、55年ぶりの改装工事を終えた教会墓地で礼拝をいたしました。私どもの教会墓地に、改装工事の前から刻まれていた主イエスの言葉について、私が短い説教をしました。当教会初代牧師の松尾造酒蔵先生の字で、文語訳でこう書かれています。「イエス言ひ給ふ 我は復活(よみがへり)なり、命なり」。「わたしは復活であり、命である」。けれどもこれを、死ぬのなんか怖くないという態度の言葉として聞き取るなら、それは大きな間違いです。
「我は復活なり、命なり」。主イエスが愛しておられたラザロという人が、既に墓に葬られたというところで語られた言葉です。そしてヨハネによる福音書は、そのラザロの死に際して、主イエスが激しく憤り、あるいはポロポロと涙を流し、最後にはその憤りと悲しみを込めたような大声で、「ラザロ、出て来なさい」と墓に向かって叫ばれたことを伝えています。その主の大声に呼ばれて、ラザロは墓の中から出てくることができました。パウロは、「イエスを信じて眠りについた人たちをも、イエスと一緒に導き出してくださいます」と書きましたが、それを先取りするような出来事が起こったのです。
けれども聖書が伝えることは、「そりゃあめでたい」というところでは終わらないのであって、ラザロを墓から呼び出してくださったイエスご自身が、死の苦しみを嘗め尽くさなければなりませんでした。このお方は、私どもの誰よりも、死を怖がっておられたのです。主が十字架につけられる前の晩に、ゲツセマネという場所で祈りをなさった。そのときのイエスの立ち振る舞いは、決して堂々たるものではありませんでした。すっかり怯え切って、悲しみもだえながら、弟子たちに、お前たちも一緒にいてくれと言われたのだと伝えます。十字架の上で息を引き取られるときにも、「わたしの神よ、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」と叫ばれて……それをヘブライ人への手紙は、このように伝えています。
キリストは、肉において生きておられたとき、激しい叫び声をあげ、涙を流しながら、御自分を死から救う力のある方に、祈りと願いとをささげ……(ヘブライ人への手紙第5章7節)。
これは、人間の言葉では説明不可能な神秘だと思うのです。そうではないでしょうか。パウロは、「希望を持たない人間のように嘆き悲しむな」と言いましたが、実は誰よりも絶望的に死を嘆き悲しまれたのは、あのイエスであったのです。
だがしかし神は、そのイエスを、死者の中から復活させられました。私どもは、このイエスというひとりのお方を信じるのです。むしろ、私どもは、このイエスというお方に出会って、初めて気づかされるのではないでしょうか。私どもは、死ぬのが怖いとか、愛する者がいなくなって悲しいとか、そう思っていたけれども、本当はどうも話が違う。むしろ、自分はまだ、このお方ほどには死を恐れたこともなければ、悲しんだこともないのではないか。ところが、このイエスというお方は、私ども罪人が知るべき死の恐れを、たったひとりで担い切ってくださったのであります。
■そのイエスを、神が復活させてくださったとき、もう私どもは、主イエスのようには死を恐れる必要がなくなりました。希望を持たない者のように嘆く必要はなくなりました。むしろ、安らかに眠りにつくかのように、死の出来事を捕らえることができるようになりました。その意味でここで注目しなければならないのは「眠りについた」という表現です。13節、14節、そして15節にも、「眠りについた」という表現が繰り返されます。死を眠りと呼ぶのは、日本語にも「永眠」などという言い方があるので、何気なく読み過ごしてしまうかもしれません。けれども、ここで聖書が言う「眠り」と日本語の「永眠」とは何の関係もないどころか、むしろ正反対の言葉です。聖書が死を眠りと呼んでいるのは、死は決して永眠ではない、われわれは絶対に永眠なんかしない、ということでしかないのです。むしろ「イエスを信じて眠りについた人たち」を、神がいつか必ず起こしてくださる、という信仰の表現です。
私どもに与えられている希望は、死んだら天国に行く、という話ではありません。お甦りになった主イエスが、もう一度来てくださる再臨の時を、私どもは待っているのです。その日のことを、15節以下ではこう書いています。
主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残るわたしたちが、眠りについた人たちより先になることは、決してありません。すなわち、合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主御自身が天から降って来られます。すると、キリストに結ばれて死んだ人たちが、まず最初に復活し、それから、わたしたち生き残っている者が、空中で主と出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして、わたしたちはいつまでも主と共にいることになります。
「合図の号令」、「大天使の声」、そして「神のラッパ」。たいへん壮大な情景が描かれています。ある人はこれを、冗談半分かもしれませんが、「神の目覚まし時計のようだ」と言いました。もっとも私などは、一度目覚まし時計が鳴っても、無意識のうちにアラームを止めてしまったりするのですが、この時にはそんなことは考えられない。私どもの死の眠りが、どんなに深い眠りであったとしても、この神の目覚まし時計が鳴る時には、目を覚ましそこなう人はひとりもいない。なぜかと言うと、「合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主御自身が天から降って来られます」。あのイエスさまが、来てくださるのです。どんなにけたたましく目覚まし時計が鳴って、私どもが死の眠りから目を覚ましたとしても、そこに誰もいなかったら、逆にこんなに恐ろしいことはないかもしれません。けれども、私どもが死の眠りから目を覚ます時というのは、主が再び来てくださる、命の朝、甦りの朝であります。「さあ、朝だよ、起きなさい」とのイエスさまの御声を聞きながら目を覚ます私どもについて、17節後半ではこう言われます。「このようにして、わたしたちはいつまでも主と共にいることになります」。私どもは、この主・イエスに愛されているのです。そして教会とは、この主・イエスを愛する群れであります。
今、私どもがこのように教会を造っているのも、この最後の甦りの朝を目指してのことであります。イエスと一緒に導き出され、眠りから起こされる人たちというのは、この教会のことです。だからこそ、今既にここで、互いに励まし合うのです。死の悲しみに向かい合いながらも、眠りについた者を最後に起こしてくださるのは、あのイエスさまだ。そのイエスの愛を信じて、今ここでも励まし合うのです。慰めを告げ合うのです。そのような命の群れが、かつてテサロニケという町に生まれ、今もこの鎌倉の地に主の教会が立てられていることを、心して受け止め直したいと思うのです。祈ります。
父なる御神、あなたの御子イエスが死んで復活されたと、わたしたちは信じています。もう私どもは、無知ではないのです。悲しみがあり、嘆きがあり、今朝もそのような悲しみの中にあるご遺族を迎えて礼拝をしておりますが、だからこそ、ただひとりの慰め主、イエスの名を信じ抜く者とさせてください。今もいつも、いつまでも共にいてくださる主イエス・キリストのみ名によって祈り願います。アーメン