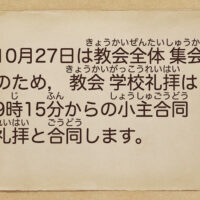いのちの不意討ち
マタイによる福音書第28章1―10節
川﨑 公平

復活主日礼拝
主がお甦りになった日の朝早く、マリアという名のふたりの女性が、主が葬られた墓を見に行きました。このとき、おそらくひとつ気がかりであったのは、いったいどうやってあの大きな石をどけることができるだろうか、ということです。当時の墓は、大きな横穴の入り口に巨大な岩を戸のように置いて封をするという形でした。その岩をどかさなければ、中に入ることができないのです。ところがそこで起こったことは、ここに書いてある通りです。「すると、大きな地震が起こった。主の天使が天から降って近寄り、石をわきへ転がし、その上に座ったのである」。
ある人がこういう考察をしています。「墓の石がいくら大きかったとしても、地震が起こったり、天使が天から降ってくるほどのことではなかったのではないか。けれどもこの朝、墓を閉じていた石が神の手によって取りのけられたということは、まさに神の手によるほかなかったのだ」。この石は、ただ神のみが転がすことのできる石でした。人間の手では動かすことができないものが、動いたのです。
その墓の中から、それこそ神にしか語り得ない言葉が響いてきました。「恐れることはない。十字架につけられたイエスを捜しているのだろうが、あの方は、ここにはおられない。かねて言われていたとおり、復活なさったのだ」。いのちの言葉、死に打ち勝つ言葉です。そしてそれ以来、この言葉は、私どものいのちを支える事実になっているのです。
マタイによる福音書に限らず、マルコ、ルカ、ヨハネ、すべての福音書が、主イエスの墓を閉じていた大きな石について語っていることは、たいへん意義深いことだと思うのです。ただの重い物体ではありません。人間の力では、どうにも動かすことのできない石。私どもを、死の恐れの中に閉じ込めようとする石です。これがどんなに大きなものであるかということは、私どももよく承知しているのです。私どもは、愛する者の墓を訪ね、場合によっては、その蓋を開き、愛する者の骨壺を見ることができる。触ることだって、抱き締めることだってできる。けれども、何をしたって、死の家を閉ざす大きな石は、本当の意味では動きません。なお大きな石が、私どもと死んだ者とを隔てていることに気づくのです。
ところが、すべての福音書が共通に伝えることは、復活の朝、その石が神の力によって取りのけられたということです。しかもマタイ福音書は興味深い情景を記します。その転がされてしまった石の上に、天使が座った。それはつまり、もう誰も、この石を元のところへ戻すことはできなくなったということでしょう。
この出来事を聞かされたふたりのマリアは、そこで直ちに、これを伝えるべき人に伝えなさいと命じられました。「あの方は、ここにはおられない。かねて言われていたとおり、復活なさったのだ。……急いで行って弟子たちにこう告げなさい。『あの方は死者の中から復活された。そして、あなたがたより先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる』。確かに、あなたがたに伝えました」。
改革者ルターは、この女性たちを「最初の伝道者」と呼びました。あの石が動いたことを宣べ伝える者として、この女性たちは走り出しました。「婦人たちは、恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走って行った」。この記述も興味深い。まだ恐れていたのです。しかもその恐れは、大きな喜びと共存するような恐れであったというのです。しかし考えてみれば、恐くて当然だったと思います。死の石を叩き潰すような神の力に触れたのです。むしろ、この恐れを知ったからこそ、その喜びを大きくすることができたのだと思います。その喜びに、ぐいぐい引っ張られるようにして、このふたりのマリアは走り始めました。
ただし、ここでもうひとつ私どもが心を打たれることは、この女性たちの喜びの全力疾走を、主イエスご自身が遮られたということです。「すると、イエスが行く手に立っていて……」。喜びにあふれて走るふたりのマリアを、主イエスが通せんぼなさった。天使は「ガリラヤに行きなさい、そこでお目にかかれる」と言ったのに、まるで天使の言葉が間違っていたかのようです。思いがけない主イエスの不意討ちを受けたのです。
私どもが人生において不安を抱くこと、それは死に不意討ちされることがないかということです。思いがけない病を得たり、愛する人が事故に巻き込まれたり、死の不意討ちを受けて、その心の痛みが、何十年たっても癒されることがないということが、私どもの周りでも実際に起こります。しかしここで聖書が語るのは、さらに思いがけないことです。復活の主が、私どもを不意討ちするために、待ち伏せしてくださるのです。
愛する者の死をきっかけに礼拝に来るようになったという人を、私どもは何人も知っています。しかし私は別に、そういう方たちだけのことを考えているわけではありません。なぜ自分は今、ここにいるのだろうか。そのことを改めて問うならば、誰でも不思議な思いに導かれるはずです。誰にとっても思いがけないことは、主イエスの恵みの不意討ちを受けるということです。ひとりひとり、思いがけず、主イエスに待ち伏せされていたという経験を持っています。だから、私どもはここにいるのです。
ふたりのマリアを待ち伏せしておられた主イエスは、「おはよう」と言われました。ここでやはり読み飛ばしにくいのが、この「おはよう」という言葉だと思います。口語訳聖書では「平安あれ」と訳されました。荘重な祝福のあいさつが、新共同訳では急にくだけた口調に変わり、いくら何でも軽薄ではないかと思ったことがあります。原文を直訳すると、「平安」というよりも、「喜びなさい」という言葉です。新共同訳も誤訳ではありません。「おはよう」という意味を持つこともあるし、ついでに言えば、「こんにちは」とか「さようなら」という意味になることもある。ここでは朝のあいさつだから、「おはよう」と訳されたのです。
「おはよう」という翻訳には、賛否両論あるかもしれません。しかし考えてみると、この場面での「おはよう」という言葉は、主イエスにしか口にすることのできないあいさつでありました。甦りの朝のあいさつ。死に打ち勝ったお方のあいさつです。キリスト教会が日曜日の朝に礼拝をするのは、主が日曜日の朝に甦られたからです。この甦りの朝は、神にしか作ることのできない朝であった。その朝を告げるあいさつを、この女性たちは聴いたのです。
「おはよう」と、何気なく私どもはあいさつをします。しかし、私どもが実はよく承知していることは、いつか必ず「おはよう」と言えなくなる日が来るということです。言うまでもなく、私どもが死ぬときのことです。けれども、そのような私どもに神が約束してくださる希望がある。主が再び来てくださる日、私どもを死の眠りから目覚めさせてくださるということです。
愛する者が、遂に息を引き取るとき、私どもは、主がその人を再び起こしてくださる日のことを思います。しかもそれは、決して他人事にはならないのであって、いつか自分自身が死ぬときのことをも考えないわけにはいきません。主が再び来てくださる日、主がわたしを目覚めさせてくださるときのことを思います。そのとき、主イエスはわたしにどういう言葉をかけてくださるのだろうか。そのことを、私はわくわくするような思いで想像します。きっとそのあいさつは、「おはよう。公平、起きなさい、甦りの朝だよ」。主イエスにそう言っていただける日を、私どもは待っているのです。この女性たちが聞いた「おはよう」というあいさつは、この復活の希望を先取りするような言葉であったのです。
ただし、そこで思い違いをしてはならないことがあります。神はこの墓の石を軽々と動かしてくださったし、主イエスにとっても、こんな石どうってことない、という話ではなかったのです。マタイ福音書によれば、主イエスが十字架の上で最後の最後に叫ばれた言葉は、このようなものでした。「わたしの神よ、わたしの神よ、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」。この大きな死の石をどんなにゆすっても叩いても、どうしようもない。そのような絶望の叫びでしかなかったのです。「神よ、なぜですか。なぜこの死の石は動かないのですか」。信じて祈れば、山も動くとまで教えてくださった主イエスです。ところがその主ご自身が、どんなに祈ってもこの石は動かないという経験をなさったのです。私どもの主であるお方は、むしろ、私どもの誰よりも深く、死を恐れておられました。
だからこそ、私は思う。父なる神が主イエスを死者の中から甦らせてくださったとき、主イエスご自身が誰よりも深く、父なる神の慰めをからだいっぱいに味わわれたに違いないのです。
天使は、「復活なさったのだ」という言葉を繰り返します(6節、7節)。私どもの翻訳では、復活した、復活したと簡単に言いますが、しかし原文を直訳すると「起こされた」という言葉です。主イエスが自分で起きたのではない。父なる神に起こしていただいたのです。実際、この「起こす」というのは、朝目覚めて起きるというときにも用いられる言葉です。「わが子イエスよ、おはよう、起きなさい」と、神が御子イエスに呼びかけてくださったのではないかと推測することは、決して間違っていないと私は思います。
その主イエスが、私どもに「おはよう」と声をかけてくださるのです。それは、主ご自身、心底神に慰めていただいたところに生まれた慰めのあいさつであり、だからこそ、世のいかなる言葉にまさって、力ある慰めの言葉になるのです。
このひと月ほど、私は、ヨッヘン・クレッパーという人の祈りの言葉を読み続けました。現代の讃美歌詩人の最大のひとりです。五年前に教文館から『キリエ』という詩集が出版され、さらに最近、そのいくつかを抜粋して写真を添えた、すてきな装丁の書物が刊行されました。このドイツの詩人は1903年に生まれ、1942年に39歳で亡くなっています。自殺したのです。当時既に文人として高く評価されていましたけれども、妻がユダヤ人であった。1942年、あるいはその前に、ヒットラー政権のもとでドイツ人がユダヤ人の妻を持っているということがどういう意味を持ったか。そのためにクレッパーは詩人としての活動を厳しく制限されました。それだけではありません。長女は幸いにして国外に逃がすことができたけれども、妻と次女は国外逃亡の時期を逸し、そのうちにユダヤ人強制収容所に送られる危険が迫ってきた。そして遂に、自宅のガス栓を放って、妻と娘と共に自殺しなければならなかったという人です。
クレッパー自身が、そのころのこころの動きを、日記に記録しています。神からいただいたいのちを自ら断つということが、どんなに恐ろしい罪であるかということを正直に見つめながら、「自殺の罪だけは、神の赦しの外に置かれるのだろうか。キリストの恵みに覆い得ない罪があるのだろうか」。そのように自ら問うております。そしてこういうことを書きます。クレッパーは、その少し前に手に入れたキリストの像を、部屋の高いところに置いていたようです。わたしたちは、このキリストの祝福のまなざしのもとで死ぬのだと書いています。
主イエスご自身が既に、クレッパー一家に先立って、「わたしの神よ、なぜわたしをお見捨てになったのですか」と、大声で叫ばれたのです。クレッパー一家の叫びもまた、その主の叫びに連なるものであったに違いない。その意味では、クレッパーの苦しみに真実に寄り添うことのできるお方は、ひとりしかいない。十字架につけられたお方、復活させられたあのお方こそ、私どもの唯一の希望なのです。
クレッパーの詩の中でも最も大きな反響を得たと言われる、「夕べの歌」という詩があります。詩編第4篇9節に基づく歌です。冒頭のみ紹介します。
主よ、あなたに守られて身を横たえ、
わたしは平安のうちに眠りにつく。
御腕に休らう者にこそ
まことの安息が与えられる。
いつも目覚め、助け癒すのは、
主よ、あなただけ、
闇夜の陰が
わたしの心を不意に怯えさせるときも。
クレッパーもまた、「闇夜の陰」が迫っていることを知っていました。「わたしの心を不意に怯えさせるときも」と言います。復活を信じることは、どんなことにもおびえなくなることを意味するわけではないのです。「神さま、こわいです。わたしはおびえています」。そのわたしを眠りにつかせてくださるのも、そして起こしてくださるのも、主よ、あなただけ。クレッパーもまた、「おはよう」という主のいのちのあいさつを聴き取っていたのではないでしょうか。そしてこれは、私どもすべてに等しく与えられるいのちの祝福であります。