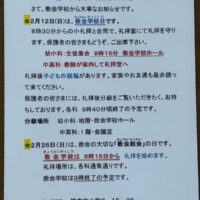滅びに勝つ神の言葉
マルコによる福音書 第13章28-32節
川崎 公平

主日礼拝
■いつものように、マルコによる福音書を読むことによって礼拝をいたします。先々週、そして先週と、この福音書の第13章を読んでまいりました。この第13章というのは、どうもとっつきにくい、異様な印象を与えると思います。それは一方では仕方のないことだと思います。二千年も昔の、その当時の特別な文章の書き方に沿って書かれているものですから、二千年後のわれわれにとって違和感があるのは当然だと言わなければなりません。そしてその文体に違和感があるために、その内容も何だかわれわれの生活の現実からかけ離れているような印象を受けるかもしれませんが、もしそうであればその印象は間違っています。むしろ、こんなにわれわれの生活の現実に密着した言葉はなかなか見つからないのではないかと思うほどです。私自身、先々週、先週とこの第13章を読みながら、その思いを新たにさせられています。
この第13章が伝えている「われわれの生活の現実」、それはひと言で言えば、「この世界は結局、滅びに向かっているのではないか」という現実感です。たとえば6節以下を読むと、国と国との間に戦争があり、地震があり、飢饉があり、しかもそのような危機に乗じて偽キリストが暗躍するだろうと言われるのですが、実のところこの主イエスの言葉には、ひとつも大げさなところはありません。私どもの生活の現実そのものです。そしてそういう現実の中で、それこそ似非救世主が語ることはだいたい相場が決まっているので、「世の終わりは近い」と言うのです。「世の終わりは近い」とか、「罪を悔い改めよ」とか、人の不安を煽るような変な看板を見かけることもあるかもしれません。そしてそういう変な看板と同じように、この第13章のような文章を読みますと、世の終わりという恐ろしい出来事がいつか来るんじゃないかとふと不安になったり、逆にこういう怪しげなことを語る聖書というのは、やっぱりちょっと宗教として怪しいんじゃないかと疑ってみたりするのかもしれません。
一方で確かなことは、ここで主イエスが見つめておられることは、世の終わりのことだということです。31節でもはっきりと、「天地は滅びるが」と言っておられます。事実、この世界は滅びるべきものなのです。逆に聞きますが、この世界が永遠に続くだろうと考えている人は、よほどの楽天家でない限りいないと思うのですが、いかがでしょうか。けれどもそこで大切なことがあります。主イエスはここで、世の終わりについて、決して悲観的なことを言っているのではありません。「世の終わりは近い」とか何とか、人の不安を煽るような仕方で宣伝するのは、たとえその背後に聖書があろうと、主のみ旨を裏切ることでしかありません。
■そこで今日読んだ箇所ですが、まずここで主イエスは、「いちじくの木から、このたとえを学びなさい」と言われます。「枝が柔らかくなり、葉が出て来ると、夏の近いことが分かる」と言われるのですが、この譬えは少しわかりにくかったかもしれません。「夏が近い」というのは、春から夏への移り変わりではなくて、寒い冬が終わるという意味です。日本では普通に四季、四つの季節と言いますが、パレスチナの気候には冬の雨季と、夏の乾季と、ふたつの季節しかありません。それはもちろん現代でも同じことで、冬が終わったと思ったら、本当にひと晩の内に夏になっているということもあるそうです。寒い、寒い、いつまで冬が続くのだろうとぶるぶる震える気持ちはわかるけれども、必ず夏が来る。「枝が柔らかくなり、葉が出て来ると、夏の近いことが分かる」。そのようないちじくの木から、学ぶべきことを学び取りなさい。既に夏の兆しが見えるではないか。命の季節、実りの季節は近いのだ。
そのように主イエスが言われた冬の寒さというのは、いろんな寒さがあるのです。それこそ戦争とか地震とか飢饉とか、そうでなくても私どもは人生のさまざまな局面で、大小さまざまな滅びの経験をするのです。もうおしまいだと言いたくなるような、泣きたくなるような経験をするのです。愛する人を喪ったり、仕事を失ったり立場を失ったり面目を失ったり、あるいは若い頃には受験に失敗したり……。受験の失敗くらいどうってことないじゃないかと、大人はそう思うかもしれませんが、当の子どもにとっては、人生そのものがだめになったような出来事に感じられることもきっとあるでしょう。逆に年を取ったら、年を取るということ自体が、滅びの経験に数えられるかもしれません。誰でもある一定の年齢になれば、自分は今、人生の冬を迎えているのだということを考えないわけにはいかないのです。
けれどもまた主イエスはこのとき、何よりもご自分の弟子たちのことを慮っておられたと思います。私ども教会の経験する冬の季節のことをお考えになりながら、「夏は近い」と言われたのだと思います。戦争があり、地震があり、飢饉があり、さまざまな滅びの兆しを見せるこの世界なのですが、もうひとつ私どもの生きるこの世界の根本的な問題は、この世界は神の子イエスを憎むような世界だということです。だから主イエスは十字架につけられたのです。そういう世界に教会が生きるとき、どうしたって冬の寒さを経験しないわけにはいきません。だがしかし、冬は必ず終わるのです。
■「いちじくの木から、たとえを学びなさい。枝が柔らかくなり、葉が出て来ると、夏の近いことが分かる。それと同じように、これらのことが起こるのを見たら……」。その「これらのこと」というのは、たとえば戦争とか地震とか飢饉とか、この世界で起こるべくして起こる悲しいことすべてのことでしょう。19節で、「それらの日には、神が天地を造られた創造の初めから今までなく、今後も決してないほどの苦難が来るからである」と言われているようなことでしょう。その前の17節で、「それらの日には、身重の女と乳飲み子を持つ女に災いがある」と言われるような悲しみのことでしょう。
「このようなことが起こるのを見たら」、けれどもそこで大切なことは、「世の終わりは近いのだから、恐れおののけ」と言われたのではないのです。そうではなくて主イエスは、「夏が近いことを知れ」と言われたのです。それを29節では譬えではなくはっきりと、「人の子が戸口に近づいていると悟りなさい」と言われます。戦争が起こったり、地震が起こったり、もう世界はおしまいだと泣きたくなるような、そういう「これらのことが起こるのを見たら」、そのときにこそ、わたしが近くにいることを悟りなさい。
考えられる限りの恐ろしいことが起こる、この世界なのです。「これらのことが起こるのを見たら」、そのとき、私どもはいくらでも絶望できるのです。「どうして、こんなことが」、「もし神がいるなら、どうしてこんな理不尽なことが」と、私どもはいくらでも望みを失うことができるのですが、「いちじくの木から、たとえを学びなさい」。冬がどんなに長くても、もう夏の兆しは見えているじゃないか。「それと同じように、これらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい」。冬は終わるのです。必ず終わるのです。命の季節が来るのです。イエスさまがいてくださるから。このお方が近くに来てくださるからです。
この主イエスの言葉は、私どもの世界観を根本的に支えるものだと思います。私どもに、徹底的に楽観的な、明るい世界観を教える言葉だと思います。それがマルコによる福音書第13章の主旨です。「あれ、先週と逆のことを言ってる」と、記憶力のよい方はお感じになるかもしれません。先週の礼拝では、主イエスはわれわれの誰よりもずっと悲観的にこの世界の現実を見ておられたという話をしたのです。戦争があり、地震があり、飢饉があり、しかも悲しいことに、そういうときにいちばんつらい思いをするのは「身重の女と乳飲み子を持つ女」たちなのです。主イエスは私どもの誰よりも冷静にこの世界の現実を見ておられた。この世界について、誰よりも悲観的であられた。そのように先週の礼拝で言ったことを、訂正するつもりはありません。今は、現に、冬なのです。厳しい冬の寒さの中で、それなのに夏の格好をして歩いていたらきっと体を壊すでしょう。しかし私どもは、冬の寒さに震えながらも、夏の到来を知っているのです。必ず夏は来る。命の季節が来るのだ。ありとあらゆる冬の寒さを見たら、人の子であるわたしイエスの近さを知りなさい、と言われるのです。そうであるならば、主イエスはむしろ私どもの誰よりも楽観的であったと、逆説的にそう言うことができるだろうと思います。
■その次の30節には――今日は私にしては珍しく、1節ずつ順番に読んでいるわけですが――「よく言っておく。これらのことがみな起こるまでは、この時代は決して滅びない」とあります。よく考えてみますと、こんなに楽観的な言葉はないかもしれません。「この時代は決して滅びない」と書いてあります。もちろんそれは、「これらのことがみな起こるまでは」という限定つきですが、「この時代は決して滅びない」。その「これらのこと」の最後には、先週の礼拝で読んだ26節以下にあるように、「その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗って来るのを、人々は見る。その時、人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで、選ばれた者を四方から呼び集める」。主イエスが来てくださるのです。その時まで、「この時代は決して滅びない」。
私どもの生きるこの世界は、放っておいてもひとりでに滅びていくのではないのです。これも私どもの何となく抱いている常識的な感覚とは真っ向から対立するのではないでしょうか。戦争があり、地震があり、飢饉があり、大小さまざまな滅びの経験があり、そういったことが重なり合って、いつかこの世界は、人間の手によって滅びてしまうのではないかと私どもは心配するのです。いろんな核兵器のことを思いますと、ちょっとしたボタンの掛け違い、あるいはボタンの押し間違いで、あっという間に世界は滅びるかもしれない、と思うのです。いろんな場所にある発電所のことを思いますと、想定外の地震とか想定外の津波とか想定外の戦争とか、悪いことが重なればそれでまた世界が滅びるかもしれない。少なくともひとつの国が滅びるくらいのことは十分起こるかもしれない。そういう滅亡のための道具を人間はいつの間にか、自分の手でたくさん作ってしまいました。ところが私どもの誰よりも楽観的であられる主イエスが言い切っておられることは、人間が世界を滅ぼすことはないということです。「よく言っておく。これらのことがみな起こるまでは、この時代は決して滅びない」。すべてのことを手の内に握っておられるのは神です。神以外の誰も、天地を滅ぼす力を持ってはいません。人間が意図的に世界を滅ぼそうとしても、きっとできないだろうと思います。すべての時を定めておられるのはただひとり、神。
■その神のみ旨に従って、しかしいつか必ず、「天地が滅びる」ということが起こります。それがその次の31節です。「天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない」。私どもの信仰に従って言えば、天地をお造りになったのは神です。神が天地万物のすべてを無からお造りになったし、今も神がこの世界を守り、保持しておられる。「我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず」。言ってみればその信仰を裏返しにして言い表したのが、「天地は滅びる」という、この言葉です。天地は、放っておいても自然に滅びるのではありません。神が滅ぼされる。そしてそのときに、滅びてはならないものをお残しになって、「これと、これと、これは滅ぼしてはならない」と、そのことをお決めになるのも神です。そのことを知っている人間は、この世のものならぬ望みを持つことになるだろうと思いますが、そこでもうひとつ不思議なのは、「天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない」と言われていることです。
なぜ、「私の言葉は滅びない」と言われるのでしょうか。なぜ「言葉」なのでしょうか。「天地は滅びるが、わたしは神の子だから滅びない」と言われてもよかったような気がしますし、ついでに、「あなたがたも滅びないよ」と言ってくれたらいちばんありがたかったかもしれませんが、そうではなくて、「私の〈言葉〉は滅びない」と言われます。
主イエスはそこでも、私ども教会のことを思いやってくださったのだと思うのです。今は冬なのです。夏が来ることはわかっているのですが、まだまだ冬は厳しいのです。しかし、というよりもだからこそ、私どもは主イエス・キリストの言葉を聞きます。冬の寒さの中で……今日繰り返してきましたように、いろんな冬の寒さがあるでしょう。その冬の寒さは、時に私どもをいくらでも絶望させるほどの厳しいものがあるのであって、それでもそのあとに夏が来るという望みに生きるためには、偽物の望みでは役に立ちません。天地が滅びても滅びることのない、まことの望みでなければなりません。そのために、教会は主イエス・キリストの言葉を聞きます。このお方の約束だけを聴き続けるのです。天地が滅びても、あなたは、ただわたしの言葉にとどまっていればよい。教会に与えられた、望みの言葉であります。
■そこで最後に32節であります。しかしこの言葉は、ある意味で意表を突かれるところがあったかもしれません。「その日、その時は、誰も知らない」と言われます。最終的に主イエスが来られる望みの日、救いの日、いちじくの木の譬えで言えば夏の到来がいつであるのか、「その日、その時は、誰も知らない。天使たちも子も知らない」。つまり、神のみ子イエスご自身もそれを知らないと言われたのです。イエスさまもご存じないなんて、そんなばかな、そんな頼りない話があるかと文句を言っても始まりません。むしろここで主イエスは、父なる神への徹底的な信頼を言い表しておられるのだと思います。「天使たちも子も知らない。父だけがご存じである」。天地を造られたのは父なる神、そして天地の終わりの時を定めておられるのも父なる神。その父なる神への信頼を言い表しながら、既に主イエスは、第14章以降に始まるご自身の十字架の苦しみのことを、忘れてはおられなかったと思います。
「天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない」。なぜ主イエスはそこで、「私の言葉は」と言われたのでしょうか。なぜ「わたしは滅びない」と言われなかったのだろうか、と先ほど申しましたが、主イエスご自身、自分がほどなく十字架で殺されること、滅ぼされることを、その父なる神のみ旨を見つめておられたと思います。この次の第14章で、主イエスはゲツセマネという場所で徹夜の祈りをなさいます。十字架の苦しみを見つめながら、死ぬほどに苦しみ悩みながら、「父よ、なぜわたしがこんなに苦しまなければなりませんか」と祈らなければなりませんでした。そしてやがて十字架の上で、「わたしの神よ、わたしの神よ、なぜわたしをお見捨てになったのですか」と、叫ばなければなりませんでした。そういう演技をなさったんじゃないんです。本当に、主イエスは神に見捨てられたのです。本当の絶望を味わわれたのです。
「その日、その時は、誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存じである」と主イエスは言われました。そのわたしの父が、なぜわたしをお見捨てになるのか、わたしも知らない。父だけがご存じである。その先に何が待っているのか、実は正確なところはわたしも知らない。十字架という滅びの先に、必ず命の季節が来ることはわかっているけれども、それがいつなのかはわたしも知らない。それでも父なる神のよいみ心を信じようじゃないかと言われた主イエスの心は、まさしくあのゲツセマネの祈りに重なるものだと私は思うのです。
しかもそこに、私どもの祈りがまた重なるのです。「その日、その時は、誰も知らない。天使たちも子も知らない」。もちろん、私たちも知らないのです。よく考えると、こんなに厳しい話はないかもしれません。私どもも、夏の到来を待っているのです。今がどんなに厳しい冬であっても、夏は必ず来る。しかし神よ、それはいつなのですか。いつまで待たなければなりませんか。「天使たちも子も知らない」。しかし、「父だけがご存じである」。
■今週の木曜日にも例会がありますが、ハナミズキの会という集まりで、祈りについての学びを続けています。『聖書の祈り31』という、私も半分関わっている小さな書物を一章ずつ読んでいます。年齢、性別を問わず、ひとりでも多くの方に来ていただきたい集会のひとつです。今週の例会では、旧約学者の大島先生のお書きになった詩編第13篇についての文章を読みます。
いつまでですか、主よ。
私をとこしえにお忘れになるのですか。
いつまで御顔を隠されるのですか。(2節)
この「いつまでですか」という祈りは、詩編の中で際立っているものだと思います。「いつまでですか」。その「いつ」がわからないから、「いつまでですか」と祈るのです。そういう祈りを絶え間なく続けるためには、たいへんな忍耐が求められるだろうと思います。私どもは、すべての時を知らないのです。いつ終わると知れない労苦の中で、戦争、地震、飢饉、いろんな苦しみの中で、詩編は私どもに祈ることを教えます。「いつまでですか、主よ」。主よ、寒くて死にそうです。夏はいつ来るのですか。
「その日、その時は、誰も知らない。天使たちも子も知らない」。しかし神よ、わたしの父よ、あなたはご存じですね。しかし、それはいつですか。いつまで、私どもは待たなければなりませんか。いつまで冬は続くのですか。そのような祈りの背後にあるのは、時が来れば必ず神の救いが来るという、深い信頼だと思います。深い信頼をもって、だからこそそれだけ切実に祈るのです。「主よ、いつまでですか」。
そこで忘れてはならないことは、もう一度申します、私どもの救い主がこのような切実な祈りをしなければならなかったという事実です。「天地は滅びる」と主イエスは言われました。自然に滅びるのではありません。私どもの罪が生む滅びです。神に滅ぼされなければ、どうしようもないこの世界なのです。その滅びの現実を一身に背負われるように、これから主イエスは十字架につけられる。そこでも主イエスは祈られたのです。「わたしの神よ、わたしの神よ、なぜわたしをお見捨てになったのですか」。「枝が柔らかくなり、葉が出て来ると、夏の近いことが分かる」。「しかし、父よ、いつまで待たなければなりませんか」。私どもは、しかし今はその祈りを、望みをもってすることができる。主イエス・キリストのお甦りこそ、その望みの、確かな根拠なのです。
私どもは、まだ冬の寒さに耐えなければなりません。このマルコによる福音書を読んだ最初の教会も、身を寄せ合うようにして、もしかしたら地下にもぐって迫害を避けながら礼拝を続けたのです。その教会をなお支え続けたのは、「主はお甦りになった」という約束の言葉です。その言葉は、天地が滅びても、決して滅びない。この決して滅びない言葉に支えられて、教会は立つ。この鎌倉雪ノ下教会も立つのです。そこに生まれる望みの祈りを、今ひとつに合わせたいと願います。お祈りをいたします。
父よ、あなただけが、すべてをご存じです。すべての時を握っておられるのも、私どもの父よ、あなただけです。冬の寒さの中で、主よ、いつまでですかと祈り続けることは、やはり時に決して容易なことではありません。耐える力を与えてください。望みを見失うことがありませんように。そのために何よりも、み言葉を聴き続けることができますように。主のみ名によって祈り願います。アーメン