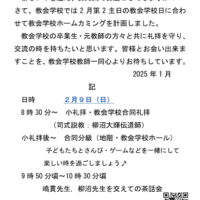空っぽになった墓
ルカによる福音書第24章1―12節
川﨑 公平

主日礼拝
主イエスが十字架の上で息を引き取られ、墓に葬られた翌々日、女性たちが主イエスの墓を訪ねました。準備していた香料を主イエスの遺体に塗り、その腐敗を少しでも遅らせようと考えていました。ところが墓に着くと、墓穴を塞いであった大きな石が、墓のわきに転がしてあり、中はもぬけの空でした。これは既にそれだけで、この女性たちにとって恐ろしい経験であったと思います。この空の墓を、しかし、神の言葉が満たしました。
「なぜ、生きておられる方を死者の中に捜すのか。あの方は、ここにはおられない。復活なさったのだ」。
カール・バルトという神学者が、このような言葉を書きました。私の大好きな言葉です。
石は墓の入り口から取りのけられた。そして、言葉が流れ出す。
死に勝つ神の言葉。歴史の中で、一度も語られたことのない言葉です。まさにここに、ルカによる福音書がまず大切にしたことがあったと思います。墓から、〈新しい言葉〉が生まれたのです。だからこそ、「そこで、婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして、墓から帰って、十一人とほかの人皆に一部始終を知らせた」(8―9節)のです。マルティン・ルターは、この女性たちこそ〈最初の説教者〉だと呼びました。「イエスの言葉を思い出し」、そしてその言葉を他の仲間たちにも伝えたのです。「あの方は、墓にはおられなかった。主イエスは、お甦りになった」。この〈新しい言葉〉によって、教会の歴史は始まりました。
もちろん主イエスは、言葉だけ、口先だけで復活なさったなんてことはないのであって、このあと実際に肉体を持ったお姿をいろんな人に現してくださいました。そのような復活の主イエスとの出会いから、教会の歩みが始まったとも言えるのです。たとえばこの先、13節以下に記される、エマオという村への途上で起こった出来事がそうです。しかしそこでも、主イエスが目の前におられたのに、ふたりの弟子はまったく気づかなかった。そのふたりに主イエスが聖書を説き明かしてくださって、そののち初めて、主のお姿に気づいた。しかも気づいたときには、その瞬間に、主のお姿は見えなくなったといいます。その意味では、このふたりにとっても決定的なことは、主イエスの体に触れたということ以上に、主の言葉を聴かせていただき、悟らせていただいたということであったのです。
ここに、私どもの教会の歩みを決定的に定める、大切なことが教えられていると思います。今、私どもの教会が何によって生かされているのか、ということです。最初に墓を訪ねた婦人たちは、主イエスの〈言葉〉を思い出したのです。その〈言葉〉を、他の仲間たちに伝えたのです。「石は墓の入り口から取りのけられた。そして、言葉が流れ出す」。今私どもも、その〈言葉〉を聴いているのです。
先週、今日の説教の準備とは関係なく、何気なくヨハネによる福音書についての書物を読んで、とても興味深い文章に出会いました。ヨハネによる福音書は、こういう言葉で始まっています。「初めに言(ことば)があった。言は神と共にあった。言は神であった」。とても不思議な表現です。この「ことば」とはいったい何か。その書物のややこしい議論はいっさい省略して、結論を言うと、この「ことば」とは愛のことだと言います。
ところで、この「ことば」とはイエス・キリストのことだ、という説明をお聴きになったことがあるかもしれません。もちろんその通りです。この学者も、それ以外に読みようがないと言います。しかし、もしそうなら、なぜ主イエスのことを「ことば」と呼んでいるのか、そのことを問わないわけにはいかないでしょう。この学者は、端的に、最初に言葉があったのだ。最後まで残るのも言葉なのだと言います。もちろんこの言葉とは、神の言葉、神の語りかけです。それをこの学者は、愛と言い換えてみせます。「愛とは、語りかけること」。「ちなみに、憎しみは語りかけるのではなく、脅すのである」という印象的な文章がそれに添えられます。
初めに愛があった。愛は、神と共にあった。この愛は、まさしく神であった。神と愛と、愛と言葉とは、不可分なものだ。その愛が、「肉となって、わたしたちの間に宿られた」(ヨハネ1・14)と言います。神の愛は、肉を取らざるを得なかった。私どもを愛するためであります。肉となって、わたしたちの間に宿られた神の愛。それがイエスというお方です。
息子が一歳半になりました。ちょうどその日付が祝日にあたりましたので、私ども夫婦も、さあ、今日は息子のために何をしてやろうかな、などと思っていたのですが、そういう日に限ってまた熱を出しました。むずかってなかなか寝付けない。やっと寝たと思ったら、また泣き出したりする。そんな息子を抱っこしたり、添い寝をしたりしながら、「ほーら、お父さんいっしょだよ、だいじょうぶだよ」などと、柄にもないことを申します。そんな休日を過ごしながら、「初めに言があった」「初めに、愛があった」。この不思議な聖書の言葉をかみしめておりました。神が私どもを愛して、「ほら、お父さんだよ。お前と一緒だよ」。この神の言葉が、肉となって、わたしたちの間に宿られた。そのお方が、ヨセフとマリアの子として育ち、遂に十字架につけられ、そしてこの肉が、お甦りになったのです。
墓の中に、神の言葉が響きます。神の愛が響きます。「なぜ、生きておられる方を死者の中に捜すのか。あの方は、ここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられたころ、お話しになったことを思い出しなさい」。神の愛は、死んではいない。あなたがたは、既にあのお方の言葉を聴いたではないか。なぜそれを思い出さないか。なぜあなたがたは、生きておられる方を死者の中に捜すような愚を犯すのか。あなたがたが来るべき場所はここではない。出て行きなさい。
彼女たちは、出て行きました。「そして、墓から帰って、十一人とほかの人皆に一部始終を知らせた」(九節)。まさに、最初の説教者になったのです。
先週、今年度最初の教会総会が行われました。「ひとりひとりが伝道者・説教者」という主題を掲げました。しかし、どうも分かりにくいという質問が出ました。確かにその通りだと思います。だいたい、「説教」という日本語のニュアンスがあまり芳しくないところがあると、私も率直に言ってそう思います。
しかし説教というのは、「主イエスはお甦りになった」という事実を、神の愛の事実として告げる言葉です。説教とは、いろんなことを語っているようで、けれども結局のところ、ひとつの事実に根ざす言葉でしかないのです。「イエスはお甦りになった」。世にも不思議な怪奇現象が起こったとか、そんな話ではありません。主イエスのお甦りは、神の愛の出来事でしかなかったのです。
この神の愛の出来事を最初に語り始めたのが、この女性たちでした。私どもひとりひとりが、同じ務めに生かされているのです。
私がひとつ気にかかっていることは、〈言葉〉という言葉が既に、悪いニュアンスを持ちかねないということです。不言実行などとも言います。確かに口先だけでは意味がありません。けれども、神の愛が口先だけの愛であったことは一度もありません。神の言葉は、肉となって、私どもの間に宿ってくださったのです。
ここに出てくる婦人たちは、ある意味では誰よりも、そのような神の愛を近くで経験したとも言えるのです。この婦人たちは第二三章五五節によれば、「イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たち」です。第八章になお詳しい紹介がありますが、主イエスの身の周りの世話をしながら共に旅を続けた女性たちです。汚れた衣服を洗濯したり、食事の準備をしたり、忙しく働きながら、この女性たちは、主イエスの言葉を聴き続けたのです。そのような生活を続けながら、この女性たちは、既に感じ取っていたと思います。「わたしは、わたしたちは、このお方に愛されている」。「神が、わたしを愛してくださるのだ」。まさに、神の愛が肉となって、わたしたちの間に宿られた。この女性たちが身をもって経験したことは、そのようなことでした。
だからこそ、他の男の弟子たちが皆姿を消してしまったようなところでも、この女性たちはなお踏みとどまって、主の十字架のもとに立ち、その葬りにも立ち会い、そして復活の朝には、さあ、わたしたちの最後の奉仕をしようと言って、墓を訪ねたのです。
けれども、この女性たちは肝心なことを忘れていた。それを天使が思い出させてくれました。ルカによる福音書の復活の記事の特色は、「思い出す」という言葉が繰り返し用いられていることです。
「まだガリラヤにおられたころ、お話しになったことを思い出しなさい。人の子は必ず、罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっている、と言われたではないか」。そこで、婦人たちはイエスの言葉を思い出した。
この女性たちは、主イエスの言葉と共に、主イエスと共にした生活を思い出したと思います。そこで知った、主の愛を思い出したに違いないのです。
この「思い出す」という言葉は、教会の歴史の中で大切な意味を持つようになりました。特に教会の礼拝、とりわけ聖餐を論じるときに、この言葉が大切な意味を持ちます。礼拝とは、聖餐とは、思い起こすべきことを思い起こす行為なのです。聖餐の際に、「これは、あなたがたのためのわたしの体である。わたしの記念としてこのように行いなさい」という聖書の言葉を読みます。「わたしの記念として」。「わたしを思い出すために」ということです。主の愛を思い出すのです。
なぜ思い出さなければならないのか。私どもが忘れっぽいからです。この女性たちと一緒です。他の誰よりも主イエスを愛していたかに思われた女性たちでしたけれども、その主に対する愛は、肝心なところで勘違いをした愛でしかなかった。けれども、神の天使がこの女性たちのそばに立ち、思い起こすべき言葉を思い起こさせてくれました。そして、語るべき言葉を語ることができるようになりました。
「復活節の疑い」という言葉があります。こういう言葉をお聴きになって、どういうことをお考えになるでしょうか。そうだ、確かにキリストの復活などと言われても、どうも信じにくい。疑いをぬぐい切れない。けれども、この言葉の意味はまったく逆で、「死の力を疑う」という意味なのです。空っぽになった主の墓の前に立ち、思い出すべきことを思い出すとき、私どもは、今まで一度も疑ったことのないことを疑い始めます。
この女性たちもそうだったと思うのです。なぜ天使に言われるまで思い出さなかったかというと、それだけ深く、彼女たちが死を信じていたからでしょう。死の力に対して、絶対的な信頼の思いを抱いてしまっているということでしょう。この女性たちが、さあ、イエスさまの死体を何とかしようと早起きしたのも、遺体に塗るための香料まで用意していたということも、すべて死を信じて疑わない者の姿でしかなかったのです。
けれども、石が墓の入り口から取りのけられ、そこから新しい言葉が流れ出すとき、私どもは、死の力を疑い始めます。それを「復活節の疑い」という言葉で呼んできたのです。
それと合わせて、「復活祭の笑い」という言葉があります。そういう決まり文句がある、というだけでなく、実際に礼拝の中で、大きな声で笑うという伝統が生まれたこともあったそうです。それは、主イエスがお甦りになった、その喜びを表すということもあったでしょうけれども、もうひとつ、死の力をあざ笑うというニュアンスでも理解されてきたところがあったようです。これまで私どもが恐れ、敬い、その絶対的な力を信じ込んでいた死の力。けれども神は、死の力を骨抜きにしてしまったではないか。そのことを信じて、死の力をあざ笑うのです。
ある人が、こういうことを言いました。「ここに現れた天使たちもまた、婦人たちをあざ笑っている」。生きている人を探しに、墓を訪ねて、手には何の役にも立ちやしない香料をしっかり握りしめて。その婦人たちを、笑い飛ばすように天使は言ったのです。「それ、いったい、何? 生きている人が墓にいるはずないだろう?」 必死な思いで主イエスを愛し抜いた女性たちにとっては、ちょっときつい聖書の読み方かもしれません。しかし、そこにどんなに深い慰めが込められていることか。この女性たちも、おそらく死ぬまでこのときのことを語り続けたと私は思います。「ほんと、わたしたち、ばかだったわね」などと笑いながら、死をも笑い飛ばすことのできる、したたかな神の愛の勝利を告げ続けたと思います。
このような〈言葉〉が、墓の中から流れ出て、今私どもひとりひとりを生かしています。その事実が既に、神のいのちの奇跡なのです。
(五月三日 礼拝説教より)