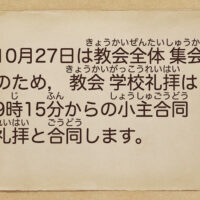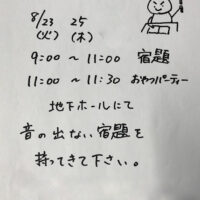主イエスはあなたの家に
川崎 公平
マルコによる福音書 第1章29-39節

主日礼拝
■まだ少し気が早いようですが、今年もクリスマスが近づいてきました。そのようなタイミングで、先週の長老会でいくつか大きなことを決めました。ひとつは、12月24日土曜日の夜に、3年ぶりにクリスマス讃美礼拝をこの場所で行います。みんなで大きな声で、のどが疲れ果てるほど讃美歌を歌うというわけにはいかないと思いますが、とにかくこの場所に集まって、クリスマスの祝いをしようということになりました。それからもうひとつ、12月から日曜日の朝の礼拝において、讃美歌を歌います。もちろんあまりに感染状況が厳しくなったら、また考え直さなければならないかもしれませんが、とにかく少しずつ歌い始めようということで、説教のあとの讃美歌を1節のみ歌います。それは私にとってもたいへんうれしい決断でしたから、長老会の翌月曜日にはさっそく、12月の礼拝で歌う讃美歌を決めました。自分の部屋で讃美歌集をめくりながら、クリスマスの讃美歌を小さな声で口ずさみながら、「ああ、こんな歌もあったな、この歌も歌いたいな」と、何だか懐かしい思いで、ひとりクリスマス気分に浸っておりました。
そんなことをしながら、改めて思わされたことがあります。クリスマスというのは、闇の中に光が輝いた出来事です。徹夜で羊の番をしていた羊飼いを天からの光が取り囲み、あるいは不思議な星が東の国の博士たちを導いたというように、聖書が既に、闇の中に輝く光というイメージで神の御子のご降誕を象徴的に伝えてくれますし、特にクリスマスの讃美歌を歌っておりますと、ますますその思いを深くいたします。「きよしこのよる 星はひかり」という、誰もが知っているフレーズを歌うだけでも、闇の中に輝いたあの光が、私どもにとってどんなに慕わしいものか、どんなに確かな希望を与えてくれるものか、よく分かると思います。
先週、いつになくたくさんのクリスマスの讃美歌をひとりで振り返りながら、少しおかしな感想かもしれませんけれども、たいへんさびしい気持ちになりました。クリスマスというのが、もともと夜の闇と深く結びついたイメージを持つからかもしれません。暗闇の中に、光が輝いたのです。しかしそれは裏を返せば、もしも神がこのクリスマスの光を灯してくださらなかったら、どうしようもない闇があったということであります。
こんなことを言うのは、まだ少し気が早いようですが、この1年の間にもいろんなことがありました。疫病があり、戦争があり、それでも私どもは、望みを捨てることなく、この教会の歩みを皆で作ってきました。神が灯してくださった光を見つめながら、それどころか「あなたがたは世の光である」(マタイによる福音書第5章13節)と言われた主イエスの言葉を信じて、私ども自身が光となって、この礼拝の生活を続けてきたのです。それは、日曜日の朝、この場所に来れば、その時間だけはいろんな暗いことを忘れることができる、つらいことから逃れることができるということではありません。本気でそんなことを夢見ている人はまずいないだろうと思います。むしろ、神を信じている人間は、ほかの誰よりも深くこの世の闇を知っているかもしれません。神を礼拝する生活をしているがゆえに、私どもはますます深く、人間の罪が作ってしまっている闇の深刻さに気付かなければならないかもしれないのです。だがしかし、その闇の中に、光が輝いたのです。
■マルコによる福音書を読みながら、私どもの礼拝の生活を続けております。マルコによる福音書というのは、ひとつの言い方をすれば、クリスマスの出来事を一切語らない唯一の福音書です。けれども、神の御子イエスがこの世に来られたことによって、神がこの世界に確かな光を灯してくださった、その光を見つめることにおいて、他の福音書に劣るところはひとつもありません。少し前置きが長くなりすぎたようですが、今朝まず皆さんと一緒に思いを集めたいのは、35節の主イエスの祈りの姿です。
朝早くまだ暗いうちに、イエスは起きて、人里離れた所へ出て行き、そこで祈っておられた。
いったい、何を祈っておられたのでしょうか。それは、今朝の礼拝の中で少しずつ明らかにしていきたいと思います。福音書を書いたマルコは、深い思いを込めて、この主イエスの祈りの姿を書き留めたと思います。この人を見よ。この光を見よ。この主イエスの祈りに、世界の運命がかかっていると言っても過言ではないのです。
「朝早くまだ暗いうちに、イエスは起きて」と書いてあります。ぼんやり読んでいると、朝早く、空が次第に白んでくるような情景を思い浮かべそうですが、そうは読めないのです。はっきりと「まだ暗いうちに」と書いてあります。直訳すると「朝早く、夜のうちに」という、「朝なのか夜なのか、はっきりしろ」と言いたくなるような表現なのですが、午前3時とか4時とか、そんな感じでしょう。ここでマルコが明確に伝えていることは、これが闇の中での祈りであったということです。朝の光の中での祈りではありません。完全な闇が主イエスを取り囲んでいる。そのようなところでなされた祈りです。
いったい、主イエスは何を祈っておられたのでしょうか。これは主イエスだけの祈りであって、弟子たちにもその祈りの場所や時間や内容は秘密であったようです。それは36節や37節に書いてあるように、弟子たちが主イエスを捜し回らなければならなかったことからも分かります。真っ暗闇の中、主イエスはひとり、人里離れた所まで歩いて行かれました。そしてそこで祈りをなさりながら、主イエスはじっと、その闇の深さを見つめておられたと思います。肉眼で見える暗闇ではなくて、神の御子キリストのまなざしをもって初めて見えてくる闇を見つめながら、ひとり祈っておられる。そのこと自体が、既に確かな光を宿した出来事であると言わなければならないと思うのです。
■ところが、今申しましたように、弟子たちが主イエスのあとを追ってきました。36節には「シモンとその仲間は」と書いてありますが、このシモンとは、のちにペトロというあだ名で呼ばれるようになった主イエスの一番弟子です。29節にも書いてあったように、主イエスは少なくともその日は、シモンとその兄弟アンデレの家に厄介になっておられました。ところが、シモンが朝起きると、昨夜にはいたはずのイエスさまがいない。慌てて仲間たちと手分けして捜し回って、遂に主イエスの祈りの秘密の場所を捜し当てて、「みんなが捜しています」と言いました。
なぜそんなに慌てて主イエスを捜し回ったのか、その理由もこの箇所を読めばすぐに分かります。カファルナウムという村の名前が21節に書いてありましたが、主イエスは前の日からそのカファルナウムという村においでになり、安息日の会堂の礼拝で悪霊につかれた男を癒やし、またシモン・ペトロのしゅうとめの熱病を癒やし、さらに村中の病んだ人たち、悩んでいる人たち、苦しんでいる人たちの癒やしのために、寝る間も惜しんで働いてくださったというのですが、朝になってみるとそのお方がおられない。慌てて捜すのは当然です。
きっと誰だって、同じように考えるだろうと思います。「みんなが捜しています」。こんなところで、何をしておられるんですか。こんな人里離れた所でお祈りなんかしている場合ではないでしょう。わたしの村には、たくさん悩んでいる人がいるんです。苦しんでいる人がいるんです。だから、早く戻って来てください。あなたのいるべき場所はここではありません。わたしの家に帰って来てください。それが、神の子イエスの使命でしょう? 「みんなが捜しています」というシモン・ペトロの言葉には、明らかに批判めいた響きがあります。そして、私どももきっと、同じように考えるのです。イエスさま、そんなところでお祈りなんかしていないで、わたしを助けてください。わたしのところに来てください。まるで主イエスがどこにいるべきか、何をすべきか、自分の方がずっとよく分かっているのだと言わんばかりです。けれどもそれは、なぜ主イエスが暗闇の中に立たなければならなかったか、そこでどういう祈りをしなければならなかったか、その主の祈りの内にどんなに確かな光が輝いていたか、何も理解していない人間の言い分でしかないのです。
主イエスにとっては、カファルナウムの村に戻って癒やしの続きをやるよりも、もっと大切なことがありました。闇の中での祈りにおいて、ご自分の進むべき道を見出されたのです。「近くのほかの町や村へ行こう。そこでも、わたしは宣教する。そのためにわたしは出て来たのである」(38節)。考えてみれば、この主イエスの祈りがあり、決断があったからこそ、日本という世界の果てにあるような国にまでキリストの福音は広がってきたのです。もしもこの時の主イエスの祈りがなかったら、私どもは遂に主に出会うことはなかったでしょう。「ほかの町や村へ行こう」。その町や村がどんどん広がって、私どもの教会の105年の歴史もまた、思い返せばあの主イエスの暗闇の中での祈りに支えられたものでしかなかったのであります。
■ここに「人里離れた所」と書いてあります。カファルナウムの村から外れて、人里離れた所まで歩いて行かれたということでしょう。街灯もないのにどうやって歩けたんだろう、何キロくらい歩いたんだろう、というのは愚問でしかありません。大切なことは、これが「人里離れた所」であったということです。ここでひとつ翻訳に注文をつけたいことは、これは既に第1章の12節、13節にも出てきた「荒れ野」とほとんど同じ表現で、ここでも「イエスは荒れ野に出て行き」と訳した方がよかったかもしれません。主が40日間、サタンの誘惑を受け、試練を受けられたという、あの荒れ野であります。ここでも主イエスは荒れ野で、しかも闇の中で悪魔の誘惑を見つめながら、そこで父なる神に祈りをなさりながら、ご自分が何のためにこの世に来られたのかを、見つめ直しておられたに違いないのです。
それこそ聖書のどこかに書いてあったように、悪魔はそのときにも主イエスを誘惑したかもしれません。「お前、昨日はすごかったな。どんどん病気を治して、人びとの悩みを解決してあげて、あっという間にスーパースターじゃないか。まあ、神の国とか神の御心とか、そんなことはどうでもいいから、まずはお前が有名になることだ。そうしたら、救い主の活動もやりやすくなるだろう?」 けれども、主イエスは34節に書いてあるように、「多くの悪霊を追い出して、悪霊にものを言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからである」。つまり、主イエスご自身は、自分が有名になろう、自分の偉さを見せつけようとして奇跡をなさったことは一度もなかったのです。むしろ、ご自分の正体をいちばんよく知っている悪霊に対して、これを誰かに宣伝することを厳しく禁じられた。そしてここでも、悪魔の誘惑を振り切るようにして、暗闇の中にひとり立ち、その祈りの内に、カファルナウムを出て行く決断をなさったのです。
ここで主イエスの祈りの場所を遂に捜し当てた、シモンをはじめとする弟子たちは、のちにもう一度、暗闇の中で祈る主イエスのお姿を目撃することになります。十字架につけられる前の晩、ゲツセマネの園という主イエスの祈りの場所に、今度はシモンたちも最初から招かれます。そしてそこで、血の滴りのように汗を流して、十字架のことを思って苦しみもだえながらも、神よ、どうかあなたの御心を行ってくださいと祈る主のお姿には、スーパースターの片鱗もありません。誰がどこからどう見たって、世界でいちばん惨めな人間が闇の中で呻いているようにしか見えなかっただろうと思います。だがしかし、私どもは知っております。まさにあのゲツセマネの祈りに、世界の救いが丸ごとかかっているのです。まさにあの場所において、闇の中に光が輝いたのです。しかし、そのゲツセマネの祈りは、実は、あのカファルナウムでの丑三つ時の祈りにおいて、既に始まっていたのです。
その祈りの内に、主イエスは決断をなさいました。「ほかの町や村へ行こう」。悪魔の誘惑を振り切って、そう言われたのです。もとよりイエスは、カファルナウムの人たちの悩みなんか別にどうでもいいと考えておられたわけではありません。ほとんどひと晩中、カファルナウムに住む人たちの悩みに向かい合いながら、そのひとりひとりのために、深い憐れみの心を込めて、癒やしをなさったに違いありません。そのときにも、既に主イエスはひそかに闇の中に立ち、祈りを続けておられたと思います。自分がここにいることの意味を、問うておられたと思います。しかもその主イエスの祈りの中に、既にわたしのことも覚えられていたのだと、そのことに気づくべきなのです。その上での決断であります。「ほかの町や村に行こう。そこでも、わたしは宣教する。そのためにわたしは出て来たのである」。
その主イエスに従う者として、ここに出てくるシモンもアンデレも、ヤコブもヨハネも主に召されました。神の国の広がりの、そのお手伝いをするために、主イエスに従う者とされて、のちに教会の使徒と呼ばれるようになりました。キリストの命を受けて伝道に励み、教会がどんどん広がって行く様子を見たときにも、この弟子たちが絶えず思い起こしたに違いないのは、あのカファルナウムの村はずれで祈っておられた主のお姿であったと思います。「ほかの町や村に行こう」と主が言われた町や村が、こんなに遠くまで広がってしまった。この鎌倉の町に立つ教会のことも、主イエスは最初から祈っていてくださったのだということを、今私どもは感動をもって思い起こすことができると思います。そうであるならば、私どももまた、主イエスの真似をするように、今新しい祈りを始め、その祈りに根ざす伝道に励まなければならないだろうと思うのです。
■ここに出てくるシモン・ペトロも、主イエスの真似をして朝に夜に祈ることを覚えたと思います。そのペトロの祈りをいつも支えているのは、あの暗闇に立ってくださった主イエスの祈りである。あの暗闇の中で、あの人のことも、この人のことも、既に覚えられていたのだ。主が祈っていてくださったのだ。そのことを信じていなかったら、伝道なんて怖くてできないでしょう。
このペトロにとって、もうひとつ忘れられないエピソードが、29節以下にささやかに記されています。「すぐに、一行は会堂を出て、シモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった」(29節)とさりげなく書いてありますが、彼らにとっては心臓が破裂しそうな思いであったと思います。なぜかと言うと、16節以下の段落を読むと、彼らはガリラヤの湖で漁師の仕事をしていた真っ最中に、突然主イエスに「わたしについて来なさい」と声をかけられて、すぐについて行ったのです。家族も捨てて、仕事も捨てて、もちろん家族に報告、連絡、相談など一切なしです。しかし、ここまで激しい形でなくても、キリストを信じることによって家族との間に何らかの亀裂が入るという経験は、多くの人の知るところかもしれません。
ところが、ここではそのシモンの家に帰って行くのです。私の想像ですが、安息日の会堂での礼拝が終わったあとで、まず主イエスが切り出されたのだと思います。シモン、この村にお前の家があるだろう。わたしたちを連れて行ってくれ。シモンはちょっと困ったかもしれません。いったい、どの面下げて家に帰ればいいのか。しかも家に帰ってみると、間の悪いことに、しゅうとめが熱を出して床に臥せっていたと言います。帰るなり、シモンは奥さんに怒鳴られたかもしれません。「どこに行っていたの! お母さんが病気なのよ!」 ところが、「イエスがそばに行き、手を取って起こされると、熱は去り、彼女は一同をもてなした」(31節)。
また少しややこしい語学的な話をすると、この「もてなした」と訳されているところは、「もてなすようになった」、あるいは「仕えるようになった」と訳した方がよいようです。この日、この時、一回だけもてなしたというのではなくて、繰り返しもてなし続けた、仕え続けた。そういう特殊なものの言い方がギリシア語にはあるのです。このとき以来、シモンのしゅうとめは、主イエスが家に来られるたびに、いつも主にお仕えした。これは推測でしかありません。しかしもっと確かなことは、シモンのしゅうとめの娘、つまりシモンの妻もまた、教会に生きるようになったということです。コリントの信徒への手紙Ⅰの第9章5節には、やや間接的な表現ですが、明らかにシモン・ペトロは信者である妻を連れて伝道していたことが記されています。そのシモンの妻も、最初はたいへんなショックを受けたかもしれません。夫が突然仕事を辞めて、イエスとかいう人について行って、いったいどういうことかと思ったに違いない。しかしいつしか、主イエスを神の子キリストと信じ受け入れて、教会に生きる者とされました。しかし今思えば、あの闇の中での祈りの内に、主イエスはシモンのためにも、その家族のためにも祈っていてくださったのです。
皆さんの多くが、まだ一緒に礼拝をしてくれない家族のことをどこかで思いながら、今ここで礼拝をしておられると思います。しかし、私どもがそのように祈りに覚えている家族、いや、あるいは既にあきらめてしまっている家族、私どもが忘れてしまっている家族のことを、実は最初から主イエスが顧みていてくださるということは、本当に幸いなことだと思います。
ある学者が、こういうことを書いています。キリストがシモンのしゅうとめの熱を癒やしてくださったというこの出来事は、聖書に記されている奇跡の中でも、いちばん小さなものである。しかし、だからこそこれは実際に起こったこと、作り話ではなくて本当に起こったことだと確信することができる。つまり、作り話でも何でもいいから、イエスさまのすごさをアピールする話を書こうと思ったら、こんな地味な話を書くはずはないと言うのです。学者というのは、しばしばそういう妙な議論をするのですが、私は妙に納得してしまいました。本当にそうだ。そしてこの聖書の中でもいちばん小さな奇跡は、しかしシモンの家族にとっては、記念碑的な出来事になったに違いありません。わたしたち家族の救いは、あそこから始まったのだ。人が見れば、本当にささやかな出来事でしかなかったかもしれません。けれどもその小さな出来事の背後にも、どんなに確かな主イエスの祈りがあったことかと思うのです。そのために、主イエスは人となり、闇の中に立ってくださいました。闇の中に、光が輝いたのです。そのことを知るとき、私どもはこの世界についても、また私どもの家族についても、確かな望みを持つことができるのです。お祈りをいたします。
主イエス・キリストの父なる御神、主がほかの町に行こうと言われたその場所が、この鎌倉の地でもあったことを、私どもの家族のことまで主が覚えていてくださったことを、心より感謝いたします。私どもがどんな闇を見つめるときにも、それに先立って、主がその闇の中に立っていてくださることを信じ抜くことができますように。神の国は近づいた、神がすべてを支配なさるのだと、望みをもって告げ続けることができますように、あなたの教会を今新しく励ましてください。主のみ名によって祈り願います。アーメン