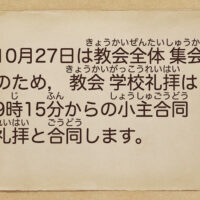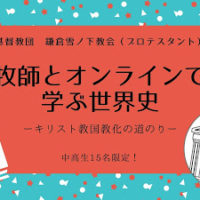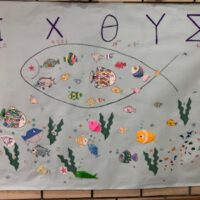友なるイエスよ
ルカによる福音書 第11章5-13節
柳沼 大輝

夕礼拝
これは主イエス・キリストが話された、たとえ話であります。ある人のところに友達が、夜、訪ねて来ました。けっして治安の良くなかった時代であります。中東の一小国で、夜、人の家を訪ねることは非常識なことであったと思います。その友達の家に向かっている途中で追いはぎに襲われるかもしれない。そのまま命を奪われて、野垂れ死ぬかもしれない。きっとこの人には、そのリスクを負ってでも、向かわなければならないような切羽詰まった事情があったのでしょう。もしかしたら住んでいた土地に居られなくなり、そこからまるで逃げ出すように飛び出して来たのかもしれません。
そこで訪ねて来た友人は、パン三つを求めます。このパンは私たちが想像するような小さなパンではありません。ここで言われているパンは、大きなパンであります。数人で一つのパンをちぎって、皆で食べられるほどにかなり大きなパンであります。つまり、この友人には、かなり多くの家族がいたのでしょう。この友人は、その者たちと自分の故郷を捨ててこの国に来ているのかもしれない。ここからかなり切迫した状況を想像することができます。
しかし訪ねられた友人も困り果ててしまいました。なぜなら、彼も同様に貧しいのであります。たくわえがないのです。彼の家に余分なパンなどないのです。一日の終わりに残っているパンなどないのです。彼も家族と今日一日を生きていくのに必死でありました。
そこで、彼はもう一人の友人のところに行きます。夜も更けております。そんな真夜中に、失礼も承知の上で、しかしもうどうすることもできない。そんな藁にもすがる思いで彼の家を訪ねるのであります。
訪ねられたもう一人の友人も当然、当惑し困り果てました。彼は答えます。「面倒をかけないでくれ。もう戸は閉めたし、子どもたちも一緒に寝ている。起きて何かあげることなどできない」。「お前がいま、困っていることは分かる。けれど、もう戸を閉めたのだ。子どもたちも寝ている。やっと私も床に入って休むことができる。だから、お前に対応することはできない。こんな夜中に、お前だって分かるだろう」。そんなふうに、まるで友を諭すように、彼は答えるのであります。
しかし訪ねた彼も後に引くことはできません。彼の背後には、切迫した状況に置かれている友人がいるのです。そして、その背後には、その友の帰りを待つ、飢え弱り果てた大勢の家族がいるのです。「その友人を、その家族を助けたい」。迷惑は分かっているけれど、ここで引き返すわけにはいかない。彼は粘りに粘ります。もう一人の友人に求め続けます。そして彼は、遂に根負けした友人からパンを受け取るのであります。
さて、このたとえ話が言おうとしていることは何でありましょうか。真夜中に、困窮した友人一家から、突然、家を訪ねられたこの彼とは、いったい誰でありましょうか。それは私たち一人ひとりであります。
私たちは、この世に生きています。この世で生きていくということは自分のことだけをしていれば、それでよいというわけにはいきません。私たちは常に誰かと関わりながら生きています。私たちは周りの誰かの命と関わらずに生きてはいけないのです。それは逆に誰かの命に関わることでいまの私の命がここにあるのだ、とそう言うこともできるかもしれません。
しかし、私たちの周りにいる誰か、その誰もが健康で無傷であるというわけにはいきません。当然、困窮し行き詰まり、ときには生死に関わるような切迫した状況に置かれていることもあるでしょう。そんな隣人が、家族が、友人が、突然、あなたの人生に飛び込んで来る。あなたの命に寄りかかってくる。私たちは、願うでありましょう。「その人のためになんとかしてあげたい」「その大切な人を、あの人を助けたい」。
しかし私たちはあの夜、突然、家を訪ねられたあの友人のように、その人のために差し出すパンなど持ち合わせていないのであります。貧しいのです。私たちだって、今日を生きるのに必死なのです。それなのに私たちはその寄りかかってくる命の重さを受け止めようとする。いや、受け止めなければならない。それが生きるしんどさ、重さというものであります。
このたとえ話で主イエスが言おうとしていること、それはこういうことであります。人は人の命に関わって生きています。自分の人生に飛び込んで来るもの、寄りかかってくる命から逃れることはできません。しかし本来、私たちにはその悩みを、痛みを十分に受け止めて、応えるだけの力はないのであります。いくらその人を助けたいと願ってもその痛みを傷をすべてその人に代わって背負ってあげることはできない。主イエスはこのたとえ話を通して、私たちに向けてそのように教えているのです。
そこで、私たちはどうするのか。もう一人の友人のところに行くのです。私のところには人を助けられるパンがないから。人の困窮に応えるだけの力が私にはないから。だから、もう一人の友人のところに行くのです。助けてください、なんとかしてくださいと叫びながら求め続けるのです。そうすると友人はあなたが執拗に求め続けるので、仕方なく応えてくれました。
このたとえ話が伝えていること、それはあなたがたにはもう一人の友人がいるということです。あなたがたには人の悩みや痛みに応えられる力はない。そんなことははっきりしている。しかしあなたがたにはもう一人の友人がいる。その友人に、その友に求めなさい。その友はあなたの叫びに応えてくれる。このたとえ話は、そのように言っているのです。
人間が生きるということは、歯を食いしばって、力を振り絞って必死に生きていれば、それでいつか道が開かれるとは、言っていないのです。そんなこと、私たちには到底できません。人間には限界があります。どんなに自分の力を振り絞って、歯を食いしばって、頑張っていても、いつかは力尽きます。生きるためのパンを失います。しかしそんなとき、私たちには、私たちを助けるもう一人の友人がいるのです。私たちは誰だってその友のところに行くことができるのです。その友に、助けてください、助けてください、と私の心にある思いを、いや、嘆きをぶつけて、求め続けることができるのです。このたとえ話は、私たちにそのように語りかけています。
このたとえ話を話された救い主イエスは、ある時、弟子たちに向かってこのように言われました。「友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。……私はもはや、あなたがたを僕とは呼ばない。……私はあなたがたを友と呼んだ」。(ヨハネによる福音書 第15章13~15節)
私たちが訪ね求めることができるもう一人の友人、それは主イエス・キリストであります。主イエスは、十字架で自らの命を捨ててくださいました。それは神から遠く離れていた罪人たちを、ご自分のもとに招くためでありました。そうして主は、私たちの「友」となってくださった。それは私たちに力があったからではありません。清く正しいものであったからでもありません。けっして、そうではない。なんの力もない。何も持ち合わせていない。生きるためのパンもない。そんな弱く貧しい私たちのために主イエスは「友」となってくださった。私たちを生かすために「命のパン」となって自らの身を差し出してくださった。
そんな「友なるイエス」に私たちはいつだって何度だって、求め続けることができるのであります。「私を助けてください」「私のあの家族を、あの友人を救ってください」と祈り続けることができるのであります。その祈りに、主は大きな愛をもって応えてくださるでありましょう。「友よ、もう一人きりで悩まなくていい。孤独に一人苦しまなくていい。私があなたの罪を赦したから、私がいまあなたと共にいるのだから。恐れるな。安心しろ。私があなたの重荷を共に担おう。」
そうやって、私たちには私の祈りを聞いてくださる「友」がいるのであります。そうやって、向き合って一緒に歩んでくださる「友」がいるのであります。私たちは一人で生きているのではありません。主の命に生かされて、いまここに私の命があるのであります。これが私たちの「祝福」のすべてであります。
この後、讃美歌312番を歌います。この曲の一節の歌詞はこうであります。
いつくしみ深き 友なるイエスは、
罪とが憂いを 取り去りたもう。
こころの嘆きを 包まず述べて、
などかは下さぬ 負える重荷を。
友なるイエスに支えられて、また私たち祝福を受けて隣人の「友」となるべく、ここから出て行きましょう。
友なるイエスよ、私たちの重荷をいまあなたの御前に下ろします。あなたのもとにこそ救いがあります。生きるためのパンがあります。あなたの命に生かされて、今日も祈りつつ、あの隣人と共に歩むことができますように。あなたの愛の心を、聖霊をお与えください。主の御名によって祈ります。アーメン