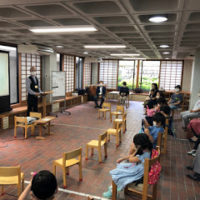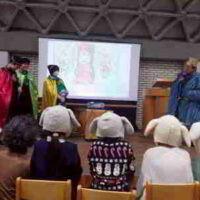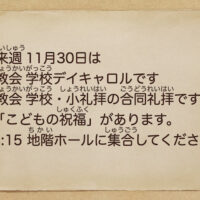信じて生きる人の強さと弱さ
ローマの信徒への手紙 第4章1-3節
川崎 公平

主日礼拝
■先月は伝道月間をはさみまして、1か月ほど間が空きましたが、今朝からまた久しぶりにローマの信徒への手紙の続きを読んでいきたいと思います。今月8月中に私がここに立つ3回の日曜日を用いて、第4章を最後まで読み終わりたいと、一応今のところそういう計画を立てていますが、今朝いきなり予告を変更して最初の3節だけを読むことにしたわけで、計画通り進むかどうか、まだ自分でもわかりません。
この第4章を貫くひとつの主題は、アブラハムというひとりの人物であります。なぜここでアブラハムが登場しなければならないかというと、この直前の第3章の終わり近くに、こういう言葉がありました。「人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、信仰による」(第3章28節)。この手紙を書いたパウロが、結局いちばん言いたかったことはこのことだと言ってよいでしょう。すべては、信仰によるのだ。だから、われわれも、神を信じるんだ。ただ、信じるだけなんだ。しかし信じるって、どういうことなんだろう。信じて生きるって、どういうことなんだろう。そのことを鮮やかに教えてくれるのが、アブラハムという人物なのです。今月、私がここに立つ3回の日曜日、もちろん伝道者パウロの書いたこの手紙を読みながら、しかしまた同時に、旧約聖書創世記の伝えるアブラハムという人の信仰の歩みについて、できる限り丁寧に学んでいきたいと願っています。
■第4章1節に、こう書いてあります。「では、私たちがアブラハムを肉による先祖としていることについては、何と言うべきでしょう」。ここで「私たちが」と言っているのは、この場合、いわゆるユダヤ人の話です。ここでパウロは、もっぱらユダヤ人を相手に論争をしているのです。その論争の内容については、追い追い触れていきたいと思います。とにかくユダヤ人というのは、「アブラハムを肉による先祖としている」のです。
これは考えれば考えるほど、本当に不思議なことだと思います。ユダヤ人というひとつの民族がこの地上に存在しているということ自体が、ひとつの大きな神の出来事なのです。そしてそれがすべて、アブラハムというひとりの先祖にさかのぼる。私どもの翻訳では「先祖」と訳されていますが、ただの先祖ではありません。もっと特別な先祖であって、原文のギリシア語でも少し特別な言葉が使われています。ちなみに、新約聖書の中でこの箇所にしか出てこない言葉です。ある人は「始祖」と訳しました。われわれの先祖は、この人から始まる。神の民イスラエル、われわれユダヤ人の家系の最初に立つのは、アブラハムである。それが、ユダヤ人のユダヤ人たるアイデンティティなのです。このアブラハムの息子がイサク、イサクの息子がヤコブ、このヤコブがまたイスラエルという名を持つようになって、そのヤコブすなわちイスラエルの12人の息子たちが、イスラエルの12部族としてさらに広がっていきました。したがって、ユダヤ人であれば誰でも、先祖をたどって行けば必ずアブラハムに行き着く。そういう意味での「始祖」です。
しかし実は、それだけではまだ説明不十分です。「最初の先祖」というのは、考えてみればおかしな話で、アブラハムにもさらにそのお父さんとお母さんがおり、おじいさんとおばあさんがおり、ひいおじいさんもひいおばあさんもいたでしょう、その人たちはどうした、ということになるわけです。なぜアブラハムが〈最初の先祖〉と言われるのかというと、アブラハムが最初の信仰者だったからです。
今日は創世記の第15章を読みましたが、アブラハムの物語は第12章から始まります。
主はアブラムに言われた。
「あなたは生まれた地と親族、父の家を離れ
私が示す地に行きなさい。
私はあなたを大いなる国民とし、祝福し
あなたの名を大いなるものとする。
あなたは祝福の基となる。 (1、2節)
アブラハムがまだアブラムという名であったときの話です。ある日突然、アブラムは神の声を聴きました。しかもその神の声は、極めて具体的な命令と、約束を含むものでした。「あなたの故郷から出なさい。あなたの行くべきところは、わたしが教える」。それは、繰り返しますが、本当に突然のことでした。アブラムが75歳の時の話であります。ええ? 75歳にもなって、今さら故郷を捨てて出かけなさい、だなんて……なんか、変な夢を見たな、と無視してしまったとしても不思議ではありません。ところがアブラムは、この神の言葉を信じて、その命令と約束を信じて、その通りにしました。神の民イスラエルの歴史は、ここから始まる。その歴史は、最初から信仰の歴史だったのです。
■私どもはアブラハムを「肉による先祖」としているわけではありませんが、それでも私ども教会の信仰の血筋は、さかのぼればアブラハムに行き着くのです。いったい、アブラハムとは、何者なのでしょうか。そのことについて、パウロがいちばん言いたかったことはこれです。パウロが、という言い方は正確ではありません、聖書がアブラハムについていちばん伝えたいことは、このことです。
「アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められた」(3節)。
アブラハムは、神を信じたのです。それが、アブラハムという人間のすべてでした。しかもそれは、アブラハム個人の問題にとどまりません。「アブラハムは神を信じた」という、まさにそこに、全世界の祝福がかかっておりました。
先ほど読みました創世記第15章の6節にも、「アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた」と書いてあります。実はこのとき、最初にアブラハムが神の声を聴いた第12章から、ずいぶん時間が経っております。そのとき、また改めて神の声が聞こえてきたというのです。「恐れるな、アブラムよ。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい」(1節)。けれども、今アブラハムは、そのような神の約束を聴いても、ひとつ納得できないことがありました。それは、自分には子どもがいない、ということでした。神さま、わたしには子どもがいません。そうであれば、あなたがどんなにすばらしいものをくださっても、受け継いでくれる人がいなければ、何の意味もないではないですか。ところが、神は彼を外に連れ出して、「天を見上げて、星を数えることができるなら、数えてみなさい」。「あなたの子孫も、この星の数ほど多くなるだろう」と言われました。それをアブラハムは、そのまま信じたというのですが、これはあまりにも単純な話です。あまりにも単純すぎて、今私どもがこの物語を読んでも、「それがどうした」と言いたくなるかもしれません。しかし、当のアブラハムにとっては、自分の人生が台無しになるか、どうかの問題であったに違いないのです。
かつて、神の約束だけを信じて、故郷を捨てて、旅立ったのです。それからずいぶん時間が経ちました。アブラハムは既に80歳を超えて、妻のサライも70歳を超えて、今なお子どもが与えられないのです。神の約束は、いったいどうなったのだろうか。もしかして、全部噓だったのではないか。かつて自分が故郷を捨てたことも、しかもそれはアブラハムがひとりでしたことではありません、妻のサライ、甥のロトをはじめ、一族郎党を引き連れて……しかし、すべては自分の妄想に過ぎなかったのではないかと考えることは、本当に恐ろしいことだと思います。
■私どもも、日々聖書を読みながら、神の約束を信じて生きているのです。「恐れるな、アブラムよ。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい」というような言葉を、今この自分のための言葉として聞き取ることができる、はずなのですけれども、それができにくいと思うのは、自分の置かれている条件があまりにも悪いと思われるときであります。聖書には確かに、ご立派なことが書いてありますねえ。神の約束、結構じゃないですか。けれども、自分のこの状態が改善されなければ、自分のこの悩みが解決されなければ、どんなに美しい約束だけ聞かされたって、何の意味もないじゃないか、と考えるのです。どんなきれいごとを言われたって、神さま、わたしが今何歳だかご存じですよね? アブラハムが、そう神さまに食って掛かったとしても不思議ではないと思いますし、事実アブラハムは、このことを巡ってみじめな失敗もしているのです。
今日読みました創世記第15章の次の第16章には、こんな話があります。「あなたの子孫は星の数のようになる」との約束をいただいたあとの話であります。アブラハムはその神の約束を信じ、それが義と認められた、そのあとの話であります。遂にアブラハムは、言ってみれば待ちきれなくなって、別の女奴隷と寝て――妻に隠れて、というのではありません、むしろ妻サライにそのことを勧められて――それがうまいこといって子どもを作ることができました。さあ、これでいよいよ、神さまの約束通りになるぞ、と目論んだわけですが、そのことがかえって、アブラハムの家庭に深刻な悩みをもたらすことになります。この女奴隷ハガルは、自分に子どもができたとわかると、正妻たるサライをあからさまに見下すようになります。サライはそれに耐えられず、アブラハムにキレてしまいます。「どうしてわたしがこんなひどい目に遭わなければなりませんか。わたしとあなたと、どっちが悪いのか、神さまに裁いていただきましょうね」。それに対するアブラハムの答えは、本当に卑怯としか言いようのないもので、「いやいや、あの女奴隷は、お前の所有物じゃないか。お前の好きにすればよい」。それでサライは、既に身重になっていた女奴隷ハガルをいじめて、結局のところ家から追い出してしまいます。ちなみに、そのハガルを、主が泉のほとりで慰めてくださったという物語は、数ある聖書の記事の中でも最も美しいものだと思うのですが、その裏にあるアブラハムの歩みは、あまりにも悲惨です。
決してアブラハムは、信仰の英雄ではありません。だからこそローマの信徒への手紙第4章2節では、「もし、彼が行いによって義とされたのであれば、誇ってもよいが、神の前ではそれはできません」と言うのです。アブラハムは、神の前に誇るべきものを何ひとつ持ちませんでした。だからこそ、「アブラハムは神を信じた」のであります。神を信じる以外に、言い換えれば神の約束に頼る以外に、自分の生きるすべはないということが、よくわかっていたのでしょう。だから、信じたのです。
■今朝の説教の題を「信じて生きる者の強さと弱さ」といたしました。先週一週間、毎日教会堂の前を通るたびに、教会のどなたかが書いてくれたこの説教の題が、わたしにも呼び掛けてくれるような思いがいたしました。「信じて生きる者の強さと弱さ」。自分で言うな、と言われてしまうかもしれませんが、「いい言葉だなあ」と思いました。本当にそうだと思うのです。私自身のこととして、そう思うのです。遂にアブラハムに息子イサクが与えられたのは、アブラハムが100歳、サライが90歳の時でした。アブラハムが最初に神の声を聴いてから、実に25年も経っています。その25年の間に、アブラハムはどれだけみじめな失敗を繰り返したことでしょうか。どんなにたくさんの罪を重ねたことでしょうか。そんなアブラハムだったからこそ、アブラハムは、主を信じたのです。私自身のこととして、そう思うのです。
信じて生きるということは、自分の弱さを知ることです。自分の手の中には、何の力もないのです。何もいい条件はないのです。だからこそ、信じるのです。神の恵み以外に、何ひとつ頼るべきよすがを持たないから、だから、ただ信じるのです。そしてそういう人間は、誰よりも弱く、そして誰よりも強い。そのような信仰者の列の先頭に立つのが、アブラハムという人物でありました。
「アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められた」と書いてあります。アブラハムがその立派な信仰によって神さまのおほめにあずかった、という話ではありません。その堅忍不抜の精神がどんなにすばらしかったか、という話ではないのです。聖書に出てくる「義」という言葉に、そんなニュアンスはありません。この「義」という、いささか難解な言葉については、しばらく前にも繰り返し説明を試みましたが、神とのまっすぐな関係のことです。あるいは、そういう正しい関係を、新しく造ってくださる神の正しさのことです。ここでアブラハムが義と認められたと言われるのも、神がアブラハムとの義なる関係を作ってくださったということでしかありません。「アブラハムよ、わたしと一緒に歩もう」。いろんな過ちを犯したアブラハムです。その過ちのゆえに、自分自身も傷を負い、家族にも痛みを負わせ、その信仰においてさえ神に逆らおうとしたアブラハムですが、それでも神の恵みがアブラハムから離れたことは一度もありませんでした。だからこそ、アブラハムもまた、この神の恵み以外に頼るべきものを持ちませんでした。「アブラハムは神を信じた」。その神との関わりを作ってくださったのは、神の愛であります。
今朝読みました創世記第15章の直前、第14章の最後のところに、あまり目立たないのですが、印象深いエピソードが伝えられています。アブラハムのところにソドムの王がやって来て、こういう申し出をしました。「人は私に返してください。財産は全部あなたにあげますから」。旅をしながらのアブラハムの歩みには、実際にはいつも非常な困難が付きまといました。きな臭い話になりますが、攻めたり守ったり、苦労が絶えませんでした。そんなときに、ソドムの王から、「欲しいものは全部あなたにあげますよ」という、思わず飛びつきたくなるような助けが差し出されたのです。けれどもアブラハムは主の前に手を上げて誓いを立て、「たとえ糸一本といえども、あなたから何かをいただくわけにはいきません」。それはなぜかと言うと、「あなたが、『アブラムを富ませたのは、この私だ』とおっしゃらないようにするためです」(23節)。アブラハムにはよくわかっていました。「わたしがアブラハムを豊かにしたのだ」と、間違ってもそんなことを言われたら、すべてが台無しになる。わたしを富ませてくださるのは神だけだ。このようなところにも、「信じて生きる者の強さと弱さ」がよく表れていると思います。私どもも今、アブラハムの信仰の血筋に生かされる者として、同じ強さと弱さの中に立たせていただくのです。
■このあと、聖餐を祝います。私どものために十字架につけられ、お甦りになったお方こそ、誰よりも強く、しかも誰よりも弱くなってくださいました。アブラハムにはそれなりの財産がありましたが、主イエスには本当に何の財産もありませんでした。神の愛以外に何ひとつ頼るべきものを持ちませんでした。だからこそ、主が十字架の上で、「わたしの神よ、わたしの神よ、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」と大声で叫ばれたというその絶望は、人間のはかりでは測り得ないほどの深みを持ったのであります。神は、このイエス・キリストを、死者の中からお甦らせになりました。私どもが義とされるのは、このお方を信じることによるのです。十字架につけられ、復活させられたお方の弱さと強さを信じることによるのです。ローマの信徒への手紙第4章の最後には、こう書いてあります。
私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じる私たちも、義と認められるのです。イエスは、私たちの過ちのために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたからです(24、25節)。
このお方に救われて、ここに立つ私どもであります。アブラハムにまさって、過ちを犯しやすい私どもですが、だからこそ、このお方を信じさせていただくほかないのです。お祈りをいたします。
私どもの信仰の始祖、アブラハムの歩みをたどることによって、信じて生きる者の幸せを学ぶことができました。アブラハムにまさって、過ちを犯しやすい私どもですが、だからこそあなたの恵み以外に頼るべきものを持たないことを、ますます覚えさせてください。今、主の恵みの食卓を祝います。主の十字架と復活をたたえつつ、主と共に死に、主と共に甦らせていただいた自分自身の命を、この食卓において見出す者とさせてください。主イエス・キリストのみ名によって祈り願います。アーメン