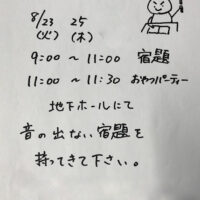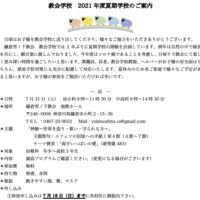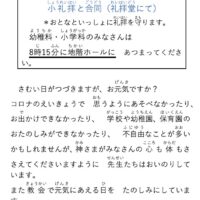神の恵みによって、わたしはわたし
コリントの信徒への手紙一 第15章1-11節
川崎 公平

主日礼拝
■今朝は、先週、先々週の日曜日に引き続き〈伝道礼拝〉と称して、まだ洗礼を受けておられない方、今朝初めてこの場所に来られた方、教会なんて人生で初めてだという方、特にそういう方たちを歓迎しながら、この礼拝をしたいと思います。歓迎と申しましても、お茶の一杯も出るわけではありません。私どもの教会が願っていることは、神が聖書の言葉をもって、皆さんを歓迎してくださる。もてなしてくださる。そのために、この教会の牧師である私が少し時間をいただいて、聖書のお話をさせていただきます。神のみ旨を教えていただくためです。もう少し丁寧に言い換えると、神のみ前に生きる人間の幸せを、今朝新しく教えていただきたい、神から教えていただきたい。そういう願いを込めて、しばらく聖書の話をさせていただきたいと願っています。
■そのために今朝は、パウロという伝道者の書きましたコリントの信徒への手紙一の第15章の最初の部分を読みました。当初の計画では、この言葉に集中してお話ししようと準備をしていたのですが、準備の過程で少し気が変わりました。礼拝の最初のところで、詩編第16篇というのを皆さんと一緒に読みました。詩編というのは、一種の讃美歌集です。神をたたえる歌、あるいは祈りの言葉集と言ってもよいだろうと思います。その中の第16篇というのが、ある時から、私にとってかけがえのない祈りの言葉となりました。その「ある時」というのは、2年前にこの場所で、この教会で長く長老をなさった方の葬儀をしました。その人の好きな聖書の言葉、という言い方ではどうも足りない。この詩編に命を救われて、神と共に生かされた教会の仲間がいました。今でもこの詩編を読みますと、ひと言、ひと言がその長老の肉声として聞こえてくるような気がいたします。
この人は、1934年、昭和9年に、牧師の子どもとして生まれました。少しばかり個人情報を漏らすようで恐縮ですが、献金の「献」という字がそのままその人の名前になりました。この子は神に献げられた子。事実、そうであったと思います。事実、神がこの人の命をしっかりとお取りになりました。この人の1歳の誕生日のときには、もうあんよができるようになって、自分の足で立っている写真が残っている。ところがその1歳の誕生日の10日後に小児麻痺にかかり、それ以降自分の足で歩くことはできなくなりました。先ほどわざわざ昭和9年生まれと申しましたが、つまり、いわゆる軍国少年として小学生時代を過ごしたということです。男は強くなきゃいかん、そうでなければお国の役に立たないという時代の中で、どんなにつらい思いをされたかと思います。
勉強が苦手な人では決してありませんでしたが、中学を卒業するとき、これ以上親に負担をかけることはできないと考えて高校進学を断念なさいます。もう一人で生きていかなくてはならない、どうしたらよいか。そのときに、詩編第16篇に導かれて、中学卒業後すぐに洗礼をお受けになります。詩編第16篇の最初に、「神よ、私を守ってください/私はあなたのもとに逃れました」とあります。神さまに守っていただこう。それが生涯を貫く祈りとなりました。
神よ、私を守ってください
私はあなたのもとに逃れました。
私は主に言います。
「あなたこそ、わが主。
あなたのほかに幸いはありません」と。(1、2節)
■その少し先の5節には、こんな言葉があります。
主はわが受くべき分、わが杯。
あなたこそ、私のくじを決める方。(5節)
この「くじ」って、いったい何だろうと思われたかもしれません。これは聖書協会共同訳という、私どもの教会では2年前から使い始めた新しい聖書翻訳が新しく採用した訳語ですが、原文の意味をよく読み取っています。その前に用いていた新共同訳という翻訳では「運命」と訳されました。「主はわたしの運命を支える方」。同じ言葉が「運命」と訳されたり「くじ」と訳されたりするわけですが、くじ引きによって、自分の運命が決まる。考えてみると、どうにもやるせない話ですし、しかもそれでいて、よくわかる話なのです。どうして自分の人生、こうなっちゃったんだろう。最近では「親ガチャ」なんていう、ずいぶんひどい言葉が使われるようになりましたが、昔も今も、人間の考えることは一緒なんです。「親ガチャ」というのはつまり、自分がどういう親の元に生まれるか、それはくじ引きのようなもので、子どもは親を選べない。親のことだけではありません、私どもはありとあらゆることで、いつも似たようなことで悩むのです。自分が人生においてどういうくじを引くか。当たりくじか、貧乏くじか。容姿はどうか、体は強いか、頭はいいか、親は金持ちか、貧乏か。もっとも金持ちだからって、いい親とは限りません。
ところがこの詩編が何と言っているかというと、「神よ、あなたこそ、私のくじを決める方」。神よ、私の運命を決めてくださるのは、あなたなのです。そんな詩編の言葉を読んで、たとえばこの長老が、どうして自分はこんな体になっちゃったんだろう、ひどい貧乏くじを引いちゃった、と嘆いたとしても不思議ではないかもしれません。けれどもこの詩編は、もちろんそんなことは言いません。
測り縄は麗しい地に落ち
私は輝かしい相続地を受けました。(6節)
「測り縄」というのも同じことで、自分が受けるべき領地の分け前が測り縄によって測られ、くじによって分配されるという話です。「あなたの取り分は、これだよ。あなたには、いちばんいいものをあげる」。「私は輝かしい相続地を受けました」。しかし、そのことを悟るために、この人は幼い頃からどんなに激しい祈りの戦いをしなければならなかったことでしょうか。
しかし事実、神はこの人のために、いちばんよいものをくださいました。妻を与え、子を与え、まさしく天職とも言うべき仕事も与えられ、しかし何より、徹底して教会に生きることを大切にされました。キリストの福音のために、誰よりも多く働きました。身体が不自由で、何かと時間のかかる人でしたが、教会は決してそれを特別扱いすることなく、自然に受け入れていました。だからこそこの人は若くして長老に選ばれ、この教会で本当によく働かれました。
■この人のことを思いますと、あの伝道者パウロの言葉が本当によくわかるような気がするのです。コリントの信徒への手紙Ⅰ第15章の10節に、こう書いてありました。
神の恵みによって、今の私があるのです。そして、私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他の使徒たちの誰よりも多く働きました。しかし、働いたのは、私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。
このパウロの言葉を、そのまま体現されたような長老でした。「神の恵みによって、今の私があるのです」。私は思うのですが、このパウロの言葉、この聖書の言葉は、決定的な意味を持つ言葉です。決定的というのはつまり、この言葉が言えるか、言えないかで、皆さんの人生が右か、左か、大きく分かれてしまうほどの決定的な意味を持つ言葉だと思うのです。もし本気でこの言葉を言えたら、自分の人生、もうこれ以上何もいらないのではないでしょうか。「神の恵みによって、今の私があるのです」。ついでに申しますと、この部分をもう少し原文どおりに直訳すると、「神の恵みによって、今あるわたしがわたしなのです」。ここは実は、英語のほうが訳しやすい。「神の恵みによって、I am what I am」。皆さんは、どうでしょうか。日々この言葉を口ぐせのように繰り返しながら、しかし、自分は果たして本気でこれを言えるかな、言えないかな、言えないとしたらそれはなぜだろうと、問い続けてみてもいいかもしれません。「今あるわたし、今ここにあるわたしが、本当のわたしなのです。神の恵みによって」。そう正直に言えるか。ほんねでそう言えるか。言えないか。
思えば、今朝ずっと紹介している長老は、本当にそのことを喜んでおられたと思います。今あるわたしがわたしであることを、心から喜んでおられました。自分が引いたのは当たりくじか、貧乏くじか、いつもそのことにこだわっている人間は、そうは言えないのです。「今あるわたしは、本当のわたしじゃない。もっといい〈わたし〉になりたい」。けれどもこの手紙を書いた伝道者パウロは言うのです。
神の恵みによって、今あるわたしがわたしなのです。そして、私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他の使徒たちの誰よりも多く働きました。しかし、働いたのは、私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。
わたしは誰よりも多く働きましたと、はっきりそう書いています。これだけ読むと、「え? これ、自慢?」と誤解されてしまうかもしれません。人間というのは、自分がちょっとでもいい働きをすると、それだけでもう何か自分が特別な人間になったかのように錯覚します。逆に自分にろくなポストが与えられなかったりすると、どうして皆わたしのことを評価してくれないのかと、ひがんだりします。そうするともう、「神の恵みによって、今のわたしがわたしなのです」とは言えなくなります。けれどもこの手紙を書いたパウロの心には高慢も卑屈もないのであって、「しかし、働いたのは、私ではなく、私と共にある神の恵みなのです」。その神の恵み、「私に与えられた神の恵みは無駄にならなかった」と言っています。
神の恵みが無駄にならなかったから、わたしはわたしであることができている。「ただ神の恵みによってのみ、今のわたしがわたしなのです」。これは、本当に激しい言葉だと思います。これをひっくり返して言い直せば、もしも神の恵みが無駄になったら、わたしがわたしでなくなってしまう。わたしの人生そのものが無駄になってしまう。
■その上で、パウロはコリントの教会の人たちに問いかけるのです。あなたがたはどうなのか。「神の恵みによって、今のわたしがわたしなのです」。しかし、あなたはどうなのか。あなたがたはどうなのか。話は第15章の1節、2節から始まっておりました。
きょうだいたち、私はここでもう一度、あなたがたに福音を知らせます。私があなたがたに告げ知らせ、あなたがたが受け入れ、よりどころとし、これによって救われる福音を、どんな言葉で告げたかを知らせます。もっとも、あなたがたが無駄に信じたのではなく、今もしっかりと覚えていればの話ですが。
ここに既に「無駄」という言葉が出てきます。この「無駄」というのは、繰り返しになりますが、本当に激しい言葉だと思います。そう軽々しく使っていい言葉ではないはずです。「あなたの人生って、ほんと無駄だったね」とか、「なんか一所懸命信じているようだけれども、その信仰は無駄な信仰だね」とか、そう簡単に人に言っていいことではありませんし、人から言われなくても、自分の人生は無駄だったのではないかと考え始めたら、これ以上悲惨なことはないだろうと思います。
ここでパウロはコリントの教会に問いかけるのです。あなたがたはどうか。無駄に信じたのだとすれば、あなたがたの人生そのものが無駄になってしまうのではないか。なぜそんなことを尋ねなければならなかったというと、まさにその点で、コリントの教会に危ういところがあったからです。その心配事の具体的な内容は、今日読んだ箇所だけでは、まだあまりはっきりしませんが、今日は11節までを読みました。その先の12節にこう書いてあります。
キリストが死者の中から復活した、と宣べ伝えられているのに、あなたがたの中のある者が、死者の復活などない、と言っているのはどういうわけですか。
主題は、死者の復活であります。もし「死者の復活などない」ということであるならば、あなたの人生そのものが、無駄になってしまうのではないですか。そのあとの12節以下の叙述は、とうてい一回の礼拝で読み切れるものではありませんが、特に強烈だと思いますのは、32節の後半です。
死者が復活しないとしたら、
「食べたり飲んだりしよう
どうせ明日は死ぬのだから」
ということになります。
飲んで、食べて、死ぬだけのあなたの命ですか。あなたの命を、そんな無駄なものにしちゃいけない。しかし、「死者が復活しないとしたら」、結局そういうことになるのではないですか。そうしたら、19節の後半にもあるように、「私たちは、すべての人の中で最も哀れな者となります」。
■そうならないようにと、パウロはコリントの教会に宛てて、このように手紙を書くのです。もう一度1節の最初から読みます。
きょうだいたち、私はここでもう一度、あなたがたに福音を知らせます。私があなたがたに告げ知らせ、あなたがたが受け入れ、よりどころとし、これによって救われる福音を、どんな言葉で告げたかを知らせます。
「もう一度、あなたがたに福音を知らせます」。そう言って、その福音とは何かということを説明して、「私があなたがたに告げ知らせた福音、あなたがたが受け入れた福音、そしてあなたがたがよりどころとした福音、これによって救われる福音」、そう言うのです。特にここで興味深い表現は、「よりどころとし」と書いてあります。ここも原文を直訳しますと、「その中にあなたがたも立っていた福音」。つまりパウロはここで、「あなたがたはどこに立っているのか」と呼びかけているのです。「あなたがたは、どこに立っているのか。何によって立っているのか。あなたがたの足もとの土台は何か」。その土台を踏み外したら、食べて、飲んで、死ぬだけの人生になってしまうのではないですか。ただここでもう少しうるさいことを言うと、この「よりどころとし」というのは、原文では過去形の動詞が使われていて、「あなたがたが立っていた福音、あなたがたがよりどころとしていた福音」、その福音を、もう一度知らせます。つまり、「あなたがたは、かつて福音によって立っていた。けれどもそれはあくまで過去形であって、今は立っていない。あなたがたは倒れた。だからこそ、思い起こしてほしい。あなたがたは、どこに立っていたのか」。その土台を踏み外したら、どんなに健康でも、どんなにお金持ちになっても、全部無駄になってしまうのではないですか。飲んで、食べて、死ぬだけの生活になってしまうのではないですか。
■そうならないように、パウロはこう言うのです。どんな言葉で私があなたがたに福音を知らせたか、それをもう一度知らせます。そこでパウロが丁寧に語り直すことは、結局ただひとつのことであって、キリストは復活された、死人の中からお甦りになったということです。死人が復活するなんて、そんな不思議なことが科学的にあり得るのか、どうなのか、という次元の話をしているわけではありません。教会の偉い人たちが話し合って、そこに科学者、生物学者まで集めてきて慎重に検討して、どうやら復活はあるらしいという意見がまとまったからといって、それで信仰が成り立つわけではありません。
100年近く昔のものですが、スイスの教会の牧師がこういうことを言っています。残念ながら、われわれの国には、子どもの頃から聖書を読み、復活を信じ、復活を疑ったことなんか一度もないけれども、その復活の信仰が何の力にもなっていない人たちが何百万人もいる。そのスイスの牧師のたとえをそのまま紹介しますが、地球は丸いと信じる、それと同じようにイエスさまは復活したと信じる。そんな信仰に何の意味もないと、その牧師は言うのです。そんな復活の信仰は、人を生かす力を持たない。それはなぜか。おもしろいのはここからで、それはなぜかと言うと、「神と和解していないからだ」と言うのです。イエス・キリストの復活を通して、神と和解させていただかないといけない。
ここでパウロが言っているのも、そういうことです。それをこの手紙では、8節以下で、こう書いています。
そして最後に、月足らずで生まれたような私にまで現れました。私は、神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中では最も小さな者であり、使徒と呼ばれる値打ちのない者です。
そんなわたしのためにも、お甦りのイエスが現れてくださった。そんな自分のことを、ここでは「月足らずで生まれたような私にまで」と言います。かつて教会の迫害者であった自分をふりかえりながら、そう言っているのです。「月足らず」、つまり未熟児として生まれたと、そう翻訳するのが日本の聖書翻訳における一種の伝統になっていますが、原文では、ちょっときつい言葉で申し訳ありませんが、死産・流産を思わせる言葉が使われています。「一応出てきたけど、もう死んじゃってる」。それがわたしだ、と言うのです。宗教改革と呼ばれる大きな運動の発端となった、マルティン・ルターという人は、聖書をドイツ語に翻訳して、そのことによって聖書を民衆の手に取り戻したということで有名ですが、ルターはこのところを、「生まれそこない」と訳しました。ドイツ語をそのまま発音すると”Missgeburt”という言葉です。Missというのは英語のミスと同じで、失敗ということです。geburtというのは、英語で言えばbirth、「誕生」ということです。「失敗の誕生」。「わたしは、誕生における失敗作として、存在を許されている」。それがわたしだと、パウロは言うのです。それにしても「生まれそこない」なんて、そんな言葉を、たとえば1歳から歩けなくなったあの長老が聞かされたら、さすがに傷つくかもしれません。けれども、そんなわたしにキリストが出会ってくださるなら……皆さんも、パウロと同じように、このように言うことができるようになるのです。
そして最後に、月足らずで生まれたような私にまで現れました。私は、神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中では最も小さな者であり、使徒と呼ばれる値打ちのない者です。神の恵みによって、今のわたしがわたしなのです。
神と和解させていただいた人間は、自分自身とも和解することができます。今あるわたしを、神の恵みによるわたしとして受け入れることができます。そこにどんなに軽やかな歩みを造ることができるか、この教会に生きる私どもは皆、その証し人です。どうかなおひとりでも多くの人が、私どもの仲間になってくださるように、神の恵みによって生かされる幸いを知ることがおできになりますように。今日ここに集められたおひとり、おひとりの上に、心より主イエス・キリストの祝福を祈ります。
私どもの救い主、イエス・キリストの父なる御神、御子キリストをお甦らせになったあなたの恵みの力が、今私どもを生かします。自分の力で生きていると、いつもそんな勘違いをしている私どもを、どうか憐れんでください。神の恵みによって生かされているわたしを、心から愛する者とさせてください。
神よ、私を守ってください
私はあなたのもとに逃れました。
私は主に言います。
「あなたこそ、わが主。
あなたのほかに幸いはありません」と。
感謝し、主イエス・キリストのみ名によって祈り願います。アーメン