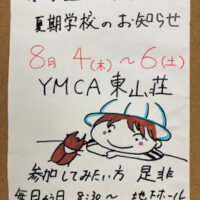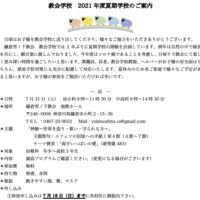揺るがない岩
マタイによる福音書 第7章24-29節
柳沼 大輝

夕礼拝
マタイによる福音書は第5章から第7章まで主イエスが弟子たちに語った一連の教え、所謂「山上の説教」というものを書き記しています。本日の箇所はその「山上の説教」の最後の部分、「締め括り」とも言える箇所であります。
しかしいつものことながら主イエスのお言葉は大変、厳しいものであります。はっきりと明白に倒れる人と倒れない人、賢い人と愚かな人とに分けて教えを語ります。
聖書の御言葉や主イエスの言葉が嫌われたり、敬遠されたりするのは、もしかたら人間の生き方をこのようにはっきりと二つに分ける、「二分法」とも言えるものにあるのかもしれません。白黒をはっきりと分けず、グレーゾーンを好む、そんな日本人の体質には、物事を二つに分ける、聖書の福音というものは馴染まないのかもしれません。
しかし実際に私たちの日常生活に目を向けてみれば、表向きはしっかりと立っているようでいても、内面はボロボロになって倒れかけている者がいます。あるいは、反対に倒れかけているようでいて、それでも、しっかりと立ち続けている者がいます。私たちの目だけでは白か黒か、あるいはグレーか判断できない。その者が立つか倒れるか最終的にお決めになるのは神であります。
だからこそ、私たちは今日「神の言葉」に聴くのです。本日の主イエスの教えは一見、単純なように思えますが、どうもそう簡単ではありません。
この「家と土台」のたとえは、ただ単に、聖書の御言葉に聴き、それを実行する大切さを教えているのでしょうか。そうなりますとどれだけ聖書の言葉に従って生きることができたか、それによって人生を豊かなものにすることができたか、あるいは自分の力によっていかに信仰を獲得することができたかといったような道徳的、または律法主義的な教えであると読めなくもないでありましょう。そうなるとあの人は聖書の言葉に従っているから立派だ、逆にあの人は聖書の言葉を聴いても実行していないから駄目だといったようになってしまうでしょう。
しかしそうであれば主イエスの「十字架」とは何でありましょうか。自分の力で「救い」を獲得することができるのであれば、主イエスの「十字架」などそんなものはもはや必要ないでありましょう。
たしかに聖書の言葉に聴いて従うことの大切さは言われています。それに周りを見回しますと皆、それなりに実行していて、皆、それなりの人生という「家」を建てているように思われます。しかし洪水や大風にたとえられる「試練」が襲い掛かってきたときにどの「家」が残って、どの「家」が倒れるのか、私たちには分からない。私たちは他人の「家」が立つか、倒れるかなど分からない。自分の「家」さえも分からないのです。自分の人生という「家」がちゃんとこのまま立ち続けていくことができるのかどうかも怪しいものであります。
しかし分からないくせに、私たちは人の「家」と自分の「家」を見比べては劣等感を抱いてみたり、優越感に浸ってみたりします。そうやって、自分の「家」は大丈夫か、自分の人生は上手くいっているか確認をしたいのです。そういう意味で、皆まことに「愚か」であります。自虐的と言われるかもしれませんが、実際、そうであります。
本日の「山上の説教」の締め括りの言葉は、ただ言われたことを実行しなさい、実行しなかったら、元も子もないといった教えではないのです。たとえどんなに多くの主の言葉、聖書の御言葉を聴いて、持っていたとしても、それらの「聴き方」を間違ってしまっていては意味がありません。
ここで「家」にたとえられているのは私たち一人ひとりの「人生」そのものであります。その中にはまるでなんとかタワーといったような立派で威勢を誇る人生もあるかもしれません。富や名声や権力、それらすべてを手に入れた人生だってあるかもしれない。あるいは、そういった俗的なものではなく、知性や思想といった、崇高なもので見事に飾られた人生もあるかもしれない。
しかし、私たちの多くは、それほど豪華で立派な「人生」の「家」を築き上げるということはないでありましょう。皆、それなりの財を利用し、それなりの名声、知性、ネットワークを築いて、それぞれに自分なりの仕方で、自分なりの「能力」をもちいて、必死に自分なりの「人生」という「家」を建て上げてきているのではないでしょうか。それは周りから見たら、とりわけ豪華ではないかもしれない。立派とは言えないかもしれない。しかし、どんなに小さかろうと、貧しかろうと、平凡な家であろうと、私たちの「人生」の「家」も私たちにとっては大切な「家」なのです。他人と比べて大きいか、小さいか、頑丈か、貧弱か、そんなことを比べるのではなく、その自分の「家」が倒れるか、倒れないかの決定的な違いをしっかりと聴くことがここでは大事なのであります。そこを外してしまうとどんなに小さな「家」と自己卑下して見せても、どこか自分の力に頼って、その「家」を立派に築き上げているかのような感覚に陥ってしまうでしょう。
雨が降り、川が溢れ、大風が吹いてくる。本日の主イエスのたとえで言われているのはもちろん人生のなかで経験する「試練」のことであります。「苦難」のことであります。それは誰にでも降りかかってくるものでありましょう。しかしここで「家」が倒れるのか、それとも倒れないかの違いはその大水や大風の「強さ」ではありません。あるいはその「家」の「立派さ」や「頑丈さ」でもありません。その「家」の立っている「場所」が問題なのです。どこにその「家」が立っているのかで、倒れないか倒れるかの違いが出てくるのです。どこに「家」を建てているのか。「砂」の上かそれとも「岩」の上か、それがここで主イエスが語っておられる決定的な違いであります。
この描写には、聖書の世界の地理的な特徴が背景にあります。聖書の世界は日本のように四季があるわけではなく、季節は大きく「雨季」と「乾季」に分かれています。乾季になると大地はからっからに乾きます。そして雨季に入ると雨が降り始めます。植物は殆ど枯れ果てて、大地は乾き切っています。そこに雨が降ってきますと、たとえそれほど強い雨でなくとも雨が大地に染み込むということがなく、降ってきた雨はすべて低い沢へと集まってきます。そしてその沢に集まった雨水は突然、鉄砲水のようになって沢を下っていくのです。
沢といっても、実際には、それほど狭いものではありません。私たちは沢と聞くと、両脇に山や丘の見えるような山間の切り立った場所をイメージするでしょうが、イスラエルではそこからさらに下っていった平地に近いところまで沢が広がっています。そして、そこから平地まで鉄砲水が押し寄せてくるのです。これはその気候や地理的な条件を知らない者にとっては予想もできない事象であります。周りを見ても、それほど近くに山が迫ってきているわけではない。平らで平凡な場所であります。しかし雨が降ると、風が吹くと、そこにまで大量の水が押し寄せてくるのです。
「砂」の上に「家」を建てるということは、そのような場所に自分の「家」を建てるということであります。明らかに両脇に山が迫ってきていて、水が流れてくるだろうと目で見て分かるような危険な「砂」の上に「家」を建てるということではないのです。ここなら「大丈夫だ」と思ってしまうような一見、平坦そうな場所に、安全そうな場所に「家」を建てたのです。しかし、いざ雨が降り始めたら、あっという間にそこまで水が押し寄せてきて「家」は押し流され、倒されてしまいました。
一方、「岩」の上に「家」を建てるとはどういうことでありましょうか。「岩」というのは「岩盤」のことです。いわばその「家」の「重さ」を支える「土台」であります。ここで「重さ」というものにも注目して考えてみたいと思います。もし「家」が「岩盤」のない砂の上に建っていたとしたらどうでありましょうか。その家の「重さ」に耐えることができるでしょうか。たとえ雨や風で押し流されずに済んだとしても、その「家」は砂の中に沈み込み、やがて傾き、崩れ去ってしまうでしょう。
この主イエスの教えを聴いている者たちは、皆、自分たちの経験とこのたとえを照らし合わせて納得したことでありましょう。主イエスはここで大水や大風で倒れる「家」と倒れない「家」との違いは、その「土台」にかかっていて「岩」の上に建てる者は「賢く」、何も知らないで「砂」の上に建てる者は「愚か」だと言われています。ですから「賢い」者というのは、ただ「山上の説教」で語られたことを、いわば、聖書の御言葉を聴いて、それらを実行した者だとは言っていないのです。それらの教えを実行することによって、それが「岩」となるというのでもありません。そこを、間違えてはならないのです。教えられたことを実行していくことは「家」を建て上げていくことなのです。
基礎となる「土台」の「岩」を自分たちが一所懸命に聖書の言葉に従うことによって築き上げていくのではありません。聴いて行って造るのはあくまで「家」の方であります。そういう意味では皆、それぞれに「立派」な「家」を建てていると言えます。「人生」という「家」です。その「家」が倒れるのか倒れないのか傍から見ただけでは分かりません。そして、建物の「立派さ」や「堅固さ」とも関係ないのです。どんなに「立派」な「家」であったとしても洪水と大風には太刀打ちできません。
その洪水と大風でたとえられる「人生」の「家」が倒れるか倒れないかの「試練」の究極的なところにあるものとは何でしょうか。それは「死」です。どんなに人の目から見て「立派」に見える「人生」という「家」を建てても、最後の最後に、「死」という大水と大風が襲って来るときにその「立派さ」や「堅固さ」では到底、太刀打ちできません。
もちろん「死」という究極の大水や大風の前に、私たちの「人生」には、様々な災難な試練が襲って来るでありましょう。平穏無事なときには分からないものです。しかしそのような大水や大風が襲って来るときにはっきりと分かるのです。自分の思想や価値観、あるいは家族関係、自分の健康とか社会的地位とか、世の中での評価等など、そういったもので打ち建てている自分の「家」の「立派さ」や「頑丈さ」では太刀打ちできない苦難や試練が起こってくる。やがて、その重荷に耐えられなくなる。打ち崩される。空しさに捕らわれてしまう。
しかし「死」という究極の大水と大風に遭う前にそのことに気づき、分かるということはまだ幸いであると言えます。何故ならまだやり直しが効くからです。大水と大風に襲われて一所懸命に自分の力で踏ん張ろうとしたけれども、踏ん張れずに「家」が倒れていく。自分の「人生」は何だったのだろうかとそう呟かざるを得ないようなときがやってくる。しかし、それはまだやり直しが効くのです。嗚呼、自分は「砂」の上に自分の「人生」という「家」を建てていた。でもまだチャンスがあるのです。やり直しが効くのです。今度こそ、「岩」の上に自分の「家」を建てよう。そういうやり直しをして、自分の「人生」にあとどれだけの時間が残されているかは分からないけれど、精一杯、自分の「家」をもう一回、建て直していこう。そういった仕方でやり直しが効くのであります。
それではどこでどうやってやり直せばよいのか。どこに「家」を建て直せばよいのか。そうです。足元をよく見るのです。主イエスの「山上の説教」の最後のたとえで言われていることはこうであります。どんな苦難、死という苦悩に最終的に襲われても「私」という「家」は倒れない。それは「岩」を土台としている「家」だからである。この「家」の「立派さ」や「頑丈さ」は関係ない。木造だろうと、石造りだろうと、鉄骨だろうと関係ない。大切なのは「土台」であります。その「土台」の「岩」はどんな大水が押し寄せようとも、どんな大風が吹き荒れようとも、その「家」を支え守る。
「土台」とか「岩」というこのたとえでは、それは無機質で、動きようのないものであるかのように聞こえるでしょう。しかしこの主イエスのたとえでは違うのです。「土台」が、その「揺るがない岩」が「家」を守るのです。支えるのです。その「岩」とは何か。その「岩」は主イエス・キリストです。死に勝利して復活し、いまもここに生きておられる主イエス、そのお方があなたの「人生」を支えるのです。十字架による全き赦しと復活による新しい命が、救いが御子イエス・キリストを通して、私たちに「土台」として「岩」として与えられている。
「家」を建て上げていくのにも、私たちはいつも迷ってばかりであります。ときに自分の「人生」という「家」がまことに歪な形になってしまうこともあります。試練もあれば、自業自得としか言いようのない苦しみもあります。そのような中で「家」は揺らぎ、何度も倒れそうになります。しかし足の下から、「家」の「土台」から言葉が聴こえてくるのです。主イエスはあなたに語りかける。
「それでもお前は赦されている。それでもお前は尊い存在だ。かけがえのない神の子なのだ。そしていつも、いや、いまも私はお前と共にいる。お前がいま、抱えているその苦しみも私が十字架上でとことん味わってきているから、お前の苦しみも辛さも私は知っている。たとえお前からすべてを奪おうとするものが現れたとしても、朽ちることのない永遠の命をもってお前を神の国へと導く。それが、私がお前に与える救いの約束だ。だから焦るな。だから恐れるな。安心しなさい」。
主イエスはどこにいるのか。本日の礼拝では共に告白いたしませんでしたが、「使徒信条」では「主は天に昇り、全能の父なる神の右に坐したまえり」と、信仰を言い表します。それも然りです。しかし私たちは本日の御言葉からもう一つの答えを与えられます。主イエスはどこにいるのか。主イエスは我らの「土台」となって、私たちの一番底、一番下で「揺るがない岩」となって、私たちを支えてくださっている。守っていてくださる。私たちの重荷を十字架でもってその身で受け止めてくださっている。
だから私たちは「大丈夫」と言えます。たとえ、大雨が降っても、大風が吹いても、それでも「大丈夫」と言える。苦しいのは苦しいのです。悲しいのは悲しいのです。けれど、苦しみながらも、悩みながらも、悲しみながらも、それでも私は「大丈夫」ですと言える。それは主を「岩」としていただいているからであります。それはどんなに幸いなことであろうか。その幸いによって生かされているこの私はどんなに恵まれた存在であろうか。
「大丈夫」とはよい言葉であります。しかし私たちは強がって、ただ虚勢を張って「大丈夫」と言うのではありません。主が、与えてくださる「救い」にしっかりと裏付けされた「大丈夫」であります。だから、もう一度、チャレンジしたい。主イエスが「岩」として共にいてくださるのですから、もう一度、頑張ってみよう。もう一度、ここから立ち上がろう。大丈夫!また共に歩き出そう。
今日、主イエスが「揺るがない岩」としてあなたの人生を支えています。もう不安に怖じ恐れる必要はありません。安心していきなさい。主からいただいた言葉を噛みしめて、反芻して、自分の「家」を「人生」を主と共に築き上げていけばよい。ここに信仰に生きる者のまことの「幸い」があるのです。
主イエス・キリストの父なる御神、あなたが土台となり岩となり、ここに共にいてくださるから、私たちは、今日ここに立っています。今日ここに生かされています。あなたからの恵みを受けて、喜びをもって、私の人生を歩んでいくことができますように。ときに雨が降るでしょう。ときに風が吹き荒れるでしょう。そのようなときもあなたに依り頼む柔和な心を私たちにお与えください。あなたが共にいる、その幸いをいただきながら、私たちはまたここからそれぞれの持ち場へと出で行きます。この心からの願い、主の御名によって祈ります。アーメン