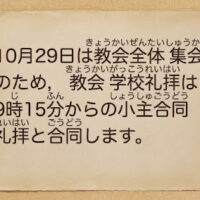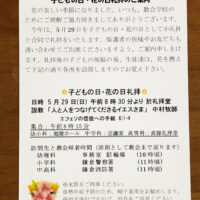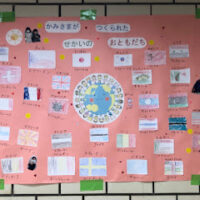父の家に帰る
ルカによる福音書 第15章11-24節
柳沼 大輝

主日礼拝
私たちは先週、礼拝のなかで川崎公平先生の説教を通して、私たちの信仰生活とは何かについて深く思いを巡らせました。先週の礼拝説教のなかで引用された言葉をここでも再び、取り上げたいと思います。「われわれの信仰生活は、よい忠告を受けるためのものではない。ためになる話を聞くのでもない。よい知らせを聞くのである」。私たちは、ついつい誤解をしてしまいます。私は、聖書のよい教えを学んで実生活に生かすために礼拝に出ているのだ。いろんな気づきを与えられて、いろんな光を与えられて、自らの人生を豊かにするために礼拝生活を続けているのだ。もしかしたらそのような願いを持ってこの礼拝に出席されている方がいるかもしれません。しかし、それが信仰生活の、礼拝の根本ではありません。礼拝の意義は「よい知らせ、福音を聞く」ことであります。福音を聞くために、私たちは、父なる神に招かれてここに来ているのです。本日は、このことを強く意識しながら御言葉に聴いていきたいと願います。
本日の御言葉は「放蕩息子のたとえ」として多くの者たちに親しまれている聖書箇所であります。私たちが手にしている聖書協会共同訳ではここのところに「いなくなった息子」のたとえという小見出しを付けました。しかし、この物語の中心はいなくなった息子本人ではありません。身を持ち崩した一人の男が父のもとに帰ることができたといった、いわゆる「いい話」を語っているのではないのであります。そのようなよいドラマをこの御言葉に聞きたいと期待するのであれば、この箇所が私たちに語ろうとしているよい知らせ、つまり、福音を聞き損ねてしまうことになります。この話の中心は失われた息子を見出した父の喜びであります。失われた者を見出す父なる神の喜びがこの御言葉には鮮明に宣言されているのです。
そもそもこの話は誰に対してなされているのでありましょうか。第15章の冒頭を見るとわかります。このたとえは徴税人や罪人たちを招いて一緒に食事をしている主イエスに対して、そんなことけしからんと文句を言ったファリサイ派や律法学者たちに向けて語られた主の言葉であります。その文脈で読み解くのであれば、ここに登場してくる弟息子とは、主のもとに近づいて来た罪人たちであり、本日、取り上げることはしませんが、後半に登場する兄息子は主イエスに対して文句を言ったファリサイ派や律法学者たちであると理解することができるかもしれません。しかし、ここで語られていることはそんな単純なものではありません。本日の部分で「いなくなった息子」とは単に主イエスのもとにやってきた罪人たちだけのことを指しているのではなく、この話は「失われた人間」すべての者のために語られた話なのであります。
弟は父に対して「自分が相続する分の財産を早くくれ」と申し出ました。この時代、相続とは親が死んでからなされるとは限りませんでした。稀なことではありますが、親が了承さえすれば、親が存命中であっても相続は可能でありました。ですから、ここで弟が父に求めたことはけっして違法なこととは言えません。
しかしこれはたとえ話であります。この弟に私たち自身を重ね合わせるのであれば、父なる神に対しての私たち人間の立場というものをしっかりと考えなければなりません。まるで当たり前のように神に対して自分の取り分があるかのようにどうして言うことができるのでありましょうか。この要求、そのものからして実はおかしいのであります。しかしそのおかしなことを私たちは日頃から平気でやってしまってはいないでしょうか。
マタイによる福音書第5章から第7章に記された「山上の説教」のなかに次のような言葉があります。
「なぜ、衣服のことで思い煩うのか。野の花がどのように育つのか、よく学びなさい。働きもせず、紡ぎもしない。しかし、言っておく。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。まして、あなたがたにはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよ。だから、あなたがたは、『何を食べようか』『何を飲もうか』『何を着ようか』と言って、思い煩ってはならない。それはみな、異邦人が切に求めているものだ。あなたがたの天の父は、これらのものがみな、あなたがたに必要なことをご存じである。」(6:28~32)
この御言葉に示されているように父なる神はもうすでに私たちのことを顧みて、十分な恵みと慈しみを与えてくださっています。しかし私たちはこの言葉を信じることができなくて一人で勝手に不安になってみたり、もっと自分の力で豊かな人生を送りたいと、神様に対してあれがほしい、こうしてほしいとさらに様々なものを要求してみたりするのではないでしょうか。そしてその要求が通らなければ、私たちはこんな神様なんてけしからんと言って文句を言い出してみたり、神様ひどいと言って、詰いてみたりするのであります。挙句の果てにはこの弟のように父なる神から離れて、自分の力だけに頼って生きていこうとするのではないでしょうか。
弟息子がまだ父親が生きているにもかかわらず、父に対して財産の相続を要求した、このことはいわば、「お父さん、あなたは私の人生にとってもう必要ない」「お父さん、頼むからもう早く死んでくれよ」という「父親殺し」のメッセージに他ならないのであります。実に生々しい描写であります。
主イエスがここで言っている「放蕩」とは何も思いのままに贅沢をしたり、酒食にふけって遊び回ることではありません。「放蕩」とは、本来、神のものであるものを自分のものだと言って自分勝手に使い、あるいはもっとよこせと要求し、そして神の言葉を疎んじ、神を捨て、神を殺し、そこから遠ざかった生活をすることであります。結果として魂が枯渇していく、枯れ果てていく、どん底に落ちていくことになるでしょう。
私たち一人ひとり「失われた者」であります。皆さん一人ひとりにきっと「脛に傷があって」自分も「放蕩息子」の一人だという自覚があるでしょう。しかしどこかで自分はまだこの弟息子ほどひどくはない。大丈夫だと、感じているところがあるのも本音ではないでしょうか。まだ自分には余裕がある、あの人の方が私よりもひどい、神様から離れている、そうやって、ファリサイ派や律法学者たちのように誰かのことを裁く思いがあるのではないでしょうか。残念ながら、私たちはわかっているつもりでいて、しかし己の力では本当の意味で自分の「悲惨さ」に気づくことができないのであります。
たとえでは、全財産を使い果たし、それに輪をかけるかのようにこの弟息子に「飢饉」という危機が襲い掛かりました。外面では上手くいっているように見えても、内面ではすでに壊れかけているということがよくあります。それに気づくことができる者もいますが、多くの者はそれに気づくことができないのではないでしょうか。この弟息子もまさにそうであったのでしょう。はじめは上手く自分の力だけで立ち回ることができたのかもしれません。ある程度の成功をおさめることもできたのかもしれない。しかし、様々な要因によって、今回は飢饉という災難によって、自分の足場が段々と崩れ落ちていきました。
そのような弟息子の悲惨な状況をたとえでは「彼は、豚の食べるいなご豆で腹を満たしたいほどであったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった」(16節)と言い表します。誰かを「豚!」と罵れば、そんな侮辱な言葉はないとされるでありましょう。しかしこの弟息子はその「豚」よりも大切にされていないのです。誰もこの息子に食べ物を与えようとする者はいないのです。さらにこの「いなご豆」という言葉は、厳密には「いなご豆の粕」を意味する言葉です。つまり、彼は豚が食べ終えた餌の残骸を漁ってでもどうにか腹を満たしたいと願ったのであります。彼にとって、この状況がどれだけ屈辱的なことであったかは想像に難くありません。一度は、己の力で成功をおさめた人間が、いまは豚の餌の粕にすがってでも、なんとか生きながらえようとしている。まさにこのとき、彼は人生のどん底に立たされていました。
それでは、人間は、そのようなどん底に落ち込んだならば、自分の悲惨さに気づき、本当に悔い改めるのでありましょうか。弟息子は「我に返って」言います。
『父のところには、あんなに大勢の雇い人がいて、有り余るほどのパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここをたち、父のところに行って言おう。「お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。」』(17~19節)
この息子が、父のもとに帰ろうとした動機は父のところには「有り余るほどパンが豊かにあるから」ということでありました。いわば、この息子は食い扶持を当てにして、まだ雇い人の一人としてなら受け入れてもられると、自分もまだその程度にはかってもられると考えているのであります。「お前なんていらない」「お前なんて早く死んでしまえ」と言って、勝手に家を飛び出していったくせに、まだ雇い人の一人としてなら父も自分を近くに置いてくれるだろうと考えているのです。父のもとに帰ろうと決意したそのとき、この息子は「どれだけ父が悲しんでいるか」「どれだけ自分が父を傷つけたか」、父の気持ちなど全くと言っていいほど考えてなどいないのであります。いかにも「言葉」だけは整っているように見えますが、言ってしまえば、まことに「独りよがり」な悔い改めでしかありません。「悔い改め」と言っていいかも怪しいですが、それでもこの息子が「父のもと」に帰ろうと思えた、そのことは「恩恵」であり、「賜物」でありました。
この息子が真に自分が「失われた者」であることがわかるのはどういうことでありましょうか。「十字架の贖い」や「復活にある救い」について「知識」として「理屈」としていくら知っていても、自分のことだけを見ていて、自分の周りのことだけを考えていたのでは、いつまでたっても、自分が「失われた人間」だとはわからないのであります。いくら反省し、自分のいたらなさを告白し、自分の不安を表明し、一本立ちできない自分の弱さを認めたとしても、それでも自分が真に「失われた者」であるということがわからないのであります。
この息子は惨めさと自分なりに父に悪いつもりだという意識をもって、しかし同時に雇い人の一人としてなら受け入れてもらえるだろうという、どこか楽天的な、お気楽な思いで、父のもとに帰ってきています。故郷に帰り、家が近くなる。まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、憐れに思い、走り寄って首を抱き、接吻して止まなかったと、聖書は語ります。
まだ誰も気づいていないのに、いや、たとえ人影を見つけたとしても、その容姿は家を飛び出していったあの自信に満ち溢れた姿とは全くと言っていいほどに違っていたでありましょう。汚く、傷だらけで惨めな姿であったに違いありません。
それではどうして父親はこの息子をまだ遠く離れていたのにもかかわらず、見つけることができたのでありましょうか。答えは簡単です。それは父親が毎日、この息子が帰ってくることを待っていたからであります。この息子が自分のもとに帰ってくることを切に祈ってずっと待ち焦がれていたからであります。だからこそ父親は自分のもとに帰ってこようとしている息子を見つけるとすぐに「喜んで」走り寄っていったのであります。
ある説教者がこの父親の姿を説き明かしてこう言いました。「さまよっている者よりも、その者の無事を祈り、帰りを待っている者の方がどれだけ苦しいか」。たしかにそうであります。あるとき、ニュース番組を見ていたら、山のなかで息子とはぐれた父親が無事に救助された息子と再会する場面を報道していました。父親はきっと何日も何日も息子の名前を大声で叫び、捜し続けたのでしょう。息子が見つけ出されたとき、その息子よりも父親の方が乾き切りやつれていた。父の悲しみは「お前はいらない」「お前は死ね」と言われたことよりも、愛する息子を失ったことへの悲しみでありました。父は悲しみに暮れながら、何日も何日も祈り続けたのです。だからこそ、遠くに息子を見つけた、そのときの父親の「喜び」はどれほど大きかったでありましょうか。
たとえに戻って「憐れに思う」とは「腸煮えたぎるように痛む」という意味の言葉であります。豚の世話をしなければいけないほどに、豚の餌の食べ粕を漁らなければ、生きていけないほどに薄汚れ、変わり果てた息子の惨めな姿を見て、この父親は心傷めずにはおられなかったのです。ゆえに父親は息子の姿をその目に捕らえると急いで「走り寄った」のであります。
「走り寄る」という言葉もまた「身を乗り出す」という意味の言葉であり、この父親はこの息子に向かって「身を乗り出し」、その腕で息子のことをしっかりと抱きしめ、その首に接吻をしたのであります。それもただ、挨拶程度に軽く接吻をしたのではありません。フランシスコ会訳という聖書では、ここのところを「口づけを浴びせた」と訳しています。つまり、この父親はその「喜び」ゆえに何度も何度もその息子の首に「口づけ」せずにはおられなかったのであります。
甘ったれたこの息子は、父が走り寄ってきて、身を乗り出すように、首にしがみつき、接吻して止まないこの姿、この態度に触れて、驚き、そして完膚なきまでに「打ち砕かれた」のではないでしょうか。そしてそのとき初めて自分がいままでしてきたことはいったい何だったのかということに気づかされたのではないか。自分はどれだけこの父に対してひどいことをしてきたか。どれだけこの父の愛を裏切り、踏みにじってきたか。だからもはや「雇い人の一人にしてください」などという言葉はこの息子の口から出てこないのです。本当の罪の告白だけがその口に残りました。
「お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。」(21節)
悔い改めるのは、他でもない、走ってくるこの父の姿に戸惑い、その腕で抱きしめられたその瞬間、自分を待ち焦がれていたその思いに驚き、こんなにも「喜ぶ」父の愛に打ち砕かれるときであります。まことの「悔い改め」はこの父なる神の愛に抱きしめられるとき、初めて沸き起こってくるのです。
私たちは、自分の正義によって互いを責め、糾弾し、相手を無理やり「悔い改め」させようといたします。しかし、仮にそれで相手が謝罪したとしても、それは本当の悔い改めにはならないのです。表面的に謝ったとしても心のなかでは余計に頑なになってしまうことが実に多いものであります。それに対して、この父に抱きしめられるのを私たちは信仰の事柄としてどこでどうやって経験するのでありましょうか。それを自分の力で構築することができないのは明らかであります。私たちはどこまでいっても己の力で、自分の悲惨さに気づくことができない。どこまでも「自分が一番で大切」で「自分の思い」を手放すことができない。まさに「独りよがり」であります。「悔い改める」、それは、神から一方的に与えられる「恩恵」の出来事であり、「賜物」に他なりません。
それでは私たち人間は何もすることができないのでありましょうか。いやけっしてそうではありません。私たちに残されたたった一つの道があります。それは、たとえ「独りよがり」であっても父のもとに行くことであります。「礼拝」という父の御前に、十字架の御前に立つことであります。「教会」という主によって呼び出され、召し出された群れ、共同体のなかにあって、「礼拝」において、十字架に相対して、神の言葉、福音を聞くことであります。そして神がどんなご配慮をもってこの自分を愛してくださっているか、守り導いてくださっているか、己の人生を顧みて、自分の生活を振り返っていくなかで、その神の言葉と自分の人生を重ね合わせていくのであります。それは知識や知恵、よい教え、よい忠告としての聖書の言葉ではなくて、生ける心のある方の言葉として、まさによい知らせ、福音として聖書に聴くとき、その言葉が私たちの心の隅々にまで響き渡ってくるでありましょう。
そのとき、私たちは自分の目の前にあるこの十字架がこの私のためのものであることに心開かれるのであります。この十字架は、神のものを自分のものだと言い張り、自分の人生に神はいらないと、神を殺した私の「罪の裁きの代償」であるとわかるのであります。その十字架に触れるとき、そしてその愛に触れられるとき、私たちはいままで自分がどれだけ父なる神を裏切り、傷つけ、苦しめてきたか、本当の自分の悲惨さに気づき、打ち砕かれるのであります。そして本当に心から悔い改めることができるのであります。「神様、ごめんなさい、神様、申し訳ない…。」そんなあなたに復活の主が語りかけるでありましょう。「恐れることはない。あなたは私の子だ」と。そうやって父なる神から赦しをいただく。父なる神の愛を信じて生きる。これが私たちの「信仰」であります。
そのようにして、私たちは「礼拝」のなかで頑なであった私の心が動いていく不思議を経験します。こんなにも喜ばれる自分なのだと知り、主の御前に「打ち砕かれる」ことがこんなにも幸いであると言えるようにされていきます。かつては自分の不甲斐なさに、愚かさに、情けない弱さに泣いた私たちであったかもしれません。しかしいまはこんなにも愛され、こんなにも喜ばれている自分とされているのだから、父の懐で、父なる神の懐で、きっといまは感謝と喜びの涙が溢れ、咽び泣くでありましょう。そして、この愛の道を教え、証しすべく、新しい歌を主に歌うべく、ここからまた立ち上がる者とされていくでありましょう。ここに「失われた者」が「父のもと」に帰り、主に見出された、よい知らせ、福音の喜びがあります。
父なる神よと、あなたに呼びかけることのできます幸いを思います。かつては「失われていた」私たちがあなたによって見出され、ここに立たされております。いかに驚くべきことか。いかに喜ばしいことか。今日もこの福音の喜びに、この赦しに生きる者とならせてください。私たちはいま、あなたの愛を知り、あなたの御言葉に従って歩みます。この祈り、救い主なる主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン