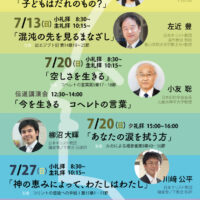イエスよ、わが喜びよ
ローマの信徒への手紙 第1章1-7節
川崎 公平

主日礼拝
■私の声につきまして、多くの方にご心配いただきました。先週の日曜日の主礼拝からだんだん喉がおかしくなり、翌月曜日にはほとんど声を出すことができなくなって、病院に行って声帯炎という診断を受けました。まだ完治には程遠い状態ですが、何とかここに立たせていただいています。「神さま、日曜日までには何とか、声を返してください」という祈りの中で、改めて伝道者パウロの書いたローマの信徒への手紙第1章1節の言葉が胸に迫りました。「キリスト・イエスの僕、使徒として召され、神の福音のために選び出されたパウロから」。わたしパウロは、神の福音のために神に召されたのだと言っています。伝道者としては当たり前のことのようですが、この言葉が今さらのように心に迫るものがありました。「神さま、もしあなたがわたしの声を、福音のためにお用いになるならば、どうかわたしの声を返してください」。「できれば、日曜日までに何とかお願いします。あなたの福音のために」。わたしの声が、何のために神に召されているかというと、福音のためである。そのことを、改めて思わされました。
先週から、この礼拝でローマの信徒への手紙を読み始めました。まだ直接には会ったことのないローマの教会に宛てて書かれた手紙です。そこでパウロが、自己紹介をするように自分の立場を明らかにしているのが、この言葉です。「キリスト・イエスの僕、使徒として召され、神の福音のために選び出されたパウロから」。「神が私を召し出してくださったのは、ほかでもない福音のためであって、今ここでも、わたしはあなたがたに福音を告げる」。そのような手紙を、今私どもも読み始めているのです。
■そこで改めてよく考えなければならないことは、この〈福音〉という言葉です。福音などという日本語は、日常ではまず使われることはありませんが、平たく言い直せば「良い知らせ」ということです。わたしは、あなたがたに良い知らせを伝えたい。わたしは、そのために神に召されたのだ。
ある人がこういうことを言いました。「われわれの信仰生活は、よい忠告を受けるためのものではない。ためになる話を聞くのでもない。よい知らせを聞くのである」。もしかしたら多くの人が、この意味で根本的な誤解をしているかもしれません。下手をすると、洗礼を受けて教会員になっている者の中にも、こういう誤解をしたまま礼拝生活を続けている場合があるかもしれません。礼拝に出て、聖書のよい教えを学んで、それを実生活に生かしていこう。よい教えを実生活に生かしていくとどうなるのか、それはよくわかりませんが、いろんな気づきを与えられたり、いろんな光を与えられたり、それでたとえば人生が豊かになるとか、世のため人のために役立つ生活ができるとか、いろんなことを人は考えるかもしれませんが、けれどもそういうことは、福音とは何の関係もないのです。いや、少しは関係あるかもしれません、福音の応用問題のような形でそういうこともあるでしょうが、それが根本ではありません。私どもの信仰生活の根本は、よい知らせを聞くことである。そのよい知らせを聞いたら、人生が根本的に新しくなるような、そのような福音を、私どもはここで聞かせていただくのです。
もちろん信仰生活をしていれば、いろいろよい教えをいただくこともあるでしょう。その教えを守って生活していれば、人生が豊かになったり明るくなったりすることもあるでしょう。それはしかし、いわゆるご利益とは違います。そして私どもは一応、そのことをよく承知しているつもりなのです。私どもの人生にはいろんなことが起こります。いろんな喜びがあり、いろんな悲しみがあり、時に耐えられないような出来事も起こる。それで多くの人が、さまざまな神仏に助けを求めたり、それこそよい忠告を受けるために神社のおみくじやら占い師やらにお伺いを立てたりするのですが、われわれキリスト教会は、どこかそういう安直な信仰をばかにしているところがあると思います。無病息災、商売繁盛、学業成就、そんなことのためにわれわれは礼拝をしているのではない、と言いながらも、いざ自分の身に良いことや悪いことが降りかかってくると、なかなか冷静ではいられません。
けれども、私どもの信仰生活の中心は、よい知らせを聞くことです。そして、本当の意味で良い知らせを聞いた人間は、どんなに悪いことが続いても、その人の人生は根本的なところではびくともしないし、逆にその人の人生がどんなに豊かで、どんなに順風満帆であっても、もしその人が本当の意味でよい知らせを聞いていなかったら、いつまでたってもその人は、砂の上に建てられた家のような不安定さを抱えたままになるでしょう。福音というのはそういうものです。
■その福音の内容について、2節以下でこのように説明します。手紙全体の冒頭に書いてあるこの言葉は、パウロがこの手紙で語り始めようとしている福音の要約であると言うことができます。
この福音は、神が聖書の中で預言者を通してあらかじめ約束されたものであり、御子に関するものです。御子は、肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められました。この方が、私たちの主イエス・キリストです(2~4節)。
〈福音〉ということでまずパウロが言うことは、「この福音は、神が聖書の中で預言者を通してあらかじめ約束されたものである」ということです。この場合の「聖書」というのは旧約聖書のことです。キリストがこの地上においでになるよりも何千年も前から、神学的に言えば永遠の昔から、神があらかじめ約束されたもの、それが福音である。ある人はそのことを説き明かして、「福音というものは、天地を貫く真理であり、歴史を通して変わらないものである」と言っています。昨日今日の思いつきによるものではない。決して一時の気まぐれによるものでもない。したがって、この良い知らせはどんなことがあっても永遠に揺らぐことがない、そういう神の約束であるということです。
このことについて明確な光を与えるのは、マルコによる福音書第12章に伝えられる主イエスの譬え話です。主イエスが十字架につけられる2、3日前に、こういう譬え話をされました。ある農場主が、丹精込めてぶどう園を造り、そのぶどう園を農夫たちに委ねて長い旅に出たというのです。このぶどう園の主人は神を意味します。そしてぶどう園は私どもの住む世界、その世界の管理を委ねられた農夫たちというのは、人間全体と言ってもよいし、あるいは神の民イスラエルと言った方が正確かもしれません。さて、農夫たちは一所懸命ぶどう園で働きました。神がよく準備してくださったからでしょう、すばらしい実りを見ることができました。「いやあ、すばらしい。われわれのぶどう園が、こんなに豊かに」。農夫たちは、どんなにうれしかったことでしょうか。と、そこにぶどう園の主人のもとから、使いの者がやって来て言いました。「さあ、あなたがたの収穫したものを主人に返しなさい」。そうしたら、農夫たちはこのぶどう園が主人のものだということを知ってか知らずか、この使いの者を袋叩きにして追い返したというのです。そののちたくさんの使いの者が次々と送られたけれども、どの使いの者も無事に帰って来ることはありませんでした。殴られたり侮辱されたり、ある者は殺されたり。それで最後に、神はご自分の愛するひとり息子を送った。すると農夫たちはこのひとり息子を見て、「こいつはぶどう園の跡取りだ。これを殺してしまえば、世界はわれわれのものになるぞ」と言って、これを殺してしまったというのです。
この主イエスの譬え話は、ロマ書第1章2節以下を見事に説き明かしたものだと思います。「この福音は、神が聖書の中で預言者を通してあらかじめ約束されたものであり、御子に関するものです」。先ほど紹介した譬え話の中で、まず心を打たれることは、たくさんの使いの者が送られ、しかもそれが例外なく農夫たちによって痛めつけられたということです。この使いの者たちというのが、ここで言う預言者にあたります。その預言者たちというのは、それこそ何かためになる話をしたのではないのです。預言者たちが伝えたことは、まさしく良い知らせ、福音の中核であって、「このぶどう園は神のものなんだよ。あなたがたの存在のすべてが、神のものなんだよ。だから、神のものは神に返しなさい」。
先週の礼拝で、ハイデルベルク信仰問答の最初の問答を紹介しました。それをここで繰り返すこともできると思います。「生きるときも、死ぬときも、あなたのただひとつの慰めは何ですか」。そう尋ねて、こう答えるのです。「わたしのただひとつの慰めは、わたしのすべてがキリストの所有であることです」。この慰めが、生きるときも、それだけではありません、死を越えて、わたしを慰める。
けれどもあの悪い農夫たちは、見事にその慰めを忘れました。それはまた私ども自身の姿でもあると思います。自分の人生は自分のものだ。自分のものを自分の好きなようにして何が悪い。その自分の人生を少しでも豊かなものにしようとして、それこそよい忠告を求めたり、ためになる話を聞いてみたり、どうも聖書が世界でいちばんためになる書物であるらしい、ひとつ人生の最後に聖書の勉強でもしてみるか、などと言ってみたりするのですが、そういう悪い農夫である私どもが根本的に間違っているのは、あなたの人生はあなたのものではない、すべては神のものなのだから、神のものは神に返しなさい、ということであったのです。しかも、実はまさにそのことが、福音そのものであったのです。
■この福音の成就のために、最後に遣わされたのが神のひとり子、わたしたちの主イエス・キリストでした。私どものすべてを神のものとして取り返すために、このお方は私どものところに来られたのです。だからこそ6節でも、「あなたがたも異邦人の中にあって、召されてイエス・キリストのものとなったのです」と言うのです。主イエス・キリスト、このお方こそ、私どもの信じる福音の中核です。私どもが信仰生活をしているのは、よい忠告を受けるためでもなく、ためになる話を聞くためでもなく、ただ主イエス・キリスト、このお方と共にいたいのです。けれども、このイエス・キリストというお方の到来の意味を知るために、まず私どもが知っていなければならないことが、「この福音は、神が聖書の中で預言者を通してあらかじめ約束されたものである」という、このことです。この神の最初からの約束は、ご自分の僕たちがどれだけ乱暴されても、そして遂にひとり息子が殺されても、それでも神の約束に揺らぐところはひとつもありませんでした。その意味でも旧約聖書と新約聖書は、本質的にひとつのものです。人間の反逆と、神の愛の真実の歴史であります。その神の愛の真実の最後に遣わされたのが、わたしたちの主、イエス・キリストです。そのことについて、さらに3節以下ではこう言われます。
〔この福音は、〕御子に関するものです。御子は、肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められました。この方が、私たちの主イエス・キリストです。
御子イエス・キリストのことを簡潔に紹介して、まず「肉によればダビデの子孫から生まれ」と言います。ダビデというのは、旧約聖書における最大の王、いわゆるレジェンドです。そのダビデの血統から救い主キリストが現れるということは、うっかりすると、「それはまあ、キリストさまだし、あまり中途半端な血筋からお生まれになるわけにもいかないよな」ということになりそうですが、聖書そのものがダビデについて何をどう伝えているかをよく考えてみると、決してそんな単純な話ではありません。ダビデは一方では伝説的な英雄でしたが、他方では非常に人間的な人間でした。数々の失敗がありました。その中でも最悪の失敗は、自分の部下の妻を奪い取ったということです。聖書というのは、こういうことを本当にびっくりするほど露骨に伝えると思いますが、あるとき、ダビデは自分の城の屋上から、きれいな女性が裸で水浴びをしている姿を見て、要するに男として我慢ができなくなったというのです。それで王としての特権を使ってこの女性を自分の寝室に招き入れ、やがてこの女性が妊娠してしまって、それを隠し通すために、この女性の夫を罠にかけて戦場のどさくさにまぎれて殺してしまったというのです。結果としては、それがイスラエルの滅亡につながったと、サムエル記・列王記は伝えるのですが、悪い農夫と言ったらダビデ以上に悪い農夫もなかなか見つからないかもしれません。ところが、まさしくそのダビデの血筋に救い主キリストがお生まれになったのです。それは、確かな神のみ旨に根ざすことでした。
■ここに「肉によればダビデの子孫から生まれ」と書いてあります。さらにわかりにくいのは、これが次の句と対になっていて、「肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められました」と続くのですが、この「肉によれば、聖なる霊によれば」という表現は、うっかりすると「悪い意味ではこうだけど、良い意味ではこうで」ということになりかねません。「肉を取ってダビデの子孫というのはあくまで外見上のことで、目には見えない本質においては神の子であられたのだ」。パウロが言っていることは、そういうことではありません。むしろここで「肉によれば」と言われていることが、どれほどの重みを持つか、そのことをよく考えなければなりません。「肉によればダビデの子孫から生まれ」。それを教会の言葉で〈受肉〉と呼びます。外見上そういう姿を取られた、という表面的な話ではありません。受肉という出来事の中に、まさにそこに神の愛の本質があり、今日の主題で言えば、福音の中心があるのです。
ヘブライ人への手紙第4章15節に、こう書いてあります。「この大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪は犯されなかったが、あらゆる点で同じように試練に遭われたのです」。受肉とはこういうことでしょう。肉を持った人間の弱さをなめ尽くしてくださいました。それはたとえば、ダビデが肉において罪を犯したとき、キリストはその弱さに同情できない方ではないということです。「罪は犯されなかったが、あらゆる点で同じように試練に遭われたのです」。しかもそのようなお方が、あのぶどう園の農夫たちのためにも、同じ目線に立って、福音を伝えてくださったのです。「このぶどう園も、いやそこで働くあなたがたの存在も丸ごと、神のものなんだよ」。「神があなたがたの父でいてくださるんだから、何も思い煩うことはないじゃないか」。
けれども農夫たちは、最後に送られてきた神のひとり子を、迷わず殺した。惜しまず殺した。けれども、それで終わりとはなりませんでした。神は、み子イエスを死人の中から復活させられました。「聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められました」とあるのは、復活によって初めてそのとき、主イエスが神の子に格上げされたということではありません。主は永遠の昔から神の子です。だからこそ、復活という出来事が当然起こらなければなりませんでした。
そこで問題は、その復活のキリストの前に、われわれがどういう態度で立たなければならないか、ということです。私どもは悪い農夫たちなのですから、いったいどの面下げてこのお方の前に立つことができるか、ということになるかもしれません。事実あの農夫たちは、自分たちの殺したはずの主人のひとり息子が生き返って、ただ震え上がるほかなかったかもしれません。もしキリストの復活が、私どもにとって福音であるならば、あの農夫たちが赦されているからでしかありません。そして事実、その通りなのです。
今、私どももお甦りの主の前で知ります。「わたしは、わたしたちは、神のぶどう園の幸せな農夫たちなんだ」。これが、福音です。よい知らせです。それを聞いた今は、何を恐れることもありません。たまたま目の前の収穫が多く見えようが少なく見えようが、何も思い煩う必要もありません。ただ悔い改めて、今復活の主と共にあることを、ただひとつの慰めとさせていただきたいと心から願います。お祈りをいたします。
私どもの救い主、イエス・キリストの父なる御神。あなたの福音を聴かせていただきました。あなたの永遠の約束の内に救い取られている自分自身の幸いを、今確かな思いで確かめる者とさせてください。今悲しみの中にある者にも、恐れの中で立ち上がれなくなっている者にも、あなたの福音が与えられているのですから、どうかそのために仕える教会とさせてください。主イエス・キリストのみ名によって祈り願います。アーメン