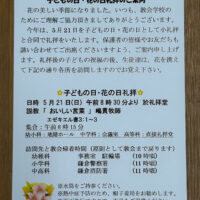神さまに捕まったら
マルコによる福音書 第6章14-29節
川崎 公平

主日礼拝
■先ほど朗読したマルコ福音書の記事は、たいへん生き生きとした描写で書かれていますから、理解するのに難しいところはほとんどなかったと思います。ヘロデという、その地域ではいちばん偉い権力者であった人が、その権力をほしいままにした結末が、洗礼者ヨハネの首をはねて、お盆の上に載せて自分のかわいい娘にプレゼントしたということだったというのです。こんな聖書の言葉を読むことによって、いったい、今朝はどのような礼拝をするのだろうかと、いぶかる方もおられるかもしれません。皆さんは、どういう感想をお持ちになったでしょうか。
今申しましたように、この記事は、たいへん生き生きと、むしろたいへん生々しく描かれています。ほかの福音書の記事が生き生きとしていないわけではないですが、福音書を書いたマルコが、この洗礼者ヨハネが殺されるいきさつを、どんなに深い思いを込めて書いたことかと思うのです。しかもこれは、ただどこかの権力者のでたらめな横暴を暴き立てるというだけの話ではないと思うのです。新聞の三面記事やネットニュースの片隅に現れるような、どこかの偉い人が実はこんなに悪どいことをした、けしからん、というだけの話ではないのです。
ヘロデが洗礼者ヨハネを殺したというのは、それはすなわち、神の言葉を殺したということです。「ヘロデは〈神〉を殺した」とまで言い換えると、さすがに語弊があり過ぎるかもしれませんが、〈神の言葉〉を殺したことは確かです。そしてそれは結局、神を殺したがっている人間の本性がそこに現れていると言わなければならないと思うのです。
■いろんな意味で、たいへん興味深い物語です。しかしまず、ここで皆さんと一緒によく考えてみたいと思いますのは、何と言っても20節です。
なぜなら、ヘロデが、ヨハネは正しい聖なる人であることを知って、彼を恐れ、保護し、また、その教えを聞いて非常に当惑しながらも、なお喜んで耳を傾けていたからである。
この言葉からひとつ明らかになることがあります。昔も今も、権力者が自分の気に食わない発言を弾圧するということはいくらでも起こるのですが、この20節を読む限り、何だか少し様子が違います。権力に対して批判的な発言をする人を不当に逮捕して、場合によっては拷問を加えて、二度とおかしなことを言えないようにする、ということを、少なくともヨハネに対しては、ヘロデは決してしなかったらしいのです。もちろん最初は、17節、18節に書いてあるように、俺様にたてつく奴は許さん、と言って逮捕したのでしょう。それで、さあ、こいつをどういたぶってやろうかと思ったら、そこに思いがけない、奇跡のような出会いが起こりました。もう一度20節を読みます。
なぜなら、ヘロデが、ヨハネは正しい聖なる人であることを知って、彼を恐れ、保護し、また、その教えを聞いて非常に当惑しながらも、なお喜んで耳を傾けていたからである。
ヨハネはヘロデに捕らえられることによって、むしろまさにそこで、ヘロデに面と向かって福音を語る機会を得ました。そしてヨハネは、その機会を逃さなかったのです。「今こそ、この人のために」と、ヘロデのために神の言葉を語りました。そしてヘロデもまた、神の言葉を聞く耳を、神の言葉を聞くための心を持っていたのです。「ヨハネは正しい聖なる人であることを知って」と書いてあります。「ああ、この人は、神の言葉を語っているのだ」。それでヘロデはヨハネを恐れ、また保護し、さらに不思議なのはそのあとです。「また、その教えを聞いて非常に当惑しながらも、なお喜んで耳を傾けていたからである」。
「非常に当惑しながらも」というのは、すぐに分かります。洗礼者ヨハネという人は、いつも悔い改めを語りました。相手がヘロデだろうと誰であろうと、何ら態度を変えることなく、「罪を悔い改めなさい」と語ったのでしょう。面と向かってそんなことを言われて、当惑しない人がむしろひとりでもいるだろうかと思います。ところがここでは、ヘロデは自分を当惑させる言葉を聞きながら、なお同時に喜んでいたというのです。「なお喜んで耳を傾けていた」という、この日本語の表現からも明らかなことですが、ヘロデがヨハネの言葉に耳を傾けたのは、ただ一度きりではありませんでした。一度聞いたらそれでおしまい、ではなくて、繰り返し、何度も聞き続けた。新約聖書の原文はギリシア語で書かれましたが、ギリシア語にはそういう動詞の特別な形があるのです。繰り返し、何度となく、ヘロデはヨハネの牢獄を訪ねて、「また神の言葉を聞かせてくれないか」と頼んだのかもしれません。そしてそのたびに、非常な当惑と、しかも同時に喜びが生まれたというのは、たいへん不思議な情景ですが、本当は不思議でも何でもないと私は思います。
■ヨハネという人は、いつでも悔い改めを語った人です。悔い改めだけを語ったのです。聖書の語る悔い改めというのは、ただ罪をあげつらうというような話ではありません。「神のもとに帰りなさい」という意味です。しかも、その帰って行った先で待ち構えている神が、鬼のような顔をしているわけではないのです。あのいなくなった弟息子が、放蕩の限りを尽くしたあげく家に帰って来たとき、父親は走り寄ってこの息子を抱きしめ、「よく帰って来た」と、喜びをもって迎えてくださいました。
ヨハネはヘロデにも、「帰って来い」と、そのことだけを語ったのです。神は待っておられるのだから、どうか、神のもとに帰って来てほしい。けれどもそのとき、あなたの家族の問題から目を逸らすわけにはいきませんね。あなたの妻ヘロディアは、あなたの兄弟から無理やり横取りしたものでしょう。それを神がご覧になって、どう思われるかね、と、そう言われたときに、ヘロデは、「非常に当惑しながら」、ああ、自分は悪いことをしたのだということが、よく分かったのです。分かっちゃいるけど、自分ではどうしようもないことだから、どうしていいか分からないから、だから当惑するのは当然です。ところがそんな自分を、それでもなお神が愛していてくださる。ヨハネの言葉を聞いていると、その神の愛が痛いほどによく分かったのだと思います。だからこそヘロデは、ヨハネの言葉を喜んで聞いたのです。繰り返し聞いたのです。「もう一回ヨハネの話を聞いてみよう」。「もう一回、今度はもっと真剣に聞いてみよう」。そこでヘロデが聞いたヨハネの言葉は、事実、神の言葉であったのです。この地上において、他の誰からも聞くことのできない言葉であったのです。
このヘロデの姿は、決して私どもにとって他人事にはならないと思います。「悔い改めなさい」と言われて、当惑しない人間がむしろひとりでもいるでしょうか。「あなたはまだ悔い改めていないではないか」と言われたら、きっと誰もが、行き場を失うほどの思いに追い詰められるのです。追い詰められて、「神のもとに帰れ」と言われるのですが、事実私どもも、そういう神の言葉を、喜びの言葉として、ここで聞き続けているではありませんか。
けれどもそこでなお問わなければならないことは、そのヘロデが結局ヨハネを殺してしまったのはなぜか。どうして、そんな悲しい結末を迎えなければならなかったか。もちろん、そのいきさつは、マルコによる福音書が生き生きと伝えてくれている通りですけれども、何とも悲しく、つらい出来事ではないでしょうか。
■ここに「ヘロデ」という名が出てきますが、聖書には何人かの「ヘロデ」という名前の人が登場します。おそらくいちばん有名なヘロデは、クリスマスの物語に登場するヘロデ大王と呼ばれる人です。新しい王が生まれたという噂を聞いて、よほどビビったんでしょう、ベツレヘム周辺に住む2歳以下の男の子を皆殺しにするという、気がふれたとしか考えられないようなことをしましたが、今日読んだところに出てくるヘロデは、このヘロデ大王の息子のひとりに当たります。
そのヘロデがここでも「王」と呼ばれていますが、ちょっと調べると、正確には王ではなかったということが分かります。分かりやすくたとえると、県知事くらいの身分だったと言われます。たとえば神奈川県知事の黒岩さんが、自分の娘に向かって「もし何だったら、神奈川県の半分でもお前にやるぞ」と言ったって、そんなことできるわけないと誰もが知っていますし、このヘロデだってそんな権限は、もともとなかったようです。ただ自分のお誕生日会で、調子に乗って飲み過ぎただけです。
そんな小さな権力者を、けれどもマルコが「王」と呼んでいるのは、マルコの知識が足りなかったのだと考える学者もおりますが、多くの人は、マルコはどうしてもこのヘロデという男を「王」と呼びたかったのだと考えます。なぜかと言うと、ヘロデには国の半分をやる権限はなかったとしても、ヨハネを殺すことはできたからです。「王」というのは、ここでは要するに、自分のしたいことを押し通すことができる人のことでしょう。何でもできる。誰も自分には逆らえない。そういう自由を持っていた王ヘロデが、その自由を最大限に行使した結果が、ヨハネを殺すということであった、はずなのですが、しかもたいへん逆説的に、マルコはこのヘロデという王が、実はいちばん不自由な男であったことを、それこそ生々しく伝えてくれます。26節です。
王は非常に心を痛めたが、誓ったことではあるし、また列席者の手前、少女の願いを退けたくなかった。
つまり、要するに、自分のメンツを守りたいとか、その裏に隠れているのは妻の機嫌を損ねたくないとか、はたから見れば実につまらないことのようですが、本人からしたらそれがいちばん大事なんです。自分の生活を変えるわけにはいかないし、せっかく横取りした妻を手放すわけにはいかないし、権力を手放すわけにはいかないし。それで結局、ヘロデはヨハネを殺しました。自分が喜んで聞き続けた神の言葉を、永遠の闇に葬ってしまいました。
ですからある人は、この箇所を説き明かしながら、ふと自分の感想を漏らすようにこういうことを書いています。ヘロデという人は、自分の弱さを知っていたのだ。その弱い自分のために、「帰って来い、悔い改めるのだ」と懇ろに語ってくれるヨハネの言葉を、正しく聞き取るだけの耳を、また心を持っていたのだ。だから、もしもヘロデが王でなかったなら、そうではなくて民衆のひとりでしかなかったなら、きっとヘロデは誰よりも真剣に悔い改めて、ヨハネのもとで洗礼を受けたに違いない。けれども、そんなヘロデが自分で自分の首をしめてしまったのは、「自分は王である」、王になりたい、王として振舞いたい。それだけの理由だったのだと、この人は言うのです。
しかし私は、その人の文章を読みながら、考え込んでしまいました。自分だって同じじゃないか。私どもだって、皆ヘロデと同じではないか。自分のメンツを守りたいとか、妻の機嫌を損ねたくないとか、あの人たちの目があるからとか、だから今はちょっと条件が悪いんだ、まだ環境が整わないんだと、いろいろ理由をつけて自分の罪を本当に悔い改めないということが、いくらでもあるだろうと思うのです。自分が悪いことをしているのは、よく分かっている。でも、だって、こっちにもいろいろ事情があるんです。神さま、あなたもご存じでしょう。私にも私の生活があるんです。職場がこんなだから、いろいろ言う人がいるから。家族がこんなだから、子どもが言うことを聞かないから。だから、自分が罪を犯してしまうのはしょうがない、条件が悪いのだと、いろんな言い訳をしながら、それでも私どもは非常に当惑しながらも、なお喜んで神の言葉を聞き続けているのです。きっとそうでしょう。ところが私どもは、いろんな言い訳をしながら、徹底的に神に服従するつもりはないのです。神の言葉を殺してでも守らなければならない、自分の生活があり、自分の幸せがあると考える、そういう私どもの心のいちばん深いところにある思いは、結局のところ、「王になりたい」、自分の好きなようにしたい、ということでしかないのかもしれません。
■ところが、話はそこで終わりません。今日の話の本題はここからです。というよりも、この福音書の記事の本題は、ヘロデがヨハネを殺した、ということではないのです。その点、私どもは注意深く聖書を読まなければならないと思います。少し余計なことかもしれませんが、私どもの聖書には小見出しが付いていて、「洗礼者ヨハネ、殺される」とありますが、本当はここで洗礼者ヨハネが殺されたわけではありません。段落の最初の14節には、「イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った」とあります。それで世間の人びとは、あのイエスとは何者だろうと噂をして、もしかして洗礼者ヨハネが生き返ったんじゃないかとか、他にもいろいろ言っていたというのですが、これを聞いて誰よりも怯えたのはヘロデであった、という話なのです。「私が首をはねたあのヨハネが、生き返ったのだ」(16節)。ですからこの段落の小見出しは、本当は「洗礼者ヨハネ、殺される」ではなくて、「洗礼者ヨハネを殺したことを、ヘロデが改めて思い出した」という話なのです。なぜ思い出したのでしょうか。イエスの名が聞こえてきたからです。
ヘロデは既に、過去の記憶として封印してしまっていたかもしれません。自分がヨハネの言葉を喜んで聞き続けたことを、けれども遂にこれを殺してしまったことを、本当は忘れたかったし、忘れていたかもしれないけれども、それをいやでも思い出さずにおれない出来事が始まりました。それが、イエス・キリストという出来事です。
そのとき、ヘロデは明らかに恐れたのです。「私が首をはねたあのヨハネが、生き返ったのだ」。なぜそう思ったかと言うと、かつて自分を当惑させ、しかも同時に喜びを与えてくれた同じ響きの言葉が、再び聞こえてきたからです。その神の喜びの言葉を、自分は叩き潰したはずなのに、今度はイエスという男が、もっと激しい運動を始めている。そのとき、あの懐かしい当惑が、再びよみがえってきたのです。「神が私を追いかけて来る。神が、まだしつこく私を捕まえようとしている。もう逃げられないのではないか」。きっと、私どもも、ヘロデと同じ経験をしていると思うのです。
■神の言葉が勝つのでしょうか。それとも、人間の罪が勝つのでしょうか。実は、福音書が語ることは、結局このひとつのことに尽きるのだと思うのです。洗礼者ヨハネを通して神の言葉が新しく響き始めたとき、何よりも、神の言葉そのものであられるイエス・キリストが現れたとき、実にしたたかな、神の戦いが始まったのです。その神の戦いというのは、ヘロデのような権力者の魂をも捕えようとする、神の愛の戦いであります。
今日読んだ、そのあとの段落を読むと、主イエスと弟子たちを囲んで、おびただしい群衆が群がっていたと言います。五千人という数字が、その段落の最後に出てきます。それほどの群衆が、ある意味ではヘロデと同じように、神の言葉を喜んで聞いたのです。ところが第6章の34節を読むと、主イエスはこの群衆をご覧になって、その「飼い主のいない羊のような有様を深く憐れみ」と書いてあります。この群衆には、この羊たちには、飼い主がおりませんでした。その飼い主のいないような群衆が、やがて主イエスがエルサレムで十字架につけられようとするときに、「イエスを殺すな、神の言葉を殺すな」と反対運動をしたわけではないのです。むしろかえって、「イエスを殺せ、イエスを十字架につけろ」と狂ったように叫び続けた、その姿はまさしく「飼い主のいない羊のような有様」で、それを主イエスはどんなに深い憐れみのまなざしでご覧になっていたかと思います。そして遂に、群衆の大声が勝った、かのように見えました。ヘロデがヨハネを殺したように、飼い主のいない群衆がイエスを殺した、かのように見えたのです。けれども神の言葉が人間の罪に負けることはありません。あり得ません。主イエス・キリストのお甦りは、その確かな保証です。
その神のみ言葉の勝利の前に、今私どもも立たせていただいているし、先週の礼拝でこの直前の段落を読んだときにも学んだ通り、主イエスは12人の弟子たちを伝道のためにお遣わしになった。その意味では、ヘロデがイエスの名を耳にして、恐れたり当惑したりした、その直接のきっかけは主イエスではなくて弟子たちであったとも言えるのです。私どもも同じように、このみ言葉の勝利のために仕えさせていただくのです。神の愛が必ず勝利するのだと信じて、そのことを告げる私ども教会の言葉は、権力者を当惑させ、恐れさせ、しかしまた確かな喜びを与える力を持つのです。そのような神の言葉に仕えさせていただくこと、これにまさる光栄はないのであります。
旧約聖書のヨナ書をあわせて読みました。大きな魚に飲み込まれたヨナの話は、多くの人が子どもの頃から覚えます。神に背く大国アッシリアの都ニネベの罪は、遂に神がこれを滅ぼさなければならないほどに大きくなった。そのことを告げるために遣わされた預言者ヨナが、一度は逃げたけれども、大きな魚に飲み込まれて三日三晩そのお腹の中で過ごすという過酷な経験を経て、魚に吐き出されたと思ったら、そこがニネベであった。そこでヨナは腹をくくって、神の裁きを告げるのですが、そこでたいへん思いがけない経験をします。それが今日読みました、ヨナ書の最後の部分です。ヨナ自身、こんな罪深い国は滅びてしまえと思っていたのですが、ところが神はこのニネベの町を惜しんで、結局滅ぼさなかったという、不思議な恵みに出会うのです。「どうして私が、この大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか」。やっぱり、どうしても殺せない。「そこには、右も左もわきまえない十二万以上の人間と、おびただしい数の家畜がいるのだから」。まさしく、飼い主のいない羊を、なおしぶとく生かそうとする神の恵みは、預言者ヨナを悩ませるほどのものがありましたが、本当はこんなにありがたいことはないのであります。私どもがあきらめても、神さまはあきらめない。この神の恵みの勝利を信じて、これに仕える喜びと誇りを、今新しくさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。
主イエスの命の勝利の中で、今私どももみ言葉を聴きます。罪深い私どもにとって、あなたの言葉は、非常に当惑しながらも、なお喜んで耳を傾けるべき恵みの言葉であります。今はもう、あなたの恵みに捕まってしまったのですから、あの12人のごとく、あるいはまた預言者ヨナのように、あなたのお遣わしくださる場所で語るべき言葉を語る者とさせてください。あなたの恵みの勝利が、全地に及んでいることを信じさせてください。御国が来ますように。御心が行われますように。主のみ名によって祈り願います。アーメン