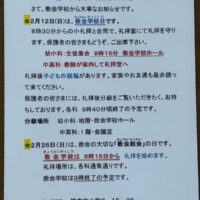キリストの奴隷は自由
川崎 公平
フィリピの信徒への手紙第Ⅰ章1-11節(II)

主日礼拝
■先週の日曜日より、伝道者パウロの書きましたフィリピの信徒への手紙を読み始めています。この手紙のいちばん最初のところに、「キリスト・イエスの僕であるパウロとテモテから」と書いてあります。しばしばパウロという人は、自分の書いた手紙の最初にこのような自己紹介の表現を用いました。「わたしは、キリストの僕パウロである」。「僕」というのは「奴隷」という意味の言葉で、むしろそう訳した方がよかったかもしれません。わたしは、キリストの奴隷である。パウロがこの手紙の最初にそう書いたとき、どんなに誇らしい思いを込めてこの言葉を書き記したことだろうかと思います。
「キリストの僕」「キリストの奴隷」というこの言葉のニュアンスを理解するために、もしかしたら思い出した方がよいかもしれないことは、パウロがこの手紙を書いたのは、牢獄につながれている時であったということであります。そのことについて、フィリピの教会の仲間たちも心配していたようです。先週も触れましたが、第1章の12節以下に、「兄弟たち、わたしの身に起こったことが、かえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。つまり、わたしが監禁されているのはキリストのためであると、兵営全体、その他のすべての人々に知れ渡り……」と書いてあります。「兄弟たち、わたしの身に起こったことを、正しく理解してほしい」。心配しすぎないでほしい。わたしは、キリストの奴隷であって、ほかの誰の奴隷にもならない。いかなる権力者といえども、誰もわたしの自由を脅かすことはできない。たとえ、信仰のゆえに牢獄につながれることがあったとしても、われわれは根本的に自由な人間である。そのことを、よく理解していただきたい。そのために、この手紙も書かれたのだと考えることができます。
■このようなことを考えますときに自然と思い出されることは、パウロがかつて初めてフィリピの町で伝道をしたときにも、すぐに牢屋の中に閉じ込められたということです。そのあたりの事情を伝える使徒言行録第16章の一部を、先ほど合わせて読みました。パウロたちがフィリピの町で伝道を始め、何人かの人に洗礼を授けることができたと思ったら、たちまち逮捕、投獄され、教会の仲間たちはどんなに心細かっただろうかと思います。ところが使徒言行録の伝えることは、「突然、大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸がみな開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった」(26節)。「牢の土台が揺れ動いた」というのは、印象深い表現です。パウロたちの自由を束縛していたはずの牢獄が、その土台ごと揺り動かされてしまった。それもまた、パウロたちがどんなに自由な場所に生かされていたかを象徴的に伝えるものでしょう。面白いのはそのあとの話で、この地震で牢獄の壁も鎖も全部壊れてしまい、牢獄を見張っていた看守は青ざめて、囚人たちは皆逃げてしまったと思って自殺を図ったというのです。そこにパウロたちが現れて、自分たちは別に逃げるつもりなんかないから、自殺なんかしちゃいかんと声をかけて、それで結局、看守とその家族も皆、洗礼を受けてしまったというのです。洗礼を受けたということは、つまりその看守と家族たちもフィリピの教会を共に作る仲間になって、のちにこのフィリピの信徒への手紙を読んだということだと思います。
改めて不思議に思うことですが、使徒言行録が伝えるフィリピでの伝道の記録は、実はほとんどが牢獄の中での話であると言ってもよいのです。ところがそこに、キリストの福音の実力が遺憾なく発揮されたというのです。それは、牢獄の外でパウロたちのことを心配していたフィリピの教会の仲間たちを、どんなに励ましたことだろうかと思います。
言うまでもないことですが、パウロが牢獄の中でフィリピの信徒への手紙を書いたというのは、この使徒言行録の話とは無関係で、ずっとあとになってからまた別の町で投獄されたところで、フィリピの教会のことを案じて手紙を書いたのであります。話が分かりにくくて恐縮ですが、どうもパウロという人は、何度も投獄されたことがあったらしいのです。しかしそれにしても、フィリピの教会の人たちは、またパウロ先生が投獄されたと聞いて、自然と最初の出会いのことを思い出しただろうと思います。そういうところでパウロは改めて、自分はキリストの奴隷なのだ、ということをどうしても言わないわけにはいきませんでした。どんなに頑丈な鎖につながれていても、いつでもわれわれはキリストの奴隷として生きているのであって、この世界にあるいかなるものも、主がわれわれに与えてくださった自由解放の喜びを脅かすことはできない。「兄弟たち、わたしの身に起こったことが、かえって福音の前進に役立ったと知ってほしい」。わたしはキリストの奴隷として、その福音の前進のために仕えているのだ。どうかそのことをよく知ってほしい。
■先ほど読みました使徒言行録の第16章25節は、何気ない言葉ですが、私どもの心を打つものがあると思います。「真夜中ごろ、パウロとシラスが賛美の歌をうたって神に祈っていると、ほかの囚人たちはこれに聞き入っていた」と言うのです。既に衣服をはぎ取られ、鞭で打たれ、足には木の足枷をはめられていたと、その直前のところには書いてあります。そのような場所で彼らが歌っていた賛美の歌に、ほかの囚人たちも思わず耳をそばだてていたというのです。いったい何だろう、この人たちの歌は。何を歌っているんだろう。何のために、誰のために、誰に向かって歌っているんだろう。喜びの歌が世界でいちばんふさわしくない場所で、どうしてこんな歌が聞こえるんだろう……。考えてみれば、実に不思議な情景であります。
それはまた、フィリピの信徒への手紙の冒頭の第1章3節以下の言葉と響き合うものがあると思います。「わたしは、あなたがたのことを思い起こす度に、わたしの神に感謝し、あなたがた一同のために祈る度に、いつも喜びをもって祈っています」と言うのですが、それは牢獄の中で、パウロはいつも感謝し、喜びをもって祈っていたというのです。先週の礼拝でも触れました、「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい」という、別の手紙にある有名なパウロの言葉を思い出しておられる方もあるかもしれません。そのような賛美の歌が、喜びの歌が、他の囚人たちの心をも捕らえた。「いったい何だろう、あの人たちが歌っている歌は」。他の囚人たちにも、よく分かったのだと思います。パウロたちの歌声の中に、地上のものではない、喜びと祈りと感謝があふれていることが。われわれと同じように鎖につながれているのに、あの人たちの歌う歌は、どうしてあんなに明るいんだろう。
私どもは今、教会堂の外にまで聞こえるような声で讃美歌を歌うことを自粛しておりますが、こういう聖書の記事を読みながら、いやあ、やっぱり讃美歌は大きな声で歌わないと、というようなつまらないことをお考えになる方はいないだろうと思います。問題は、私どもがパウロと同じように、喜びに生きているか、祈りと感謝に生きているかということです。私どもの隣にも、さまざまな種類の鎖につながれている人びとが生きていると思うのです。ところがその人たちが、私どもの生き方に触れて、何よりも私どもの礼拝の姿勢に触れて、思わず目を見張るような、思わず耳をそばだてるような魅力ある姿を見せることができているか。本当は私どもにも既に、そういうすばらしい生活が与えられているはずなのです。そういう私どもの生活の特質を、パウロは繰り返し、「喜び、祈り、感謝」という言葉で描いてくれましたし、そのような生活を与えられた人間の光栄ある身分のことを、「キリストの奴隷」という強烈な言葉で表現してくれていると思うのです。
■今申しましたように、私どものうちほとんどの者は、別に牢獄につながれているわけではありません。そうでありながら、さまざまな鎖につながれている、実は非常に不自由だと感じているのではないでしょうか。キリストの奴隷ではなくて、ほかのいろんなものの奴隷になってしまっている。たとえば、新約聖書の時代の、古代ギリシアのある哲学者たちはこんなことを言いました。本来自由な存在であるべき自分の魂が、けれども肉体という牢獄に捕らえられている、そこから自分自身の魂を解放しなければならない。しかしそんなことは、実は魂とか肉体とか、小難しい言葉を使わなくたってわれわれがよく承知していることなのです。われわれ人間を不自由にしているのは、実は結局、ほかでもない自分自身である、という話でしょう。自分自身の奴隷になっている。自分の欲望の奴隷になっている。
けれどももう一方で、私どもが人間として生きるときに、いちばんわれわれを不自由にしてしまうこと、その意味でいちばん煩わしいことというのは、人間関係だろうと思います。人間同士が出会うということは、本来楽しいことです。私どもの人生の豊かさというのは、どれだけ豊かな出会いを与えられたかによって決まると言ってもよいほどで、ところがそうでありながら、私どもの人生をいちばん悩ませる問題もまた、結局は人間関係なのです。互いに愛し合うことができなくて、何を言っても言われても疑心暗鬼になってしまうような人間の関係の中で、既にわれわれは地獄になんか行かなくたって今ここで地獄の生活をすることがあるのです。私どもが多かれ少なかれ、体験的に知っていることです。
パウロが牢獄の中にありながらも、フィリピの教会のために手紙を書かなければならなかったのには、やはりそれなりの理由があったようです。この手紙の執筆の動機を暗示しているのは、第2章1節以下であります。
そこで、あなたがたに幾らかでも、キリストによる励まし、愛の慰め、“霊”による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、わたしの喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって、互いに相手を自分よりも優れた者と考え、めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい(第2章1~4節)。
ここに書いてあることは、何も難しいことはありません。学校に行く前の子どもにも分かるような話です。ちゃんとお友達のことも考えてあげなさい。利己心とか、虚栄心とか、わがままばかり言ってはいけませんよ。けれども、私どもが同時によく知っていることは、その幼稚園児でも分かるような話が、実は世界でいちばん難しいことなんです。その意味で、先ほどから申しておりますように、私どもは別に牢獄なんかに入っていなくたって、実に不自由そのものである。それを聖書は、われわれは〈罪の奴隷〉になっていると、そう言うのです。
■ところが神は、そんな私どもを愛して、罪の奴隷状態から解き放つために、御子キリストをお送りくださったと言うのです。それが今日合わせて読んだ、第2章の6節以下が書いていることで、このフィリピの信徒への手紙がいちばん伝えたかったことは、このことであると言ってもよいかもしれません。ついでに申しますと、この第2章6節以下の部分は、当時の教会でよく歌われた讃美歌ではなかったかと言われます。それをここで引用しているということは、パウロはフィリピの教会の仲間たちと一緒にこの讃美歌を何度も歌ったのかもしれません。フィリピの牢獄に閉じ込められたときにも、心からの喜びを込めてこの歌を歌い、その歌に他の囚人たちが聞き入っていたのかもしれません。
キリストは、神の身分でありながら、神と等しい者であることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、僕の身分になり、人間と同じ者になられました。人間の姿で現れ、へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした(6~8節)。
ここにも「僕」、あるいは「奴隷」とも訳すことのできる言葉が出てきます。私どもの主であるイエス・キリストこそ、実は誰よりも徹底して奴隷の身分にご自分を置かれたというのです。神の僕、神の奴隷として、だからこそ神のご意志に徹底的に従順に従われました。その神のご意志というのは、神が私どもを愛されたという、そのひと言に尽きるのです。神の愛が貫かれるために、ただそのために、御子イエスは神の奴隷として、従順を貫かれました。
「キリストは、神の身分でありながら、神と等しい者であることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、僕の身分になり、人間と同じ者になられました」。ここに、私どもの誰も知ることのなかった、ただ神のひとり子イエスだけが持っておられた自由がありました。人を愛する自由です。そのために、僕になり切る自由であります。
「へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした」と書いてあります。そこには利己心も虚栄心も、そのかけらもありませんでした。あるのはただ、神に対する奴隷のごとき服従だけであります。このお方が十字架につけられたとき、誰もこのお方をほめたりしませんでした。「ああ、この人はわたしたちのために、立派な犠牲の死を遂げてくださったのだ」とか、そんなことは誰も言わなかったのです。私どもはきっと、誰かの犠牲になる、誰かのために自分が痛みを負うというときにさえ、その自分の献身的な行為を誰がほめてくれるか、誰が認めてくれるか、そんなことばっかり考えていると思います。利己心と虚栄心の奴隷であります。けれどもキリストは、私どもに対する愛のゆえに、すべての利己心と虚栄心を捨てて、徹底的に神のみ旨に、奴隷のように従われたのであります。まさしくその意味で、このお方は、私どもの誰よりも自由でした。それに比べて、私どもの生活はどれだけ不自由なことでしょうか。そんな私どもを、まさしくその不自由から救い出すために、主イエス・キリストの十字架があり、その服従があったのだと、この讃美歌は歌うのです。
このため、神はキリストを高く上げ、あらゆる名にまさる名をお与えになりました。こうして、天上のもの、地上のもの、地下のものがすべて、イエスの御名にひざまずき、すべての舌が、「イエス・キリストは主である」と公に宣べて、父である神をたたえるのです(9~11節)。
このような歌を歌い始めるとき、しかしそのとき既に私どもも、罪の奴隷ではありません。パウロがこの手紙の最初に、「われわれはキリストの奴隷である」と、そう書き記したとき、それは本当に誇らしい、神の自由解放の救いの出来事をたたえるような思いを込めたに違いないのです。
■奴隷の生活の特色というのは、自分には主人がいる、ということだと思います。奴隷には、自分の生活なんてものはありません。許されていることは、ただ主人の意志に従うということだけであります。問題はしかし、どんな主人に仕えるかということです。私どもはキリストの奴隷になると言うのですが、キリストは決して私どもを強制的に、暴力的に奴隷にしようとされたことはありません。しかしもしも強制ということを言うならば、キリストの愛によって強制されたのであります。愛によって強制されるというのは、どうもおかしく聞こえるかもしれませんが、強烈な愛を受けたことのある人なら、よく分かるのではないかと思うのです。誰かある人から本当に愛されて、命を捨てるほどの愛に生かされて、あの人の愛があったから今の自分があると悟った人間は、そののちどんなことがあっても、その人の愛を裏切ることのないように、それ以外の生き方は考えにくくなるものです。自分のことをいちばん愛してくれた人のことを思い、当然自分もその人のことを愛して、ただその人のために生きる、その人の愛を裏切らないように生きていくことができたとしたら、それはいちばん幸せな生活であるに違いありません。
「キリストの奴隷」というのは、そういう意味でしかありません。パウロという人は、まさしくキリストの強烈な愛を受けて、だからこそ、キリストの奴隷となって、キリストの愛に全生涯を束縛される歩みをささげることができました。こんなに幸いなことはないし、しかもこの幸いは、私どもひとりひとりに等しく与えられているものなのです。
そんなパウロたちがフィリピの牢獄で歌っていた歌というのは、このキリストの愛を体いっぱいに受けた者の歌であったのです。牢獄という、人の目にはいちばん不自由と見える場所にあって、キリストに対する喜びと感謝の歌を歌うことができました。キリストの奴隷として生かされている人間が、どんなに確かな自由を与えられているか、どんなに確かな喜びに生かされているか、そのことを見事に証しする歌となりました。それが聞く者の心を動かし、遂には牢獄の壁までも破壊してしまったという出来事は、私どもにも無限の励ましを与える出来事であると思います。お祈りをいたします。
「わたしはキリストの奴隷である」と名乗ることのできたパウロの喜びと誇りを学びつつ、これに驚きつつ、私どもも今、喜んでこのお方に従うことができますように。わたしを愛し、わたしのために身をささげられた神の御子キリストの献身を賛美しながら、私どももキリストの奴隷として、解き放たれて生きることができます。自由に愛に生きることができます。「主よ、われをばとらえたまえ、さらばわが霊は解き放たれん」(讃美歌333番)と、今、確信をもって歌うことができますように。主のみ名によって祈り願います。アーメン