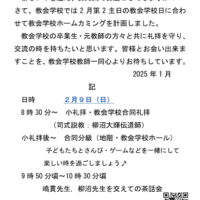今や救いの時、慰めの時
川崎 公平
ヨハネの黙示録 第7章1-17節

聖霊降臨記念主日礼拝
■今日はペンテコステ、聖霊降臨の記念の礼拝です。今から約二千年前、エルサレムの片隅で、弟子たちが集まって祈りをしていたところに神の霊が注がれて、そこに教会が生まれました。教会には、何の力もありませんでした。誰がどう見ても、教会が大きな力を持っているようには見えませんでした。けれども教会は、ただ神の霊をいただいて。神さま以外何も頼るものを持たない。けれども、ただ神の霊を注がれて、教会は初めて教会として、生まれることができました。この鎌倉雪ノ下教会もまた、ただ神の霊に生かされてここに立つ。その事実を証しする礼拝の生活を、今日もまた新しく続けさせていただきたいと願います。
今朝もいつものように、ヨハネの黙示録の続きを読みました。ここには、聖霊とか霊とかいう言葉はひとつも出てこないようですが、聖霊降臨日にいちばんふさわしい聖書の言葉を神が与えてくださったと、私は心から感謝しながら礼拝の準備をすることができました。なぜかと言うと、この箇所には教会のことが書いてある。教会のことしか書いていない。教会がなぜ教会として生きることができるか。教会の力の秘密を、こんなに鮮やかに描いてくれている聖書の言葉は、そう多くないとさえ思うのです。
■1節に、「この後、わたしは大地の四隅に四人の天使が立っているのを見た」とあります。「わたしは見た」というのは言うまでもなく、ヨハネが神から特別に幻を見せていただいたという話です。「彼らは、大地の四隅から吹く風をしっかり押さえて、大地にも海にも、どんな木にも吹きつけないようにしていた」。たいへん不思議な幻だと思います。だいたい「大地の四隅」って、いったい何でしょうか。当時の人びとは、丸い地球の形を知りませんでした。平面の、正方形の形をした大地があり、その四隅に四人の天使が立っているというイメージでしょう。そこで大切なことは、その大地の四隅の内側で何が起こっているかということです。
そこでどうしても思い起こさなければならないことは、これに先立つ第6章です。小羊キリストが、神の右の手にあった巻物の七つの封印を、ひとつひとつ開いていかれます。そこで明らかにされたことはしかし、滅びゆくこの世界の有様でしかありませんでした。戦争があり、飢饉があり、疫病があり、実は私どもが知っているとおりの世界の現実が、次々に幻の中に映し出されていきます。しかもそのような世界というのは何よりも、神の言葉と、それを証しする教会を押しつぶすような世界でしかありませんでした。ヨハネは、幻のうちに、殉教者たちの叫びを聞きました。そして第6章の最後のところ、第六の封印が開かれたところで遂に明らかになったことは、神の怒りのゆえに天地が激しく揺さぶられる姿です。人びとが山と岩に向かって、「どうかわれわれの上に覆いかぶさってくれ。神の怒りに触れて滅ぼされるよりは、生き埋めにされた方がましだ」と叫び始めると言うのです。
先週の礼拝でも申しましたが、もしかしたらこのところについて、ヨハネの黙示録というのは恐ろしい文書だと、あるいはあまりに現実離れしているようだとお感じになるかもしれません。けれども私はそうは思いません。むしろ、まさにここに、この世界の現実が、ありのまま正直に描かれているのではないでしょうか。この世界は、神の怒りによって滅ぼされるべき世界でしかないのです。
けれども、これに続けて、直ちにまったく別の情景を、ヨハネは見せていただいています。嵐が吹きまくっている、その大地の四隅に四人の天使が立って、その風をしっかりと押さえているというのです。どうしていきなり、そんな話になるのでしょうか。聖書の学者たちは、この第7章は前後と話が全然つながらない、まったく異質なものがあとから挿入されたのだと言います。私は、そういう学者の説明に一応は納得しながらも、もっと素直に聖書を読めばよいのにと思います。第6章では、滅びの風、死の大風が吹きまくっているのです。そう言えば、主イエスご自身もあるところで、「天地は滅びるが、わたしの言葉は決して滅びない」と言われたことがありました。「天地は滅びる」。事実、滅びるのです。ところが、それでも、神が最後まで滅びないように守ってくださるものがある。それは神の僕たちだというのです。四人の天使たちが、「大地の四隅から吹く風をしっかり押さえて、大地にも海にも、どんな木にも吹きつけないようにしていた」。そして2節に進むと、さらにもうひとりの天使が現れて、3節でこう言うのです。「我々が、神の僕たちの額に刻印を押してしまうまでは、大地も海も木も損なってはならない」。たいへん不思議な話ですが、教会に生きている人間は、このヨハネの幻がよく理解できるはずです。自分たちの姿が描かれているからです。
■当時の教会も、そして私どもも、さまざまな嵐を知っていると思います。何も特別なことを考える必要はないのです。そして私どもは、目に見えるさまざまな嵐を見ながら、切実に願うのです。この嵐さえ止めば。この嵐さえ静まれば。そうすれば、わたしは幸せになれるのに。特に黙示録が書かれた当時の教会は、ローマ帝国の支配の中で、ずいぶん厳しい経験をしていたと思います。「殉教」という、私どもにとっては遠い言葉が、当時の教会にとっては決して遠い現実ではありませんでした。
けれども私どもは、この世界に起こっているさまざまな嵐について考察するために礼拝に集まるわけではありません。もしそんなことなら、何の意味もないだろうと思います。大地の四隅に四人の天使が立って、荒れ狂っている嵐を押さえている。私どもは、このような天使の姿をきちんと見つめているでしょうか。2節でも言うのです。「わたしはまた、もう一人の天使が生ける神の刻印を持って、太陽の出る方角から上って来るのを見た」。そのような天使の姿を、私どもは見たことがあるのでしょうか。
ここに出てくる「太陽の出る方角」という表現は、当時の教会の礼拝の姿を反映していると言われます。当時の教会は、日曜日は仕事が休みというような社会に生きていたわけではありませんから、日曜日の朝、夜明けと共に礼拝をしたようです。朝日が昇るごとくに主がお甦りになったことを賛美しながら、いつも東を向いて礼拝をしたというのです。黙示録の第1章10節を読みますと、ヨハネがこの黙示録を書いたのも、「ある主の日のこと」であったと言います。ヨハネもまた、仲間たちと共に、東を向いて礼拝をしていたのでしょう。まさにその礼拝の中で、このような幻を見せていただきました。東の方からひとりの天使が上って来て、見ると手に「生ける神の刻印」を持っている。そして私どもひとりひとりのためにも、もちろん今朝洗礼を受けたふたりのためにも、「この人は神のもの、この人も滅びてはならない、神さまのものだから」と、しるしを付けてくれるというのです。
しばらく前に、明らかに臨終が近いと思われる教会の仲間を訪ねたことがありました。感染症のことが油断なりませんから、こういう牧師の訪問がなかなか許されないのですが、そのときには特別な計らいがあって、訪問が叶いました。息も絶え絶えに、私の訪問を喜んでくださいましたが、とても寂しそうな顔で、「教会の礼拝に行きたい。教会の礼拝に行きたい」と、何度も繰り返して言われたことが印象的で、私も涙を抑えることができませんでした。私はしかしそこでも、大げさでも何でもなく、神さまに幻を見せていただいたと思いました。主イエスがお甦りになった、その命の光が射してくる方角から、ひとりの天使がやってきて、この人のためにも、神の僕のしるしをしっかりと刻んでくださる。「我々が、神の僕たちの額に刻印を押してしまうまでは、大地も海も木も損なってはならない」。いろんな嵐があるでしょう。そして私どもの知る最後の嵐は、何と言っても死の嵐でしょう。けれども四人の天使がしっかりとその風を押さえてくれて、今、まさに、ここに、嵐を忘れさせるような静かな時を過ごさせていただいている。そのための、主の日の礼拝であります。
■今朝は、おふたりの洗礼入会式を行うことができました。ここで天使が、「我々が、神の僕たちの額に刻印を押してしまうまでは」と言っているのも、それはすなわち洗礼のことだと理解することができます。4節には、「わたしは、刻印を押された人々の数を聞いた。それは14万4千人」と書いてあります。先ほどの洗礼入会式の最後の祈りの中に、「その名をみもとにあるいのちの書に書き加えてくださいました」という言葉がありました。「みもとにあるいのちの書」というのはつまり、神の僕たちの名簿です。その数は14万4千人というのは、もちろん象徴的な表現で、天国の定員は思いのほか厳しい、という話ではありません。14万4千1番目以降の人は不合格、天国から締め出される、というように読むなら、それは聖書を完全に誤解していると言うほかありません。
それはなぜかと言うと、次の段落の9節に、「見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった、だれにも数えきれないほどの大群衆」と書いてあります。刻印を押された14万4千人と、数えきれないほどの白い衣の群衆と、別々に存在しているわけではありません。誰にも数えることができないほどの14万4千人というのは理屈に合わないようですが、この14万4千人という数は、5節以下に丁寧に書いてあるように、神の民イスラエルの12部族、それぞれ1万2千人の合計ということです。12というのは完全数です。12の部族を完全に、それぞれの部族1万2千人、神は救うべきものを、最後のひとりまできっちり完全に救い取ってくださるという話です。ひとりも欠けることはない。私どもの信じる神は、もしも14万4千人のうちひとりが迷い出たとすれば、そのひとりを必ず最後まで探し続けてくださるお方です。その神の完全な恵みに対する確信が、14万4千人という数字の意味です。
今朝の洗礼入会式も、その完全なる神の救いの出来事が、ここでまた新しく起こったということでしかないのです。洗礼入会式の祈りの中にあったように、「この救いに入れられるようにと、そのまだ生まれない先にこれを選び」……今ここで私どもが知るべきことは、神はご自分がお選びになった人を、どんなことがあっても忘れない。どんな嵐があったとしても、その嵐の中で、神が私どもを見失うようなことは絶対にない。そのためにきちんと天使を遣わして、神の僕のしるしを刻んでくださる。あなたのためにも。そこに教会が立つのです。
■今ここにも、数えきれないほどの大群衆の、そのごく一部が集まって、そこで何をしているかというと、小羊イエスのために賛美をささげるのです。
……だれにも数えきれないほどの大群衆が、白い衣を身に着け、手になつめやしの枝を持ち、玉座の前と小羊の前に立って、大声でこう叫んだ。
「救いは、
玉座に座っておられるわたしたちの神と、
小羊とのものである」。 (9、10節)
どんな嵐の中にあっても、私どもは小羊イエスを礼拝し続けるほかありません。それ以外に、嵐に耐える道もないのです。「救いは、玉座に座っておられるわたしたちの神と、小羊とのものである」。興味深いことは、その大群衆の賛美、つまり私どもの礼拝に対して、天のみ使いたちが「アーメン」と答えてくれました。
また、天使たちは皆、玉座、長老たち、そして四つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前にひれ伏し、神を礼拝して、こう言った。
「アーメン!」 (11、12節)
「アーメン、その通り!」 教会よ、あなたがたが今賛美を歌った通り、本当にその通りなのだ。さらに心を打たれるのは、13節です。長老のひとりがヨハネに問いかけるのです。「この白い衣を着た者たちは、だれか。また、どこから来たのか」。この白い衣を着た人びとの中に、ヨハネ自身も既に入っていたと、私は思います。そして私どもも皆、もちろん今朝洗礼を受けたおふたりも、この白い衣を着た大群衆の中に入っています。「この白い衣を着た者たちは、だれか。どこから来たのか」。ヨハネはもちろん、「わたしの主よ、それはあなたの方がご存じです」と答えるほかありません。長老は答えます。「彼らは大きな苦難を通って来た者で、その衣を小羊の血で洗って白くしたのである」。最初に申しましたように、ここには教会のことしか書いていない。
そして最後に15節以下です。何の解説もいらないと思います。
それゆえ、彼らは神の玉座の前にいて、
昼も夜もその神殿で神に仕える。
玉座に座っておられる方が、
この者たちの上に幕屋を張る。
彼らは、もはや飢えることも渇くこともなく、
太陽も、どのような暑さも、
彼らを襲うことはない。
玉座の中央におられる小羊が彼らの牧者となり、
命の水の泉へ導き、
神が彼らの目から涙をことごとく
ぬぐわれるからである」。 (15~17節)
旧約聖書の詩編第23篇を思い起こされる方も多いと思います。「主はわたしの羊飼い。わたしには何も欠けることはない」。「たとえ死の陰の谷を歩むとも、わたしは災いを恐れない」という、たいへん慰め深い詩編です。私どもも今、それこそこれに「アーメン」と答えたいと思います。「玉座の中央におられる小羊が」私どもの牧者でいてくださるならば、そしてもし神が私どもの目から涙をことごとくぬぐってくださるならば、「わたしには何も欠けることがない」。まさにそこに、神によって生かされる教会の姿が鮮やかに現れてくるのだと思います。お祈りをいたします。
アーメン、本当にその通りです。神よ、あなたがわたしの神でいてくださるならば、何も足りないことはありません。さまざまな嵐の中で、けれども今、驚くべき静けさの中に立たせていただいていることを、信じ抜くことができますように。死に勝つ望みを抱きつつ、最後まで、礼拝の生活を続けさせてください。主のみ名によって祈り願います。アーメン