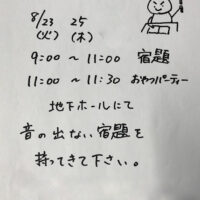神に対する憎しみ
マタイによる福音書 第27章11-26節
川崎 公平

主日礼拝
■主イエスが、ローマの総督ピラトの裁判において、死刑の判決を受けるという福音書の記事を読みました。既に第26章において、ユダヤ人の最高法院が死刑の判決を下していたはずですが、当時のユダヤ人には人を死刑にする権限がなく、その土地を占領していたローマの総督、ピラトの裁判によらなければならなかった。それで、第26章、第27章と、二度の裁判の記事が続くのです。今日読んだところには、小さなゴシック文字で小見出しがついていて、「ピラトから尋問される」、そして、「死刑の判決を受ける」と書いてありますから、ピラトが、イエスに死刑の判決を下した、という内容を予測してしまいそうですが、実際はそうではないのであって、ピラトはここで、裁判官としての責任を放棄しています。
ピラトは、それ以上言っても無駄なばかりか、かえって騒動が起こりそうなのを見て、水を持って来させ、群衆の前で手を洗って言った。『この人の血について、わたしには責任がない。お前たちの問題だ』」(24節)。
つまり、どちらかと言えば、もともとは主イエスを死刑にしたくなかったのだけれども、狂ったように叫び続ける群衆に圧倒されて、ピラトは、正義のためというよりは、自らの保身のために、こういう判断をしたのだという話です。そのようにして、主イエスは十字架へと引き渡されていく。歴史を分かつような裁判が、このように結審するのです。おそらく、皆さんの多くは、このような聖書の記事をお読みになって、どうも歯切れの悪い感じがしたかもしれません。
ここで興味深いのは、これはマタイによる福音書だけが伝えることですが、この場面でたったひとり、主イエスを処刑することに反対した人が出てきます。総督ピラトの妻が悪夢を見て、それを裁判の席についている夫に伝言させたというのです。「あの正しい人に関係しないでください」。はっきりと、ナザレのイエスは正しい人だと言っています。決してあの正しい人を殺したりしてはならない。きっと、とんでもないことになるに違いないから。「その人のことで、わたしは昨夜、夢で随分苦しめられました」。夢というのは、少なくとも聖書においては、ことにこのマタイによる福音書において、たいへん大切な意味を持ちます。たとえば主イエスの父とさせられたヨセフは、夢の中で天使のみ告げを聞き、既に身ごもっていたマリアを妻とする決心をしたり、そのあとヘロデから逃げるためにエジプトに避難したり……。そのような神の与える夢が、ここでは思いがけないことですけれども、ピラトの妻に与えられたというのです。
いったいピラトの妻はどんな夢を見たのでしょうか。ある人が、こういう想像をしています。夢の中で、多くの人が集まって、何かを唱えている。何だろうかと思ってよく聞いてみると、「主は聖霊によりてやどり、処女マリヤより生れ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ……」。つまり、使徒信条であります。あれ、どうしてこの人たち、こんなところにわざわざ集まって、夫の名前を唱えているんだろう……。使徒信条だけでなく、実は世界的には使徒信条よりも広く礼拝で用いられているニカイア信条でも同じことで、主イエスはポンテオ・ピラトによって苦しめられた、このピラトのせいで十字架につけられたのだと言うのです。ピラトの妻が使徒信条を唱えている教会の夢を見たというのは、もちろん何の根拠もない想像でしかありませんが、信仰的にはたいへん含蓄の深いものがあると思います。使徒信条のピラトの名前のところに、仮に自分の名前が入っていると考えてみてください。それを、何千年も世界中の人が唱え続けて、そのために自分の名前が末代まで覚えられるというのは、まさに悪夢でしかないでしょう。
しかしそれにしても、どうして使徒信条にピラトの名が出てくるか、これは疑問に思われる方も多いだろうと思います。そもそもピラトは、そこまでの悪役として描かれてもいない。もしピラトがあの世でわれわれの礼拝の様子を見たとしたら、言い訳のひとつもしたくなるかもしれません。いやいや、違うんですよ、本当は助けたかったんですけどね、いやー、家内にも言われたんですよ。でもあの群衆たちがあまりにもあれだったから……。けれども、そんなことをぐるぐる考えていても仕方がないんで、問題は、私どもがどこに立っているのかということです。わたしはどこにいるのか、それが問題です。「ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け」、それを言い換えて、「主はこのわたしのせいで、わたしのために、苦しみを受け」と言えるか、言えないか。
■誰よりも激しく、主イエスの死を求めたのは、むしろ群衆であったと言います。ここで私どもが、心を痛めつつ思い出さなければならないことは、このエルサレムの群衆が、数日前には喜んで主イエスのことを迎えたという事実です。ホサナ、ホサナと、声の限りに賛美をささげて、ろばに乗った王イエスを迎えた。それがどうして、こんなことになったのだろうか。というよりも、いったい主イエスは、この群衆のことを、いかなる思いで見つめておられたのだろうか。わずか数日前の群衆の賛美を、そしてここでの、「十字架につけろ、十字架につけろ」という群衆の叫びを、主はいかなる思いで聞いておられただろうかと思うのです。
マタイによる福音書を礼拝の中で読み続けてまいりまして、ようやくその終わりが見えてまいりました。この福音書において、いつも隠れた仕方で、けれども大切な役割を果たしてきたのは、「群衆」と呼ばれる人たちです。群衆などと言うと、無名の人びとのようについ考えがちですけれども、本当はひとりひとり、その人だけの人格を与えられたひとりひとりであって、私どもは聖書において「群衆」という言葉を抵抗なく読んでいたとしても、自分がそのひとりだとはあまり考えたがらないと思います。そんな群衆なんて、十把一からげに言わないでほしい。わたしはわたしなんだ。しかしマタイによる福音書は、おそらく他の福音書と比較しても「群衆」という言い方を好意的に使っていると思います。主イエスを愛し、主イエスに愛される存在として描かれるのです。
マタイによる福音書で最初に「群衆」という言葉が出てくるのは、あの〈山上の説教〉の冒頭です。無数の群衆が集まってきて、主イエスについて来た。主はその群衆をご覧になり、山に登って、そのひとりひとりに語りかけるように、「心の貧しい人々は、幸いである」。「悲しむ人々は、幸いである」。主が群衆に向かって、そう語りかけてくださったとき、既にこの群衆は、特別な幸いの中にあったと言わなければなりません。
その〈山上の説教〉のあと、少しだけ間が空きますが、第9章の最後に、改めて主イエスの群衆に対する特別な思いが語られるところがあります。
また、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て、深く憐れまれた。
ここで「深く憐れまれた」と訳されている言葉は、何度か説明したことがありますが、お腹の中にある「内臓」という言葉に由来する表現です。日本語で言えば「胸が痛くなる」ような、それよりもおそらくもっと深い、お腹のいちばん深いところが痛くなってくるような憐れみを、主イエスがここで呼び起こされてしまったのはなぜかというと、「この羊たちには、飼い主がいない」。だからこそ、このとき群衆は、「十字架につけろ、十字架につけろ」と、狂ったよう叫び続けたのです。自分たちが十字架につけようとしているのが、実は自分たちのまことの飼い主であるとも知らずに……。そういう群衆をご覧になって、まさにそこでも主イエスは、深い憐れみに胸を痛めておられたに違いないのです。
なぜ、数日前にはホサナ、ホサナと歓喜していた群衆が、こんなことになってしまったか、理由と言えば、確かに理由がありました。20節で、「しかし、祭司長たちや長老たちは、バラバを釈放して、イエスを死刑に処してもらうようにと群衆を説得した」というのです。「祭司長たちや長老たち」。本当は、彼らこそが群衆の羊飼いとなるべき存在でした。そのために神に立てられた人たちなのに、今や彼らは群衆を迷わせる存在でしかありませんでした。もとよりそれは、群衆の罪深さを免責することにはなりません。ここに私ども自身の愚かさ、浅はかさ、罪深さが見事に描かれているということに、気づくべきなのであります。そしてそのような群衆に注がれた、まことの羊飼いイエスの深い憐れみを、聖書は証しするのです。
■さて、ピラト、ピラトの妻、そして群衆と見てまいりましたが、もうひとり忘れることができないのが、バラバという存在です。飼い主を失った群衆、そのためにまったく盲目になってしまった群衆が何をしたかというと、主イエスよりもバラバの命を助けることを求めたというのです。16節に、「バラバ・イエスという評判の囚人がいた」といいます。主と同じ名前であったのです。バラバは、自分が助かることだけで頭がいっぱいで、主イエスのことなんか見向きもしなかっただろうと思いますけれども、主イエスは、バラバに対しても、同じような深い憐れみのまなざしを注いでおられたと、私は信じます。「きみもイエスっていうんだ? わたしと同じ名前だね」。
「評判の囚人」と言います。他の福音書を読みますと、暴動を起こして人殺しをしたとも書いてあります。革命家であったとも言われます。それで、人びとは、イエスのような無力な人間よりも、バラバのような勇ましい革命家を好んだのだと説明されることもあります。そうかもしれません。けれどもマタイによる福音書は、そんなことはひとつも言っていない。ただ単純に、この群衆は、人殺しの男よりも神の御子を憎んだのです。人間にとっていちばん憎むべき存在が、実は神ご自身にほかならなかったということは、人間の愚かさがここに極まったと言うほかありません。しかしまさにそこで、主イエスの憐れみもまた極まった。
主は、喜んで、バラバの身代わりになってくださったと思います。それだけの価値が、バラバにはあったのです。そして、まさにそれこそ、私どもの姿です。私どももまた、主がわたしの身代わりとして死んでくださったと言えるようになったのです。
マタイによる福音書の写本の中には、「バラバ・イエス」とは書かずに、単に「バラバ」としているものもあります。おそらく、写本を書き写した人が、こんな殺人犯が主と同じ名前であることを忌み嫌って、バラバの「イエス」という本名を削ったのだと考えられます。しかし考えてみれば、考えることもできないほどの恵みではないでしょうか。神の御子が人となり、イエスという名を取ってくださったのは、バラバのためでもあったのだ。……わたしのためでも、あったのであります。
■最後にもうひとつのことを考えてみたいと思います。この裁判の間、群衆の叫び声が聞こえる中、主イエスはずっと黙っておられたというのです。
祭司長たちや長老たちから訴えられている間、これには何もお答えにならなかった。するとピラトは、「あのようにお前に不利な証言をしているのに、聞こえないのか」と言った。それでも、どんな訴えにもお答えにならなかったので、総督は非常に不思議に思った(12~14節)。
ここで多くの人が、旧約聖書のイザヤ書第53章を思い出します。イザヤ書第53章の6節以下に、こう書いてあります。
わたしたちは羊の群れ
道を誤り、それぞれの方角に向かって行った。
そのわたしたちの罪をすべて
主は彼に負わせられた。
苦役を課せられて、かがみ込み
彼は口を開かなかった。
屠り場に引かれる小羊のように
毛を切る者の前に物を言わない羊のように
彼は口を開かなかった。
まさしく、飼い主のいない羊を深く憐れむ、神の御子の姿であります。「わたしたちは羊の群れ/道を誤り、それぞれの方角に向かって行った」。その私どものために、「苦役を課せられて、かがみ込み/彼は口を開かなかった」と言うのです。
ある人が、こういう考察をしています。ここに出てくるさまざまな人たちの中で、たったひとり、主イエスだけが、本当の自由に生きておられる。そう言うのです。18節に、「人々がイエスを引き渡したのは、ねたみのためだと分かっていたからである」と書いてあります。主イエスをいちばん憎んだユダヤの権力者たち、けれどもその根っこにあったのは、単なるねたみでしかなかったというのです。けれども私どもも、実はよく分かるんです。ねたみという感情が、実にしばしば、私どもをどんなに腐らせ、どんなに不自由にしてしまうことか。そんな祭司長たち、長老たちに見事に騙された群衆も、そしてその群衆の圧力に負けて、保身に走ったピラトも、それぞれ自分の思いがあり、計画があり、それに従って自分の自由意志によって行動し、発言していたつもりだったんだろう。けれども、真実の自由において行動している人はひとりもいない。この場面において、本当に自由にご自分の意志を貫いておられたのは、ただひとり父なる神であり、その父のご意志に従順に従っておられる御子イエスの姿が、このように記されているのだと、そう言うのです。
その意味では、この主イエスの沈黙というのは、ただ何も口答えしない、という話ではありません。父なる神のご意志に、ひたすらに従順であろうなさったのです。私どもに対する愛のゆえに、そうなさったのであります。飼い主のいない羊のための神の深い憐れみが、断固として貫かれる。主イエスの沈黙とは、その神の変わることのないご意志を表すものです。どんなに群衆がたけり狂っても、どんなにピラトが意気地なしであっても、あるいはバラバがどれほどの極悪人だったとしても、いやまさにそれだからこそ、断固として貫かれる神の愛が、この主イエスの沈黙のうちに鮮やかに示されているのです。祈ります。
今は、私どもも気づかせていただきました。私どもはもう、飼い主のいない羊ではありません。御子イエスよ、あなたこそ、私どもの真実の救い主、私どもの羊飼いです。どうか今、自分の罪を憎み、それだけにますます、あなたを愛する者とさせてください。主イエス・キリストのみ名によって、この祈りをみ前にささげます。
アーメン