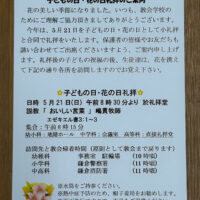聖なる神の民・教会
ペトロの手紙Ⅰ第2章1-10節
川﨑 公平

主日礼拝
「味わい、見よ、主の恵み深さを」。聖餐に際して、詩編第34篇の一部を招きの言葉として必ず読みます。主の恵みは、ただ言葉で理屈を学ぶようなことではない。味わうべきものである。それは何よりも、聖餐において味わう恵みであると、古来教会は理解してきました。
それを言い直したのが、ペトロの手紙Ⅰ第2章3節です。「あなたがたは、主が恵み深い方だということを味わいました」。「恵み深い」と訳された言葉は、広い意味を持つもので、たとえば食べ物について用いられると、「おいしい」という意味になります。「ああ、あの時のごちそうはおいしかったな……」。理屈ではなく、体で覚えてしまうのです。そのように、私どもは、主イエスの恵みの味わいを忘れることができなくなったのです。「あなたがたは、主のおいしさを味わいました」と訳してもよいかもしれません。
2節では、「生まれたばかりの乳飲み子のように、混じりけのない霊の乳を慕い求めなさい」とも言います。「霊の乳」とは、神のみ言葉のことだとも読めるでしょうし、それこそ聖餐のパンと杯を意味していると理解することもできます。生まれたばかりの赤ちゃんは、何もできなくても、お母さんのおっぱいを飲むことだけはできます。その味わいを知っているのです。それに似て、私どもはこの礼拝において、乳飲み子のように霊の乳を頂き、主の恵み深さを味わうのです。
このような信仰者のこころを、既にこの手紙は第1章8節でこのように言い表しておりました。「あなたがたは、キリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせないすばらしい喜びに満ちあふれています」。私どもは、主イエスを愛しています。主イエスを愛することは、言葉では言い尽くせないほどのすばらしい喜びなのです。それを言い換えたのが第2章3節です。「わたしたちは、主の恵みの味わいのすばらしさを知っている」。
植村正久という、鎌倉雪ノ下教会の建設に際しても大きな働きをした牧師が、その最晩年に「汝我を愛するか」という説教をしています。そこで、自分が二〇歳の時に名古屋で出会った老年の信者を紹介しています。あまり上品な男ではなかったけれども、いつも口癖のように、「俺は飯よりもイエスが好きだ」という調子であった。その言葉が、何十年たっても忘れられない。そして言うのです。若いときに聞いたこの老人の言葉によって、いつも自分が試されているのではないか。果たして自分は飯よりイエスが好きであろうか。そう植村牧師は問います。
ところで、ここで主の恵みの味わいと厳しく対立するものとして挙げられているのは、三度の飯などではなくて、「悪意、偽り、偽善、ねたみ、悪口」(1節)です。主の恵み深さを味わうときに、私どもがどうしてもしなければならないことがある。「悪意、偽り、偽善、ねたみ、悪口をみな捨て去る」のです。
洗礼を受けるということは、「古い人を脱ぎ捨てる」ことです。たとえばエフェソの信徒への手紙第4章23節以下はそう言います。ここでペトロの手紙Ⅰが、「悪意、偽り……をみな〈捨て去って〉」と言っているのも、エフェソの信徒への手紙の〈脱ぎ捨てる〉と原文では同じ言葉です。主の恵みを味わうために、脱ぐべきものを脱ぐのです。だから、ある説教者は言います。「悪意、偽り、偽善、ねたみ、悪口」。これらを捨ててしまったら、われわれは素っ裸になってしまうではないか。それこそ乳飲み子のように無防備になってしまうではないか。それが怖いから、われわれは多少の偽りを、多少の悪口を、わが身を守るために身にまといたくなるものだ。
たとえば「偽り」です。なぜ私どもは嘘をつくのか。自分を守るためです。「偽善」もそうでしょう。裸のままの自分をさらけ出すわけにはいかないと思うから、表面をごまかすのです。だからと言って、心の中の悪意をむき出しにして生きるのが正しいとは誰も考えません。この手紙も、まず「悪意」を捨て去ろうと言っているのです。「ねたみ、悪口」。これは結局、ひとつのものでしょう。誰かの批判を得意げに口にするだけで、私どもは自分が偉くなったように錯覚するものです。何年か前に、「他人の不幸は蜜の味」ということわざが脳科学の視点からも見事に証明されたという、たいへん悲しいニュースを聞いたことがあります。どんなにごまかしたって、人間の脳は最初からそのようにできている。だから仕方がないとあきらめるのか。いや、俺の脳みそはそうなっていないと反論を試みるのか。聖書の語るところはいずれでもありません。あなたがたはしかし、もっとおいしい味を知っているはずではないかと言うのです。悪口を言う快感に対立するように、キリストの恵みの味わいが向かい合うのです。
そのために私どもは、「混じりけのない霊の乳を慕い求め」るのです。「混じりけのない」という翻訳は、少々柔らか過ぎたかもしれません。「偽りがない、陰謀がない」という言葉です。神の恵みの言葉に陰謀はない。裏表はない。私ども人間の言葉には、どんなに繕っても、やはりどこか偽りがあるのです。偽善があるのです。自分に親切にしてくれる人には気持ちよく挨拶をしても、自分を悪く言う人にも同じように気持ちよく挨拶できるか。心の中では「ばか野郎」などと思いながら、けれども私どもは大人ですから、外面だけはニコニコしているのが私どもの生活の真相であるかもしれないのです。けれどももし、神の御心の真相が、「他人の不幸は蜜の味」ということであったならば、こんなに恐ろしいことはないと思います。ここでペトロは言うのです。神は何の偽りも陰謀もなく、私どもを愛してくださる。その神の恵み深さを味わおう。
「味わい、見よ、主の恵み深さを」。「恵み深い」と訳されている言葉は、食べ物について用いられると「おいしい」という意味になると申しました。人について使われると「親切な」という意味にもなります。そういうことを少し丁寧に辞書で調べ直しながら、ふと立ち止まってしまったことがありました。しかし、この言葉は、悪い意味で用いられることもある。「あの人は単純だ。お人好しだ」。そういう意味で、「あの人はばかだ」。そういう意味で使われることもあるというのです。「主は恵み深い」。「神はばか正直だ」。しかし私は、本当にその通りだと思いました。私どもが偽りで自分を守ろうとしているときに、神はただひとり、ばか正直な生き方を貫かれた。そこに主の十字架が立ったのです。
9月27日には伝道礼拝を行います。そのための案内はがきにペトロの手紙Ⅰ第2章23節を引用しました。主イエスのことをこのように紹介しているのです。
ののしられてもののしり返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。
ここに〈本物の生き方〉があると、案内のはがきに書きました。自分で書きながら、こんな厳しすぎることを書いてだいじょうぶかなと心配しました。「ののしられてもののしり返さず、苦しめられても人を脅さず」。悪意を捨て、ばか正直を貫かれた神の愛は、この主イエスの十字架のお姿に現れているのです。しかも私は、伝道礼拝の説教題を「本物の人間の生き方」としました。「本物の人間」とは、まず主イエスのことです。けれどもまた、私どもひとりひとりの〈本物の生き方〉がここにあると、私は言いたいのです。しかしそれにしても、「ののしられてもののしり返さず、苦しめられても人を脅さず」。ずいぶん激しい、また厳しいことです。
この第2章23節の言葉は、直接には「召使いたち」に語りかけられた言葉です。奴隷たちです。主人から不当な苦しみを受けている召使いたちに、このような主イエスのお姿を紹介しながら、あなたがたも、このお方に従うのだと言います。「あなたがたが召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなたがたのために苦しみを受け、その足跡に続くようにと、模範を残されたからです」(21節)。こんな言葉を説教したら、伝道どころか、誰も来てくれないかもしれません。
しかも、話は奴隷に限ったことではありません。ペトロの手紙Ⅰに色濃く表れていることは、教会が厳しい迫害を受けていたという事実です。ただキリスト者であるというだけで、世間から悪く言われたのです。けれどもそこでペトロが語ることは、主イエスがまず人びとから捨てられたということです。
主は、人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた、尊い、生きた石なのです(4節)。
従って、この石は、信じているあなたがたには掛けがえのないものですが、信じない者たちにとっては、「家を建てる者の捨てた石、/これが隅の親石となった」のであり、また、「つまずきの石、/妨げの岩」なのです(7、8節)。
当時の人びとは、石で家を建てました。その建築用の石です。家を建てる専門家は、そのあたりに転がっている石を見て、それが役に立つか立たないかを見抜くことができたのでしょう。けれども、この世の知恵ある人びとは、このイエスというお方を、この石は役に立たないと言って捨てたのです。けれども神は、この石を生かしてくださいました。イエス・キリストを、神の家である教会のかなめ石としてくださったのです。
しかし話はそこで終わりません。私どもも、主イエスと同じように、生きた石として用いられます。「あなたがた自身も生きた石として用いられ、霊的な家に造り上げられるようにしなさい」(5節)。私どもも、主イエスと同じ味わいを持つ存在として用いられるのです。
ペトロの手紙。ペトロという名前は、生まれながらの名前ではありませんでした。主イエスの弟子とされ、主イエスからじきじきに、「あなたはペトロ」と新しい名前をいただいたのです。「岩」という意味です。「あなたはペトロ、岩である。わたしはこの岩を用いて、わたしの教会を建てる」。それは、主イエスに拾い上げていただいて、死んだ石が生きた石として用いられることでありました。
そのペトロが、教会の仲間たちにも呼びかけるように、こう書くのです。「あなたがた自身も生きた石として用いられ、霊的な家に造り上げられるようにしなさい」。世間的に見れば、あっという間に消滅しそうな弱小集団であったと思います。その集団が、悪意を捨て、偽りを捨てて、「ののしられてもののしり返さず、苦しめられても人を脅さず」という主のお姿を、そのままに映し出すのです。
第3章に進むと、ペトロはこのような驚くべき言葉を記します。「妻たちよ、自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです」。これほど誤解されやすい言葉もないかもしれません。なぜ、「妻の無言の行い」なのでしょうか。「ののしられてもののしり返さず」。キリストご自身が、黙っておられたのです。そのキリストと同じ味わいの存在とされた人の姿を、このように描いているのです。黙って夫に従いながら、心のなかで夫を見下していたら何の意味もありません。悪意も偽りも捨てた妻の無言の行いが、夫を救いに導くのです。
そのことを、第2章5節、そして9節では、「あなたがたは祭司である」と言っているのです。「しかし、あなたがたは、選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です」(9節)。教会という神の選民には、祭司としての務めが与えられています。神と人間との間に立ち、その間を取り持つ務めです。「それは、あなたがたを暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある業を、あなたがたが広く伝えるためなのです」。み言葉を信じない夫の前に、妻の無言の行いが向かい合うとき、既にその妻は、ひとりの祭司として、ばか正直なほどの主の恵み深さを証ししているのです。
10月の全体集会の主題は、「ひとりひとりが伝道者・説教者」です。この第2章9節が語っていることこそ、まさにそのことです。この全体集会のために、ボーレン先生の『日本の友へ』という書物を紹介させていただいています。その終わり近くに、「日本の印象」という章があります。この鎌倉雪ノ下教会を訪ねたときのボーレン先生の挨拶が書き起こされています。そこで引用されたのも、このペトロの手紙Ⅰ第2章9節以下でした。
おそらく皆さんは、ご自分が、どれほどの社会的身分を与えられているか、まだ正しく承知しておられないのではないかと思います。洗礼を受けられたら、天の国の王子、王女になっておられるのです。「王の系統を引く祭司」なのです(217頁)。
今日は振起日です。こころを振るい起こされるような思いで、この教師の呼びかけを、主の呼びかけとして聴き取りたいと願います。
(9月6日 礼拝説教より)