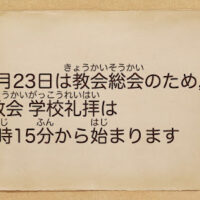神に招かれる人とは
ルカによる福音書14章1-14節
川﨑 公平

主日礼拝
ある安息日の食事の席で、主イエスが「水腫」という病気を癒してくださいました。具体的な病状はよく分かりませんが、とにかく、体の一部あるいは全体に体液が溜まって、ひどいむくみが出る。昔も今も、難病であることに変わりはないようです。私もそういう症状の人を見舞ったことがあります。体中が膨れ上がって、息をするのも苦しそうだった人のことを思い起こします。しかも当時、この種の病気は、罪深い生活をした報いであると信じられていました。
そのような病気の人が、主イエスと共に食事をしていたと言います。「ファリサイ派のある議員の家」に招かれたのです。ここで多くの人が首をかしげました。潔癖派であるファリサイ派の家に、なぜこんな嫌われた病気の人が入り込み得たのか。ひとつの説明はこうです。ファリサイ派たちが、主イエスを訴える口実を手に入れようとして、わざと主イエスの目の前に水腫の男を連れて来たのではないか。「人々はイエスの様子をうかがっていた」(一節)とありますから、そうかもしれません。きっとあのイエスという男は、目の前の病人を癒したくなるに違いない。そうしたら、安息日には働いてはならないという神の戒めに背くことになる。
もし、本当にそうであったとしたら、これは本当に悲しいことです。ひとりの病人を、主イエスを罠にかけるための道具としてしか見ていない。もしそうでなかったとしても、主イエスは、ご自分の様子をじっとうかがっている、人びとのよこしまな思いにお気づきであったと思います。しかし実は、この水腫の人が罠であろうがなかろうが、関係ありませんでした。主イエスにとって、この人はかけがえのない大切な人だったのです。
「すると、イエスは病人の手を取り、病気をいやして……」(四節)。この訳でも間違いではありませんが、ギリシア語原文に「手」という言葉はありません。直訳すると、「イエスは彼をつかんで」という言葉です。体のどこをつかんだのか、それはよく分からない。ですから、別の聖書の翻訳では「イエスはその人を抱いていやし」と言います。こちらの方が原文に近いかもしれません。
かつて、「イエスはその人を抱いて」という翻訳に基づく、この場面の絵を見たことがあります。絵と言っても、教会学校の教材のようなものです。いつどこで見たのかも、はっきり覚えていないのですが、「ああ、イエスさまはこの病人を、抱いていやされたのだ。抱き締めずにおれない、大切な人だったのだ」ということが深く記憶に残りました。その絵の中で、イエスさまに抱かれた人は、びっくりしたような表情をしていました。その周りに、ファリサイ派や律法の専門家たちが、おもしろくなさそうな顔をしている。けれども、他の人がどんな顔をしようが、主イエスは、この水腫の人を愛しておられる。その肝心の主イエスの表情がどんなだったか、これはどうも記憶がありません。しかしこれは、皆さんがそれぞれに想像なさるといいと思います。今、このわたしを招き、もてなしてくださる主イエスの表情は、いかなるものであろうか。そのことを思うべきであります。
もうひとつこの四節について、多くの人が指摘することは、主イエスが癒しに際して、言葉をひとつも用いておられないということです。癒しの前後にはいろいろお語りになっていますけれども、癒しそのもののためには言葉を用いておられない。「言葉を用いず、ただ、ジェスチャーを伴われた」とある聖書学者は分析します。そこが大事です。その主イエスのジェスチャーが、手を取るという形であったのか、体全体を抱きしめるようなしぐさであったのか。いずれにしてもそこで主イエスは、見るべきものを見てほしい、悟るべきことを悟ってほしいと、願われたに違いない。この人を抱いている、このわたしが今何をしているか、分かるか。
そのことを改めて説明するように、五節で言われました。「あなたたちの中に、自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといって、すぐに引き上げてやらない者がいるだろうか」。ある説教者は、ここで「ぎくりとした」と申します。主イエスはここで、この水腫の男を、〈自分の〉息子、〈自分の〉牛にたとえておられる。けれども、少なくともその場には、主イエス以外、この水腫の人の痛みを〈自分の〉痛みとして見ていた人は、ひとりもいなかったのではないか。そこでこの説教者は、「喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい」という、ローマの信徒への手紙第12章の言葉を思い起こすのです。
「〈自分の〉息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといって、すぐに引き上げてやらない者がいるか」。せめて、そのくらいの同情の心は生まれないのか。いや、そこにとどまらない。主イエスは言われるのです。あなたがたが何を言おうが、何を考えようが、わたしにとっては、この水腫の人は、自分の息子、自分の牛、いや、それ以上の存在なのだ。今、わたしはこの人をつかんで、この人を抱いて、癒した。今ここで、見るべきものを見てほしい。この神の愛を。そう主は言われるのです。
そのような主のしぐさは、今朝ここに整えられている、聖餐の食卓において、最も鮮やかに見えてくるものであると、私は信じます。神が、私どもを招き、もてなしてくださるのです。
このような主イエスのもてなしの出来事が起こった、まさにその席上で語られた言葉が、七節以下です。七節以下に語られるのは、招待を受けた人たちへの言葉、一二節以下は、客を招いた人に対する言葉です。
まず前半の方、七節以下は、いったい何を言おうとしているのでしょうか。「自分から上席に着くな」。「あなたより偉い人がいたらどうする。『そこをどけ』と言われて、恥をかくぞ」。特に日本人には分かりやすい話かもしれません。しかし、なぜこんな常識的なことを、わざわざ主イエスが教えられたのか。そこがかえって分かりにくいかもしれません。
しかし、こういうことをお語りになったきっかけは、はっきりしています。「イエスは、招待を受けた客が上席を選ぶ様子に気づいて」とあります。ここは、むしろ分かりにくいかもしれません。当時のユダヤの人たちは、先を争って上席に座ったのでしょうか。日本人には理解しがたいことです。けれども案外、心の中は、「誰が上か、誰が下か」、そういうことでいっぱいだったりします。勧められもしないのに上席に進んだりしたら、いろいろ批判されるからいやだというだけのことです。
こういう説明も可能です。「上席を選ぶ様子に気づいて」とあります。「どこにしようかな」と選ぼうとしているだけで、実際に上席に座ったわけではないと理解する人もいるのです。その心の内にあるものを、主は見抜かれた。ですからある人は、「彼らがみな上座をねらっているのを見た」と訳しました。いったいあなたは何を狙っているのか、と主は言われるのです。何を狙っているのでしょうか。自分が重んじられることです。
こういうことは、いろんな形で現れてきます。私どもが狙うのは、いわゆる上席だけではありません。自分の評判を高めるために、あえて末席に着くこともあるでしょう。ずうずうしいやつだという批判を避けるために、その人にとっては、末席こそが最高の上席になることもあるのです。認められたい。批判されたくない。重んじられたい。軽んじられたくない。私どもは、むさぼるようにして社会の上座を求め、そのために末席を奪い合い、上席を譲り合うということさえ、起こるのです。
主イエスは、そういう私どもの心の動きに気づいて、一〇節ではこう言われました。「招待を受けたら、むしろ末席に行って座りなさい。そうすると、あなたを招いた人が来て、『さあ、もっと上席に進んでください』と言うだろう。そのときは、同席の人みんなの前で面目を施すことになる」。これも、分かるような、分からないような言葉です。「上席に招かれるための策略として、まずは末席に着け」と言われているのでしょうか。そうだとしたら実に陰湿です。もちろんそうではありません。主イエスはここで、「本当に最後まで、軽んじられる人になれ」と言われたのです。「だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる」(一一節)。
いつ、誰が、へりくだる者を高めてくれるのでしょうか。遠慮がちにしていれば、あの人は控え目でいい人だと、評判がよくなるということでしょうか。そうではありません。神が、あなたを高めてくださる。その神との関わりが問われます。
へりくだる者を高めてくださる神のみ心は、まさにあの水腫の人を抱き寄せてくださった主のお姿において、鮮やかに見えています。この主のお姿が見えなくなる時、私どもの心はおかしなものを狙い始め、その心そのものがおかしくなってしまいます。誰が上か、誰が下か。自分は何番目か。そういうことに心奪われ、心まで病みそうになる時に……ほかの何が分からなくなってもいい。あなたは、神に愛されているではないか。
その神の招きを見るために、ひとつだけすべきことがあります。低く、へりくだるのです。そこで初めて、神の愛がいかなるものであるかを知るようになります。あのファリサイ派たちには見えませんでした。高ぶっていたからです。
一二節以下では、こうも言われました。「昼食や夕食の会を催すときには、友人も、兄弟も、親類も、近所の金持ちも呼んではならない」。なぜか。「その人たちも、あなたを招いてお返しをするかも知れないからである」。「宴会を催すときには、むしろ、貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい」。なぜか。「その人たちはお返しができないからだ」。では今度から、宴会の時はそういう人たちを呼んでみるか、と決心するのも結構ですが、もっと大切なことがあります。「お返しのできない人として招かれたのは、このわたしだ」ということです。皆さんのことです。主イエスは、そのことを分かってもらおうとして、あの水腫の人を抱いて、見るべきものを見せてくださったのです。
私が高校生の頃、キリスト者であった母が、滝乃川学園という施設の知的障害者を自宅の夕食に招き続けていたことがありました。どのくらいの頻度であったか、その記憶も曖昧です。滝乃川学園というのは、日本で最初の知的障害者のための、しかも教会の信仰に基いて建てられた施設です。どういう経緯で母がそういうことを始めたのか、聞いたことはありません。恥を忍んで申しますが、まだ子どもだった私にとって、楽しい時間ではありませんでした。何を話していいか分からない。早く帰らないかな、などと不謹慎なことを考えていました。けれども身勝手なもので、母と同じ教会に通っていましたから、教会の中で母の行為をほめる人の言葉が聞こえてくると、誇らしい思いになりました。しかしまた、一度だけですが、母を批判する言葉も聞きました。それだけのことをして何になるか、という趣旨の批判です。滝乃川学園の障害者を、全員招くことができるのか。何年かかってでも、全員を一度ずつ招くことができたとして、それで本当にその人たちを受け入れたことになるのか。母のいないところで、反論できない仕方で批判をした人がいたものですから、私はとても悔しい思いをいたしました。考えてみれば、私には悔しがる資格など、最初からないはずですが。しかし、いつの間にか、滝乃川学園の障害者の方たちが家に来ることもなくなりました。
私は、母を持ち上げたりおとしめたりするために、こういう話をしているのではありません。私自身の話をしているのです。早く帰らないかな、などと考えていたくせに、母がほめられると誇らしいし、批判されると悔しい。そういう私の心の動きは、どこか、あの水腫の人の苦しみさえも自分の食い物にして上座を求める、ファリサイ派に似ているような気がしてならないのです。そんな私が、神に愛され、招かれたことを思う時……そこでこそ悟ります。お返しのできない人として神に招かれたのは、私だ。その私のために、ここまで低くなってくださった方がおられる。
「宴会を催すときには、貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい」。今は分かります。母が何を考えていたかを。いや何よりも、主が何を願っておられたかを。私どもがそのように、身を低くして隣人に仕え始める時に、私どもは、もっと低いところに立ってくださった主のお姿を認めるのです。このお方の招きに対して、何のお返しもできません。私どもはただ、憐れみを受けたのです。この神の憐れみの中では、上席も末席もない。ただ神の憐れみの中で高くされることを、私どもの喜びとしたいと願います。