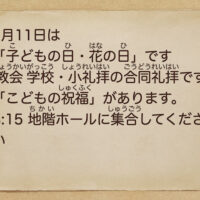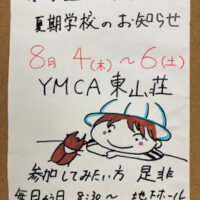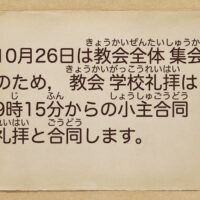あなたの涙を拭う方
ルカによる福音書第8章40-56節
柳沼 大輝

夕礼拝
教会は主を「信じる」者たちの群れであると言われます。それでは「信じる」とはいったいどういうことでありましょうか。主イエスは言われます。「恐れることはない。ただ信じなさい」(50節)。この主の言葉は、私たちにいま、何を語りかけるのでありましょうか。
本日の新約聖書の箇所には「十二年間」苦悩を背負って生きてきた者たちの姿が描かれております。一方には「十二年間」という凄まじく長い時間、病に苦しみ続けた婦人、他方には「十二年間」目に入れても痛くないと譬えられるほど深く愛してきた「娘」を失おうとしている父親。本日はこの父親の姿に目を向けて「信じる」とはどういったことか、共に御言葉に聴きたいと願います。
この父親は「会堂長」でありました。つまり、宗教上の指導者であります。そのような者が主の足元にひれ伏して、自分の家に来て死にかけている自分の娘を助けてほしいと願い出たというのです。そこで主イエスは会堂長ヤイロの家へと向かわれます。しかしその「途中で」ある出来事が起きました。「十二年間」病に苦しみ続けてきた婦人が主イエスの衣の裾に触れることで癒されるということが起こったのです。しかし主イエスはその婦人の密かな行為をそのままやり過ごすということはなさいませんでした。敢えて「私に触れたのは誰か」と立ち止まって問うてくださり、もう隠しきれない、すべて主がご存じなのだと知った婦人は、進み出て、民全員の前で事の次第を話しました。婦人が話したその祈りに主イエスは「娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい」(48節)と憐れみ深い言葉を語りかけてくださった、そういったことがこの箇所の前半に記されております。
そのように主イエスがまだ話しておられるときに、会堂長の家から使いの者がやって来ました。そして大変、悲しい知らせをもたらします。「お嬢さんは亡くなられました」と言うのです。この言葉は、大変な悲しみ、ショックであろうと思います。ここに言われていることは一人娘の死であります。そのことがどんなにこの父親を悲しませたことか、そのことは想像に難くありません。一人娘を失うこと、それは親にとって絶望することであります。どんなにか口惜しく、どんなにか悲しく、どんなにかやるせなく、また、どこか訴えるところがあるなら、気が狂わんばかりに訴えたいような、そういう場面でありましょう。一人娘、それはヤイロにとって何よりかけがえのないもの、彼の人生のすべてであります。その人生のすべてを失うという悲しみがここにあるのです。
ヤイロは人々から尊敬を受ける指導者であります。指導的な立場にあります。それが会堂長ということであります。しかし、そういう者だからといって、個人としての悲劇が決して襲わないということはありません。人はその人がどんな地位にあり名誉があり、また人々から羨ましがられるような者であったとしても、そしてどんなに素晴らしく立派な者であったとしても決して悲しみや苦しみから除かれることはないのであります。皆、それぞれに苦悩を抱えて生きているのです。誰にも言えない重荷を抱えて生きているのです。だからこそあの婦人も、会堂長ヤイロも主の御前に「ひれ伏した」のであります。そしてそのことはどんな者であっても、やはり悲しみや苦しみを負う者として、それは同時に主イエスの「憐れみ」から外れている者ではないことを示しています。
私たちは一方的なところだけを見ます。どうしてあの人があんな悲しみに遭うのか、あんな苦しみに遭うのか、こんなの理不尽だと一方的な見方をします。しかしここで聖書が示していることはそういう一方的な見方ではなくて、もっと深い見方を私たちに教えてくれています。この人はたしかに民の指導者であります。人々から尊敬を受けています。しかしそういう人もまた悲しみに遭う。どんなに立派な者であっても悲しみがある。つまりそれは「どんな人も神を必要としている、主の憐れみを必要としている」ということであります。神の憐れみなくして、神の恵みなくして、人は生きることはできないのです。どんなに立派な者であろうと、どんなに優れた者であろうと、やはり神を必要としないでは生きていけないのであります。それは、誰もが主の憐れみを必要としている者であるということであります。そしてそれは同時に主はそれらの者を憐れんでくださるということを示しています。それがこの聖書の箇所であると言ってよいでありましょう。
会堂長ヤイロは絶望のどん底に突き落とされています。しかし悲しみのどん底にある者として、なお、彼は憐れみのうちにあります。それがここでの出来事であります。悲しみや苦しみのどん底にある者と「主が共にいてくださる」のです。
しかし「お嬢さんは亡くなられました」というこの知らせは、一人娘を失った者にとってどんな深い絶望であったかと思います。おそらく一瞬のうちにいろいろなことを思ったと思います。例えば、主イエスを憎んだかもしれません。わざわざ「途中で」立ち止まらなくてもよかったではないか。たしかに一人の婦人が癒されたことはよかったことですし、そこには大事なことが語られているわけですが、一人娘の父親の思いからすればそんなことはどうだっていいのであります。それなのにどういうわけか、主イエスはご自分にちょっと触れた者のために立ち止まって「私に触れたのは誰か」とやり取りをされる。足を止められる。このことは娘を持つ父親にとってどんなにか口惜しいことであったに違いありません。
あるいはまた、この婦人を憎んだかもしれません。何故こんなときに、私が頼んで、私のために道を急いでいるのに、どうして邪魔をするのかと婦人を憎んだかもしれない。おそらくそれくらいやるせない気持ちを持ったと思うのです。ある意味では、もはやパニックになっている、どう受け止めたらよいか分からない、何かに当たれるものなら当たりたい、心が宙に浮いている、そういう思いのただ中に、いまヤイロはあるのであります。
しかしさらに娘の死を知らせる伝言にはまだ続きがありました。「この上、先生を煩わすことはありません」。つまり「もはや手遅れだ」ということです。主イエスが来ても「もう手遅れ、間に合いません。だから、もうイエス様の出る幕ではありません」と、言うのです。それはつまり死の前ではすべてが無力であって、いくら主イエスといえども、死の前では何もするべきことはないと言っているのです。
それでは死に際してすることはどういうことか。52節「人々は皆、娘のために泣き悲しんでいた」とあります。もはや絶望の淵で泣き叫ぶしかない。泣き叫ぶことによって弔うしかない。泣き叫ぶことによって自らを慰める以外に道はない。そういうことがそこに既に起こっているのです。
私たちは死の前に無力であります。死の前に経験することはああすればよかった、こうすればよかったという悔やみ、と同時に自分たちは無力であると知ることだと思います。そのことを彼らは主イエスに言ったのであります。
けれども決してそうではありませんでした。主の前に手遅れということはありません。主の前にもはやなす術がないということは決してないのであります。人がもう手遅れと思う時、そんな時であっても、もう何もなす術がないという時であっても、そこでこそ、主が働かれる場所があり、働かれる時があるのです。そこでこそ、語りかける主の言葉があるのであります。
主イエスは様々な思いが一瞬のうちにその心を支配し、乱れ、そしてなす術もなく死に翻弄されているヤイロに向かって言ってくださいました。「恐れることはない」。当然、恐れでしかないでしょう。不安でどうしたらよいか分からないでいるでしょう。しかし主は「恐れるな」と言うのであります。そして「ただ信じなさい」と言うのです。自分のすべてである一人娘を失ったヤイロ、それは自分の存在を失っている、絶望の淵にいるということであります。そんなもはや手遅れと諦めるしかない、そういうところで、そういう時に「ただ信じなさい」と主は命じるのであります。
実はそこでこそ、信仰が問われるのです。信仰が必要であることを主イエスは教えておられるのです。理由があって信じるのではありません。理由があって信じるのであれば、理由がなくなったら信じることをやめてしまうでありましょう。まさに自分が失われてしまっている時に、何の根拠もなくなった絶望の淵で、信じることもできないようなそういうところで、一番信仰が問われているのです。一番信仰が求められているのです。それがこの主の言葉であります。
日本人流にこのところを見ますと、主イエスに願ったのに間に合わなかった、しかも途中で立ち止まって時を過ごされた、そういうところで思うことは主イエスへの妬みつらみで、こんなに必死に願ったのに駄目だった時には、「神も仏もない」という言い方をします。この言葉はまさにそこで信仰を失ったという告白であります。
まさにヤイロも信仰が失われる、そういう状況に立たされています。しかし、信仰を失っている、そういう時に主は言われる。「ただ信じなさい」。これは主イエスが彼を「信仰へと呼びかけてくださっている招き」であります。信仰を失っている時に、主が命じてくださる。ご自分のもとへ「来い」と招いてくださる。ここでこそ、信仰の導きを必要としているから命じてくださる。そういう恵みがここに言い表されているのであります。
大切なことは信仰が確かかどうかということではありません。信仰のかけらも見えないところで、かけらすら、失われているところで主の言葉は信仰を呼び起こすのです。この主の呼びかけが信仰を生み出すのです。神の呼びかけが、主の呼びかけがあるから、信仰を持ち得るのです。もはや自分のうちに根拠は一切ない。もはや自分で信じられる要素は一つもない。いや信じられないという思いでしかない。そこでこそ、神の呼びかけがあるから、主の信仰への呼びかけがあるから、信仰が起こされるのであります。
それでは主が命じてくださった「ただ信じなさい」とはどういうことか。「信仰」が問われているとはどういうことか。もちろん「神を信じること」でありましょう。しかし、ヤイロからすれば娘が死んでしまったことはすべての終わりであります。ですからこういう伝言も言われるわけです。「もうすべて手遅れだ」。それではその上でなお「信じる」とはどういうことでありましょうか。主イエスは続けて言います。「そうすれば、娘は救われる」。「信じる」ということがどういう結果をもたらすか、そのことをヤイロは知りません。「信じる」とはどういうことかも分かりません。そこで主は言ってくださるのです。「そうすれば、娘は救われる」と言ってくださるのです。
しかし私はこの言葉もヤイロはまた理解し得なかったと思います。「救われる」と言われても何を言っているか、分からなかったと思うのです。私たちはよく「救い」ということを言いますが、「救い」とは、抽象的な言葉であります。具体性を欠いております。「そうすれば、娘は生き返る」と言われれば、半信半疑かもしれませんが、その意味は分かったでありましょう。しかし主はそうは言われない。「娘は救われる」と言うのです。
それでは「ただ信じなさい」とはどういう意味でありましょうか。それは「私に信頼し、私に任せなさい」ということであります。もはや「どうなるか」ではない。もはやどういうことが起こるか、そういうことでもない。絶望してどうしたらよいか分からなくなっている者に「私に信頼して任せなさい」と主は言われるのです。しかも失われたその身のままで、そのままに「私に任せなさい」と言ってくださる言葉、それが「ただ信じなさい」という主の言葉であります。
そしてそれは言葉を変えて言えば、「私があなたを、あなたの娘を引き受けた」というそういう宣言であるとも思うのです。「ただ信じなさい」、この言葉は、その人の心を奮い立たせようとする、そういう言葉ではありません。そうではなくて、信じられなくなった者を、もはや誰がどう言おうと信じられないであろう、そういう者を主は「引き受けた」と言ってくださる。「私が引き受けたのだから任せなさい」と言ってくださる言葉であると思うのです。そうであるからこそ、この言葉には力があるのです。そうであるからこそ、ここにその者を支える慰めがあるのです。
私たちが信じられるかどうかということではありません。信じられないのに、そこに信仰の出来事が起こるということは、主イエスがそこでそういう者を引き受けてくださっているからです。「あなたを引き受けた」いや「あなたの娘を私は引き受けた」、そうやって主が引き受けてくださっているからこそ、だからこそ「信頼して任せよ」と言ってくださる。それがヤイロに示された信仰であります。
信仰とは、信じられない者がそういう信じられない思いの淵でなおかつ「主にお任せする」ことであります。もはや、どうしようもない者として、信じる術もない者として「主イエスにお任せする」ことであります。それしかない、そこに本当の意味での信仰があるということを私たちはこの言葉から教えられているのではないでしょうか。
主イエス・キリストはご自身のうちに、絶望の淵にあるこの父をも引き受けてくださいました。もはや手遅れ、もはやなす術もないと思われている娘をも引き受けてくださいました。
主イエス・キリストにとって、手遅れもなければ、死もまた終わりではありません。死にある者であっても、もはや手遅れな者であっても、望みのない者であっても、主はご自分のもの、あなたを「神のもの」として引き受けてくださいます。だからこそ「恐れずに、安心して任せなさい」と言ってくださるのであります。私たちが「救い」に与るということは、主が「引き受けた」と言ってくださった、その恵みに生きることであります。
最後に、主イエスは絶望しているヤイロをそのままに引き受けて、彼の家に行きます。そして、泣いている者たちに向かって言われます。泣かなくてもよい。娘は死んだのではない。眠っているのだ」。そうやって人々の涙を拭われた主は娘に言う。「子よ、起きなさい」。これは主の十字架と復活にある永遠の命を指し示す言葉であります。主が引き受けてくださっている者にとって死は終わりではありません。絶望ですべてが終わるのではありません。なおそこから「起き上がる」のです。主の言葉を受けて、そこから命をいただき、「立ち上がる」のです。
そしてこの出来事に立ち会ったのは三人の弟子たちと当事者だけでありました。三人の弟子たちは弟子たちの代表でありますから、いわばここに「教会」の姿があります。
私たちはここでこの「礼拝」の場で主の言葉を聴くのです。それぞれに苦悩があります。痛みがあります。恥があります。どうしてあの時という怒りがあります。もはや泣くしかないと流した涙があります。しかし主はそんな失われたあなたを招いてくださっている。「その悲しみも苦しみも私はちゃんと知っている。だから私に任せない。私を信じなさい」と言ってくださっている。そして主は宣言してくださるのであります。「泣くな」「恐れるな」「起き上がれ」。ここに救いがあります。ここに生きる喜びがあります。いま、信じることができない自分も、どうしたらよいか分からないでいる自分も、そのままで主にお任せすればよいのであります。主の前に手遅れということはない。主の前に諦めということもない。主が引き受けてくださる。主が支えてくださる。だから恐れることはない。主に涙を拭われて安心してまたここから出で行こう。大丈夫、主がいつもあなたと共におられるのですから。
主イエス・キリストの父なる御神、信じることのできない私たちを憐れんでください。私たちの人生には苦悩があります。重荷があります。どこにも救いがないとあなたを憎み、涙を流し、絶望の淵に立たされる時があります。しかし、そこにも主が共にいてくださる。そこに変わることのないあなたの真実があります。主の言葉に私のすべてを任せることができますように。御霊を注いでください。力を与えてください。私たちはいま主の言葉を受けて、ここから立ち上がります。ここからまた新たな一歩を踏み出します。主よ、終わりまで、我らを支え導きたまえ。この願い、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン