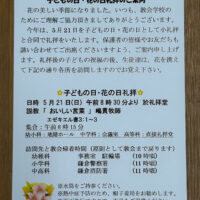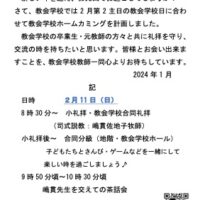空しさを生きる
コヘレトの言葉 第5章17-18節
小友 聡(日本旧約学会会長,元東京神学大学教授)

主日礼拝
今日、初めて教会にお出でになった方がいるでしょうか。空いた席に座って、自分がここにいていいのだろうかと、不安な気持ちでいるかもしれません。けれども、そういう人たちを歓迎します。この礼拝で一緒に聖書の言葉を聞いて、この聖書の言葉から皆さんが生きる力を、明日に向かって生きようという励ましを聴き取ってくだされば、幸いです。
今日は、コヘレトの言葉をまず紹介させていただきます、旧約聖書の中にコヘレトの言葉という一風変わった書があります。一風変わったというのは、この書には聖書らしくない、少々神聖さを欠いた言葉が目に付くからです。たとえば、こういうことが書いてあります。「銀を愛する者は銀に満足することがなく、財産を愛する者は利益に満足しない。これもまた空である。富が増せば、それを食らう者たちも多くなる。持ち主は眺めるほかどのような得があるのか。たらふく食べても、少ししか食べなくても、働く者の眠りは快い。富める者は食べ飽きていようとも、安らかに眠れない。」(5章9-11節)皮肉たっぷりに書かれています。現代にも当てはまる風刺的格言だと言えるのではないでしょうか。富を得るために目をギラギラさせて生きる金持ちを揶揄しています。さらにこういうことをコヘレトは書いています。「一人の男がいた。孤独で、息子も兄弟もない。彼の労苦に果てはなく、彼の目は富に満足しない。「誰のために私は労苦し、私自身の幸せを失わなければならないのか。」これもまた空であり、つらい務めである。」(4章8節)さしづめ猛烈に働く企業戦士の姿と言ってよいでしょうか。富を得ることだけが目的で、家族も友人もいらないという生き方をする人間がいる、というのです。自分は何のために働くのか、誰のために働くのかを考えることもせず、ひたすら富を得るために奔走している。それでいいのかとコヘレトは問うています。
コヘレトがいったい何を語ろうとしているか、それを知るヒントになることがあります。それは、コヘレトが「空」あるいは「空しい」(新共同訳)という言葉を連発する、ということです。「空」はヘブライ語でヘベルと言います。コヘレトの言葉で、38回も繰り返されるキーワードです。この書の冒頭から「空の空、いっさいは空である」と書き記されます。ヘベルは「空しい」とも訳せますが、意味はそれだけにとどまりません。無、不合理、不条理、無意味、矛盾、虚無、虚栄、不可能、蜃気楼、気泡、水蒸気、狂気、謎、などなど。さまざまな訳語が可能です。それらをすべて含むのがヘベルですが、しかし、「束の間」と訳すのが最もふさわしいのではないかと考えられます。コヘレトは人生をヘベルと呼んで、その人生が束の間であることを表現していると思われるからです。
皆さんは創世記の「カインとアベルの物語」を知っているでしょうか。カインが弟のアベルを妬んで殺してしまう物語です。そのアベルという名はヘベルと同一のヘブライ語です。束の間の人生であったアベルが「ヘベル」であるとすれば、ヘベルを「束の間」と考えるコヘレトの意図がわかります。コヘレトは「すべては空である」「風を追うようなことである」と述べるとき、人生が束の間であるという現実を直視して、その束の間の人生をどう生きるかを考えているのです。
旧約時代から新約時代にかけて、人間の平均寿命は40歳に満たなかったことがわかっています。今から2000年以上前の古代社会では、人生はだいたい30代半ばで終わったのです。二十歳になった若者があと生きられるのは十数年。コヘレトは「若さも青春も空である」(11章10節)と書いていますが、青春が束の間ということは現実でした。9章9節には、「愛する妻と共に人生を見つめよ。空である人生のすべての日々を」と書かれていますが、結婚生活は束の間であったということです。七十歳、八十歳まで普通に生きられる、今日のような時代ではなかったのです。
そこで、今日の聖書の言葉の意味がほどけて来るように思われます。「見よ、私が幸せと見るのは、神から与えられた短い人生の日々、心地よく食べて飲み、また太陽の下でなされるすべての労苦に幸せを見いだすことである。それこそが人の受ける分である。神は、富や宝を与えたすべての人に、そこから食べ、その受ける分を手にし、その労苦を楽しむよう力を与える。これこそが神の賜物である。」(5章17-18節)
コヘレトは労苦とは神が与える幸せだと言います。労苦すること、この「労苦」とは、人生そのものと言ってもよいでしょう。その人生が神から与えられた賜物だと言うのです。とても意味深いことです。額に汗し働いて一日を終え、家族と共に食事をする。ああ、今日も一日働いた、その心地よさに感謝する。富を得るためではない。仲間より秀でることでもない。自分に与えられた務めを、神からの賜物と感謝し、精一杯働く。そのことが幸せであり、それこそが神から与えられた受ける分だとコヘレトは見ています。
この「心地よく食べて飲み」ということは、しばしば享楽主義者、快楽主義者の言葉だと誤解されることがありますが、そうではありません。食べること、飲むことは宴会のご馳走ではありません。日常の食事です。食事が幸せだなど、ふだん誰も考えません。しかし、人生は短く、束の間で、明日はもう生きられないかもしれない。今日という日が自分にとって最期というとき、ほんのささやかな食事であっても、それは最大の喜びとなります。一日働いて、家族と共に心地よく食べて飲むことこそ、何物にも代えがたい喜びであり幸いなのだとコヘレトは見ています。人生は束の間であることが分かれば、日常のほんの小さな喜びが大きな喜びとなります。与えられた労苦は、今日という日を神から与えられた人生最後の日として生きることです。そのような労苦は神から与えられた幸いだとコヘレトは教えてくれます。
コヘレトの言葉はソロモンによって書かれたと言われることがあります。コヘレトは自分をソロモン王に喩えて書いています。かつてソロモン王は最高の知恵者であり、最高の財産家であり、最大の権力者でした。しかし、ソロモンのように、たとえどんなに知恵があっても、どんなに財産があっても、どんなに権力があっても、すべてはヘベルだとコヘレトは言います。
このソロモンを話題にしている箇所が新約聖書にあります。マタイによる福音書6章26節以下です。イエス・キリストがソロモンの喩えを語るのです。「空の鳥をよく見なさい。種も蒔かず、刈り入れもせず、倉に納めもしない。だが、あなたがたの天の父は鳥を養ってくださる。あなたがたは、鳥よりも価値あるものではないか。あなたがたのうちの誰が、思い悩んだからといって、寿命を僅かでも延ばすことができようか。なぜ、衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか、注意して見なさい。働きもせず、紡ぎもしない。しかし、言っておく。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。まして、あなたがたはなおさらのことではないか。」主イエスが語った有名な山上の説教の一節です。「空の鳥、野の花を見よ」という警句はよく知られています。この中に、「ソロモンの栄華」という表現でソロモンが登場します。このソロモンの栄華の直前に、それとは対照的に「人間の寿命の短さ」が語られます。この寿命の短さはまさしく「ヘベル」ということです。ここは、コヘレトの言葉を念頭に置いているのです。人生が束の間であることを主イエスもまた教えています。
主イエスもまたコヘレトと同じ目線で「野の花を見よ」と教えているのです。明日は炉の中に投げ込まれる、儚い野の草でさえ神によって命を守られている、という現実認識があります。私たちの寿命は、限られているけれども、神から与えられた、掛け替えのない賜物だということです。人生はまさしく「神の賜物」です。人生は限られています。終わりへと向かう今の時間は、決して無意味ではありません。コヘレトは終わりから逆算した束の間の人生を肯定します。逆説的です。人生は死という破局に向かっているのではない。むしろ、人生は、死があるからこそ人生なのであって、千年、二千年生きられるような、永遠に続く人生は幸せではない、とコヘレトは考えます。
聖書の言葉は、私たちに対して、今日を生きるのだ、「今日を生きよ」という励ましを語ります。多くの人は競争に勝つことはできないかもしれません。勝つどころか、どころか、時に蹴落とされ、自分の居場所を失い、そして消えてしまいたいと追い詰められることさえある。人生にはそういう、ままならない労苦があります。そういう私たちに、コヘレトは、明日に向かって今日を生きよ、全力で生きよと、と教えます。
今日この日が人生最後の日であるならば、この日は自分にとって神から与えられた賜物です。この日をどう生きるかが問われます。そもそも、人生が与えられた賜物ならば、人生に無意味なことなどないのです。さあ、自分に与えられたこの日を精一杯生きよ。聖書の言葉は、こういう生き方へと私たちを招いています。人生はままなりません。空しく、果てしなく労苦するばかりの人生です。しかし、聖書の言葉はいつでも私たちに寄り添い、生きよと呼びかけます。空しいから諦めるのではありません。空しいからこそ生きるのです。教会は、この聖書の「生きよ」という言葉を毎週、礼拝で一緒に聞き取り、共に歩む共同体です。「生きよ」という呼びかけに答えて、さあ、ここから共に歩み出しましょう。キリストは言われます。「さあ、明日に向かって、今日を生きよ」。