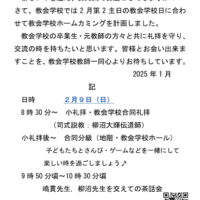誘惑に陥らぬよう
マルコによる福音書 第14章32-42節
川崎 公平

主日礼拝
■主イエスが十字架につけられる、その前の晩に、ゲツセマネという場所で徹夜の祈りをなさいました。いろいろな意味で、衝撃的な聖書の記事だと思います。神の御子キリストが、なぜこれほどまでに苦しまなければならなかったか。その苦しみとは、ここで主がなさった祈りの内容からも明らかなように、死の恐怖に怯えておられたのです。「私は死ぬほど苦しい」(34節)と言われました。ほとんど泣き言を言っておられるようにも聞こえますし、もしかしたら本当に泣いておられたかもしれません。ヘブライ人への手紙の第5章7節には、「キリストは、人として生きておられたとき、深く嘆き、涙を流しながら、自分を死から救うことのできる方に、祈りと願いとを献げ」と書いてあります。なぜそこまで、神のみ子が弱々しい姿を見せておられるのでしょうか。
このことについて、私どもに深い洞察を与えてくれるのが、先ほど合わせて朗読したイザヤ書第53章であります。先週の礼拝でもこのイザヤ書第53章を読みましたし、来週の礼拝でもまた同じ第53章の別の部分を読みます。聖書というのは、本当に不思議な文書だと思うのですが、その不思議さにおいて、このイザヤ書第53章は特に際立っているかもしれません。この言葉を書き記した預言者は、まるで主イエスのことを何百年も前から知っていたかのように、まるで自分の目で見ていたかのように、このように書くのです。「彼には見るべき麗しさも輝きもなく/望ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ/痛みの人で、病を知っていた」と言うのですが、なぜこのお方がここまで苦しんでいるかというと、「彼が担ったのは私たちの病/彼が負ったのは私たちの痛みであった」。わたしの苦しみを、このお方が代わりに苦しんでいるのだ。
主イエスご自身、このイザヤ書第53章を暗誦しておられたでしょう。子どもの頃から。そしてここゲツセマネにおいても、このイザヤ書の言葉を思い起こしながら、ひしひしと胸に迫るものがあったに違いないと思います。
■この福音書の記事が伝えていることは、主イエスの苦しみであります。しかし、何をそんなに苦しんでおられるのでしょうか。33節の最後に、「イエスはひどく苦しみ悩み始め」と書いてあります。ちなみに少し前まで使っていた新共同訳という翻訳では、「イエスはひどく恐れてもだえ始め」と訳されました。「恐れ、もだえる」が「苦しみ、悩む」になりました。「どちらの翻訳が好きですか?」とアンケート調査をしてみてもよいかもしれませんが、私が率直に言って不満に思っていることがあります。むしろここは、「イエスは驚き、悩み始められた」と訳すべきです。主イエスはここで驚かれたのです。驚愕なさったのです。「驚く」という、ギリシア語の同じ動詞がマルコによる福音書の中でも何度も出てきますが、聖書協会共同訳は他の箇所ではすべて「驚く」あるいは「ひどく驚く」と訳しているのに、なぜこの箇所だけ「驚く」という翻訳を避けたのか。しかもこれは聖書協会共同訳、新共同訳だけではありません。どういうわけか大部分の日本語訳聖書が「イエスが驚いた」ということを無視する翻訳をしています。たいへん率直に申しまして、一種の忖度が働いているのではないかと疑っています。つまり、神の御子キリストともあろうお方が、死を前にして苦しんだり、悩んだり、恐れたり、しかしそのくらいならまだ許容できる。しかし「驚く」というのはいかがなものか。何か思いがけないことが起こったかのように、イエスさまが驚き、慌てるというのはおかしい、という妙な遠慮が働いたのではないか。しかしたとえば、文語訳聖書はこの点をはっきり訳しています。「甚(いた)く驚き、かつ悲しみ出でて言ひ給ふ」。
主イエスが驚かれたというのは、つまり、ここで主は、決して予定通り、予想通りのプログラムをこなしておられるのではない、ということです。驚きという感情は、予想を裏切られるから、驚くのでしょう。「ええ? なんで? 話が違うじゃないか……」。もちろん主イエスは、ずっと前から、ご自分が十字架につけられなければならないことを知っておられたし、それが神のみ心であることを受け入れておられたし、そのことをまた弟子たちにもはっきりと予告しておられたのです。そういう主イエスが、ここでいよいよ最後の祈りをなさるのです。「アッバ、父よ、あなたは何でもおできになります。あなたにできないことはありません。ですからどうか、この十字架という苦しみだけは、勘弁してください。しかし、わたしの願いではなく、あなたの願いが実現しますように」という祈りをされたときの主イエスの最初の感情は、「ええ? なんで? 話が違う!」という、極度の驚きであったというのです。主は、何をそんなに驚かれたのだろうか。そのことを、私どもはよく考えなければならないと思うのです。
繰り返しますが、主イエスはすべてをご存じでした。既に、いつの間にか、十二弟子のひとり、イスカリオテのユダが姿を消していることにも気づいておられたでしょう。きっと今頃、武器を持った人びとを集めて、自分を捕らえようと手はずを整えているのだろう。そのあたりのことについては、来週の礼拝で43節以下を読みます。43節に「そしてすぐ、イエスがまだ話しておられるうちに、十二人の一人であるユダが現れた。祭司長、律法学者、長老たちの遣わした群衆も、剣や棒を持って一緒に来た」とありますが、今逃げれば、まだ間に合うのです。逆に、今逃げなければ、もう生き延びるチャンスはないのです。もちろん主イエスは、これが神のみ旨であると承知しておられましたから、その場を動くことはありません。逃げることもないのです。しかもそうでありながら、堂々と、悠々と、十字架の死を受け入れられたのでもありませんでした。今から自分が味わう死というものは、こんなにも恐ろしいものなのかと、その恐ろしさの前に、「イエスはひどく驚き慌てた」と聖書は書いてはばからないのです。
■このときの主イエスの驚きは、主イエスだけが知る驚きであり、そしてこのとき主が味わわれた死の恐怖も、ほかの人には知ることのできない恐怖であったと思います。「杯」という言葉が出てきます。父なる神が御子キリストに、「これを飲み干せ」と、無理やり飲ませようとしておられる苦しみの杯です。ここで主イエスはたったひとりで、父なる神の前に立っておられます。父なる神の差し出される苦い杯の前に生まれる驚きであり、「こんなにも、苦いのか」という恐れであります。
その関連で、もうひとつ皆さんに考えていただきたいことがあります。主イエスはここで、たったひとりで神の前に立っておられると、たった今申しましたことを訂正するつもりはありません。事実そうなのですけれども、にもかかわらず、この記事においてひとつ際立っていることは、ここで主イエスはおそらく初めて、ご自分の祈りの場所に三人の弟子たちを伴われました。たいてい主イエスは、ひとりで祈りをなさるのです。ふと弟子たちが気づくと、いつの間にか主イエスはたったひとりで祈りをしておられる。そういう福音書の記事をいくつも思い出すことができるのですが、ここに至っておそらく初めて、ご自分の祈りの場所にペトロ、ヤコブ、ヨハネという三人の弟子たちを同行させられました。
なぜなのでしょうか。主イエスの最後の祈りの証人とさせようとされたのでしょうか。きっとそういうこともあるだろうと思います。しかしまたある説教者は、主イエスは孤独に耐えかねたのだという趣旨のことを言っています。私はそれを最初に読んだとき、「そんなばかな」と思いました。私ができる限りその説教集を参照する、尊敬する説教者の言葉でしたから、ずっと昔から、ゲツセマネの箇所を説教するたびにこの説教者の言葉を思い出し、「いや、でも、これは違う」と思っていたのですが、最近になって考えを改めました。本当にそうなのかもしれない。主イエスは、孤独に耐えかねたのかもしれない。
その説教者の言葉をなぞるように申しますが、「少くとも、この三人の弟子たちに、何かを期待しておられたにちがいありません。できれば一緒に祈ってほしい、と思われたのだろうと思います。主イエスのように、祈ることのできるものは、だれもなかったでしょうが、それであっても、いや、それであればこそ、主イエスは、自分と一緒に祈ってほしい、と思われたにちがいないと思います。しかし、この弟子たちは、眠りこけてしまって、主イエスは、ただ、ひとり、神の前に立たれたのであります」。結局、この三人の弟子たちは、主イエスの孤独を慰めることはできませんでした。もとより主は、そんなことは最初からご存じだったと思います。主イエスの孤独は、主ご自身だけが担うことのできる孤独であって、それは神のみ子イエスにとっても耐えがたいほどの苦しみであって、だからこそ、「主イエスは、自分と一緒に祈ってほしい、と思われたにちがいない」とこの説教者は言うのですが、しかし、その横でぐうぐうと眠りこけてしまった弟子たちの姿は、結果として、ますます主イエスの孤独を際立たせる結果にしかなりませんでした。「そんなばかな、神の御子キリストが孤独を恐れたり苦しんだりするなんて」と、のんきな感想を言うとしたら、それはまだ私どもが本当の死の恐ろしさを知らないからでしかありません。
ここで主イエスは、たったひとりで神の前に立っておられる。しかもその神の手から、死の杯を、十字架の苦しみの杯を受け取ろうとしておられるのです。十字架というのは旧約聖書の信仰に従うならば、神に呪われた者の死であります。神に捨てられるという、その孤独であります。ところが、あにはからんや、「彼が担ったのは私たちの病/彼が負ったのは私たちの痛みであった」。このお方は神のひとり子ですから、神に捨てられるなんて、本来そんな恐怖を知る必要はないのです。だからこそ主は驚かれたのです。
■ところがそれと対照的に、弟子たちは眠り込んでしまいました。ある神学者がそのことについて、こういうことを書いています。「なぜ弟子たちは眠ることができたのか。自分を信じていたからだ」。一度聞いただけではわかりにくかったかもしれません。しかし、深い言葉だと思います。なぜ弟子たちは眠ったか。自分を信じていたから。本当には神を信じていなかったから。神なんかいなくても自分の力でやっていけると、どこかでそう思っていたから、平気で眠ることもできたのだというのです。
けれども、主イエスはそうではありませんでした。神以外に頼るものを持ちませんでした。このお方は、まことに神の子であらせられましたから、それゆえに、神以外に頼るべきものを持ちませんでした。しかもそのお方が、今、神に捨てられようとしているのです。そこに恐れが生まれ、悲しみが生まれ、あるいは絶望と言ってもいいほどの驚きが生まれるのは当然です。ぐうぐう居眠りするなんて、考えられません。そう言えば、主イエスが十字架の上で最後に叫ばれた、「わたしの神よ、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」という叫びもまた、深い驚きの叫びであったに違いないと思います。「神さま、どうして、わたしを」。神さま、あり得ないじゃないですか。そのような驚きと恐れを、主イエスはこのゲツセマネにおいても、父なる神の胸を打ち叩くように訴えられたのです。「父よ、これが本当にみ心なのですか。違うんじゃないですか。お願いですから、やっぱり十字架は違うよ、とおっしゃってください。しかし、この十字架が本当にあなたのみ心なら、その通りにさせてください」。
ここに「アッバ、父よ」とあります。アッバというのは、子どもが父親を呼ぶときの呼び方で、したがって「父よ」というような呼び方とは異質のものだと言わなければなりません。「お父さん、お父さん」。そのような言葉で神を呼んだ人は、主イエスより前には誰もいなかったのです。しかしそれにしても、その「お父さん、お父さん」という主イエスの叫びは、なんと頼りないことでしょうか。よく、本当に偉い人は死ぬときにも取り乱したりはしないなどと申します。そして事実、私どもの知るたくさんの偉い人たちが、堂々と、あるいは安らかに自分の死を受け入れてきたのです。ソクラテスという哲学者は、最後まで弟子たちと議論を交わしながら、平然と毒の杯を飲み干したと言われますが、主イエスはそんな死に方はなさいませんでした。なぜかと言うと、まさしくこのお方は神のひとり子であったから、だからこそ神に捨てられて死ぬということが、このお方にとっては耐えがたい絶望になったのです。
この期に及んでぐうぐう眠りこけた弟子たちと、その傍らでがたがた震えながら、ただ「お父さん、お父さん」と泣き続けた主イエスと、実に対照的であります。どちらが本当の祈りの姿なのだろうか。もちろんそこで、それならわれわれも主イエスの祈りの真似をしてみようか、と言って猿真似をしてみても意味はありません。なぜ主イエスはここで、こんなに驚いておられるのだろうか。なぜこんなに恐れておられるのだろうか。なぜここまで絶望しておられるのだろうか。そのことをよく考えなければなりません。「彼が担ったのは私たちの病/彼が負ったのは私たちの痛みであった」。私ども罪人が神の前で負わなければならない苦しみを、もっとはっきり言えば罪責、罪の責任を、主イエスはひとりで背負って、苦しんでおられるのです。
■主イエスの十字架は、私どもの罪のための苦しみだと、教会に来ると繰り返しそのことを教えられます。私どもの罪の責任を肩代わりしてくださって、このように苦しんでおられるというのですが、そのことを私どもは何度教えられてもなかなか理解しないと思います。
しかし考えてみますと、私どもも自分の罪のために苦しみ、あるいは血の気が引くほどに驚くことがあるかもしれません。それは特に、自分の悪行が思いがけない仕方で誰かにばれたときであるかもしれません。あるいは自分のしたことが、思いがけず誰かにとんでもない迷惑をかけていたということがわかって、どうしたって何らかの形で自分が責任を取らないといけない。そういうときに、それこそ体中ががたがた震えてくるということが起こるかもしれません。そういう経験をしたことがなければ、ある意味で幸せなことだと思います。どんなに悪いことを心の中で考えていたとしても、それが神さまには全部ばれていても(いや、最初から全部ばれているのですが)、人にさえばれなければ、私どもは案外偉そうな顔をして生きることができるのです。
ところがここで主イエスが神から差し出された杯というのは、すべての人の罪の責任をひとりで負わなければならない、そのような十字架であって、要するに主イエスはここで、「悪いのは、お前だ」と、人からも、そして神からも、そう言われることを引き受けようとしておられるのです。「悪いのは、お前だ。だから、お前が死ね」。十字架というのは、そういうことです。すべての人の罪の責任を負って、人からも神からも捨てられるのです。そのときに、驚愕と、恐怖と、絶望が生まれるのは当然であります。
私どもにとって、「あなたが悪いんだよ」と、そう言われることほどきついことはありません。私どもにとって、ほとんどいつも悪いのは他人であって、自分ではないからです。実際ほとんどの場合、われわれはそう考えて毎日の生活を作っているのです。ところがまさしくそのところに、罪人の罪人たる最大のしるしが現れているので、ところがそんな私どもが、人生の中でそんなに頻繁ではないかもしれません、ごくまれに、どうしたって決定的に悪いのは自分だということが明るみに出されて、そのときに信じられないほどの驚愕と、恐怖と、絶望を経験したりするものです。
けれどもここで私どもが知るべきことは、主イエス・キリストは、ご自身は何も悪いことをしていないのに、すべての人の罪を肩代わりしようとしておられる。「父よ、それがあなたのお考えなのですね」と、祈りの内に確かめておられるのです。
今日の説教の題を、「誘惑に陥らぬよう」としました。38節で、「誘惑に陥らぬよう、目を覚まして祈っていなさい」と主は言われました。誘惑とは何でしょうか。居眠りするな、ということでしょうか。そんなつまらない話でないことは明らかです。私は思うのですが、ここでいちばん激しく誘惑と戦っておられたのは、主イエスご自身であったと思います。だからこそ、「あなたがたも、一緒に祈ってほしい」と言われたのだと思います。「誘惑に陥らないように」。考えてみれば、話は実に単純なんで、このときの主イエスにとっての誘惑と言ったら、十字架から逃げることこそが、いちばんの誘惑であったに違いありません。主イエスが十字架から逃げたって、誰も主イエスのことを悪く言う人はいないのです。「正しいのは自分だ。自分は何も悪くない」。そう言ってやりたい、という誘惑は、主イエスにとっても小さくはなかったと思います。「だったら、なぜわたしが十字架につかなければならないか。冗談じゃない」。けれども、主イエスはその誘惑に打ち勝ってくださいました。「彼が担ったのは私たちの病/彼が負ったのは私たちの痛みであった」。すべては、私どもが今赦されて、神の前に立つためであったのです。
■かくして、今神の前に立ち、礼拝をしている私どもであります。しばしば聖餐への招きの言葉の中で言われるように、「罪人の頭」として私どもは神の前に立つのです。ここで私どもは、主イエスが味わわれたような驚愕や、恐怖や、絶望を知る必要はありません。全部赦されているのですから。もう決して自分は神に捨てられていないと、確信をもって主の食卓を祝うことができます。しかし、自分の罪を忘れることはできません。自分の罪のために、あり得ないほどの驚愕と絶望を味わわれた主の痛みを思いつつ、畏れと感謝とをもって、今聖餐のパンと杯を噛みしめ、味わい直したいと願います。お祈りをいたします。
罪人の頭として、今み前に立ちます。私どものために、このわたしのために、主がどんなに深い痛みを負ってくださったか、その恵みの事実に新しく目覚めさせてください。み子イエスの絶望のゆえに、今私どもは確信をもってあなたの愛の中に立つことができます。その十字架の痛みのゆえに、今私どもは赦され、晴れてこの祝いの食卓を囲むことができます。今私どもも、誘惑に勝つことができますように。自分の罪を忘れたくなる誘惑から、「悪いのはあいつだ」と言いたくなる誘惑から、私どもをお守りください。われらに罪を犯す者をわれらが赦すごとく、われらの罪をも赦したまえ。そしてわれらを誘惑に遭わせず、悪より救い出したまえ。主のみ名によって祈り願います。アーメン