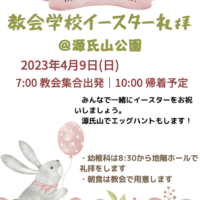人を生かす言葉
ガラテヤの信徒への手紙 第3章1-14節
川崎 公平

主日礼拝
■10月31日は、鎌倉雪ノ下教会の伝道開始の記念日です。108年前の10月31日、教会堂も専任の牧師もいないところで、ある信徒の自宅に集まって最初の礼拝をしました。そこから始まる私どもの教会の、伝道開始108年を記念する礼拝において、いつものように『雪ノ下讃美歌』11番を歌いました。
潮さいもほど遠からぬ 海のほとりに
キリストのみ声が聞こえ
召し出された ちいさい群れが
神を父と呼ぶよろこびを分かちあう
そこに生まれた 主のからだ
108年前の10月31日、鎌倉の片隅でいったい何が起こったか。そのことを、このように歌うのです。特に私がいつも静かな感動を覚えるのは、「キリストのみ声が聞こえ」という言葉です。キリストのみ声が聞こえたのです。ほかの誰の声を聴いたのでもない。私たちは、キリストの声を聴いたのだ。「そこに生まれた 主のからだ」であります。
ここに「教会とは何か」ということが、実に簡潔に、また鮮やかに歌われています。この鎌倉雪ノ下教会というひとつの教会の歩みがどこから始まったのか。今、この教会を生かす力がどこから来るのか。その原点は「キリストのみ声が聞こえた」ということであり、そして今も私どもはキリストのみ声を聴く礼拝をいたします。
■今朝、そのような礼拝のために神が与えてくださった言葉であると信じて、ガラテヤの信徒への手紙第3章の最初の部分を読みました。ガラテヤの教会もまた、キリストのみ声を聴くことによって生まれました。そのことを、パウロはここでかなり丁寧に問い直しています。第3章の2節と5節で同じ質問を繰り返しているのも、まさしくそのことを確かめようとしているのです。
あなたがたにこれだけは聞いておきたい。あなたがたが霊を受けたのは、律法を行ったからですか。それとも、信仰に聞き従ったからですか(2節)。
神があなたがたに霊を授け、あなたがたの間で奇跡を行われたのは、あなたがたが律法を行ったからですか、それとも信仰に聞き従ったからですか (5節)。
ずいぶん激しい問いかけの言葉だということは、すぐに理解できると思いますが、それにしては話が入って来ないという印象もあったかもしれません。「律法を行ったからですか。それとも、信仰に聞き従ったからですか」と言うのですが、特にこの「信仰に聞き従ったからですか」というのがよくわからない。ここは、聖書協会共同訳が苦心して、またずいぶん工夫して訳したところだと思います。
「律法を行ったからですか。それとも、信仰に聞き従ったからですか」。この部分を直訳すると、まず文章の軸となるのは、「行いによるのですか、聴くことによるのですか」ということです。「行い」という言葉と「聴く」という言葉が対立して挙げられます。「あなたがたが霊を受けたのは――この〈霊〉という言葉についてもあとで改めて説明しなければならないと思いますが――行いによるのですか、それとも聴くことによるのですか」。その「行い」、「聴くこと」というふたつの言葉に修飾語がついて、「律法を行うことによるのですか、信仰を聴くことによるのですか」と言うのですが、「信仰を聴く」と言われても、ちょっと意味がわかりません。それでたとえば以前用いていた新共同訳は、「福音を聞いて信じたからですか」と訳しました。「律法を行ったからですか。それとも、福音を聞いて信じたからですか」。新共同訳のほうが日本語としてはずっとわかりやすいのですが、ここでパウロが問いただしていることを曖昧にしてしまっていると思います。ここでパウロが尋ねていることは、「行ったからですか、信じたからですか」ではなくて、「行ったからですか、聴いたからですか、どちらですか」。すべては、聴くことから始まったのです。ガラテヤの教会は、何を聴いたのでしょうか。今、私どもは何を聴いているのでしょうか。ここには「信仰を聴いた」と書いてあります。それはいったい、どういうことでしょう。
■皆さんが大切に読んでいる聖書の翻訳を批判するというのは、たいへん申し訳ないような思いもあるのですが、私はこの部分の聖書協会共同訳の翻訳について、喜んでいるところと残念に思っているところがあります。喜んでいることは、これに先立つ第2章15節以下において、従来は「信仰」と訳されてきた言葉をすべて「真実」と訳し直したことです。「信仰」と訳すことも「真実」と訳すこともできる言葉ですが、ガラテヤ書の文脈で言えば、やはり「真実」と訳したほうがよいでしょう。たとえば第2章16節にはこうあります。
しかし、人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、ただイエス・キリストの真実によるのだということを知って、私たちもキリスト・イエスを信じました。これは、律法の行いによってではなく、キリストの真実によって義としていただくためです。なぜなら、律法の行いによっては、誰一人として義とされないからです。
私どもが義とされるのは、言い換えれば神に救われるのは、「律法の行いによるのではなく、ただキリストの真実によるのだ」と書いてあります。従来はここを、「キリストの真実」ではなく「キリストへの信仰」、「キリストを信じる信仰」と訳しました。「律法の行いによるのではなく、信仰によって義とされるのだ」。ところが聖書協会共同訳は、そのような理解を捨てました。われわれが信じるか信じないか、神の救いは、そんなことに依存しない。私どもの信仰が深くなったり浅くなったり、強くなったり弱くなったり、そのことによって神の救いが増えたり減ったりすることはない。こちら側の状態がどうであろうと、ただキリストの真実によって救われる。もちろんそうであれば、私どももこのお方を信じないわけにはいかないのです。「私たちもキリスト・イエスを信じました」と、第2章16節の真ん中にそう書いてあります。
もうひとつ、今度は私が残念に思っていることです。その「真実」という同じ言葉が第3章にも続けて出てくるのですが、どうしてここでまた急に「真実」という翻訳を捨てたのだろうか。「律法の行いによるのか、キリストの真実によるのか」という話がずっと続いているのですから、同じ言葉で翻訳してほしかったと思います。先ほど読みました第3章の2節にも5節にも、「真実」という言葉が出てくるので、そのように読み直してみます。
あなたがたにこれだけは聞いておきたい。あなたがたが霊を受けたのは、律法を行ったからですか。それとも、(キリストの)真実を聞いたからですか。
神があなたがたに霊を授け、あなたがたの間で奇跡を行われたのは、あなたがたが律法を行ったからですか、それとも(キリストの)真実を聞いたからですか。
「行ったからですか、聴いたからですか」。私どもは、聴いたのです。キリストの真実を聴いたのです。すべてがここにかかっています。その「聴く」ことによって、「あなたがたは霊を受けた」と書いてあります。霊を受けるとは、これまたわかりにくい話で、いろんな想像をたくましくする人もいるかもしれませんが、ここで大切な意味を持つのは、第4章6節です。
あなたがたが子であるゆえに、神は「アッバ、父よ」と呼び求める御子の霊を、私たちの心に送ってくださったのです。
「霊を受ける」とは、決して特別なことではありません。私どもすべてに与えられた神の祝福です。私どもは、神の霊を受けて、神を「アッバ、父よ」と呼ぶ。『雪ノ下讃美歌』11番も、まさしくそのことを歌います。「神を父と呼ぶよろこびを分かちあう そこに生まれた 主のからだ」。そのような教会を造るのは、もう一度申します、「キリストのみ声が聞こえた」。ここに、すべてがかかっているのです。
■「伝道開始」108年と言います。これはよくお話しすることですが、私どもの教会では昔から、こういう言い方をします。教会設立108年ではありません。108年前、この教会はまだ正式に教会の名をいただいておりませんでした。それなら「礼拝開始108年」でもよかったかもしれませんが、そうも言わないのです。私どもが108年間、ひたすらし続けてきたことは、伝道であります。108年前の10月31日、「潮さいもほど遠からぬ 海のほとりに キリストのみ声が聞こえ」、そのキリストのみ声をひたすら聴き続けてきたわけですが、聴いたら聴きっぱなしというわけにはいきません。聴いたことを、伝えなければなりません。何を伝えるのでしょうか。キリストの真実を、聴いてもらうのです。ただ、それだけなのですが、それがまた難しいということを、私どもはよく承知しております。
先週の日曜日、年に一度の全体集会を行いました。主題はやはり伝道であります。またぞろ「伝道って難しいね」という声があちこちから聞こえます。確かにそうです。伝道は難しい。しかし、なぜ伝道することは難しいのか。その根本的な理由を、きちんと考えなければならないと思うのです。私は思うのですが、伝道の何が難しいって、「私たちがすべきことは、聴くだけなんですよ。何の行いにもよらないんですよ」。まさにそこに、伝道の難しさがあるのではないでしょうか。ガラテヤの教会は、まさにそこから落ちた。聴くだけでは足りないと考え始めたのです。キリストの真実を聴いた、けれどもそれだけでは足りなくて、それに何か自分の行いを付け足さないとだめだと考え始めた。「行ったから救われたのですか。聴いたから救われたのではないですか」。「私たちがすべきことは、ただ聴くだけなんですよ。何の行いを加える必要もない。なぜそのことを忘れるか」。
今のものの言い方は、あまりわかりやすくなかったと思います。そこでもう少し具体的な話をします。先週の全体集会で、私もいくつかのグループを回りました。確かに伝道は難しい。特に若い人たち、とりわけ40歳代、50歳代の働き盛りの人たち、その人たちをいったいどうやって教会に連れて来ることができるか。けれどもその一方で確かなことは、すべての人が「幸せになりたい」と願っているのです。その幸せの形は、人によって、あるいは年齢層によってさまざまだろうと思いますが、とにかくすべての人が、幸せになりたいと願っているに違いないのです。
その全体集会のグループの話し合いの席で、ある人がこういうことを言いました。「こうすれば幸せになれますよ」。特に現代というのは、そういう言葉があふれている時代なのではないか。確かにそうだと思いました。本屋さんに行けば、たくさんのハウツー本が並んでいます。ハウツー本というのはつまり、「こうすれば幸せになれますよ」、「こうすれば儲かりますよ」、「こうすれば若返りますよ」、「こうすれば人生、もっと楽になりますよ」、そういうことを教えてくれる本のことです。電車にでも乗れば、いくらでもそういう本の宣伝が飛び込んできます。そしてそういう書物のタイトルが実によくできていて、私の説教題なんか逆立ちしてもかなわないほどです。私の記憶に刻まれた、印象深いタイトルをいくつか挙げてみると、『嫌われる勇気』。なるほど、確かに大事かもしれない。『考えすぎない練習』。そう、言われてみれば、確かに。『人は話し方が9割』。うーん、特に牧師なんかは、こういう本で勉強したほうがいいのかな……。
たとえば教会が、そういうハウツー本に対抗するように、「いや、われわれ教会のほうがもっと幸せになる道を教えることができますよ。そのためには、こういうことをしなさい。こういう考え方をしてごらんなさい。聖書には、あなたの人生を幸せにし、豊かにする教えがたくさん書いてありますよ」、という話ができたら、もう少し教会の人気も出てくるのではないか、つまりもっと伝道が盛んになるのではないかと思うのですが、教会は絶対にそういう話をしません。なぜかというと、今紹介したようなハウツー本が提供している幸せは、条件付きの幸せです。「こうすれば、幸せになれますよ」。けれども、神が教会に聞かせてくださるキリストのみ声は、条件付きの祝福ではありません。条件付きの祝福、そんなキリストのみ声を教会は一度も聴いたことがありません。
「あなたがたが霊を受けたのは、律法を行ったからですか。それとも、キリストの真実を聞いたからですか」。あなたが何をするかじゃない。あなたの全部が神に愛されているんだ。あなたは祝福されているんだ。「心の貧しい人は、幸いである」と主イエスが言われたとき、それは決して、こうすれば幸せになれますよ、という話をなさったのではないのです。嫌われる勇気を持ちなさい、そうすれば心の貧しい人も幸せになれますよ、という話ではないのです。「悲しむ人は幸いである」と主イエスが言われたとき、それは何の条件もなく、ただ悲しむ人は幸せだと断言されたのであって、考えすぎない練習をしなさい、そうすれば悲しみを乗り越えることができますよ、などという話ではないのです。無条件の祝福です。「悲しむ人よ、あなたは幸せなんだ。わたしがあなたを慰めるからだ」。このキリストのみ声を聴きなさい。「あなたがたにこれだけは聞いておきたい。あなたがたが霊を受けたのは、あなたがたが神の子として救われたのは、何かをしたからですか。そうではなくて、ただ聴いたからではないですか。キリストの真実を、ただ聴いたからではないですか」。
「ああ、愚かなガラテヤの人たち、なぜあなたがたはその祝福から落ちたのか」。そうパウロは言うのですが、けれども本当は、すべての人が同じところに落ちているのです。すべての人が、条件付きの幸せを欲しがっているのです。今なんだか偉そうに話をしている私自身だって例外ではありません。「人は話し方が9割」とか言われたら、やっぱり気になりますよ。特に私のようにいつも人前で話をしている人間からしたら、その話し方で9割が決まるなら、その話し方を磨けば、今よりもずっと人気のある牧師になれるかな、なんてことをやっぱり考えますよ。けれどもそういうところで、私ども人間が何を考えているかというと、〈条件付きの幸せ〉が欲しいのです。「こうすれば幸せになれる」。そうやって、自分の人生を幸せにしたい、確かなものにしたい。そういうことを考える私ども人間の根本的な問題は、神なんか信じていない、ということなのです。「あなたは神に愛されています」、そんなこと言われたって、屁のつっぱりにもならんと、どこかで考えているのです。無条件のキリストの真実よりも、律法の行いによる条件付きの幸せのほうが、ずっと大事。しかし、まさにここに、人間の根本的なみじめさがあることに気づくべきです。
■10節に「律法の行いによる人々は皆、呪いの下にあります」と書いてあります。たいへん厳しい言葉ですが、本当はこれこそ現代人が聴かなければならない言葉であると思います。「律法の行いによる人」、もう少し丁寧に言い直すなら、「自分の行いをよりどころとする人」です。キリストの無条件の愛を聴いているだけでは、屁のつっぱりにもならない。それに加えて、自分の働き、自分の行い、自分の力によって、自分で自分を幸せにしないと。そう言いながら、私どもは自分で自分を神の祝福から切り離すようなことをしているのです。
ガラテヤの教会の人たちも、ひとたびはキリストの真実を聴きました。キリストのみ声が聞こえた。すべてはそこから始まった、はずなのに、そこから落ちた。そしてもう一度、律法をよりどころとする〈条件付きの幸せ〉に、呪われた幸せに逆戻りしてしまったのです。そんな教会に呼びかける、伝道者の言葉です。
ああ、愚かなガラテヤの人たち、十字架につけられたイエス・キリストが、あなたがたの目の前にはっきりと示されたのに、誰があなたがたを惑わしたのか(1節)。
「十字架につけられたイエス・キリストが、あなたがたの目の前にはっきりと示された」と言っても、ガラテヤの教会のどこかにキリストの像が立っていたという話ではありません。今私どもがしているのと同じように、説教を聴いたということです。礼拝を通して、キリストご自身のみ声を聴いたということです。「十字架につけられたイエス・キリストが、あなたがたの目の前にはっきりと示されたではないか」。あなたがたは、このお方の真実を聴いたではないか。なぜそれを忘れるか。
13節ではこうも言います。「キリストは、私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。『木に掛けられた者は皆、呪われている』と書いてあるからです」。今から私どもがいただく聖餐は、この十字架につけられたキリストの体、そのものであります。この聖餐を味わい、噛み締めながら、私どもはキリストの受けてくださった呪いを味わいます。神から見捨てられた人間のみじめさを知ります。神に捨てられた人間のみじめさが、どれほどのものであったか。それが最も鮮やかに示されたのが、キリストの十字架であったのです。このお方の十字架のもとで、私どもはキリストの真実に触れます。このお方のみ声を聴くのです。「だから、あなたはもう、見捨てられてはいないんだ」と。すべての人が聴くべきキリストのみ声を、今ここで、新しく聴き取りたいと願います。お祈りをいたします。
今私どもの目の前にも、十字架につけられたイエス・キリストが、はっきりと示されています。「キリストは、私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました」。律法の呪いに縛られているこの世界であり、私どもひとりひとりであることを悲しく思います。だからこそ、キリストの真実のみ声を聴かなければなりません。聴いたならば、私どもはそれを語らなければなりません。今新しい思いで、キリストのみ声に心を開かせてください。それを語る力を、新しくあなたの教会にあたえてください。主のみ名によって祈り願います。アーメン