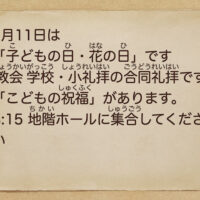死を見つめよ、神の愛の中で
ローマの信徒への手紙 第5章12-21節
川崎 公平

主日礼拝
■伝道者パウロの書きました、ローマの信徒への手紙を読み続けています。先ほど聖書朗読をお聞きになりながら、おそらく多くの方が、「何だろう、これは」とお感じになったのではないかと思います。ここで主題となっているのは、人間の罪と、人間の死であります。なんか、また難しい話が始まりそうだ。そういう印象があったとしても、それは仕方のないことかもしれません。
ここで特にわかりにくいこと、そして実際、聖書の学者たちの間でも議論が分かれることは、12節の最初に「このようなわけで」とあります。ところがよく読むと、どういう話のつながりで「このようなわけで」と言っているのか、よくわからないのです。11節までの話は、私どもがどんなに確かな救いの中に導かれたか、どんなに大きな喜びの中に守られているかということです。たとえば10節以下にはこうあります。
敵であったときでさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は、御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を誇りとしています。このキリストを通して、今や和解させていただいたからです。
私は、私たちは、愛されているんだ。救われているんだ。だから私たちは、この神を誇る! このような誇りと喜びがあるから、「このようなわけで」、どうなるかというと、「一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、すべての人に死が及んだのです。すべての人が罪を犯したからです」。あれ、ちっとも話が続かないじゃないか。あれほどの喜びを語っておきながら、急に何だ。
このことについて、先ほども申しましたように、いろんな人がいろんな解釈をするのですが、何と言っても強烈な印象を残したのは、竹森満佐一という説教者の解釈です。ご存じの方があると思いますけれども、「メメントー・モーリーmemento mori」という言葉があります。「死(ぬこと)を忘れるな」という意味のラテン語です。なぜその言葉が、しかもラテン語でよく知られるようになったかというと、あるカトリックの修道院のひとつの伝統で、この言葉が挨拶の代わりに用いられたからです。「おはよう」「こんにちは」「さようなら」という挨拶の代わりに、「メメントー・モーリー」。「われわれは、必ず死ぬんだよね」。ところがそこで、この竹森満佐一という説教者は言うのです。
しかし、この言葉は、少なくともわれわれの信仰からいえば、ただ死を忘れるな、ということではなくて、死を忘れるな、そして恵みを忘れるな、ということであると思います。ただ、死を見つめているということだけでは、実は、死に見つめられているだけで、こちらが死を見ていることにはならないのであります。
特に最後の部分は、ぞっとする言葉であるかもしれません。ことに、死の恐れに直面している人、受け入れがたい死を経験したことのある人なら、ますますそうであるかもしれません。われわれのほうから死を見つめようったって、そうはいかない。そんなことをしたら、逆に死に見つめられて、蛇に睨まれた蛙のようになるだけだ。けれどもそこで竹森先生が言われることは、「死を忘れるな、そして恵みを忘れるな」。その神の恵みの中で、私どもは初めて望みを持って「メメントー・モーリー」と、われわれが死ぬことを忘れないようにしよう、と言うことができるようになるのです。
■もう何十年も前のことですが、この教会で、46歳という年齢のご婦人の葬儀をしました。たいへん熱心に求道生活をされて、ある年のクリスマスに洗礼を受けて、それで雪ノ下通信にも自己紹介を書いて、「ここからが私の人生の新しいスタートだ」と、喜びにあふれた文章をお書きになったのですが、年が明けて春になって、癌の宣告を受けます。「せいぜい、もって6か月ですよ」。その通り、6か月で地上の命を終えられ、この場所で葬儀が行われました。中学生と高校生の娘さんふたりと、のちにやはりこの場所で洗礼をお受けになったご主人が残されました。最近、ある機会がありまして、この方が病床で最後に書き残されたという短い手記を読みました。それをぜひ、この礼拝で紹介させていただきたいと思いました。
病床にて記す
私は今、病院の窓から外を眺めている。外は昨夜からのシトシト雨だ。今春、桜の花が雨に打たれていた時も、私は窓から外を眺めていた。あの時は京都東山のホテルの窓から、春雨に煙る山々を眺めていた。きれいな雨だった。
あれから6か月という時が流れ今は秋の雨、京都の雨は紅葉をぬらしているだろうか。今、私は病を得て病室にいる。絶対安静という医師からの指示に従ってベッドの上にいる。時の流れとは何なのだろうか。4月に主人が私の命の制限を言い渡された。「奥さんの命はせいぜいあと6か月です」。そしてこの月がその制限の6か月目になろうとしている。しかし私はまだしぶとく生き続けている。人の命とは何なのだろうか。それは医師が定めるものではない。ましてや自分自身で定めるものでもない。神に与えられ神に戻す人間の生命を他人任せにするのは、人間としてあまりにも無責任ではないだろうか。与えられた命を大切にして毎日毎日を大事に生きること、これは人間としての命を与えられた者にとって犯しがたい責任でもあろう。
今回癌という病にあって、まったく今まで見えなかったものが見えてきたように思う。わずか6か月が過ぎたにすぎないが私にとってはこの6か月は長い長い道のりであった。今まで見えなかったもの、「家族」、「友人」、「親戚」、まわりのさまざまなものがこの6か月で見えてきたように思える。振り返れば春からの6か月、それは私には長い長い年月のように思える。40数年間かかって学んだ以上に濃く、重い6か月でもあった。
こういう言葉について、安易な感想を述べることさえ憚られますが、見事な文章です。余計な言葉はひとつもありません。なぜ私がこの文章を紹介したいと思ったか、すぐに理解していただけたと思います。見事に死を見つめています。ただ死を見つめているつもりで、実は逆に死に睨まれているだけの人間の言葉ではありません。既に死に勝っている人間の言葉です。どのようにして死に勝ったのでしょうか。自分の命の初めと終わりを定めるのは、神さまだけだと書いておられます。だからこそその命を、きちんと責任をもって、神さまにお返ししないといけない。
だからこそ、この文章の最後に「今回癌という病にあって、まったく今まで見えなかったものが見えてきた」とも書いています。死だけを見つめて、逆に死に見つめられている人間には、こんなことは書けないのです。神の恵みが見えてきた。自分が40年以上かかって学んだ以上に濃く、重い6か月。今まで見えなかったものが見えてきた。
それはある意味では、ご家族のために残す遺言だったのだろうと思います。夫と、まだ中学生、高校生の娘と、いちばん気がかりなのはこの家族のことだ。でも、お母さんはだいじょうぶだからね。今までまったく見えなかったものが、今は見えているから。何が見えたのでしょうか。「メメントー・モーリー」。「死を忘れるな、そして恵みを忘れるな」。この手紙を書いたパウロもまた、その神の恵みの中で、このような言葉を書いたのだと思います。
■聖書の学者たちの中には、こういうことを言う人もいます。この手紙はまず第1章、第2章、そして第3章の前半まで、徹底的に人間の罪について書きました。そのあと第3章の後半から第4章、第5章の前半まで、その人間を救う神の恵みについて書いてきました。それなのに、なぜ今さら、またこんな暗い話が始まるのだろう。それこそ、話がつながらないじゃないか、という戸惑いを隠さない人も多いのですが、実はここで大切なことがあります。パウロはこの第5章12節以下で、初めて死について語るのです。人間の罪については、この手紙の最初から、これでもか、というほどに書いてきましたし、その罪は当然滅びを招くのですが、正面切って「死が来た」と書くのは、ここが初めてなのです。「死が入り込んだ」、「すべての人に死が及んだ」と言います。なぜここで死について語り始めるのでしょうか。死の陰の谷に、光が射し込んだからです。そうして初めて、人間は死をまっすぐに見つめる準備を得たのです。もう一度、第5章の10節以下を読みます。
敵であったときでさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は、御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を誇りとしています。このキリストを通して、今や和解させていただいたからです。
その恵みの中で、パウロはここで初めて人間の死について語り始めます。自分たちが、どんなに恐ろしい場所から救われたか。あんな恐ろしいところに自分たちはいたのであって、だからこそ自分たちは、死をまっすぐに見つめることさえできなかった。しかし今は、そのことがよくわかる。今は神に救われて、神と和解させていただいて、初めて自分の死を正しく見つめることができる。
■そのときに、ここでまた初めて登場してくるのがアダムという名です。創世記の最初に、アダムとエバという人類最初の夫婦が出てくることは、聖書を読んだことがない人でも、どこかで聞いたことのある話だと思います。12節に出てくる「一人の人によって罪が世に入り」というのが、アダムのことです。これがまた、多くの人を戸惑わせるのです。最初の人類であるアダムという人が、妻と一緒になって、なんか罪を犯したらしい。まあ、それはわからないでもない。きっとそんなこともあるだろうし、昔話にしてはよくできているな。ところがここには、その「一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、すべての人に死が及んだのです」と書いてあります。ひとりの人、アダムによってこの世界は罪に支配されるようになった。そのことによって死がすべての人に及んだのだ。こんな無茶な話があるか。最初の人アダムの犯した罪と、この〈わたし〉と、いったい何の関係があるか。と、思うのですけれども、ここで大切なのは理屈ではなくて、まず現実だろうと思います。ここでパウロは、「すべての人が罪を犯したからです」と書いています。事実として、現実問題として、すべての人が罪を犯しているのです。そのために、苦しんでいるのです。事実、今も、私どもは自分の罪のために、他人の罪のために、また世界中の人間の罪のために、苦しんでいるのではないでしょうか。いったい、この罪というものはどこから来たのだろうか。そのことを考えないわけにはいかないのです。
特にここで強烈だと思うのは、12節の後半に「すべての人に死が及んだ」とあります。「及んだ」と訳されている言葉は、わりと強い表現です。前半にも「一人の人によって罪が世に入」った、「罪によって死が入り込んだ」と言うのですけれども、それに重ねて後半ではもう少し強い言葉を使うのです。ある人は、「死がすべての人にしみ通ってしまったのである」と訳しました。「すべての人に死がしみ通ってしまった」。「通過する、通り抜ける」という意味を持つこともありますが、ここでは、死が通過してしまうのではなくて、買ったばかりの白いシャツに墨汁がしみ込んでしまった。一本一本の繊維の奥まで、しみ通ってしまった。そう簡単には落ちないのです。いや、今のたとえは誤解を招くかもしれません。白いシャツの片隅に小さなしみができたというのではなくて、シャツ全部がドボンと墨汁の池に落ちてしまって、私という存在の、すべての繊維の一本一本に至るまで死がしみ通ってしまって、どんなにごしごし洗ってもどうしようもない。「メメントー・モーリー」。われわれは、必ず死ぬんだ。わたしは、そういう存在なんだ。
■そういう、人間という存在のいちばん深いところにある罪の現実を、最も明らかにしてくれるのが、アダムの話だというのです。いったい、アダムは何をしたのでしょうか。ひとつの見方をすれば、何のことはない、ただ食べてはいけないと言われていた木の実をひとつ食べただけです。「え、たったそれだけですか。たったそれだけのことで、全人類の心の、細胞ひとつひとつに至るまで、死がしみ通ってしまったって、それはいくら何でも」という感想もあるかもしれません。けれども、わかる人にはわかると思うのです。
蛇がアダムの妻を誘惑したとき、「これを食べると、あなたは神のようになるのだ」と言いました。それが自分にとっての誘惑にならない人がいるでしょうか。神のように、何でもできるようになりたい。何でも知っている人間になりたい。そこまでいかなくても、でもなるべく力を得て、知識を得て、負け組にはなりたくない。勝ち組になりたい。そうして自分を喜ばせたい、自分を楽しませたい。そんな思いが、人間をどんなにだめにしていることか。大げさでも何でもなく、まさにこの聖書の言葉が語っている通り、人類全体の命をどんなに損なっていることかと思うのです。その根本的な問題は、私ども人間の心の中に、神を神として拝む思いがないということなのです。私どもの心に、罪がしみ通っている。死がしみ通ってしまっている。
罪とは、あれやこれやの悪いことをすることではありません。もちろんそういうことも含むかもしれませんが、それが根本的な問題ではありません。神のようになりたい。そのためには、神なんか邪魔だ。神から独立して、神から自由になって、自分が自分の主人になって、自分の人生を支配したい。それが罪です。
そういうアダムのところに、これを食べたら神のようになれるぞ、という誘惑がありました。その結果が、死であります。どうして、と言われても、そんなことは当たり前です。私どもの命の初めと終わりを定めるのは、神だけなのですから。その神から自由になりたい、神から自由になって、自分で自分の人生を支配したい、自分で自分を楽しませたい、というのであれば、その人の命が根本的に神の命から切り離されたものになるのは当然です。自分で自分の命を神から切り離しておきながら、そんな自分が死ななければならないなんて納得できない、と言ったって、それは無理な注文です。
■けれども、たとえば、最初に紹介した病床で短い手記を書き残されたあのご婦人は、自分の死と向き合う中で、「わたしの命は神さまのものだ」と、それまでのどの時間よりも濃く、重く、そのことを学び直すことができました。自分の命は神からいただいたもので、神にお返しするべきもので、それを人生の最後に、きちんとしなければならない。自分の責任で、自分の命を神さまにお返ししないといけない。まさしくそのような出来事を、第5章10節以下で「和解」と呼んでいるのでしょう。
敵であったときでさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は、御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を誇りとしています。このキリストを通して、今や和解させていただいたからです。
この和解のために、私どものところに来られたお方が、イエス・キリストです。14節の最後に、「このアダムは来るべき方の雛形です」と書いてあります。「来るべき方」、もちろんイエス・キリストのことです。アダムは、イエス・キリストの雛形であった。新共同訳はここをもう少し説明的に訳しました。「実にアダムは、来るべき方を前もって表す者だったのです」。不思議なことではないでしょうか。アダムを見つめていると、それと重なるように、イエス・キリストの姿が見えてくるというのです。アダムとイエス・キリストと、どこがどう重なるのでしょうか。
アダムという人は、私どもすべての代表です。アダムによって、罪が世に入り、すべての人に死が及んだ。「メメントー・モーリー」。必ず死ななければならない私どもひとりひとり、その代表がアダムです。ところがそのアダムに重なるように、神のひとり子イエス・キリストが人となって、十字架の死を死んでくださいました。「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」と、十字架の上で叫ばれたイエス・キリストは、死に支配された私どもの代表であり、また代理であったのです。
「メメントー・モーリー」。死を忘れるな、死を見つめよと言われます。だがしかし、キリストの死を見つめずに、自分の死だけを見つめても、望みはありません。アダムだけを見つめて、ああ、自分にそっくりだなと言っているだけでは、本当のことはわからないのです。私どもが見つめるべきアダムとは、実は来るべき方の雛形であった。イエス・キリストを前もって表す者であった。そのキリストの死を見つめつつ、私どもは自分の罪を知ります。神に見捨てられるべきわたし、いやむしろ、自分から神を捨てていたわたしの代わりに、そう、まるでわたしと重なるように、イエス・キリストが死ななければならなかったことを知るのです。
このあとご一緒に祝う聖餐という食卓は、このキリストの死の記念の食卓、そして復活の祝いの食卓です。今日読んだところの最後の21節には、こう書いてありました。「こうして、罪が死によって支配したように、恵みも義によって支配し、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命へと導くのです」。罪の支配にはるかにまさる恵みの支配、命の支配の中に、今共に立ちます。お祈りをいたします。
私どもの神は、あなただけです。どうか今、私どもの命を、私どものすべてを、あなたにお返しすることができますように。自分の命を自分のものにしたがる罪を思います。神のようになりたいという私どもの思いが、私どもの生活を、またこの世界を、どんなにだめにしていることかと思います。今、自分の死を見つめつつ、いや何よりも、み子キリストの死と復活を見つめつつ、あなたの恵みの支配の中にまっすぐに立たせてください。主のみ名によって祈り願います。アーメン