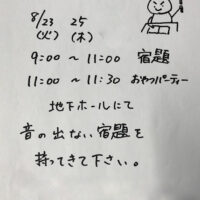あなたの人生に触れる神の言葉
ルカによる福音書 第4章38-44節
柳沼 大輝

主日礼拝
伝道者という人々に神の言葉を伝える働きをしていますと、よく周りから「あなたはどのようにして神様を信じて、神様に従って生きていこうと決心したのですか?」という質問を受けることがあります。
しかしこれはけっして伝道者として日頃から、教会に仕えている者だけではなくて、キリスト者として神を信じて生きる者であれば、きっと一度や二度、誰かに聞かれたことがある質問だと思います。「あなたはどのようにして神様を信じようと思ったのですか?」「あなたはどのようにして神様に従って生きていこうと決めたのですか?」
このような信仰者として皆が投げかけられるであろう問いに思いを巡らすとき、自らの人生の歩みを振り返ると同時に、いまここにいる皆さん一人一人にもきっとそれぞれにそれぞれ特有の神様との「出会い」があり、神様を知った、何かきっかけがあったのではないかと思います。
あなたは、どんな神との出会い、どんな経験を経て、いまこの礼拝の場におられるでしょうか。
本日は、最初に今日の説教の「中心」をお伝えします。本日のポイント、それは主イエスの救い、福音といったものは、「いきなり」起こるのではないということです。まるで稲妻に打たれたかのようにして「いきなり」神様を信じるのではないのです。それぞれの人生の歩みのなかで、神様との出会い、神様を知るきっかけがあって、人は、神を信じて、救いに生きる者とされていく。それがまさに聖書の証しする神の国の福音といったものであります。
本日の箇所を見てみますと、主イエスはペトロの家にお入りになったとあります。まだこのときはペトロとは言われていません。シモンと呼ばれています。その後にシモンは主イエスからペトロ(岩)といういわゆるニックネームを与えられました。実は、本日の箇所のすぐ後にこのシモン・ペトロが召し出され、主イエスの弟子となったという召命記事が記されています。(5章1節以下)
しかし、マタイによる福音書やマルコによる福音書など、この箇所の並行記事が記されている他の福音書と見比べてみますと、流れが逆なのです。他の福音書では、ペトロが弟子となってから主イエスは彼の家を訪れています。けれどもこのルカによる福音書では、その順序が逆転しています。これはいったい何を意味しているのでしょうか。
それはペトロが主イエスに「恐れることはない。今から後、あなたは人間をとる漁師になる」(5:10)と言われて、網を捨て、持ち舟を捨て、すべてを捨てて、主イエスに従っていくという自らの人生を左右する一大決心をしたのは、その場で「いきなり」なされた決断ではなかったということです。
その前にきっかけとなる出来事があって、その出来事がいわば「布石」となって、ペトロは大きな決心をし、主イエスに従っていくという行動を起こすことができたのです。
本日の箇所の最後で、主イエスは「ほかの町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために遣わされたのだ」(43節)と宣言なされます。しかしその福音は「いきなり」すべての町の人々に受け入れられ、一瞬にして、皆が信じるといったものではありませんでした。いわば、その前段階となる神からのアプローチがあるのです。その先駆けとなる出来事にしっかりと目を留めなさい、と本日の箇所は私たちにそう語りかけるのであります。
本日の箇所の内容を詳しく見ていく前に、この箇所の場面設定を簡単に説明します。カファルナウムというローマ軍が駐留するような大きな町で、主イエスは会堂に入り、人々に向けて、聖書のお話をなされました。その日は安息日であったとあります。そして、主イエスがお語りになったその言葉には、権威があり、悪霊を追い出すほどの力がありました。その言葉を聴いた人々は皆、それぞれに思いを巡らしながら、胸を震わせて、会堂からそれぞれの家へと帰っていきました。
その後、本日の箇所が続きます。主イエスも身体を休まれるために会堂を後にします。そこで、お入りになられたのが先ほど、申し上げた通り、漁師をしていたシモン・ペトロの家でありました。きっとこのとき、もうすでに主イエスとペトロとの間には、ある程度の関係性があり、この日もペトロの方から主イエスに対して「どうか自分の家に来てください」とでも言ったのでありましょう。しかし、実際にペトロの家に行ってみると、そこにはしゅうとめ、つまりペトロのお嫁さんの母親、義理のお母さんがひどい熱を出して苦しんでいました。
そこで、床で寝ているしゅうとめの枕元に立って、主イエスは何をなされたか。熱を叱りつけたとあります。熱を叱りつけた、実に面白い表現であります。まるで熱を擬人化して描いているかのようであります。いわば、ここではしゅうとめを縛り付ける悪しき力が高熱として現れ、彼女のことをひしひしと苦しめているのです。その悪しき力は、どうも人間の力でコントロールすることができるようなものではない。熱よ、下がってくれと言っても下がってくれない。悪しき力は熱という目に見える症状として現れ、身体で体感できるようなものによって、しゅうとめを捕らえて、離れようとしないのです。そんな悪しき力としての熱を主イエスは叱りつけたのであります。
皆さんも子どもの頃、何か悪戯をして、親から叱られたという経験をされたことがあるかと思います。そのように叱るとは、誰かが悪さをしたり、へまをしたりしたとき、その者の罪を指摘し、咎めることであります。ここで主イエスも悪しき力としての熱に向かって、その悪行を咎めました。「何をやっているのだ。いつまでこの婦人を苦しめ続けているのだ。早く彼女を解放しないか」と言ったところでありましょう。
すると熱は、何の抵抗を示すこともなく、この婦人から去っていきました。ここでも主イエスの権威の大きさが明らかにされています。主イエスの言葉が悪しき力を追い出したのです。そして、熱が下がった婦人は、たちまち起き上がって「一同に仕えた」とあります。この婦人は悪しき力が去って、元気になったら、皆のために奉仕した、仕えたというのです。元気の源は、悪しき力からの解放でありました。
このように主イエスが病気を癒してくださるという噂は、たちまちカファルナウム中に広まっていきました。そこで、日が暮れると、町中から多くの人々が主イエスのもとに押し寄せてきました。ここでどうして日が暮れてからかというと、そのときがちょうど安息日が明けるときだからであります。聖書の世界では一日は、日没で始まり、日没で終わります。ということは、金曜日の日没から土曜日の日没までが安息日であります。その間は、一切、働いてはならない、動いてはならない、そのように、律法によって行動が制限されているわけです。しかし、日が暮れることによって日付が変わり、安息日が終わりました。
そこで人々は一気に主イエスのもとへと押し寄せてきました。けれども、それは何も主イエスの癒しの業を一目、見ようとしてやってきたような野次馬としてではありません。そうではなくて、悪しき力としての病気によって痛んでいる、苦しんでいる大切な家族や、あるいは、友を抱えて、彼らの病を主イエスにどうにかして癒してもらおうと人々はまるで藁にもすがるような思いで、主イエスのもとへとその人々を連れてやってきたのです。どうかこの人を助けてほしい、救ってほしい、とそう心から祈りながら、願いながら、彼らは主イエスのもとにやってきたのです。
そこで、主イエスは、その人々を拒むのではなく、彼らを招き入れ、その一人一人に手を置かれて癒されました。一人一人に手を置かれた、ここで重要なことは、癒しというものは、皆一様にではなく、いわば、十把一絡げではなく、一人一人に対してなされるということであります。主イエスのもとへと連れて来られた人々は、皆、それぞれに悪しき力に捕らわれて、苦しんで、辛い思いをして、痛みを負ってきた人々なのであります。たとえ、同じ病気で苦しんでいたとしても、誰一人として同じ痛みを負っている人などいません。
だから、主イエスは、皆を一気にその場で「いきなり」癒されるというようなことはなさいませんでした。そうはなさらず、主イエスはその一人一人に手を置き、一人一人と向き合い、その人が歩んできた人生という歴史に目を向けながら、その人がいままで苦しんできた痛み、味わってきた辛い過去、目を背けたくなるような弱さと向き合いながら、まるでその人の人生をすべて抱え込むかのようにして、その傷に触れ、その人を悪しき力から解放し、癒してくださったのです。ここに主イエスの深い憐れみが示されております。
そのとき、悪霊が叫び出し「あなたは神の子だ」と言って、人々から出て行ったとあります。ここで「叫びながら」と訳されている言葉は、原典から直訳すると「大きな声で言い続ける」という意味の言葉であります。「あなたは神の子だ」と、悪霊はそう大声で言い続けたのです。
何故、こんなことをするのか。それは何も自分の力を周りの人々に見せつけたいというわけではありません。悪霊と主イエスとでは、その権威の大きさがまるで違うのです。そんなことは、人間よりも悪霊の方がよく分かっていました。その証拠に悪霊は主イエスをメシア、つまり救い主であると知っていたとあります。自分たちの力では到底、救い主である主イエスに太刀打ちできるはずがない。抵抗してもまるで無駄である。もうこの人から出て行くしかないと、悪霊はそう覚悟を決めていました。
しかし、最後に彼らはまるで悪足掻きでもするかのように「あなたは神の子だ」と言って、大声を上げて叫び続けるのです。そこで主イエスは、そんな喚き立てる悪霊を叱りつけたのであります。このときも主イエスはペトロのしゅうとめの熱を叱りつけたときと同じように「そんなに大声で叫んでいないで、早くこの人たちから出ていかないか」と悪霊を叱りつけたのです。悪霊はもうこの主イエスの命令に従って、この人々から出ていくしかありません。
この一連の癒しの出来事は、日が沈んでから夜の間に行われました。まるで夜間緊急診療のように主イエスは休む間もなく次から次へと連れて来られた者に対して、癒しの業をなされたのです。
やがて、朝が来て、主イエスはさぞかし、お疲れになられたのでしょう。それもそのはずです。悪霊を追い出す、癒すということは、先ほど、申し上げたように、その人に触れ、その人と向き合い、その人の「人生」という歴史にコミットし、関わっていくということであります。
私たちで言えば、それはちょうど一晩中、誰かの人生の話にじっと耳を傾ける、傾聴するということに近いかと思います。そうやって私たちは誰かの人生に触れることができますが、これは非常に多くのエネルギーを要することであります。
主イエスは神の子としての全能の力を用いて、病人たちを一度に癒したのではありません。一人一人に手を置き、その一人一人と向き合うなかで激しい疲労感を抱かれたのであります。そこで、主イエスは人里離れた寂しい所へ一人退く必要があると感じました。おそらく、そこで一人祈るためでありましょう。主イエスは、群衆から離れ、静かに一人、父なる神に相対して、祈るなかで力を回復しようとされたのです。
一方、群衆はというと、主イエスがいなくなってしまったことにひどく動揺しています。そこで彼らは、懸命に主イエスを捜し回ったとあります。彼らは、不安でたまらなかったのです。どうしてよいか分からなかったのです。そして、やっと主イエスを見つけ出したら、彼らはこう言いました。「どうか自分たちのもとを去らないでください」。彼らは、しきりに主イエスを自分たちのもとに引き止めようとしました。
しかし主イエスは、彼らの願いを断わります。「ほかの町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために遣わされたのだ」。主イエスはそう言って、ご自分がこの世に来た目的、使命をはっきりと人々にお伝えになります。神の国の福音は「限定的」ではない。「全世界」に広がっていくものなのだと宣言なされたのです。
この後、主イエスは、この言葉通りに、ユダヤの諸会堂を回って宣教なされます。しかし、考えてみますと、このことも実に限定的であります。いくら主イエスがユダヤ地方を巡って、そこで福音を宣べ伝えたとしても、そこでいくら癒しの業をなされたとしても、それが一気に世界中に広がっていくというわけではありません。主イエスがユダヤの諸会堂を回ったところで、そんなのたかが知れています。
けれども、ここで私たちは主イエスがお教えになった「種蒔きのたとえ」を思い出したいのです。たとえ、わずかな言葉、わずかな時間、わずかな出来事であったとしても、そこで蒔かれた種は六十倍、百倍にまで広がっていく。神の国の福音とは、まさにそのようなものであります。(マルコ4章1節以下)
本日、ペトロの弟子としての召命記事に先立ち、示された主イエスの癒し、解放は何度も申し上げてきたように、十把一絡げに起こるものではなく、神様とその人との人格的な出会いのなかで、起きていくものでありました。つまり一人一人が、自らの人生のなかでいままでに味わってきた痛み、辛さ、後悔、怒り、弱さ、恥、その一つ一つに主イエスが触れて、タッチしてくださるなかで、時間をかけて、人はその人を縛り付ける悪しき力から解放されていくのであります。
しかし、それは、ただ神様があなたに一方的に触れてくださるということに留まるのではありません。そこには、たしかな私と神様との交流が生まれます。神様との対話が生まれていきます。主イエスに触れていただくとき、私たちは、神に訴え、祈っているのです。「悔しい」「悲しい」「寂しい」「情けない」。そんな自己受容できない自分の気持ちを主イエスにぶつけているのです。
しかし神様に手を置いて、触れていただいていくなかで、必死にその祈りを聞いていただくなかで、神様から私たちへの「言葉」が聞こえてくる。そうやって神との対話が生まれる。その交流のなかで、少しずつ悪しき力からの解放が起きていく。
福音といったものは、群衆が切望していたように、主イエスが物理的にずっと私のそばにいてくださるということではありません。
私の人生に手を置いて、主に触れていただいて、そこで私たちのうちなる、あらゆる思いを全部、聞いていただいて、そういったなかで、私たちには、神からの言葉が与えられるのです。「そうか辛かったね」「ずっと苦しんできたのだね」「悔しかったね」「それは自己嫌悪にもなるよね」「それは怒りたくなるね」。
私たちは、そうやって主イエスに触れていただいて、心にある思いを全部、聞いていただいくなかで、少しずつ、悪しき力から解放され、癒されていくのです。神の言葉によって、立ち上がり、新しく歩み出す者とされていくのです。
そして、その歩みは導かれ、導かれ、やがて、十字架の主の御前へと招かれていきます。やはり一足飛びとはいかないのです。稲妻に撃たれたかのようにして「いきなり」とはいかないのです。
それぞれにプロセスがあって、「布石」となるきっかけがあって、それぞれが主イエスの十字架の御前に立たされます。そこで十字架を仰ぎ見て、見上げていくなかで、釘打たれ、血を流し、死んでいった主イエスの御姿を心の目で見、その言葉に耳を傾けていきます。
そのとき、主はあなたに語りかけます。「もう恐れることはない。血の代価が払われたその主の真実をもって、あなたの罪は赦された。あなたはあなたを苦しめる悪しき力から解放されるのだ。いまそれを約束としてあなたに与えよう」。
その神からの約束こそが「洗礼」であります。洗礼とは何かが分かったから、何かの知識レベルに達したから、それで受けられるといったものではありません。けっしてそうではないのです。
主イエスに触れていただいて、祈りと御言葉の交流を通して、それぞれのプロセスを経て、主の十字架の御前に立たされ、罪の赦しを与えられる。「あなたの罪は赦された。だから何も恐れる必要はない」という救いの約束に生きる者とされていく。その罪の赦しを受け取り、差し伸べられた主イエスの、その御手を握り返すとき、私たちは、神に救い出され「洗礼」へと導かれます。悪しき力から解放されて「福音の喜び」に、真の「幸い」に生きる者とされていきます。
そうやって、悪しき力から解き放たれ、救われた者は、キリスト者として自分だけがよかったというようにはいきません。そこに留まるのではありません。今度は、いまなお悪しき力に捕らわれ、苦しめられている、悩んでいる、あの人のためにあの家族のために、あの友のために自分なりに何かできることをしようとします。それが「仕える」ということです。本日の箇所で、元気になって、起き上がったペトロのしゅうとめがした「一同に仕えた」と言われていることです。
「仕える」と言われても、多くの人がこんな私に何ができるのかと考えてしまうかもしれません。自分には、何もできないと思ってしまうかもしれません。しかし、あなたにしかできない神様への仕え方があるのです。いま、悩み喘いでいるあの人に主イエスの言葉を届けてみたり、やはり黙ってその人の傍らにそっと寄り添ってみたり、心にあるその人への思いを手紙に綴ってみたり、その人のために一人、静かに祈ってみたりする。それはほんのわずかな愛のわざかもしれません。けれども、それでよいのであります。そこからきっと神の国の福音は、蒔かれた種として少しずつ、しかし、何十倍にも、何百倍にも大きく広がっていきます。私たちはそう一人一人、その「喜び」に、その「幸い」に召し出されています。
贖いの主、宣教の主である主イエス・キリストの父なる御神、あなたが私たち一人一人の人生に触れて、あなたとの出会いを与え、御言葉と祈りを与え、この日まで、私たちの歩みを一歩一歩、守り導いてくださったことを心より感謝いたします。ときに痛みを負い、一人涙する日がありました。怒り、他者を、自己を傷つけた日がありました。しかし、そのような日々も、あなたが私たちとともにいてくださったことを思います。今日もあなたの御手に私のすべてを委ねます。あなたに救われた者として、今度は、私があの人にあなたの言葉を届けることができますように。どうか、あなたの名によって、私たちをお遣わしください。この願いと感謝、救い主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン