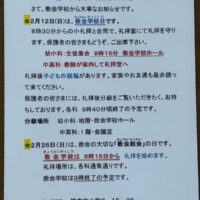孤児にはしておかない
ヨハネによる福音書 第14章18-31節
嶋貫 佐地子

主日礼拝
私どもは、どうして生きていけるのでしょうか。
いろいろありながらも、どうして生きて行かれるのでしょうか。
とても素朴に申しますと、それは、主の愛があるからだと思います。ほんとうは理由なんて、それしかないくらいに、私どもは主の愛があるから、生きていかれていると思うのです。
生活や心配事もいろいろあるが、病気もあるが、もう死にたいとさえ思うこともあるが、それらを全部これに替えてしまう「愛」というものによって、今、私は、この愛で生きている。この愛で生かされている。そう言えるのだと思います。
だからもしこの愛がなければ、私はきっと私ではないし、私自身を作っているものは、もはや、この愛でしかないと思います。
でもそのことを、割と簡単に忘れてしまう私どもです。この愛をすぐに忘れてしまう。だから、あまりうまくいかないで、誰かを愛することもすんなりできないで、自分が苦しくなりますし。神を愛することなんて、自分にできているのかと思わされます。けれども、私の中にある「愛の主体」というのは、じつは私から生まれたものではなくて、それははるか向こうから、あの最上のところから来て、私の中に住まう愛です。
だからほんとうはこの愛が私を形作っています。この愛が私を生かしてくれています。そのうえこの愛は時間も空間も飛び越えています。最後まで残るのはこの愛です。
だから、それはどんな別れにも勝っています。別れと言って、一番は「死」を思いますけれども、それにもこの愛は勝っています。最強なのです。この中のおよそ多くの方は、愛する人との別れを経験しておられると思いますけれども、この愛は、その別れに、勝っています。
主イエスが、別れを経験されました。
主イエスもまた弟子たちとの別れを経験されました。人としての厳しい別れを経験されました。私どもが知っている厳しさというものはすでに主イエスが経験されています。それはもちろんこれから、主イエスが十字架に向かわれるからですけれども、そして主がもとおられた、父の許にお帰りになるからです。
別れなきゃいけないのです。別れないとならないのです。
だからそこで主イエスが、「愛が極まった」(13:1)というのは私ども人間にはほんとうに理解できます。弟子たちをこの上なく愛し抜かれたのです。その者たちとの別れなのです。でも主イエスがそこで言われた別れの言葉というのは、人間には言えないものでした。
「私は、あなたがたをみなしごにはしておかない」(14:18)
「あなたがたのところに戻ってくる。」(14:18)
主イエスが約束されたのです。
「あなたがたをみなしごにはしておかない」。
戻ってくる。
こんな約束、涙が出ます。こんなことを言えるのは、主イエスだけです。こんなこと言えるのは、戻ってくる人しかいないです。死なれたのに…戻ってくるなんて。
死んだのに…戻ってくるなんて。どんなに、それが叶ったらいいでしょう。だから、こんな約束をできるのはこの方しかいないです。死を超える約束なのです。これにこみ上げるけれども、でもこれはただの感傷的なことではなくて、この主イエスの「確かな約束」に泣けてきます。
置いてかないと言われているのではないのです。置いて行かなきゃならないのです。でも主イエスがここで言われているのは、私が「行けば」ということでした。私が父のもとに行けば、父は別の弁護者を遣わしてくださる。聖霊なる方を私の代わりに遣わしてくださる。だから主は、そのために、そこに行かれます。
そしてそれは主ご自身が、霊において、また戻って来てくださることでもありました。主イエスが霊において、また戻って来てくださる。だから言い方を変えますと、主は、また「来る」ために、父のもとに「行かれる」のです。
でもそれだけではなくて、もともと主イエスは、天へ「行く」ために、地に「来られ」ました。不思議なことですが、主はもともとそうだった。主はそこへ「行く」ために、地に「来られた」のです。
ヨハネ福音書がとても大事に言っておりますのは、この方は神の御子だったということです。神の御子が「人」となって私どものところに「来て」くださった。それは「永遠」という神の世界から、私どものところに来てくださった。そしてそれは何のためかというと、私どもに「永遠の命」を与えるためだった。するとその「永遠の命」とは何か。それは「神が永遠に一緒にいる」命のことです。永遠なる神が、ずっと一緒にいてくださる命。こんなにいいことはないのです。
そして、主がそのことを成し遂げてくださって、それで、主は、今はどこにおられるかというと、天におられます。『雪ノ下カテキズム』も言っています。
「あの方は今どこに」。
あの方は天におられる。「永遠」の世界におられる。でもその主イエスが、そこから来て、私どもの所に来て、そして私どもの所から、そこに行かれたのですから、私どももその主によって、その「永遠」につながりました。道ができた。
神の「永遠」とつながったのです。
主イエスが、そうして、天と地を結ぶ、道となってくださいました。
この少し前に、主イエスが、「私はあなたがたのために場所を用意しに行く」(14:2)と言ってくださっています。父のところには「住まい」がたくさんある。私はそこに「行って」、あなたがたのために「住まい」を用意してあげよう。そうしたら、また「戻って来て」(14:3)あなたがたを私のもとに迎えると、主はそこでも戻ってくると言ってくださっていました。
でも、この「戻って来る」というのは、私どもが思う終わりの日の再臨のことだけではなくて、そんな遠いことだけではないようです。そうではなくて、主は「しばらくすると」(14:19)とおっしゃっていますが、それは少しの間という意味で、主のおよみがえりの直後と思われます。主イエスが復活のお姿で、弟子たちに真っ先に会いに来てくださいましたが、復活の朝の再会という場面は、ほんとうにまばゆいものでした。もし、そうでなければ弟子たちは主に見捨てられたと思ったことでしょう。終わりの日まで待てなかったことでしょう。でも復活の直後に主イエスが会いに来てくださった。お急ぎで会いに来てくださった。だから弟子たちは、むしろそこから終わりの日に、もう一度、主が来てくださる再臨を、心から待つ教会になったのです。
ですから、これは別れであって、ほんとうは、別れではなく、別れの克服であったのです。天と地はつながった。だから、もう別れはなくなった。そのために主は、天に行かれたのです。
この福音書が、もしかしたら一番言いたかったのは、そのことかもしれません。福音書全体でそのことが言いたかったのかもしれません。
神の御子が「来られた」。そして言われた。
「私は、あなたがたをみなしごにはしておかない」。
そのお言葉に息をのんだ。そうだ。これが全部だ。主が確かに約束された。
「あなたがたをみなしごにはしておかない。」
もう別れはない。それが永遠の命なんだ。
そしてこれは神の、「私は、あなたがたをみなしごにはしておかない」ということだったんだ。
私の神学生時代の仲間で、ある牧師が、ここのところで「空き家」の話をしていました。空き家というより、最初は空き部屋と言っています。それがとてもよいので、ちょっと引用したいと思います。
「人は心の中に、たくさんの部屋を持っている。キリストが死なれた時、弟子たちの中に空き部屋ができた。むしろ、心全体が一つの空き部屋になった。」
人の心の中には、たくさんの部屋がある。
主イエスが死なれた時、弟子たちの心の中に、空き部屋ができた。心に、誰もいない部屋ができた。いや、むしろ、心全体が一つの空き部屋になった。
誰かがいなくなった。
それは私どもも、多くが知っていることです。
誰かがいなくなった。
昨日まで、おとといまで、確かにいたのに、そこにその人がいなくなった。使っていた物もそのままになった。そしてもう、その部屋にはだれもない。
愛する者を亡くした者というのは、そういう毎日を繰り返します。朝、起きて、いるべきところに、いるべき人がいない。余韻はつらすぎる。残り香が慕わしい。何年も、何十年もその虚無を繰り返し。それは変わらない。
その心の空き部屋は、埋めようがない。
そうして、もはや、自分が、「空き家」となった。
でもそこに、主が入って来てくださいました。
死に勝って入って来てくださいました。
今度は、「慰め主」として、今度は「聖霊」において、私の中に住んで、この空き家を満たしてくださいました。
だから私どもは、生きることができる。
この愛が、天と地を結んでくださったので、もう別れはなくなって。愛する人との永遠の別れはなくなったのです。この方が別れをなくしてくださったのです。
あなたがたをみなしごにはしておかない。と、いうのは、そういうことでもあったと思います。
さっきの牧師が言いました。
「廃屋に光が注ぐ」。
廃屋に光が注ぐ。主はこんなことも言ってくださいました。互いに愛し合いなさい。この掟を守る人。私の父はその人を愛される。「父と私とはその人のところに行き、一緒に住む」(14:23)。父と私はその人を愛して、その人のところに行って、一緒に住む。
廃屋に光が注ぐ。
そうしたら、その家の中で、私というものの中で、愛が動き始めるのです。
『雪ノ下カテキズム』も言います。
「主が愛によって私どもとともに居てくださるところ、そこに愛が生まれます」(問140)。
そしてこのことは、愛する人を置いて行く方にとっても朗報です。これから愛する人を置いて行かなくてはならない。その遺す方にとっても、天にも「住まい」があるように、自分が愛する、置いて行く人の中にも、同じ方が、父と共に、住んでくださるのですから。
感謝して、祈ります。