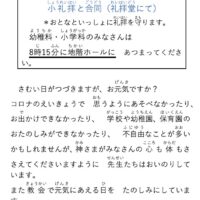わたしの心に刻まれる神の愛
ローマの信徒への手紙 第2章1-16節
川崎 公平

復活主日礼拝
■主イエス・キリストはお甦りになりました。「イースターおめでとう」と互いに挨拶を交わしながら、この喜びの祝いの輪の中で、「いったい、何がめでたいんだろう」といぶかっておられる方のためにも、主のお甦りの祝福を告げたいと思います。主イエス・キリストは、お甦りになりました。ほかの誰のためでもありません。私どものために、このわたしのために、主は死人の中からお甦りになりました。それが私どもの喜びになるのは、私どもの生活が、根本的に新しくなったからです。この世界が、抜本的に新しくなったからです。二千年前、イエスという名前の男が、一度死んだけれども生き返ったらしい。へえ、すごい、というだけの話なら、わざわざ日曜日を犠牲にして礼拝をする必要もないのです。しかし、何がどう新しくなったのでしょうか。
今日は年に一度のイースター、復活の祝いの日ですが、いつも通り伝道者パウロの書きましたローマの信徒への手紙を読みます。年が明けて以来、私がここに立つときには、この手紙を初めから少しずつ読み続けてまいりまして、今日はたまたま第2章のこのような言葉を読むことになりました。先ほど聖書朗読をお聞きになりながら、復活の喜びに心が震えたという人は、いたとしてもかなり珍しいタイプの方ではないかと思います。このように、毎日曜日聖書の順番に従って読んでいくという習慣は、私どもの教会のひとつの伝統になっています。そこで問題になることは、今日はイースターだ、今日はクリスマスだ、というときに、どうもなんだか全然関係ない話を聞かされるということになりかねない、ということです。別に私は意固地になっているつもりはありません。何が何でも順番通りに聖書を読んでいかなければならないわけではありませんし、実際、特別な礼拝の日に特別な聖書の言葉を選ぶことはいくらでもあります。しかし今回は、ローマの信徒への手紙の続きを読むことにしました。
しかしそこで改めて考えてみたいのですが、今日読んだローマの信徒への手紙第2章は、主のお甦りと何の関係もないのでしょうか。それでも、今週与えられた聖書の言葉はこの箇所だからしょうがない、何とかこじつけて復活の話をしなければならないのでしょうか。これはしかし、イースターがどうとかいう話を越えて、私どもが聖書というものをどのように読んでいるか、その基本的な姿勢が問われるところだと思います。
■このローマの信徒への手紙を読み進めていくと、第14章にこういう言葉があります。この第14章については、しばらく前の説教でも、しかも何度か紹介したことがありますが、どうもその頃ローマの教会の中で、肉を食べていいか、悪いか、ということが問題になったらしい。そのために、お互いに裁き合い、一緒に生きることが難しくなったらしいのです。その問題を解きほぐさないといけない、ということも、パウロがローマの教会に手紙を書くことになったひとつの理由であったと考えられるのです。そこでパウロはこう言うのです。
私たちは誰一人、自分のために生きる人はなく、自分のために死ぬ人もいません。生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。従って、生きるにしても、死ぬにしても、私たちは主のものです。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。それなのに、なぜあなたは、きょうだいを裁くのですか。また、なぜ、きょうだいを軽んじるのですか。私たちは皆、神の裁きの座の前に立つのです(第14章7-10節)。
これは、それこそイースターであろうとクリスマスであろうと、いつでも心に刻んでいなければならない福音の言葉だと思います。私どもが地上に生きる限り、常に忘れることのできない聖書の言葉だと思います。何度でも読み返していただきたいと思います。「キリストが死に、そして生きたのは」、つまり甦られたのは、「死んだ人にも生きている人にも主となられるためです」。イエスは主である。わたしの主、そしてあの人の主でもいてくださる。この人の主でもいてくださる。そのために、主イエスはお甦りになったのです。私どもが日々の生活の中で隣人と共に生きるとき、いつも主の甦りの光の中で、隣人を見ることを教えます。甦りの光の中で、隣人と共に生きるのです。特にここでは、食事が問題になっております。「箸の上げ下げまで」という日本の表現がありますが、それこそ私どもの生活の箸の上げ下げに至るまで、キリストの復活の命が宿るようになる。キリストが、わたしの主でいてくださるのです。「それなのに、なぜあなたは、きょうだいを裁くのですか。また、なぜ、きょうだいを軽んじるのですか。私たちは皆、神の裁きの座の前に立つのです」。「私たちは誰一人、自分のために生きる人はなく、自分のために死ぬ人もいません。生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。従って、生きるにしても、死ぬにしても、私たちは主のものです」。
そのような、私どもであります。主が甦られた今や、「生きるにしても、死ぬにしても、私たちは主のものです」。そういう私どものために、ローマの信徒への手紙は書かれました。第1章も、第2章も、第3章も。この手紙の中に、主の甦りの光の中で書かれなかった言葉は一文字もありません。
■復活を信じるとは、非常に単純な言い方をすれば、死の向こう側の世界を信じる、ということです。主イエス・キリストのお甦りを信じる私どもは、また自分自身の甦りを信じます。共に生きる者の、あるいは既に死んだ者、愛する者の甦りを信じます。甦りを信じるとはつまり、地上の死の、その向こう側を信じるということです。しかし、私が素朴に感じていることですが、死んだらそれでおしまいだ、と考えている人は、少なくとも日本人の中ではむしろかなり少数派だと思います。どこかで、何らかの形で、死後の世界をぼんやり信じている人のほうが大多数だと思います。何の根拠もないのですけれども、何かがあるに違いない。おそらくは人間が観測し得る広大な宇宙の、さらにその外側に、何かがあるに違いない。そうでも信じないとやりきれないからでしょう。
しかし、そこでどのような死後の世界を望み見るのでしょうか。この手紙を書いたパウロははっきりと、「私たちは皆、神の裁きの座の前に立つのです」と書いています。先ほど読んだ第14章にもそう書いてありました。「それなのに、なぜあなたは、きょうだいを裁くのですか。また、なぜ、きょうだいを軽んじるのですか。私たちは皆、神の裁きの座の前に立つのです」。あなたの隣人と共に生きるとき、あなたがあなたの隣人を裁くとき、死の向こう側のことを考えたことがありますか。今日読んだ第2章の6節以下でも、このように言うのです。
神はおのおのの行いに従ってお報いになります。耐え忍んで善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には、永遠の命をお与えになり、利己心に駆られ、真理ではなく不義に従う者には、怒りと憤りを下されます。すべて悪を行う者には、ユダヤ人はもとよりギリシア人にも、苦しみと悩みがあり、すべて善を行う者には、ユダヤ人はもとよりギリシア人にも、栄光と誉れと平和があります。神は人を分け隔てなさいません(6-11節)。
それこそ、先ほど聖書の朗読をお聞きになりながら、皆さんはどういう感想をお持ちになったでしょうか。何と申しますか、あまりにも当たり前すぎることが書いてあります。「いいことをした人には永遠の命、悪いことをした人には神の怒りと憤り」。死んだあと、閻魔大王がどこかで待ち構えていて、という話と何が違うのでしょうか。けれどもそういう話が、まじめに聖書に書いてあると、話があまりにも率直すぎて、逆に私どもは困るのです。今読みましたところの最後に、「神は人を分け隔てなさいません」と書いてあります。これもまた、至極当然のことです。神は人を分け隔てなさらないというのは、神さまはどんな人も愛しておられますよ、という意味ではありません。少なくともこの文脈ではそういう意味ではありません。神はどんな人も分け隔てなく、お裁きになる。そのことについて、さらに12節ではこうも言います。
律法なしに罪を犯した者は、律法なしに滅び、また、律法の下にあって罪を犯した者は、律法によって裁かれます。
この「律法」というのは、ユダヤ人のアイデンティティです。ユダヤ人と呼ばれる人びとは、今でも変わらないことですけれども、他の民族と自分たちは決定的に違う、その決定的なしるしは、自分たちには律法が与えられていることだと考えていました。律法を知らない他の人びとは「異邦人」、つまり「外人」と呼んで、しかしわれわれはあいつら外人とは違う。われわれには律法が与えられているのだ。それが神の前にも通用する特権であると考えていたのです。ところがここでパウロははっきりと言うのです。「神は、人を分け隔てなさいません」。「律法なしに罪を犯した異邦人・外人は、律法なしに滅び、また、律法の下にあって罪を犯したあなたがユダヤ人は、律法によって裁かれます」。ここで多くの人が、この「律法」という言葉をそのまま「洗礼」と言い換えて、教会のための言葉とすることも許されるだろうと、注を付けています。その読み方に従って、12節以下を少し読んでみます。
洗礼を受けずに罪を犯した者は、洗礼なしに滅び、また、洗礼を受けた上で罪を犯した者は、洗礼によって裁かれます(その人が洗礼を受けたという、その事実によって裁かれます)。洗礼を受けた者が神の前で正しいのではなく、洗礼にふさわしい生活をする者が義とされるからです。
……と、そんな調子で聖書を読んでいきますと、ますます居心地が悪くなってきます。私どもは、それこそ洗礼を受けていてもいなくても、自分の生活について確信がないのです。確信がないくせに、他人のことになると、あれはけしからん、いくら何でもあれはだめだと、平気で裁くのです。いや、むしろ確信がないからこそ、他人を裁いて、少しでも自分はましだと安心したいのかもしれません。
■7節には、「耐え忍んで善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には、永遠の命をお与えになり」と書いてあります。何気ない文章だと思われるかもしれません。それはそうだ。当たり前のことが書いてある。けれどもこの言葉には、伝道者パウロが教会の仲間を一所懸命励まそう、慰めようとした、その思いが強く伝わってくるような気がします。「耐え忍んで、善を行い」と言うのです。「耐え忍ぼう」。私どもはうっかりすると、善人というのは何の苦労もなしにいつもニコニコして、善いことばかりしているように思っています。あるいは、条件さえ整えば、いつでもその気になれば善を行うことができると考えているのではないかと思います。けれども自分自身のことを考えると、なかなかそうはいきません。あいにく今は条件が悪いのだ。あの人のせいだ。この人のせいだ。環境のせいだ。それでわたしは十分に善を行うことができないのだ。けれども実際には、そんな条件が整うことなんか、絶対にないのです。それは、自分自身の生活のことを真剣に考えれば、すぐにわかるはずのことだと思います。だから、「耐え忍んで、善を行え」と言うのです。何をどう、耐え忍ぶのでしょうか。
やはり伝道者パウロの書きました、コリントの信徒への手紙Ⅰ第15章32節に、こういう言葉があります。「死者が復活しないとしたら、『食べたり飲んだりしよう/どうせ明日は死ぬのだから』ということになります」。強烈な言葉ではないでしょうか。私どもは皆、明日死ぬかもしれない生活をしているのです。もしも復活がなかったら、何のために耐え忍んで善いことをする必要があるでしょうか。どうせ死んだらおしまいなんで、それなら、なるべく好き勝手な生活をして、好きなものを好きなだけ食べて、好きなだけ飲んで、好きな人とだけ付き合って、嫌いな人とはなるべく距離を取って、何なら思いっきり関税でも取って……けれどもそれは、決して幸せな人間の生き方ではないのです。復活の望みに生きる人は、そのような生き方から解き放たれています。
けれどもそこで、どうしても避けることができないことは、「耐え忍ぶ」という、このことです。忍耐するのです。新約聖書には、「忍耐」を意味するいくつかの言葉がありますが、特にここに出てくる「耐え忍ぶ」と訳されている言葉は、私どもの忍耐の生活の特質をよく表していると思います。元の言葉をなるべく厳密に直訳すると、「下に・留まる」という意味の言葉です。逃げ出したくなる。こんなところにはいたくないと、よそに行きたくなる。けれどもそこで、じっと何かの下に留まるのです。何の下に留まるかは書いていないようですが、実はちゃんと書いてあります。「耐え忍んで善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には、永遠の命をお与えになり」。既にキリストはお甦りになったのですから、既に私どもにも「栄光と誉れと朽ちないもの」が約束されているのですから、そこに留まろう。キリストの命のもとに、じっと留まるのです。
私どもの生きるこの世界において、復活の望みのもとにじっと留まるということは、必ずしも容易なことではありません。どんなに悪が強く見えても、耐え忍んで、神の勝利を待つのです。さまざまな罪に誘惑されるときにも、わたしは必ず、お甦りの主のみ前に立つのだと、その望みに支えられて、耐え忍んで罪と戦うのです。愛する者が死んだ。何をやっても空しい。何をやってもつまらない。自分も死のうか。そこでなお耐え忍んで、主の甦りの命のもとに、じっと留まるのです。「死者が復活しないとしたら、『食べたり飲んだりしよう/どうせ明日は死ぬのだから』」、ということになるのだろうか。そうじゃないだろう。あなたは、神の前に立つのだ。そのための、この主の日の礼拝であります。そのための、この聖餐の食卓であります。
キリストは、お甦りになりました。わたしの主、私どもの主となってくださるためです。このお方のみ顔の前で、私どもはなお、毎日の生活に励みます。それこそいろんなものを飲み食いし、またいろんな人と一緒に生きる生活をするのです。どうせ明日は死ぬのだから、という飲み食いの生活ではありません。生きるときも死ぬときも、日々何を飲むにせよ、何を食べるにせよ、それがいつもキリストの甦りに支えられ、慰められた生活になるならば、どんなにすばらしいことかと思います。特に今、厳しい試練の中にある方たち、悲しみに暮れている方たち、望みを失っている方たちが、この甦りの主の慰めの中に立つことができるように、耐え忍ぶことができるように、共に手を取り合うようにして、主の甦りの命のもとにしっかりと留まることができるように、その祈りをひとつに集めながら、この祝いの食卓にあずかりたいと心から願います。お祈りをいたします。
み子イエスを死人の中から復活させてくださいました父なる御神、どうかそのみ力のもとに、私どもひとりひとりをしっかりと立たせてください。ここに留まらせてください。食べるときにも飲むときにも、どんな人と共に生きるときも、どんな忍耐を強いられるときにも、そしていつかこの世を去るときも、私どもを支えるただひとつの望みは、キリストのお甦りです。今、心の底から慰められながら、主の命の食卓にあずかる者とさせてください。主のみ名によって祈り願います。アーメン