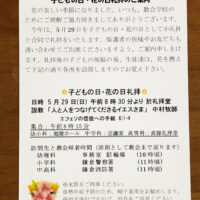わたしの母、わたしの兄弟とはだれか
川崎 公平
マルコによる福音書 第3章31-35節

主日礼拝
■皆さんもよくご承知のことだと思いますが、私どもの教会の仲間の誰かが亡くなりますと、可能な限りこの礼拝堂で葬儀をいたします。ご遺体をこの場所に迎えて、もちろんご遺族もこの場所に集まって、そのようなときに私がいつもありがたく思っていることは、そこにまた多くの教会の仲間が集まってくださるということです。このことは、しばしばきちんと言葉に出してお願いしていることです。教会の仲間の葬儀は、公の礼拝、日曜日の礼拝に準ずるものだから、ぜひ多くの方に来ていただきたい。香典、花料などを持参する必要はまったくないし、亡くなった方と面識がなくたって、大切な教会の仲間であることには変わらないのだから、ぜひどうぞ、としばしばお願いをしておりますし、実際にまた、いつも多くの方が積極的に葬儀に参列してくださいます。
このようなことは、長く教会生活をしていると何だかそれが当たり前のことのように感じてくるかもしれませんが、実は決して当たり前のことではないと思います。たとえば、これを遺族の立場に立って考えてみれば、よく分かるかもしれません。遺族も皆キリスト者であるというような場合は、ここでは考えません。そうではなくて、ここで皆さんにも想像していただきたいのは、ご遺族がほとんどキリスト者ではないという場合です。そういうご家族が、自分のお母さんの葬儀をする。お父さんの葬儀をする。あるいは妻の葬儀をしなければならない、というときに、もちろんいちばんつらい思いをしているのはご遺族であるに違いない。近しい家族を喪うということは、やはり人生におけるひとつの危機です。ところがそういうご遺族にとってきっと思いがけないことは、そういうご遺族がご遺体を囲んでこの礼拝堂に座るだけでなく、遺族が全然知らない教会の人たちがぞろぞろ集まってくるのです。もちろん中には知っている顔もあるでしょう。「ああ、あれはお母さんの教会の、聖歌隊のお友達の○○さんだ」。「あれ、でも知らない人がたくさんいるなあ……」。いつの間にか、家族、親族よりも教会の人間の数の方がずっと多いじゃないか、ということになると、ご遺族にとってはきっと意外な印象を与えることがあるだろうと思うのです。
そしてそういうとき、私はしばしば言葉に出して、ご遺族にお願いすることがあります。注意を喚起することがあります。「ぜひこの機会に、この礼拝堂のたたずまいをよく感じていっていただきたい。あなたがたのお母さんがいちばん大切にした場所ですよ」。「ここに集まる教会の仲間たちの姿を、よく覚えていただきたい。この人たちは、あなたの奥さんのいちばん大事な家族なんですよ」。もちろんこういうことは、言い方に気を付けないと、「は? 俺の妻の家族?」ということになるかもしれませんが、私の経験上、多くのご遺族が教会の葬儀を喜んでくださいます。「今日の葬儀はよかった」と感謝の言葉を伝えてくださいます。教会の葬儀の何がよかったのか、それはいろんな感想があるだろうと思いますが、多くのご遺族がはっきりと口にしてくださることは、「この教会の皆さんに出会えて、母は幸せだったと思います」。「この教会に出会えて、妻は本当に幸せでした」。
■そういうときに、私はしばしばこの主イエス・キリストの言葉を感謝をもって思い起こすのです。
「見なさい。ここにわたしの母、わたしの兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、わたしの兄弟、姉妹、また母なのだ」(34、35節)。
主イエスの家族。したがってまた〈神の家族〉であります。教会とは〈神の家族〉である。これは、教会とは何かということを表す最も美しい表現のひとつだと思いますし、その恵みの事実がたいへん具体的に現れてくるひとつの場面が、教会の葬儀という特別な礼拝のときだと思うのです。「そうだ、この人は、教会という神の家族の中に生きていたんだ」と、そのことを地上の家族、肉親の家族も自然と認めざるを得なくなることが、実際に起こるのです。
しかしまたそれは、葬儀のときに、つまり誰かが死んだときになって初めて明らかになるようなことでは決してありません。今ここで、このように礼拝をするたびに、私どもは自分が何者であるかを知ります。「わたしは決して、自分でここに来たのではない。主イエスに招かれて、わたしはこの場所に来たのだ」。そしてそこで、主イエスの言葉を聴くのです。「見なさい。ここにわたしの母、わたしの兄弟がいる」。日曜日の礼拝こそ、この主イエスの御心を思い出すための場所です。「そうだ、わたしもイエスさまの家族なのだ」。
その話をするために、なぜことさらに葬儀の話なんかから説教を始めたかというと、大きく言ってふたつの理由があります。ひとつ目の理由は、主イエスがここにお造りになった神の家は、死に勝つ望みに生きる家だからです。ただ何となく仲がいいとか、互いに愛し合うその愛の深さが他とはレベルが違うとか、そんな話ではないのです。死に勝つ教会、それが神の家族であって、その教会の実質がいちばん鮮やかに現れる場所は、やはり葬儀の礼拝だということになるでしょう。
しかしもうひとつ大事な理由があります。この神の家族たる教会をお建てになるために、どうしても主イエスは信仰上の戦いをしなければならなかったし、その戦いというのは、しばしば地上における家族との間にきしみを生じさせることがあるからです。それは、この福音書の記事をよく読めば、すぐに明らかになることですし、ここにおられる皆さんの中にも、こういう聖書の言葉を、どこか身につまされる思いで読んでいる方があるだろうと思うのです。
教会の葬儀の話なんかをしたわけですが、こういう話をあまり素直に聞けなかった方もあるかもしれません。自分の大切な身内の葬儀を、お寺の坊さんにしてもらわなければならなかったり、あるいはいつか自分が死んだとき、自分の家族はきっと自分の葬儀を教会ではなく、お寺でやってしまうだろう、ということを悩んでおられる方だって何人もいるはずなのです。というよりも、毎週の日曜日の礼拝に来ていること自体、実はあまり家族には歓迎されていない、そのことについて絶えず心の痛みを感じながら、それでも神の愛にすがるように礼拝生活を続けていらっしゃる方もあるだろうと思うのです。
敢えて言うなら、まさしくそういう方たちのための福音書の記事だと、私は思うのです。主イエスというお方は、実は私どもの誰よりも、地上の家族との心の行き違いというか、信仰をめぐって家族との関係がぎくしゃくしてしまう、そのつらさを味わっておられました。今朝読みました福音書の記事は、まさしくその主イエスの悩みと、また主イエスの戦いの内実を明らかにするものだと思うのです。
■今朝はマルコによる福音書第3章の31節以下を読みました。しかしこの言葉を理解するためには、少なくとも20節まではさかのぼらなければなりません。「イエスが家に帰られると、群衆がまた集まってきて」(20節)と書いてあります。主イエスは「家」に帰られたのです。主イエスの家であるならば、当然そこに主イエスの家族がいるということになるのかもしれませんが、しかしその家というのは、明らかに主イエスが生まれ育った家ではありません。まさにその家に、主イエスの昔からの家族、肉親の家族がやってきます。「身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。『あの男は気が変になっている』と言われていたからである」(21節)。主イエスは、30歳まではナザレの村で生まれ育って、父ヨセフの仕事を継いで大工の仕事をしておられたのです。ところが突然家を飛び出して、「神の国は近づいた」と説教したり、病気を治したりいろんな奇跡をしたり、そこにまたたいへんな数の人びとが集まってくるのです。しかも他方でそれを見た律法学者の偉い先生がたは、「あの男は頭がおかしいのだ」と断言するようになった。家族が心配しないわけはないのです。ことに母マリアは、どんなにはらはらしたかと思うのです。
それである日、意を決して、家族皆でイエスを取り押さえて、家に連れ帰ろう、ということになりました。それで、今日読みました31節以下に飛びますが、イエスが話をしておられる家まで訪ねて行ったのでしょう。玄関の外に立って、誰かに伝言を頼みました。「お話を聞いている最中に申し訳ないけれども、あそこで話をしているイエスはわたしの息子なんです。ちょっと呼んできてくれませんか」。もちろん頼まれた人は、ふたつ返事で主イエスに伝言を伝えます。ところが主イエスは外に出ていくことなく、「わたしの母、わたしの兄弟とはだれか」。これは誤解の余地のない、たいへん厳しいものの言い方です。しかもその上、こう言われるのです。「見なさい。ここにわたしの母、わたしの兄弟がいる」。これまた誤解の余地のない、たいへん厳しい言葉です。「ここに」いるのが、わたしの家族だ。「ここに」わたしの家があるのだ。「ここに」いないマリアたちは……外に立ったままなのです。そして、少なくともマルコによる福音書だけを読むならば、ここで主イエスの肉親の家族は姿を消します。その意味では、まるで主イエスはここで、家族に絶縁状を突き付けたかのようです。いったい、主イエスは何を考えておられたのでしょうか。
このような聖書の言葉だけを典拠にして、だからわれわれも地上の家族にとらわれてはいけないのだとか、信仰を貫くためには家族を軽んじることがあっても仕方がないんだとか、あるいは家族の意向で仏式の葬儀に出るようなことがあっても、焼香なんか絶対にしちゃいかんとか、実際にそういう指導をする教会もあると聞いたことがあります。しかしそれはたいへんにおかしなことだと思います。
主イエスとて、いたずらに親不孝をなさったわけではないのです。むしろ主イエスの母マリアに対する愛情は、それこそこの地上のものをはるかに越えるものがあったと思いますし、そのことについてはあとで触れたいと思います。しかしここでは、主イエスは外にいる肉親の家族のことを思いながら、けれども「周りに座っている人々を見回して」、そしてこう言われたのです。「見なさい。ここにわたしの母、わたしの兄弟がいる」。繰り返しますが、肉親の家族をばっさり切り捨てるための言葉ではありません。死に勝つ家を造るための戦いです。永遠の命を宿した新しい家族を造るために、ここで主イエスは戦いを始めておられるし、しかも実はすべての人が、そのような本物の命を宿した家に対する憧れを持っていると思うのです。「家に帰れば、わたしは本当の命に生きることができる。そのような本物の命に生きる家に、わたしは帰りたいのだ」と、誰もがそのような憧れに似た願いを持っているのではないかと思うのです。
■また話が飛ぶようで恐縮なのですが、1年と少し前に、私の父がすい臓がんで急逝しました。本当に急逝とも言っていい死に方で、がんであることが分かったと思ったら、たった2週間で逝ってしまったわけですが、幸いだったことは、息を引き取る前日に病院を出て家に帰ることができたことでした。何が何でも家に帰りたいという、父の執念のような願いが叶って、それで私も父が息を引き取る30分前に、家に帰ることができました。家族、親族の歌う讃美歌に囲まれるようにして、静かに息を引き取っていきました。また三週間ほど前に妻の母が亡くなるということがありましたが、こちらは本当に最後まで自宅で看取ることができました。いちばん近くにいた家族の労苦はたいへんなものがあったと思いますが、そういう人の話を聞くと、多くの人が「うらやましい」と、「自分もできれば家で死にたい」というようなことを言うのです。
ところがまた別の方の話ですが、私が以前長野県の教会におりましたときに、最後までお連れ合いを自宅で看取られた方がいました。ところがその方が困ったことは、ご主人が自宅の布団の中で、「家に帰りたい、家に帰りたい、おい、何とかしてくれ」と、妻の前で嘆き続けたというのです。仕方がないから、奥様が肩を貸してあげて、家をぐるっと歩き回って、「ほら、わたしたちの家ですよ」と言ってあげると、いつもひどくがっかりしてしまわれたというのです。
そこでこの方が求め続けた〈家〉というのは、ただの建物ということではなくて、本当に自分が帰るべき場所、自分がいちばん安心できる場所、その家に帰れば、自分が自分らしく、生き生きと生きることのできる場所、そういう意味での「わたしの家」に帰りたい。それは人間としての根源的な〈憧れ〉と言ってもよいだろうと思います。そのような「家に帰りたい」という人間の根源的な願いが、自分の死を見据えたときに最も激しく現れるのは当然だと言えますし、しかしまた、私どもが地上のどんな場所に帰っても、そこに主イエスがおられなかったら、私どもは結局、死に対して決定的に無力なのです。
まさしくそのために主イエスの戦いがあったのであって、ここで主イエスは故郷を捨て、母を捨て、家族を捨て、仕事も捨てて……しかしそれはただ不信仰な家族を裁いて切り捨てるだけの戦いでは意味がないのです。そうではなくて、永遠の命の望みに生きる家を造るための戦いを、新しく始めておられるのです。
その戦いのために、主イエスは家族を捨てなければならなかった。それはなぜかと言うと、地上の家族が自分の命の支えになってはならないからです。故郷も、家族も、仕事も、この地上にあるいかなるものも、本当の意味で私どもの命を支える力にはなりません。神の力以外に何の支えも持たない家を新しく造るために、主イエスの戦いがあったし、事実私どもの教会は、神の力以外に何の支えも持たない家として建てられています。
そういう教会の本質的な姿が、ある意味でいちばん鮮やかに現れる場所が、やはり葬儀の礼拝だと思うのです。既に息を引き取った仲間のなきがらを見つめながら、もちろんいろんな思いが生まれるのです。立派な仕事をした人であったかもしれない。すばらしい人柄の人物であったかもしれない。中でも、神さまが与えてくださった家族の絆は、いちばん感謝しなければならないことであるかもしれない。けれども、その家族の絆も含めて、すべてが取り去られるのです。最後に残されたこの人の支えは、神の力だけだ。神の命だけだ。その神の命だけに支えられた礼拝をするときに、いつも主イエスの言葉が聞こえてくるはずなのです。
「見なさい。ここにわたしの母、わたしの兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、わたしの兄弟、姉妹、また母なのだ」。
「神の御心を行う人こそ」と言われると、ちょっとひるんでしまうかもしれません。ただ教会員になっただけではだめなので、やっぱり少しは頑張って神の御心を行わないと、神の家族としてはふさわしくないのだろうか。しかし私は、神の御心を行うその第一のことは、まさしく今しているように、主のみもとに集まることだと思います。今ここに、主の御心が成就しているのです。
■先ほど申しましたように、マルコによる福音書に限って言えば、ここで主の母マリアの姿は完全に消えるのです。しかし歴史的に明らかなことは、主の母マリアもまたのちにキリストの教会に生きる者とされました。いったい、どこでどのように信仰に導かれたのでしょうか。4つの福音書の中で、ひとつだけ例外的に、その後の母マリアのことを伝えてくれる箇所があります。ヨハネによる福音書の第19章26節以下です。主イエスが十字架につけられた、その十字架の下に、母マリアが立ち続けていたと言うのです。このときの母マリアの姿が、たいへん豊かな芸術の題材になりました。皆さんもピエタとか、スターバット・マーテルとかいう外国語を聞いたことがあるかもしれませんが、それはただ、人間の悲しみの極みを描いたというだけでなくて、マリアの悲しみの心に注がれる主の思いの深さに、多くの人が心を打たれてきたということだと思います。
ヨハネによる福音書第19章26節に、こう書いてあります。主イエスが十字架の下にいるマリアにこう言われたのです。
イエスは、母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、「婦人よ、御覧なさい。あなたの子です」と言われた。
悲しみの母に、新しい家族を与えておられます。「見なさい。わたしの愛するこの弟子を見なさい。これは、あなたの息子です。あなたの家族です」。そしてその愛する弟子にも言われます。
「見なさい、あなたの母です」。
「そのときから、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取った」と書いてあります。このふたりは、同じ家に、共に住むようになったというのです。たいへん具体的なことです。しかしここで、多くのことを話すいとまはありません。明らかにここで主イエスは、教会を造っておられるのです。人間的な血のつながりを越えた、主の命によってのみ立つ教会を、ここで主イエスは造っておられるのです。
■想像力のある方は、しかし、今読んだところだけでハッピーエンドになるわけがないと、お気づきになるだろうと思います。「そのときから、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取った」というのですが、主イエスが十字架につけられた金曜日の夜、この母マリアと、そのマリアを引き取ったこの弟子は、ふたりでどんなにつらい夜を過ごしたことかと思います。会話が弾んだわけがないのです。食事ものどを通らなかったでしょう。ところが、さらに第20章を読むと、こういう記事が続きます。
週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして、墓から石が取りのけてあるのを見た。そこで、シモン・ペトロのところへ、また、イエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。「主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか、わたしたちには分かりません」(1、2節)。
ここに、ふたたび「イエスが愛しておられた弟子」、すなわち母マリアを自分の家に引き取った弟子が登場します。それにしても、こんな特別な呼び名を与えられた弟子というのは誰のことだろうと、学者たちはいろんな推測をしますが、よく分かりません。けれどもある人は、この「愛する弟子」というのが誰のことか、難しく問い詰める必要はない。「この弟子は、主イエスに愛されていたのだ。わたしたちのことだ」と言います。私も、その通りだと思います。その「イエスに愛された弟子」に、復活の知らせが届きます。
「二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方が、ペトロより速く走って、先に墓に着いた」(4節)。「それから、先に墓に着いたもう一人の弟子も入って来て、見て、信じた」(8節)。そして、「それから、この弟子たちは家に帰って行った」(10節)と言います。ここにもまた「家」という言葉が出てきます。当然その家には、一緒に住み始めたばかりのマリアがいるのです。恐れと悲しみに撃たれた母がいます。けれども、この弟子はマリアに告げます。「イエスはお甦りになった」。
この弟子は、息を切らせて家に帰り、「お母さん、たいへんだ!」と叫んだかもしれません。おかしな想像かもしれませんが、この「愛する弟子」と呼ばれる人は、その時ようやく、マリアのことを「お母さん」と呼ぶことができたのではないかと、私は思います。主イエスが十字架につけられたあと、思いがけない展開でマリアを自分の家に引き取って、それにしてもいきなりその人を「お母さん」とは呼びにくかったのではないかと思うのです。けれども、主イエスがお甦りになった時……そのときようやく、主のご意志の確かさを確信したとき、「お母さん、たいへんだ!」 あのお方はお甦りになった。
その言葉を聞いたとき、マリアもまたそこで初めて、かつて息子から聞かされた言葉を、真実の命の言葉として聞き直すことができたのではないかと思います。「見なさい、ここにわたしの母、わたしの兄弟、わたしの姉妹がいる」。そのときには、なんて冷たい息子、としか思えなかったこの言葉を、今は感謝をもって聞き取ることができる。悲しみの家ではなく、命の支配する家を主イエスが立ててくださいました。それはまた、この鎌倉雪ノ下教会のことでもあるのです。そこにまた、私どもひとりひとりも招かれて、今帰るべき家に帰ることができているのです。お祈りをいたします。
「いかに幸いなことでしょう、あなたの家に住むことができるなら。まして、あなたを賛美することができるなら」(詩編第84篇5節)と、詩編の言葉を今私どもの祈りの言葉とすることができます。教会の主、命の主であられるイエスよ、今私どもも帰るべき家に帰ることができました。賛美の歌を歌いつつ、ここに主イエスの家族が生きている、その恵みの事実を受け入れさせてください。私どもの地上の家族のためにも、すべての隣人のためにも、新しい祈りを始めさせてください。主のみ名によって祈り願います。アーメン