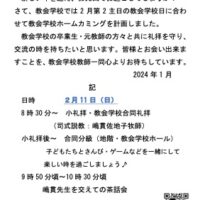後ろのものを忘れて走れ
川崎 公平
フィリピの信徒への手紙 第3章12-16節

主日礼拝
■フィリピの信徒への手紙の第3章は、聖書の中でも異彩を放っている箇所だと思います。伝道者パウロという、教会の歴史の始まりにおいていちばん大きな働きをした人が、ここで突然のように、自叙伝のような文章を書いているからです。自叙伝というほど整ったものではないかもしれませんが、自分がどういう生まれ、どういう育ちの人間であるか、その結果、かつての自分はどういう考え方をする人間であったか。けれどもそんな自分がキリストに出会って、今はどうなっているか、今わたしは何をしているのか。パウロがここまであからさまに自分自身のことを語っている箇所は、他にほとんどないのです。このパウロの自伝的な文章が始まるのは、厳密には5節からです。4節から読んでみます。
とはいえ、肉にも頼ろうと思えば、わたしは頼れなくはない。だれかほかに、肉に頼れると思う人がいるなら、わたしはなおさらのことです。わたしは生まれて八日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤミン族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非のうちどころのない者でした(4~6節)。
あまり私どもには馴染まない固有名詞も出てきますが、大ざっぱな意味をつかむのに苦労はしないと思います。要するに、自分はこれ以上考えられないほど立派な、完璧な人生を歩んできたのだと、そう言っているのです。ところがそういう自分がキリストに出会って、今はどのように生きているか、今自分は何をしているのか。パウロの自叙伝はさらに7節、8節、9節と続いていって、新共同訳では途中に大きな区切りがありますが、その区切りを超えて、14節までがパウロの自伝的文章にあたるということになると思います。
わたしは、既にそれを得たというわけではなく、既に完全な者となっているわけでもありません。何とかして捕らえようと努めているのです。自分がキリスト・イエスに捕らえられているからです。兄弟たち、わたし自身は既に捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリスト・イエスによって上へ召して、お与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです(12~14節)。
イエス・キリストに出会って、今わたしは何をしているのか。それは、実はひとつしかないのだ、と言って、「なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ」、前へ、前へとひたすら走り続けることだけだ。なぜかと言うと、これを追い求めるために、キリストはわたしを捕らえてくださったのだから。そう言うのです。
これは、非常に印象深い文章です。しかもそれでいて、どこか捕らえどころのない、結局何を言っているのだかよく分からない、という感想もあり得るかもしれません。今日の説教の題を、「後ろのものを忘れて走れ」としてみました。われながらずいぶん気取った題だと思う一方で、「後ろのもの」とはいったい何でしょうか。「前のものに全身を向けつつ」とパウロは言うのですが、その「前のもの」とは何でしょうか。なぜ走るのでしょうか。まだわたしは完全な者にはなっていないからだ、とパウロは言うのですが、完全って何でしょうか。何となく印象深いけれども、実はさっぱり中身が分からないような、とにかく不思議な印象を残す聖書の言葉だと思うのです。
■けれども、このような自伝的な文章をパウロが書かなければならなかったのには、かなりはっきりとした動機がありました。非常に具体的な、困った問題があったのです。第3章の2節に、「あの犬どもに注意しなさい。よこしまな働き手たちに気をつけなさい。切り傷にすぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい」という、たいへん激しい発言がありますが、ちょうどそのころ、パウロがフィリピから離れていたときに、フィリピの教会の信仰をぐらつかせるような、別の指導者たちの影響があったらしいのです。それをここでは「あの犬どもが」とまで言うのです。
この偽教師たちがどういうことを主張していたか、ここから読み取れることはそんなに複雑ではありません。「割礼を受けなさい」と言うのです。ユダヤ人になるための儀式です。これが、現代の私どもにはさっぱり理解できないのです。「これだから聖書は難しいんだ」と言いたくなる気持ちは分かりますし、もちろん私どもにとって、割礼なんてものは全く何の意味もありません。けれどもそこで丁寧に考えなければならないことは、事実フィリピの教会は、こういう偽教師たちの影響を受けたのです。それだけの説得力があったということです。それはなぜか、ということを、よく考えなければなりません。
割礼を受けるということは、もう少し丁寧に言えば、「割礼を受けて、ユダヤ人になりなさい。そうすれば、あなたは救われる。あなたも完全な者になれる」という話です。ところがそれに対して、パウロは12節で、「わたしは完全な者になんかなっていない」と言うのです。完全とか完全じゃないとか言われても、全然ピンとこないかもしれませんが、本当にそうでしょうか。12節でパウロは、「わたしは完全な者になっているわけではない。むしろ、何とかして捕らえようと努めているのです」と言うのですが、私どもはこういう言葉にいちばん共感できると思います。本当にそうだ。わたしも何十年も生きてきたけど、無駄に年を重ねるばっかりで、全然成長していないようだ。完全な者になるなんて、夢のまた夢。けれどもそういうときに、こうすればあなたも完全な者になれるんだ、あるいはそこまで言わなくても、完成に近づくことができるんだ、と言われたら、案外私どもも誘惑されるかもしれません。それとも、もうそんなことはとっくに諦めているのでしょうか。
うすうす感づいておられるかもしれませんが、私どもの教会は、こういうことに関して、実に不親切なところがあると思います。「洗礼を受けて何十年も経つのですが、全然成長していないようです。どうしたらいいんでしょう」と、そんなふうに悩みを牧師に相談してみる、長老に相談してみる。けれどもきっと、はかばかしい答えは返ってこないのです。説得力のある答えを用意していない側にも問題があるのかもしれませんが、それを受け取る側の問題もあるかもしれません。「主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたは救われるんだ」と言われても、それだけでは不安なのです。「あなたはキリスト・イエスに捕らえられているんだから」と言われても、言葉でそう言われるだけでは、まだ何か足りないような気がするのです。だから、それプラスアルファ何かをして、それでようやく落ち着くのです。そのプラスアルファというのが何なのかはよく分かりませんが、とにかくそういう誘惑は、いつどこにでも、いろんな形で生じてくるものです。
そういうときに、「割礼を受けなさい。救われるとは、割礼を受けて、神の民の一員になることなんだ。何しろ、われわれの割礼の伝統には、何千年という歴史があるんだからな」と言われると、それが不思議な魅力を持ったのです。それで割礼を受けて、「ああ、よかった。これでわたしもひとかどの人間になったんだ」。しかし、それの何が悪いのでしょうか。
■既に今月の最初の日曜日から、この第3章を読み始めました。それを先週発行した雪ノ下通信6月号にも載せました。そのときの説教で用いた表現で言えば、私どもは〈手すり〉が欲しいのです。自分の人生を支えるために、これを少しでも確かなものにするために、いろんな手すりがないと不安なのです。パウロが5節以下に、「わたしは生まれて八日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤミン族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です」と、延々と列挙していることも、自分は誰よりもそういう丈夫な手すりをたくさん持っていたということです。6節の最後には、「律法の義については非のうちどころのない者でした」とまで書いています。わたしは、誰よりも〈完全な〉人間だった。そういうパウロが、生まれて八日目に割礼を受けたということは、まさしく自分のすべてがそこにある、というほどの重みがあったのです。ところが、7節以下で、こう言うのです。
しかし、わたしにとって有利であったこれらのことを、キリストのゆえに損失と見なすようになったのです。そればかりか、わたしの主キリスト・イエスを知ることのあまりのすばらしさに、今では他の一切を損失とみています。キリストのゆえに、わたしはすべてを失いましたが、それらを塵あくたと見なしています。
「わたしはすべてを失いました」と書いていますが、それはパウロにとって、決して大げさな表現ではありませんでした。繰り返しますが、「わたしは生まれて八日目に割礼を受け」というのは、パウロにとって、まさしく〈自分のすべて〉であったのです。割礼という手すりに支えられていたから、パウロは〈完全な人間〉として生きてこれたのです。そんなパウロが、すべての手すりを突然主イエスによって取り上げられて……しかしそれは、パウロにとって、救いの出来事でしかありませんでした。
そのような自分の歩みを振り返るようにして、ここでは「わたしの主キリスト・イエスを知ることのあまりのすばらしさに、今では他の一切を損失とみています」とまで言うのです。ここで「キリストを知る」と言っているのは、ただ知識を得るという話ではありません。愛によってキリストに結びつくことです。このお方のすばらしさを知ってしまった今は、かつての自分が完全だ、完成だと思っていたところが、とうていゴールだとは思えなくなったと言っているのです。キリストを知ることの、いやむしろ、キリストに知られていることの、そのすばらしさの前では、かつて大切にしていたいろんな完全さは、屑でしかなくなった。だがしかし、そのキリストを知ることのあまりのすばらしさを、わたしは既に得たというわけでもない。それを完全に手に入れたというわけではないのだ、ただ何とかして捕らえようと努めているのだ、と言うのです。
先ほど、「われわれの教会には、どうも不親切なところがあるだろう」と申しました。つまり、「なかなか自分は人間として成長しない。完成しない。どうすればいいでしょうか」というようなことを相談してみても、牧師からも長老からもろくな答えが返ってこない。その不親切な態度には、しかし、きっと大切な意味があると思うのです。「この手すりにつかまれば大丈夫だよ」というような事柄が、ひとつでもあってはならないのです。
わたしは、既にそれを得たというわけではなく、既に完全な者となっているわけでもありません。何とかして捕らえようと努めているのです。自分がキリスト・イエスに捕らえられているからです(12節)。
私どもに何か支えがあるとするならば、「自分がキリスト・イエスに捕らえられている」、このひとつのこと以外にありません。このこと以外、何の支えもない。何の手すりもいらない。ただこのひとつのことを根拠にして、私どもも、パウロと同じように走るのです。
なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリスト・イエスによって上へ召して、お与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです(13、14節)。
■今日読みました聖書の言葉の中で、もしかしたら分かりにくいかもしれないことは、なぜ走るのか、ということだと思います。だいたい、ただでさえ苦労の絶えない地上の生活なんだから、日曜日の礼拝のときくらい、ゆっくり休ませてほしい。礼拝に来てまで、「走れ、走れ」と、そんな疲れるお説教は聞きたくないと、そう思う方があっても不思議ではありません。ある意味ではまさにその通りなので、私どもの人生というのは、怠けていてもどうにかなるようなものでは、決してありません。だからこそ私どもは、別に神さまに促されなくなって、自分の人生を責任あるものとして全うするために、一所懸命走り続けているのです。立ち止まるわけにはいかないのです。途中で疲れたり、転んだり、とんでもないところに迷い込んだりしながらも、それでも走るのをやめるわけにはいかないのです。
パウロという人は、その意味で誰よりも熱心に、妥協することなく、生まれたときから全力で走り続けた人でした。けれども、もしも、その走っている方向が最初からでたらめであったとしたら、これほど悲惨なことはないのです。「律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非のうちどころのない者でした」とパウロは自分の歩みを振り返るのですが、それは、誰よりも速く、誰よりも力強く、誰よりも真剣に走り続けていた自分が、どんなにでたらめな方向に走り続けていたか。そのことを振り返っているのです。もしかしたら私どもも、パウロにならってこういう自叙伝を書くことができるかもしれません。
ところが、そんなパウロを、神が呼び止めてくださいました。そっちじゃないよ。こっちだよ。14節には、「神がキリスト・イエスによって上へ召して、お与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走る」と書いてあります。直訳すれば、「上の方への招きという神の賞」であります。この神のご褒美が欲しいから、わたしは走り続けるのだ。
なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリスト・イエスによって上へ召して、お与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。
この神の賞を与えるために、キリストは私どもを捕らえてくださったのです。この神のご褒美を目指して、私どもも走るのです。ある説教者は、われわれは、この神のご褒美をいただきたいという野心に生きるのだ、と言いました。野心という言葉はよくないかもしれませんが、それなら「聖なる野心」とでも呼べばよい、と言います。「しかし、一つの野心を持った者は、その野心に反するようなほかの野心はみな捨てなければならない」と言うのです。
賞が欲しいから、ご褒美が欲しいから頑張るというのは、何だか幼稚な気がします。しかし考えてみますと、私どもの地上の生活というのは、いろんな野心によって成り立っているものだと思います。そして私どもも絶えずいろんな野心を抱き、そしてその野心の実現のためには、努力を惜しまないものです。出世したいとか、お金を稼ぎたいとか、絶対にあの人と結婚したいとか、これがこうなったらいいのに、あれがああなったらいいのに、そうしたら自分の人生はより完全なものになるはずだと、そう思うのです。野心とか野望とかいうと言葉はきついようですが、ただ平凡な人生を全うするだけでも、そのために私どもはどんなに涙ぐましい努力をすることでしょうか。そういう意味で、走り続けなくてもよい人生なんてものは絶対にあり得ないし、先ほど紹介した説教者が言うように、「一つの野心を持った者は、その野心に反するようなほかの野心はみな捨てなければならない」。そのために、私どもも案外、自分でもびっくりするくらいの頑張りを見せることがあるものです。
■けれども問題は、私どもが生まれつき抱く野心というのは、この世限りのものであります。ここでは割礼が問題になっています。もちろん割礼それ自身は、神のお定めになった聖なるしるしです。ところがその割礼も、罪深い人間の手にかかると、地上的な意味しか持たない、野心の道具にしかならなくなるのです。第3章19節以下には、やはり割礼にこだわる偽教師たちについてこう書いています。
彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。しかし、わたしたちの本国は天にあります。
私どもがふだん忘れていることです。私どもは、天国の市民なのです。その「わたしたちの本国」たる天から、パウロを呼ぶ声が聞こえたのです。それをここでは、「神がキリスト・イエスによって上へ召して、お与えになる賞」と言うのですが、「召す」というのは、ふつうの日本語で言えば「呼ぶ」ということです。パウロも、神に呼ばれたのです。「おーい、そっちじゃないよ。あなたの走るコースはこっちだよ」と……神が身を乗り出すようにして、与えようとされる賞であります。この賞をぜひ、受け取ってもらいたい。その神の招きの声が、パウロにも聞こえたのです。
人生は、走ることだと申しましたが、おそらく、走ること自体がつらいのではないと思います。私どもが人生においていちばん悩むことは、そもそもどっちに向かって走ったらいいのか分からないことだと思うのです。ここでパウロは明らかに、当時のギリシア文化においても盛んに行われた陸上競技の競走のことをイメージしているわけですが、しかし私どもの人生は陸上競技のようにコースが決まっているわけではありません。それでも私どもは、出世コースだとか勝ち組だとか言って、このコースを走って行けばいいんだと言ったりするのですが、それが現実にどれだけ人間を幸せにしているか、分かったものではありません。どっちに向かって走ったらいいのか、それが分からないから、私どもはしばしば、一歩も踏み出すことができないほどに疲れ果てるのです。けれどもそういうときに、もしも誰かがゴールの方から呼んでくれたら、その声が聞こえたならば、どんなに力づけられるでしょうか。ここでは、「わたしたちの本国は天にあります」。その天から、わたしを呼ぶ声が聞こえると言うのです。
先ほど紹介した同じ説教者が、こういうことを書いています。ある英国の神学者がまだ学生だった頃に、よその教会にお手伝いに行きました。日曜日の夜、もうあたりは真っ暗で、土地勘もない田舎のことです。するとその教会の牧師が学生を通りまで連れて行って、向こうに灯りが見えるだろう、何でもいいからあの灯りを目指して歩いて行きなさい、そうしたら帰れると言ったというのです。
ここでは灯りが見える代わりに、神が呼んでくださるのです。パウロもまた、その神の呼び声を聞きました。誰よりも熱心に神に仕え、だからこそ誰よりも熱心に教会を迫害していたときに、突然主の光に打たれて、パウロは地面に打ち倒されたといいます。そのとき、パウロを打ち倒した主の光というのは、同時に、パウロを真実に生かす恵みの光でもありました。「わたしたちの本国は天にあります」という、その天の国籍を象徴するような光を、パウロは見せていただいたのです。今、私どもも、同じ光を見せていただいているのです。そうしたら、後ろのものは全部塵あくたになるのは当然です。そこに、どんなに望みに満ちた歩みが造られることかと思います。お祈りをいたします。
今、私どももキリストに捕らえていただいて、確かな望みの光を見せていただいています。この地上には決して見出すことのできない望みの光を見せていただいた今は、もう後ろのものに心を惹かれることはありません。互いに励まし合いながら、何よりもあなたのみ声を聴きながら、走るべき道を正しく走り抜くことができますように。主のみ名によって祈り願います。アーメン