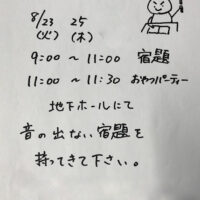丘の上の羊飼い
嶋貫 佐地子
ヨハネによる福音書 第10章11-21節

主日礼拝
このところ、むやみに涙が出そうになるのはなぜでしょうか。人間の惨めさを思うからでしょうか。ここ数日起こっていることを、灰色の空に、突然光る禿鷹が現れて着弾することと、自分が普通に、食事もして温かいふとんで寝ていることの乖離でしょうか。
加藤常昭先生も親しくされていたトゥルナイゼン先生が、ご自分の本の中で、19世紀のロシアの思想家ドストエフスキーを紹介しながらこのようなことを語っています。ドストエフスキーは「人間とは何か」を問うたんだ。
彼の書いた世界に入ると、自分がまるで人間の外側まで行って、遠くから人間を眺めるようになるんだ。それは自分と同じ「人間」なのだが、そこから帰ってくると、今まであのように穏やかに見えていた同居人の中に野生の本能を見つけるようになるんだ。彼の書く人間は、平和な街の中でほんとうに平和に生きている。そこでは榴弾もさく裂しないし、死体も見られない。すべてのことがごくありふれた日常生活の中で起こるんだ。でもそれだけ、人間の全く違った暗い姿が、いよいよ物凄く、いよいよ真実なんだ。
それはちょうどわれわれが、歩いて行くのと同じ方向に進む列車がすぐ横を通り過ぎてゆくのと同じで、危うくその車輪の中に落ちそうになる。そんなふうにその「人間」は、われわれの二重人格のようにわれわれの側をよぎって進んでゆくんだ。こんな人々とは一緒に歩きたくないのに、一切やめたいと思っているのにできない。彼らの中の謎に、言いようもなく痛切に、われわれの謎を見るからだ。そして先生は言いました。
「われわれは、われわれに会った。われわれは人間に会った。」
私どもはいま改めて、人間というものに会っている気がします。戦争があってもなくても、人間とは何か。人間というのはこういうものだと。
けれども、そのただ中に、
ひとりの羊飼いが立っている。
「人間」の中に、私どもの中に、
ひとりの羊飼いが立っている。
ある詩人が言いました。
「高い荒地を、ハイエナの遠吠えがよぎる。羊飼いは立っている。まどろむことなく、眼光を闇深くとどろかせ、風雨にさらされ、杖にもたれて。彼は散在する羊たちに眼を注いでいる。その一匹一匹が脳裡にある。」
その羊飼いの眼光は鋭く、遠く闇深くまでとどろいて、散らばった羊たちに眼を注いでいる。羊飼いには、その一匹一匹が脳裡にある。だから羊飼いは、瓦礫の中にも踏み入る。
じつはこのような状況になるまで、私はのんきに良い羊飼いを想像していました。牧場の丘のうえに立つ良い羊飼いです。でもそんな立ち方ではありませんでした。ほんとうに羊は悲惨です。かの地だけではないのです。羊は毎日、死におびえているし、逆に死にたいとも思っている。暗い本能があって、神様を思うことと自分の二重人格です。でもこの方は、その一匹一匹が脳裡にある。だからその名前を呼ぶ。すると羊には、その声が聴こえるのです。
羊は羊飼いの声を知っているから、そしてほんとうは待っていたから、瓦礫の中でも待っていたから、レスキューに抱えられる。抱きかかえられて、羊飼いはわたしを連れてゆく。人間の外側の神のところまで連れて行くのです。
トゥルナイゼン先生が言いました。われわれから、彼のほうに一歩も進めない時、それだけいよいよ確実に、彼から、われわれのほうへ一歩が進められる。啓示はここに告げられる。終末に向かって、生命の問題は神が解決なさる。人間の歩いて行く向こうのかなたに、赦しの光が照るんだ。
羊飼いは、羊を連れ出して、ご自分の門の中に入れます。それは十字架の門であり、命に至る門で、私どもはその中の牧場で、永遠の命を見つけます。生きているものも死んだものも、その牧場で永遠の命を見つけます。だからそのために、この方は言われました。
わたしは命を捨てる。
「わたしは良い羊飼いである。」「良い羊飼いは羊のために命を捨てる。」(10:11)
良い羊飼いは自分の命を羊に与えるのです。
永遠の命を与えるのです。
神からの牧者、私どもの主イエスは
自分の命より羊が大事なのです。
しかしながら、主イエスが命を捨てるのには、もう一つの大切なことがありました。それは父なる神の願いであります。
主は言われました。
「わたしは命を、再び受けるために、捨てる。それゆえ、父はわたしを愛してくださる。」(10:17)「だれもわたしから命を奪い取ることはできない。わたしは自分でそれを捨てる。わたしは命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは、わたしが父から受けた掟である。」(10:18)
これは父から受けた掟だと、主は言われました。父がわたしに与えられたご命令、任務である。羊のために十字架で死ぬことと、羊のために復活させられることは父からの掟であって、父の願いなのだ。だから、父がそうしたいと思われるのだから、わたしはそうする。
これはまったく自発的なことなのです。
主は「わたしは自分で」「それを捨てる」と言われました。
いやいやではなくて、引きずられるのではなくて、わたしは自分で。
だから主は自分で、「命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる」(10:18)といわれました。「できる」というのは、この方だけが持っている力です。神の子の権威、力です。命のことは人にはどうすることもできません。人は誰も自分で失った命を自分で受ける力は持っていません。でも主は、望むときにそれを捨て、望むときにそれを受けることがおできになるのです。
主イエスは、十字架のときに、大勢の兵士たちが武器を持って、主イエスを捕えようとして来たとき、「わたしだ」と言われるだけで、兵士たちは地に倒れました。それだけの権威と力がこの方にはあるのです。ですから、
主は、あのとき、十字架の上で、そこから降りることもおできになりましたし、主は、神の軍勢をそこで呼び出して兵士たちを倒すこともおできになりました。でもなさいませんでした。そうではなくて、
十字架の上でこそ、なされたのは、この自発的な、愛であります。
父の望みを守り、羊のために。自分で。
望むときに主はそれを捨てたのであります。
十字架の上でも、あの丘のうえでも、命の決定権はキリストにあったのです。命をどうするかはキリストにあったのです。それはご自分だけでなく、ご自分によって与えられる全人類の、命の決定権でありました。主があの丘のうえで自主的に命を捨て、それゆえ、命をお受けにならなければ、私どもに永遠の命はなかったからです。
命の解決は神がなさるのです。
ある人が言っていました。あそこでは、人間は「キリストを殺すことしかできなかったのだ。」人間はそれしかできなかったのだ。けれどもそれは、キリストが自ら命を、父に渡したのであって、人間に命を取られたのではない。
キリストがご自分で決められたことなのだ。だから主が言われたように、誰もこの方から、命を奪い取ることはできないのです。
いま、主日礼拝で川崎公平牧師が、フィリピの信徒への手紙を説いておられますけれども、じきに第二章、キリスト賛歌と呼ばれるところに入ります。キリスト賛歌。キリストへの信仰の告白です。そこでも言われているのは、主イエスのこの自発的な、従順であります。
このようにフィリピのキリスト賛歌はあります。
「キリストは、神の身分でありながら、神と等しい者であることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、僕の身分になり、人間と同じ者になられました。人間の姿で現れ、へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。」(フィリピ2:6-8)
キリストは、神の身分でありながら、僕の身分となって。私どもが絶望しかかっている「人間」となってくださいました。でもそれは真実の人間でした。それがほんとうの人間でした。ほんとうの人間はキリストでした。その方が神に向かう人間となって、神の子がそれを受け取って、それを与えて、十字架の死に至るまで従順でした。
捕えられ、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、従順でした。そうして、
神の御子主イエスは、
命を失ったのではなく、与えたのです。
命を奪われたのではなく、受け入れられたのです。
羊のために。私どものために。それゆえに、父は、
主は言われました。
「父はわたしを愛してくださる。」(10:17)
私は、「父はわたしを愛してくださる」というこのお言葉を、十字架の上からお聴きするように思いました。
「父はわたしを愛してくださる。」
その関係を、父と子の、愛と信頼の関係を、主は私どもにもくださいました。
主が、「わたしは良い羊飼い。わたしは自分の羊を知っており、羊もわたしを知っている」と言われたときに、こうおっしゃったのです。
「それは父がわたしを知っておられ、わたしが父を知っているのと同じである。」(10:15)
わたしとあなたがたの愛と信頼は、
父とわたしのそれと、同じなのだ。
その方に呼ばれたなら、羊は、その方を愛してついてゆきますし、「人間」っていうのは、そうやって、ほんとうの、神に造られた人間になれるんだと思いますし、そしてそんな羊が世界にはいっぱいいるのです。そして主が言われるように、
「こうして、羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。」(10:16)
いまも瓦礫をゆく、この羊飼いについてゆく、
世界中のわれら羊は、今、一つの群れになるのです。
天の父なる神様
あなたと御子の愛と信頼を私どもにくださり感謝をいたします。どうぞ羊をたすけ、導き、永遠に向かう一つの確かな群れとしてくださいますように。
主の御名によって祈ります。
アーメン