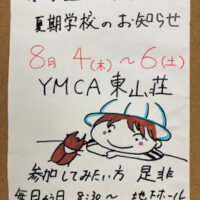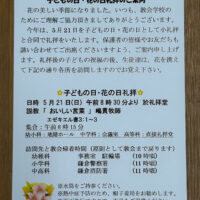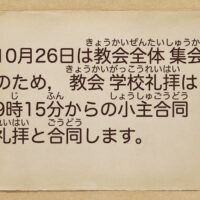主イエスの与える休み
川崎 公平
マルコによる福音書 第2章23-28節

主日礼拝
■皆さんの中にもお使いの方がいらっしゃるかと思いますが、私どもの教会で毎年作成している「みことばカレンダー」というものがあります。私のおります牧師室にもこのカレンダーがあって、新年を迎えて新しく2023年1月の頁を開きました。そこに、創世記第1章31節の言葉が印刷されています。
神はお造りになったすべてのものを御覧になった。見よ、それは極めて良かった。
これは、聖書の最初に記されている、天地創造の物語の最後に置かれている言葉です。神が最初の六日間で、天地万物をお造りになった、そのあとに、「神はお造りになったすべてのものを御覧になった。見よ、それは極めて良かった」。そう言うのです。
これは、決定的な重みを持つ言葉です。そして、何度読んでも不思議な思いにさせられる聖書の言葉だと思います。この世界は、神がお造りになったものです。神がお造りにならなかったものは、この世界にひとつも存在しない。「見よ、これらはすべて、極めてすばらしい」。しかしこれは、いろんな思いを呼び起こす言葉だと思います。
新しい年を迎えて、しかし私どもの心は、それほど単純ではないのであります。「見よ、極めて良かった」なんて言われたって、いやいや、何もよくないじゃないですか。神さま、きちんとこの世界をご覧になってくださいよ。あなたが造ったんでしょ? 責任を持って、最後までよくご覧になってください。こんなことやあんなことや、「見よ、極めて良かった」なんて、そんな夢みたいなこと言われても、困ります。
そんな私どもが日曜日の朝に礼拝の場所に集まるのは、そういうあれやこれやの俗世のことを忘れて、せめて日曜日の朝だけは清らかな気分になってみよう、なんて話ではないのです。もとよりここには、そんな方はいらっしゃらないだろうと思います。むしろ私どもは、ここで神の言葉を聴きながら、神がこの世界をご覧になっている、そのまなざしでこの世界を見ることを学び直すのです。
■そこで、もう少し創世記第1章の話をさせてください。私どもの教会が毎月発行している「教会の祈り」というプリントに、この創世記第1章31節についての短い説教を私が書きました。そこにも書いたことですが、現代の聖書学の常識からすれば、創世記第1章の天地創造の物語は、紀元前6世紀か、もしかしたら5世紀ごろに作られたと言われます。こういう話をすると、「なんだ、聖書はやっぱりただの作り話か」ということになりそうですが、それは軽率な読み方です。世界は神がお造りになったものであり、今も世界のすべてを神が支配し、導いてくださるのです。問題は、その神に対する信仰を、紀元前6世紀か5世紀という時代の人びとがどのように受け止めたか、それをどのような信仰をもって言い表したか、ということです。そこで鍵となるのが、紀元前6世紀に起こったバビロン捕囚という出来事です。創世記第1章の天地創造の物語は、このバビロン捕囚という歴史を踏まえて書かれました。それが何を意味するのか、ということです。
バビロン捕囚というのは、実は旧約聖書の中でいちばん重大な歴史的な出来事であるかもしれません。バビロニアという強大な帝国によって、神の民が滅ぼされたのです。これも今月の祈りのプリントに書いたことですが、都は荒らされ、神殿も破壊され、女性も子どもも無差別に殺され、そして二度と歯向かえないようにと、国の主だった人、さまざまな知識や技術を持つ人たちも皆、バビロニアに強制移住させられました。ふとウクライナ周辺で続いている戦争のこと、難民となった人たちのことを思い起こします。しかもこのバビロン捕囚という国難が厳しい意味を持ったのは、ただ侵略者バビロニアはけしからんという話ではすまなかったのであって、そうではなくて、これは自分たちの罪の報いでしかない。自分たちが神の恵みを踏みにじるような歴史を作ってしまった、その何百年にもわたる自分たちの罪の報いでしかなかったのです。
そのような試練を経験した神の民が、けれども新しい思いで神の言葉を聴きました。創世記第1章1節以下、すなわち聖書のいちばん最初のところに、こう書いてあります。
初めに、神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた。神は言われた。「光あれ」。こうして、光があった。神は光を見て、良しとされた。
こういう物語を読んで、科学的にあり得ないとか、幼稚な作り話だとか言って軽蔑するのは、あまりにも軽率だと言わなければなりません。「地は混沌であって、闇が深淵の面にあり」と書いてありますが、何となくうまい話を作ってやろうと、こんなことを書いたのではないのであります。都が焼かれ、神殿が壊され、無数の人びとが殺され、そういう混沌と闇を、私どもは2500年たった今もよく知っているのです。底知れぬ闇が大きな口を開けて自分たちを飲み込もうとしている、まさにそこで、この創造物語を書いた人たちは、「光あれ」という神の声を聴いたのです。「神は言われた。『光あれ』。すると光があった」。
バビロン捕囚という、これ以上考えられないほどの絶望を経験した神の民は、だからこそ、「わたしたちの助けは、天地を造られた主の御名にある」、そのことを知りました。戦争があり、災害があり、疫病があり、経済不安があり、何よりも私どもの罪がこの世界をこのまま滅ぼしてしまうのではないかと絶望しそうになるところで、その絶望の思いに真っ向から抵抗しながら、いいや、違う、この世界は神に祝福されているのだと信じ抜いたのです。「神はお造りになったすべてのものを御覧になった。見よ、それは極めて良かった」。
■この言葉には、続きがあります。最初の六日間で神は天地のすべてをお造りになり、そして七日目には「神は御自分の仕事を離れ、安息なさった」(創世記第2章2節)と書いてあります。「この日に神はすべての創造の仕事を離れ、安息なさったので、第七の日を神は祝福し、聖別された」(3節)。このような由来で、週の最後の日が〈安息日〉と呼ばれるようになりました。この聖書の言葉を読むたびに、私は言いようのない感動を覚えます。神が、ご自分のお造りになった世界をご覧になって、ご自分の作品をひとつひとつ愛でるように、これも、これも、実にすばらしい。本当にいいものができたと、そのように、安息の日を存分に楽しまれたのです。そのような神の言葉を、バビロン捕囚という絶望の中で聞き取ったということには、無限の重みがあると思います。そうではないでしょうか。
ところで、この安息日と呼ばれる日が、歴史的にどこからどのように生まれてきたか、その由来を学問的に突き詰めようとすると、実は分からないことの方がずっと多いのです。学者たちは、けっこういろんなことを言いますが、とにかく何千年も昔の話ですから、突き止めようがありません。しかしひとつ分かっていることは、バビロン捕囚の時代に安息日を重んじる傾向が強まったらしいということです。言われてみれば、何となく分かります。ふるさとを失ったのです。心のよりどころであった神殿も、叩き壊されたのです。そのようなところで、それでも安息日を守るということで、自分たちのアイデンティティを守り続けたのです。無理やり外国に連れて来られて、ほとんど息もつけないほどのところに追い込まれて、それでも七日のうち一日だけ、やっとの思いで休んだ、その休みを与えてくださるのは、天地を造られた神だと信じたのです。「見よ、すべては極めて良かった」。この世界は、丸ごと神に祝福されているんだ……それを信じることができなかったら、もう完全に絶望するほかないではないですか。当時の人びとが、どれほどの思いで安息日を重んじたか、想像するに余りあるものがあります。どこにも平安なんか見つからないところで、それでも目に見えるありとあらゆる現実に抵抗するように、神の与えてくださる安息を信じたのです。
70年を経て、遂に神の民イスラエルは、ふるさとに帰ることができました。エルサレムの神殿も再建することができました。そして、安息日を守るということは、ますます強力な国家のアイデンティティになっていきました。人びとは、熱心に安息日を守りました。全力で守りました。神が与えてくださった聖なる安息の日なのだから、絶対に仕事をしてはいけない。けれどもどこかで、ボタンの掛け違いが起こったようです。そのようなところに神の御子イエスが現れたとき、まさしくこの安息日をめぐって、深刻な論争が生じました。いったい、何を間違えたのでしょうか。
■マルコによる福音書第2章の最後の部分を読みました。最初のきっかけは、本当にささいなことでした。弟子たちが、主イエスと一緒に麦畑の中を歩きながら、ひょいと麦の穂を摘み始めたというのです。そうしたら、ファリサイ派の人びとが現れて、「安息日にそんなことをしてはいけません」と、これを咎めました。勝手に他人の畑の作物に触っちゃいかんという話ではありません。興味深いことに、旧約聖書の申命記に、他人の畑の作物を自由に食べてよいという掟が記されているのです。食べたいだけ、いくらでも食べてよい。ただし、もちろん籠とか鎌とかを持ってきて収穫をしてはならないと言い添えます。もちろんその心は、貧しい人が飢え死にしないようにという、実に単純な、しかし考えられないほど人道的な掟です。けれどもここで問題になったのは、それをしたのが安息日だったということでした。それこそ特にバビロン捕囚以降、安息日というものがますますきちんとした形をとるようになり、そこにたいへん詳細な掟が作らていきました。安息日にしてはいけないことは何か、していいことは何か。ここでは、イエスの弟子たちが麦の穂を摘んだ。つまり収穫の仕事をしたことになる。安息日に仕事をしてはいけないんじゃないですか。
しかしこれは、明らかに何かが間違っています。しかし、何を間違えたのでしょうか。来週の礼拝で読む第3章1節以下でも、再び安息日にしていいことは何か、してはいけないことは何かという論争が始まります。その結果、第3章6節。「ファリサイ派の人々は出て行き、早速、ヘロデ派の人々と一緒に、どのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた」。安息日の掟をめぐって、殺す殺さないの話に発展してしまいました。明らかに何かが間違っています。何が間違っているのでしょうか。
ひとつの考え方からすれば、こんなくだらない因縁をつけられても、相手にしないのがいちばんだったかもしれません。「すみません、次は気を付けまーす」でおしまいにしてもよかったかもしれません。ところが主イエスは、ファリサイ派の問いかけに対して、真正面から対決しておられるかのようです。そのことは第3章1節以下で、ますます明らかになります。そしてこのことで、主イエスの命が危なくなり始めたというのですが、もちろん主イエスは、そのことを最初から承知しておられたと思います。承知の上で、ファリサイ派と真正面から対決なさったのです。ファリサイ派の安息日が、何の休みにもなっていなかったからでしょう。神のお定めになった安息日を、本物の安息日とするために、わたしは命をかける。そうおっしゃっているかのようです。
■少し飛ばして27節以下で、主イエスはこう言われました。
「安息日は、人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから、人の子は安息日の主でもある」。
「安息日は、人のために〈創造された〉」と、多くの聖書学者が訳します。創世記第1章の、「『光あれ』。こうして、光があった」というところの「ある」という動詞も、旧約聖書のギリシア語訳では同じ言葉が使われています。「神は言われた。『安息日あれ』。こうして、安息日があった」。それはたとえば、バビロン捕囚という苦しみにあえぐ民のためにも、安息を与えてくださるのは主なる神であって、その安息日の主である人の子、わたしイエスがここにいるのに、どうしてそのことが分からないか。そう言われるのです。
「人の子は安息日の主でもある」。「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。わたしがあなたがたを休ませる」(マタイによる福音書第11章28節)と、主イエスは言われました。このようなところで、必ず私どもが気づかなければならないことは、私どもは自分で自分を休ませることはできないということです。一時の気休めを見つけることはできるでしょう。たまにおいしいものを飲み食いしてみたり、何とか仕事の合間を縫って旅行をしてみたり、きっと皆さんも、自分なりの休み方を心得ておられるだろうと思います。自分が本当にきちんと休むためには、こういうことをして、こういうことはやめて、こういう場所に行って、こういうものを食べて、できればあの人とあの人には会わないようにして、でもそれはなかなか実現が難しい……などと夢見るだけであるかもしれません。けれども、本当に私どもに休みを与えることができるのは、「わたしが安息日の主である」、「わたしがあなたがたを休ませる」と言われたお方をおいてほかにないのであって、けれども人間の根本的なみじめさというのは、まさしく神の祝福から断ち切られている。だから自分自身も本当の休みを得ることができないし、自分の隣人にまことの安息を与えることもできないのです。
■今も終わりが見えない戦争のために、安息日どころではない、安らかに息をつく暇さえ与えられない人びとの多いことを思います。「神はお造りになったすべてのものを御覧になった。見よ、それは極めて良かった」。それは、あのバビロン捕囚の苦しみの中で神の民が聞き取った言葉だと申しました。今も神は、世界のすべてをご覧になっていると思います。「見よ、それは極めて良かった」という言葉が、今も戦争のために苦しむ人たちのために与えられているのだと考えるのは、しかし、どうにもやりきれないものがあります。「見よ、極めて良かった」。冗談じゃない。誰がそんなこと言った。
そんなことを考えながら、正月休み明けに今日の礼拝の準備をしておりましたら、にわかに話題になり始めたのが、クリスマス休戦というやつです。どう考えてもうさんくさい話題でしかなかったわけですが、そう言えばそんな言葉もあったな、と皆さんの心にも留まったかもしれません。クリスマスを12月ではなくて1月に祝う教会があるなんて初めて知ったという方もあるかもしれません。
もともとクリスマス休戦というのは、1914年、第一次世界大戦が始まった年のクリスマスに、12月24日から25日にかけて一時的に戦いが止んだという出来事です。敵同士がそれぞれの国の言葉で、ドイツ語と英語で「きよしこの夜」を歌い交わし、一緒にクリスマスを祝い、遂にはサッカーの試合を楽しんだということまで伝えられています。こういう話を聞くと、うっかり感動しそうになります。けれども、決して忘れてはならないことは、1914年のクリスマス休戦の後、しかし戦争はますます激しくなったということです。そして第一次世界大戦の間、1915年にも、1916年にも、1917年にも、そしてその後いかなる戦争においても、クリスマス休戦などというものはなかったし、もちろん今年の1月7日にも、昨年の12月にも、何もいいことは起こらなかったのであります。そしてそういう事態を遠くから眺めながら、ただ今の戦争の当事者たちだけを批判したって、何の意味もないだろうと思うのです。私どもは、決して自分で自分を休ませることができないし、隣人に真実の安息を与えることもできないのです。その理由は、結局のところ、私どもが罪人だからだ。神の祝福から断ち切られているからだとしか、言いようがないのです。
■ファリサイ派の人びとは、自分たちで決めた安息日の掟を根拠にして、主イエスの弟子たちを裁きました。そこに何の安息もなかったことは明らかです。安息日には、これをしてはならない、これもしてはならないと、安息日の禁止規定を積み重ねて、誰かがひょいと麦の穂を摘み取ったりしないか、目を光らせながら、それを完璧に守り切れば、完璧な安息を実現できると彼らは思ったのですが、かえって息もつけない日になりました。彼らからしたら、自信満々で正しいことをしているのですが、その正しさは、誰のことも幸せにしない正しさでしかありませんでした。しかし私どもだって、ひとりひとり、そういう自分だけの正しさを隠し持っていると思います。自分自身にも隣人にも、何の慰めも、何の安らぎも与えない正しさを。そういうところから、国と国との争いも始まるのでしょう。
たとえば今私どもが、「クリスマスには戦争をしてはいけません」という新しい掟を作っても、きっと何の安らぎも生まれないだろうと思います。その掟を根拠に、ますます裁き合い、争い合うだけで終わるでしょう。私どもは、自分で自分を休ませることはできないのです。その私どものみじめさに、主イエスはもちろん気づいておられました。「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。わたしがあなたがたを休ませる」。あの安息日に、弟子たちが麦の穂をひょいと摘み取ったとき、彼らは何も気づいていなかったのですが、既に彼らはこの主イエスのもとにある安息のうちに置かれていたのです。その安息を妨げることがあるならば、それがどんなにささいなことであったとしても、主イエスは断固として対決なさいます。「人の子は、安息日の主である」からです。
■まだ25節以下に触れていません。しかし、それほど長い話をする必要はないと思います。
「ダビデが、自分も供の者たちも、食べ物がなくて空腹だったときに何をしたか、一度も読んだことがないのか。アビアタルが大祭司であったとき、ダビデは神の家に入り、祭司のほかにはだれも食べてはならない供えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないか」。
これは旧約聖書のサムエル記上第21章に記されている出来事です。不思議なことは、このダビデの話は、安息日とは何の関係もないということです。そうでなくても、おそらく皆さんの多くは、この25節、26節の部分はどうも分かりにくいという印象を持ったのではないかと思います。いったいダビデと主イエスの弟子たちと、何の関係があるか。
しかしダビデにとっては、この出来事は、一生忘れることができないものであったと思います。「祭司のほかにはだれも食べてはならない供えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えた」というのですが、本当に九死に一生を得たという思いだったと思います。明らかに、掟には違反していることをしたのです。まだ王になる前のダビデが、命を付け狙われて逃げ回るような生活をしていたときに、空腹のままに祭司を訪ねて、食べ物を恵んでほしいと言ったけれども、あいにく供え物のパンしかなかった。この供え物のパンは祭司しか口にしてはいけないものであったけれども、神がダビデを助けてくださったのです。この「供えのパン」というのは、神のみ前に供えたパンということですが、その原語の意味を強調して訳すと「神が見ておられるパン」という意味になります。神のために供え物をしながら、けれどもそのパンを神が見ていてくださる。われわれは神のまなざしの中にあるのだという信仰の表現です。
そのパンを食べて命を得たダビデが、のちにイスラエルの王になります。それに似て、主イエスご自身がやがて「ダビデの子」と呼ばれるようになります。そして、主イエスと共にある弟子たちもまた、神のまなざしの中にあり、その弟子たちが、安息日にひょいと麦の穂をつまんだときにも、彼らは何もそのことに気づくところはなかったのですけれども、既に確かな安息の中に招かれていたのです。「神はお造りになったすべてのものを御覧になった。見よ、それは極めて良かった」という神の祝福の事実が、まさかただ麦の穂をつまむという小さな行為にまで及んでいるとは、弟子たちは夢想だにしなかったに違いありません。主イエスが、この弟子たちと共にいてくださったのです。今私どもも、安息日の主であるお方と共にある。だからこそ、私どもも安息日の主であるお方と共に、「見よ、すべては極めて良かった」と、神の祝福を信じることができるのです。お祈りをいたします。
教会の主にして、世界の主でいてくださるイエス・キリストの父なる御神、この世界にあって、あなたの与えてくださる安息を信じ抜くことは、決して容易なことではありません。争いがあります。どのように安息日を過ごすかということをめぐっても、裁き合うことしか知らない私どものみじめさを、どうか憐れんでください。今、あなたのみ子の招きの言葉を聞き、私どももみもとにまいります。あなたのもとにある安息の中にしっかりと立ち、それゆえにまた、私どもも隣人のために安らぎを与えることのできる者としてください。主のみ名によって祈り願います。アーメン